2章
総論(復興庁設置以降)
3節 法制度
- 1. 東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)
- 2. 復興庁設置法(平成23年法律第125号)
- 3. 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)
- 4. 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)
- 5. 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)
- 6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)
- 7. 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号)
- 8. 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律(平成23年法律第34号)
- 9. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号)
- 10. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)
- 11. 津波対策の推進に関する法律(平成23年法律第77号)
- 12. 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)
- 13. 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第124号)
- 14. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)
- 15. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号)
- 16. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)
- 17. 地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)
- 18. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号)
- 19. 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成23年法律第64号)
- 20. 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成23年法律第102号)ほか
- 21. 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第39号)
- 22. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号)
- 23. 原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)
- 24. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)
- 25. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)
- 26. 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)
- 27. 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(平成25年法律第32号)
- 28. 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成25年法律第97号)
- 29. 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年法律第112号)
- 30. 国会法の一部を改正する法律(平成23年法律第111号)
- 31. 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成23年法律第42号)
- 32. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)
- 33. 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)
- 34. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律(平成23年法律第11号)
- 35. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)
- 36. 特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第15号)
- 37. 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律(平成23年法律第69号)
- 38. 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第86号)
- 39. 災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成23年法律第100号)
- 40. 東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成23年法律第103号)
- 41. 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成24年法律第6号)
- 42. 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第80号)
- 43. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第89号)
- 44. 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号)
- 45. 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第116号)
- 46. 平成二十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成23年法律第88号)
- 47. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成23年法律第2号)ほか
- 48. その他の規制緩和措置等
(1) 概要
東日本大震災に当たっては、被災地の復旧・復興、被災者の生活の再建や産業・生業の再生、さらに原子力災害への対応等のために、様々な法律上の措置が必要となった。その中には、東日本大震災に特化した特別立法として措置されたものもあれば、適用対象を東日本大震災に限らない一般法としての制定・改正で措置されたものもあった。これらを単純に集計すると、下記一覧(図表 2-3-1)に掲げた計47本に及ぶ。
なお、東日本大震災を教訓として、全国の防災・減災対策の強化や原子力政策見直し等のために制定・改正された法律であっても、東日本大震災を対象としないもの等については、原則として、一覧には掲載していないが、関連法律の解説の中で「その後の改正等」として適宜触れている。また、累次改正がなされた法律は1項目にまとめることとし、主な改正については、当初の制定法又は改正法の解説の中で「その後の改正等」として適宜触れている。
(2) 国会情勢等
東日本大震災の発生は第177回国会(常会)の会期中であったが、復興に当たって総合的対策を樹立するため、衆参両院に東日本大震災復興特別委員会が設置された(衆議院は平成23年5月19日、参議院は平成23年6月13日に設置)。その会期については、当初の6月22日までから70日間延長されている。
また、同国会においては、衆議院では政権与党(民主党、国民新党)が過半数を占める一方、平成22年7月の参議院選挙によって参議院では与党が過半数席を保持していない、いわゆる「ねじれ国会」の状態にあった。
このような国会情勢や直面する課題に対して緊急の措置が求められたこと等を背景に多くの法律が議員立法として成立し、あるいは内閣提出法案に対する議員修正がなされることとなった(内閣提出法案28本(うち議員修正あり7本)、議員立法19本)。
なお、一覧掲載の法律について、国会回次ごとの成立本数は以下のとおりで、その多くは発災時の第177回国会で成立している。
| ・ 第177回国会(平成23年1月24日~8月31日) | :27本 |
| ・ 第178回国会(平成23年9月13日 ~9月30日) | :2本 |
| ・ 第179回国会(平成23年10月20日~12月9日) | :9本 |
| ・ 第180回国会(平成24年1月24日~9月8日) | :6本 |
| ・ 第183回国会(平成25年1月28日~6月26日) | :1本 |
| ・ 第185回国会(平成25年10月15日~12月8日) | :1本 |
| ・ 第187回国会(平成26年9月29日 ~11月21日) | :1本 |
(3) 分類別概説
本節では、各法律について次の分類により、それぞれの立法経緯・制定趣旨、法概要、適用実績、その後の改正等について解説している。
1) 復興庁所管法律
1.~6.では、復興政策の基本的枠組となる法律など復興庁所管の法律について詳述する。なお、「復興庁設置法」(平成23年法律第125号)については、第2章第2節で記述のとおりである。
2) 復旧事業・まちづくり・事業再生に係る立法措置
7.~13.は、復旧事業・まちづくり・事業再生に係る立法措置となる。被災地における復旧事業や災害廃棄物処理に当たっては、市町村の行政機能の喪失やそもそもの執務能力を超える膨大な業務が発生したため、その一部について、県や国が代行する必要が生じた。また、復興まちづくりにおいては、津波による市街地や生産基盤の流出等のため、地域の土地利用を抜本的に再編するなど新たな防災まちづくりの考え方や法的枠組が必要となった。
3) 震災被害に係る臨時特例等に係る立法措置
14.~21.は、震災被害に係る臨時特例等に係る立法措置となる。激甚災害に係る災害復旧事業については従来から国庫補助の嵩上げ等の制度があったが、東日本大震災の被害の甚大さから、公共施設の復旧から社会保険関係にわたる幅広い分野で追加措置や被災者等への特別な助成・負担軽減等が必要となった。また、地方債や死亡を支給事由とする各種給付金における行方不明者の取扱に係る特例等も必要になった。
4) 原子力災害関係の立法措置
22.~30.は、原子力災害関係の立法措置となる。原子力災害については、原子力事業者による巨額の賠償をいかに担保・迅速化するか、広範囲に飛散した放射性物質の除染や処分を誰がどのように行うか、広域に避難した住民への行政サービスをどのように提供するか等、既存の法律では想定していなかった課題が発生し、新たな法的枠組の創設等が必要になった。なお、「福島復興再生特別措置法」(平成24年法律第25号)及び「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(平成24年法律第48号)については、4.及び5.で詳述している。
5) その他立法措置
31.~47.は、その他立法措置となる。復興等のための財源確保に必要な措置、国の会計制度や地方交付税の特例、相続等民事法上の課題への対応、被災地の金融機関の信用力強化のための措置等が必要となった。
6) 規制緩和等
また、48.では、政令以下の法的措置を含め、震災対応として行われた規制緩和等について、内閣府による「東日本大震災に関連した各府省の規制緩和等の状況」(平成23年4月19日公表・平成24年12月12日更新)1を掲載している。なお、当該資料は、一部、16.等と重複する立法措置も含まれているが、当時の政府において規制緩和等を網羅的に整理した貴重な資料であるため、重複排除等はせず、そのまま掲載することとした。このほか、立法措置と規制緩和のいずれでもないが、法令上の課題に係る措置として行われた、民事法上の対応についても記述した。
(No.に下線があるものは議員立法、破線があるものは議員修正のあった閣法。<>は主たる担当省庁)
| No. | 法律の名称 | 公布日 | 概要 |
|---|---|---|---|
1 |
東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号) <復興庁> |
H23.6.24 | 東日本大震災からの復興について、基本理念、資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項や復興庁の設置に関する基本方針等について規定。 |
2 |
復興庁設置法(平成23年法律第125号) <復興庁> |
H23.12.16 | 復興庁の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するために必要な組織に関する事項を規定。 |
3 |
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号) <復興庁> |
H23.12.14 | 東日本大震災からの復興に向けた取組を推進するため、復興特別区域基本方針、復興推進計画の認定及び特別の措置(規制・手続の特例、税制特例、利子補給)、復興整備計画の実施に係る特別の措置(規制・税制の特例)、復興交付金等について規定。 |
4 |
福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号) <復興庁> |
H24.3.31 | 原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するため、福島復興再生基本方針の策定、福島復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣の認定並びに当該認定を受けた福島復興再生計画に基づく避難解除等区域の復興及び再生並びに原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等について規定。 |
5 |
東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号) <復興庁> |
H24.6.27 | 東京電力原子力事故による主に自主避難者を対象とした被災者の生活支援等の施策を推進するため、基本理念、国の責務や政府による基本方針の策定等について規定。 |
6 |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号) <復興庁> |
H23.11.28 | 東日本大震災により過大な債務を負っている事業者の二重ローン問題を解消し、その再生を図るため、新たに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を設置し、金融機関からの債権買取り等の業務を規定。 |
| 復旧事業・まちづくり・事業再生に係る立法措置 | |||
| 7 | 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号) <国土交通省> |
H23.4.29 | 東北地方太平洋沖地震による被害を受けた地方公共団体の地域の実情に鑑み、国又は県が被害を受けた地方公共団体に代わって公共土木施設(漁港、砂防、港湾、道路、海岸、地すべり防止、下水道、河川及び急傾斜地崩壊防止)の災害復旧事業及びこれに関連する事業に係る工事を施行するための措置について規定。 |
| 8 | 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律(平成23年法律第34号) <国土交通省> |
H23.4.29 | 東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画等のため必要があり、かつ、市街地の健全な復興のためやむを得ないと認めるときは、一定の要件に該当する区域を指定して、期間を限り、建築制限又は禁止を行うことを可能とする措置について規定。 |
| 9 | 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号) <農林水産省> |
H23.5.2 | 東日本大震災に係る津波による災害に対処し、早期営農再開を図るため、国等が緊急に行う災害復旧及び除塩並びにこれと併せて行う区画整理等の事業を円滑に実施できることとする等の措置について規定。 |
10 |
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号) <環境省> |
H23.8.18 | 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理が喫緊の課題となっていることに鑑み、国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理するための特例その他の国が講ずべき措置について規定。 |
11 |
津波対策の推進に関する法律(平成23年法律第77号) <内閣府(防災担当)> |
H23.6.24 | これまでの津波対策が十分でなかったことを国として反省し、基本的認識を示すとともに、地方公共団体によるハザードマップ作成等への国の財政上の援助や11月5日を津波防災の日とすること等について規定。 |
| 12 | 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号) <国土交通省> |
H23.12.14 | 津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとともに、津波防護施設の管理、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等について規定。 |
| 13 | 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第124号) <国土交通省> |
H23.12.14 | 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴い、水防法、土地収用法、都市計画法その他の関係法律について必要な規定を整備。 |
| 震災被害に係る臨時特例等に係る立法措置 | |||
| 14 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号) <財務省> |
H23.4.27 | 東日本大震災による被災納税者への緊急的な対応として、現行税制を適用した場合の負担を軽減する観点から、雑損控除及び雑損失の繰越控除の特例、震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付、住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除、被災自動車に係る自動車重量税の還付等の税制特例措置について規定。 |
| 15 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号) <財務省> |
H23.12.14 | 東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の一層の推進を図るため、住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の限度額・控除率の拡充、新規立地促進税制等を含む復興特区税制の創設等の税制特例措置について規定。 |
| 16 | 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号) <内閣府(防災担当)> |
H23.5.2 | 東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について規定。 |
| 17 | 地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号) <総務省> |
H23.4.27 | 東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域における固定資産税等の免除、住宅の再取得等について住宅ローン控除の対象化、被災した農用地等の代替資産について不動産取得税の免除等の税制特例措置を規定。 |
| 18 | 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号) <総務省> |
H23.8.12 | 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するため、警戒区域設定指示等の対象となった区域等について、固定資産税等の免除、代替資産を取得した場合の不動産取得税の免除、廃車とした自動車についての自動車税等の免除等の税制特例措置及び地方債による減収補填措置について規定。 |
| 19 | 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成23年法律第64号)(※令和4年4月廃止) <外務省> |
H23.6.8 | 東日本大震災により多数の被災者が一般旅券を紛失し、又は焼失したことに対処するため、当該旅券の紛失届を提出した被災者に対し、国の手数料を徴収することなく、当該旅券の有効期限までを有効期間とする震災特例旅券を発給することを可能とする特例措置を規定。 |
20 |
東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成23年法律第102号)ほか2 (※平成24年の改正により、「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」へ名称変更。また、平成30年の改正により、「東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」へ名称変更。) <総務省> |
H23.8.30 (改正法:H24.6.27) |
東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、平成23年度においてなお合併特例債を発行することができる被災市町村について、合併特例債の発行可能期間を10年度から5年度間延長。 平成24年の改正法では、被災市町村以外の合併市町村においても市町村建設計画に基づく公共的施設の整備事業等の実施が困難となっていること等に対処するため、被災市町村以外の合併市町村における合併特例債の発行可能期間を10年度から5年度間延長するとともに、被災市町村における合併特例債の発行可能期間を15年度から5年度間延長。 なお、平成30年の改正法では、さらに、被災市町村以外の合併市町村における合併特例債の発行可能期間を15年度から5年度間延長するとともに、被災市町村における合併特例債の発行可能期間を20年度から5年度間延長。 |
21 |
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第39号) <総務省> |
H24.6.27 | 東日本大震災の影響により、過疎対策事業の大幅な遅れが想定され、過疎地域自立促進特別措置法の期限内(平成28年3月31日)において総合的かつ計画的な施策を展開することが困難な状況が生じていたことから、被災市町村等から法の期限延長を求める強い要望が上がったことを受け、各党各会派で協議が重ねられた結果、法の有効期間を平成33年(令和3年)3月31日まで5年間延長。 |
| 原子力災害関係の立法措置 | |||
22 |
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号) <文部科学省> |
H23.8.5 | 原子力発電所事故による被害を受けた者を早期に救済する必要があること、これらの者に対する特定原子力損害の賠償の支払に時間を要すること等の特別の事情があることに鑑み、当該被害に係る応急の対策に関する緊急の措置として、当該事故による損害を填補するための国による仮払金支払及び原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助について規定。 |
23 |
原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号) (※「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」へ名称変更) <内閣府(原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当室)> |
H23.8.10 | 原子力事業に係る巨額の損害賠償が生じる可能性を踏まえ、原子力事業者による相互扶助の考えに基づき、将来にわたって原子力損害賠償の支払等に対応できる仕組みを構築するため、原子力損害賠償支援機構の設置、機構への負担金の積立、機構による原子力事業者への援助等について規定。 |
24 |
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号) <総務省> |
H23.8.12 | 原子力発電所事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することとすることができる特例を設けるとともに、住所移転者に係る措置を規定。 |
25 |
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号) <環境省> |
H23.8.30 | 原子力発電所事故により放出された放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するため、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、汚染廃棄物対策地域や除染特別地域等の指定や、廃棄物処理や除染等の役割分担等について規定。 |
| 26 | 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号) <環境省> |
H26.11.27 | 中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、法律において中間貯蔵や最終処分場の確保に関する国の責務を明記するとともに、国等の委託を受けて日本環境安全事業株式会社(JESCO)が中間貯蔵や除去土壌等の収集及び運搬等の業務を行う旨を規定。 |
| 27 | 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(平成25年法律第32号) (※平成30年12月廃止) <文部科学省> |
H25.6.5 | 原子力発電所事故の被害者が時効の完成を懸念することなく原子力損害賠償紛争審査会による和解の仲介手続を利用できるようにするため、緊急に必要な措置として、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなす旨を規定。 |
28 |
東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成25年法律第97号) (※「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効の特例に関する法律」に名称変更) <文部科学省> |
H25.12.11 | 原子力発電所事故による災害が大規模で長期間にわたる未曽有のものであり、原子力損害を被った者のうちに今なお不自由な避難生活を余儀なくされその被った損害の額の算定の基礎となる証拠の収集に支障を来している者が多く存在すること、個々の被害者に性質及び程度の異なる原子力損害が同時に生じその賠償の請求に時間を要すること等により、その賠償請求権の行使に困難を伴う場合があることに鑑み、短期消滅時効を「10年間」に延長し、その起算点を「損害が生じた時」とする旨を規定。 |
29 |
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年法律第112号) ※平成24年10月失効 |
H23.10.7 | 原子力発電所事故の直接又は間接の原因や、関係行政機関等が当該事故に対し講じた措置の究明又は検証のための調査等を行うとともに、これらの調査の結果に基づき、原子力に関する基本的な政策及び当該政策に関する事項を所掌する行政組織の在り方の見直しを含む原子力発電所の事故の防止等のため講ずべき施策又は措置について提言を行い、もって国会による原子力に関する立法及び行政の監視に関する機能の充実強化に資するため、国会に、施行から1年の間の措置として、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置くこと等を規定。 |
30 |
国会法の一部を改正する法律(平成23年法律第111号) | H23.10.7 | 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法が有効な間の措置として、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置く旨を規定。 |
| その他立法措置 | |||
| 31 | 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成23年法律第42号) <財務省> |
H23.5.2 | 平成23年度第一次補正予算の財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ、並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付等を規定。 |
32 |
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号) <財務省> |
H23.12.2 | 復興に必要な財源を確保するため、税外収入に関する措置(国債整理基金特別会計への財政投融資特別会計からの繰入れ及び国有株式の所属替)、復興特別所得税(25年間2.1%)及び復興特別法人税(3年間10%、平成26年に1年前倒し廃止)の創設、並びに復興債の発行・償還等を規定。 |
33 |
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号) <総務省> |
H23.12.2 | 全国防災事業の財源を確保するため、臨時の措置として個人道府県民税及び個人市町村民税の均等割の標準税率について、それぞれ500円を加算する地方税法の特例措置を規定。 |
34 |
平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律(平成23年法律第11号) | H23.3.31 | 早期の生活再建及び復旧復興に資するため、平成23年4月から9月までの各議院の議長・副議長及び議員の歳費の月額をそれぞれ50万円ずつ削減する措置を規定。 |
35 |
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)ほか3 <内閣官房内閣人事局※・防衛省・総務省><法務省> ※制定当時は総務省 |
H24.2.29 | 平成23年9月の人事院勧告を鑑みた給与の改定とともに東日本大震災に対処する必要性等から、国家公務員の人件費を削減するため、平成24年度及び25年度の国家公務員の給与に関する特例(本省課室長相当職員以上の俸給月額9.77%の減額支給等)を規定。 |
| 36 | 特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第15号) <財務省> |
H24.3.31 | 復興財源確保法(平成23年法律第117号)附則第17条第2項の規定を踏まえ、復興事業に関する経理を明確にするため、東日本大震災復興特別会計の設置、管理及び経理(歳入・歳出)等、並びに附則において復興庁廃止時の復興特別会計の廃止等を規定。 |
37 |
東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律(平成23年法律第69号) <法務省> |
H23.6.21 | 東日本大震災の被災者である相続人が、相続の承認又は放棄をすべき期間を徒過することにより不利益を被ることを防止するため、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、相続の承認又は放棄をすべき期間を、平成23年11月30日まで延長する旨を規定。 |
38 |
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第86号) <内閣府(防災担当)※> ※改正当時は厚生労働省 |
H23.7.29 | 災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に、一定の条件の下、死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹を加え、東日本大震災以後に生じた災害について適用する旨を規定。 |
39 |
災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成23年法律第100号) <内閣府(防災担当)※> ※改正当時は厚生労働省・内閣府(防災担当) |
H23.8.30 | 災害により死亡した者の遺族に対する弔慰金及び災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対する見舞金の支給並びに自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建の支援を確実なものとするため、災害弔慰金及び災害障害見舞金並びに被災者生活再建支援金について、差押えを禁止すること等を規定。 |
40 |
東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成23年法律第103号) <内閣府(防災担当)※> ※改正当時は厚生労働省 |
H23.8.30 | 東日本大震災関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら東日本大震災関連義援金を使用することができるようにするため、東日本大震災関連義援金について、差押えを禁止すること等を規定。 |
41 |
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成24年法律第6号) <法務省> |
H24.3.29 | 東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センター(法テラス)の業務の特例として、3年間の時限の措置として、東日本大震災法律援助事業(被災者の資力を問わず、民事裁判等手続やADRに関し、訴訟代理援助、書類作成援助及び法律相談援助を実施する旨を規定。 |
| 42 | 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第80号) <金融庁> |
H23.6.29 | 東日本大震災により金融機能に様々な影響が懸念される中、広域にわたる被災地域において、面的に金融機能を維持・強化するとともに、預金者に安心感を与える枠組みを設けるため、震災特例金融機関等が国の資本参加を受けようとする場合に経営責任が問われないことを明確化するなどの震災の特例を規定。 |
| 43 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第89号) <農林水産省> |
H23.8.3 | 東日本大震災により漁業者・農業者に甚大な被害が発生する中、漁業者・農業者の経営再開・再建に向け、農漁協系統の金融機能を維持・強化するとともに、漁業者・農業者等の貯金者に安心感を与える枠組みを設けるため、東日本大震災に対処して特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るため、その自己資本の充実に関する震災の特例を規定。 |
| 44 | 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号) (※40により、「東日本大震災に対処するための平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」へ名称変更) <総務省> |
H23.5.2 | 平成23年度第一次補正予算に伴う地方財政補正措置として、東日本大震災に係る特別の財政需要に対応するため、平成23年度分の地方交付税の総額に1,200億円を加算するとともに、上記の加算額の全額を、特別交付税とする特例を規定。 |
| 45 | 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第116号) <総務省> |
H23.12.2 | 平成23年度第三次補正予算に伴う地方財政補正措置として、東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応する「震災復興特別交付税」を交付できるようにするため、平成23年度の地方交付税の総額を1兆6,635億円増額するとともに、震災復興特別交付税の額の決定時期等に関する特例等を規定。 |
| 46 | 平成二十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成23年法律第88号) <財務省> |
H23.7.29 | 平成23年度第二次補正予算の財源として、新たな国債発行に依存しないという観点から、平成22年度歳入歳出の決算上の剰余金を充てるため、歳入歳出の決算上の剰余金のうち2分の1を下らない金額は、公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法(昭和22年法律第34号)第6条第1項の規定を平成22年度の剰余金について適用しない旨を規定。 |
| 47 | 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成23年法律第2号)ほか4 (※「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」へ名称変更) <総務省> |
H23.3.22 | 東北地方太平洋沖地震により著しい被害を受けた地域について、平成23年4月に予定されている統一地方選挙の期日を延期する等の震災の特例を規定。 |
- 2 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第36号)及び東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第19号。議員立法。)
- 3 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第5号)
- 4 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第55号)及び東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第92号。議員立法。)。
1. 東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
発災後、政府においては、捜索・救助、応急復旧や避難生活の支援等の初動・応急対応に全力を挙げてきた。しかし同時に、復興へと歩みを進めていくため、政府の復興に向けた体制を立ち上げること等も求められていた。国会においても、阪神・淡路大震災と比べて、復興に向けた基本法の制定や体制の整備が遅い等の指摘がなされ5、その体制については、関東大震災における帝都復興院や阪神・淡路大震災等にも言及しつつ、これらと比較した被害の広域性等から専任の行政組織の設置を求める声が上がっていた。また、一方では、行政機関の機能性等から新たな行政組織を設けるのではなく、本部体制を採るべき等の意見も示された6。
こうした中、政府としては、平成23年4月5日に内閣官房に設けた「被災地復興に関する法案等準備室」において、被災地域の復興についての基本理念を明らかにするとともに、復興に関する組織等の基本的な枠組みを定めるための法律案の検討を進めて、同年5月13日に「東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案」(以下「政府案」という。)を閣議決定し、第177回通常国会に提出した。
この政府案においては、「阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律」(平成7年法律第12号。以下「阪神・淡路復興法」という。)に準じて、被災地域の復興の基本理念、国の講ずる措置や復興対策本部の設置等の規定が設けられた。被災地域の復興の基本理念としては、
① 単なる災害復旧にはとどまらない抜本的な対策が推進されるべきこと
② 国と地方公共団体との適切な役割分担・連携協力、全国各地の地方公共団体の相互の連携協力の確保とともに、被災地域の住民の意向が尊重されるべきこと
③ 国民相互の連帯を基本とすべきこと
④ 人口減少等の我が国が直面する課題や、エネルギーの利用制約・環境負荷等の人類共通の課題の解決に資する先導的な施策に取り組まれるべきこと
⑤ 安全な地域づくり・雇用創出と社会経済の再生・地域文化の振興と地域社会の絆の維持強化のための施策が推進されるべきこと
等が掲げられた。
また、阪神・淡路復興法にはないものとして、地方公共団体の講ずる措置、東日本大震災復興構想会議の設置(阪神・淡路大震災では同等の委員会を政令設置)、原発事故からの復興に関する合議制の機関等の規定が盛り込まれた。さらに、附則においては、復興のための行政各部の施策の統一を図るため必要となる事項の企画及び立案並びに総合調整を行う復興庁の設置について検討し、法施行後1年以内を目途として必要な法制上の措置を講ずることとされた。
しかし、この政府案に対して国会においては、阪神・淡路復興法の焼き直しであり、両震災の違いを考慮していない等の指摘がなされている7。また、報道においては、法案提出に時間を要したとの指摘、より強力な推進体制を構築すべきといった意見や「器」づくりにエネルギーを過剰に割くべきではないといった見解等が示された。
- 5 平成23年5月1日、片山虎之助議員(たちあがれ日本)(第177回国会(参)予算委員会会議録第13号37頁)等。
- 6 平成23年3月23日、福井照議員(自由民主党)(第177回国会(参)内閣委員会会議録第2号11頁)、平成23年5月1日、片山虎之助議員(たちあがれ日本)(第177回国会(参)予算委員会会議録第13号38頁)等。
- 7 平成23年5月19日、石破茂議員(自由民主党)(第177回国会(衆)本会議録第21号3頁)等。
| 平成7(1995)年 阪神・淡路大震災 | 平成23(2011)年 東日本大震災 | |
|---|---|---|
| 発災 | 1.17 発災 | 3.11 発災 |
| 2.15 阪神・淡路復興委員会設置(政令) | ||
| 1か月後 | 2.17 阪神・淡路復興法案閣議決定・国会提出 |
4.11 復興構想会議設置(閣議決定) |
| 2.22 同法成立 | ||
| 2.24 同法公布・施行、復興対策本部立ち上げ | ||
| 2か月後 | 5.13 政府案閣議決定・国会提出 |
| 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律(平成7年法律第12号)※1 | 東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案(政府案) | |
|---|---|---|
| 目的 | ・阪神・淡路地域の復興を迅速に推進 |
・被災地域の復興を迅速に推進 ・現在及び将来の世代にわたる国民経済の健全な発展、国民生活向上 |
| 基本理念 | ・国と地方公共団体の適切な役割分担と協同、地域住民の意向尊重 ・生活の再建及び経済の復興と安全な地域づくりの緊急な推進 ・活力ある関西圏の再生 |
・単なる災害復旧にとどまらない抜本的な対策推進 ・国と地方公共団体との適切な役割分担及び連携協力、被災地域の住民の意向尊重 ・国民の相互の連帯、多様な主体の自発的協働 ・人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組 |
| 国等の措置 | ・基本理念に則った、国による復興に必要な措置の実施 |
・基本理念に則った、国、地方公共団体による復興に必要な措置の実施 |
| 復興組織 | ・総理府に、阪神・淡路復興対策本部を設置 |
・内閣に、東日本大震災復興対策本部を設置 |
| 所掌事務 | ・関係行政機関が講ずる復興のための施策に関する総合調整 |
・復興施策に関する基本的方針の企画・立案・総合調整 ・関係行政機関が講ずる復興施策の実施の推進・総合調整 |
| 組織体制 | ・本部長:内閣総理大臣 ・副本部長:国務大臣※2 ・本部員:上記外の全ての国務大臣 |
・本部長:内閣総理大臣 ・副本部長:内閣官房長官及び復興対策担当大臣 ・本部員:上記外の全ての国務大臣等 |
| 現地組織 | - | ・本部の地方機関として、現地対策本部を設置 |
| 会議等 | -※3 | ・東日本大震災復興構想会議の設置 ・原子力発電施設の事故災害地域の復興に関する合議制の機関の設置 |
| 附則 | ・施行の日から起算して五年を経過した日にその効力を失う。 |
・復興庁の設置について法律施行後一年以内を目途に必要な法制上の措置の実施 |
※2 内閣官房長官及び阪神・淡路大震災復興対策担当大臣(平成7年8月8日の内閣改造以降は国土庁長官)。
※3 阪神・淡路復興委員会を政令で設置(平成7年2月15日)。
一方、東日本大震災からの復興に向けた基本理念や組織体制については、平成23年5月18日に自由民主党が「東日本大震災復興再生基本法案」(以下「自民党案」という。)を国会提出、同月19日には公明党も「東日本大震災復興基本法案骨子」(以下「公明党案」という。)を公表した。
自民党案では、基本理念として、東日本大震災からの復興再生は21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指すものであることを旨として行わなければならないことが掲げられ、別に法律で定めるところにより、東日本大震災復興再生院を設置することとされた。政府案における復興庁は行政各部の総合調整を所掌するものとされたが、この東日本大震災復興再生院は施策の実施に係る事務までを所掌するものとされた。
公明党案では、基本理念に「人間の復興」が掲げられた。また、別に法律で定めるところにより、施策の実施までを所掌する東日本大震災復興庁を設置すること、さらに、東日本大震災復興特別区域を指定することが盛り込まれた。
また、自民党案、公明党案のいずれもが政府案にはなかった公債の発行について規定していた。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
5月19日の(衆)本会議において、(衆)東日本大震災復興特別委員会の設置が可決されるとともに、政府案、自民党案、「内閣法及び内閣府設置法の一部を改正する法律案」(内閣提出)8の趣旨説明及び質疑がなされた。翌20日の(衆)東日本大震災復興特別委員会では、これらの3法案及び政府案に付随する「地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件」の提案理由説明がなされ、5月23日から25日にかけて3法案の質疑、被災地の商工業、農業及び漁業関係者に対する参考人質疑が行われた。また、同月27日には、岩手県、宮城県及び福島県において、3県の知事と同委員会に所属する委員との意見交換が実施された。
その後、政府案、自民党案及び公明党案の調整を図るために、5月30日から民主党、自由民主党及び公明党の3党による与野党協議が開始され、同月31日から6月6日までに計6回に及ぶ実務者協議が行われた結果、同月7日に修正案に対する3党合意が成立した。
これを受けて、6月9日の(衆)東日本大震災復興特別委員会において、政府案、自民党案が撤回され、改めて、民主党・自由民主党・公明党の共同による「東日本大震災復興基本法案」起草案が提出された。同案には、政府案にはなかった復興債の発行や復興特区に係る規定が追加され、また、復興庁は総合調整機能だけではなく、施策の実施に係る事務もつかさどることとされた。この起草案は、同日、賛成多数で委員会提出法律案とすることが可決された9。あわせて、同委員会には、3会派提出の起草案に付随する「地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件」が付託された。
本法律案については、6月10日の(衆)本会議においても賛成多数で可決され、13日には(参)本会議で(参)東日本大震災復興特別委員会の設置が可決されるとともに、趣旨説明・質疑がなされた。(参)東日本大震災復興特別委員会においては、同日、本法律案の提案理由説明、翌14日から質疑が行われ、20日に賛成多数で可決、同日の(参)本会議においても賛成多数で可決・成立し、同月24日に公布・施行された。
東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号。以下「基本法」という。)の国会審議においては、主に以下の点について議論がなされた。
- 8 東日本大震災に対処するため、当分の間、国務大臣、内閣総理大臣補佐官、内閣府副大臣及び内閣府大臣政務官を増員することを内容とするもの。
- 9 同案が復興財源のための増税を示唆している等の理由から、みんなの党及び共産党が反対。
1) 復興庁の設置
復興を担う国の組織について、政府案においては、内閣総理大臣を長とする復興対策本部が政策の企画・立案や省庁間の調整を担い、被災地には現地対策本部を置いて国の出先機関や省庁間の調整を行うこととした。また、附則において、復興対策本部を引き継ぐ復興庁の在り方について、今後、総合的な検討を加え1年以内に設置を目指すこととした。これに対して、自民党案は、復興に関する基本計画を一元的に策定し、施策を実施する組織として、内閣に「東日本大震災復興再生院」を設置し、復興担当大臣がこれを率いることとし、公明党案でも、「東日本大震災復興庁」に施策の実施までの役割を持たせることとしていた。
こうした相違が調整された結果、6月9日の3会派提出の起草案では、本則に第4章として、復興庁の設置に関する基本方針が設けられ、復興対策本部から復興庁へのできるだけ早期の移行について規定されることとなった。また、その所掌については、震災からの復興に関する施策の企画・立案、総合調整に加え、復興に関する施策の実施に係る事務その他必要な事務を実施することとされた。同月13日の(参)本会議では、法案提案者から復興庁創設の意義として、
・ 復興施策の各省庁の縦割りの弊害を打破し、政府として被災者の方々や地方公共団体のニーズをワンストップで一元的に引き受け、迅速に対応することを狙いとするスーパー官庁として創設するもの
・ 復興対策本部の役割が企画・立案、総合調整にとどまるのに対し、復興庁は、それらに加え、施策の実施に関する事務、いわゆる分担管理事務まで行う権限を有すること
・ 行政組織上の位置付けとして、普通の省庁と同じように横並びの組織ではなく、内閣府と同様に、内閣に置かれ、内閣総理大臣が主任の大臣となり、その命を受けて一切の事務を統括する復興担当大臣の指揮監督の下に事務を執行する機関であること
といった点が挙げられている10。
- 10 平成23年6月13日、加藤勝信議員(自由民主党)(第177回国会(参)本会議録第21号8頁)。
2) 復興特区制度の整備
公明党案に盛り込まれた復興特区制度については、3会派提出の起草案においても復興特別区域制度の整備として第10条に規定されることとなった。
6月13日の(参)本会議では、法案提案者からその趣旨について、
・ 被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、復興特区制度を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図ることが定められ、このために必要な復興特区制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるもの
・ 公明党の主張が民主、自民の両党の理解を得て本法律案に取り入れられた
との説明がなされた11。
また、(参)東日本大震災復興特別委員会では、特区制度整備の進め方等について議論され、枝野官房長官からは、
・ 既存の構造改革特区制度に比べ、復興特区は、地域における創意工夫を生かして行われる復興に向けた取組の推進を図るための仕組みであるため、より広範に規制の特例措置に加えて、被災地域の様々な支援措置が制度のメニューとして総合的に盛り込まれる必要がある
・ 当面は復興対策本部の下、復興対策の担当大臣やその下の事務局のもとで一体的にこの特区制度を運用し、できるだけ早く具体的な中身の法案等も国会に御審議をお願いしたい
旨述べられている12。
- 11 平成23年6月13日、石田祝稔議員(公明党)(第177回国会(参)本会議録第21号9頁)。
- 12 平成23年6月15日、枝野内閣官房長官(民主党)(第177回国会(参)東日本大震災復興特別委員会会議録第3号24頁)
3) 復興財源
政府案及び自民党案が審議された5月23日の (衆)東日本大震災復興特別委員会では、政府案に復興の財源について明確な規定がないことに対する指摘が相次ぎ、自民党案に規定された「復興再生債」、公明党案で示された歳出の徹底削減や国会の議決を経て復興債を発行すること等に対する所感について菅直人内閣総理大臣からは、これに先立つ民自公3党の合意13を踏まえ、共通の考え方で検討を進めたい旨答弁があった14。
このような議論も踏まえ、3会派提出の起草案においては、第7条で資金確保のための措置として、復興以外の施策に係る予算の徹底的な見直しによる歳出削減や財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ることが規定されるとともに、第8条において、
・ 別に法律で定めるところにより、復興債を発行するものとすること
・ 復興債は他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置により、あらかじめその償還の道筋を明らかにすること
が規定されることとなった。
- 13 「平成23年度第一次補正予算等に関して」(平成23年4月29日民主党政策調査会長・自由民主党政務調査会長・公明党政務調査会長合意書)において、「復旧・復興のために必要な財源については、既存歳出の削減とともに、復興のための国債の発行等により賄う。復興のための国債は、従来の国債と区別して管理し、その消化や償還を担保する」こととされた。
- 14 平成23年5月23日、菅直人内閣総理大臣(民主党)「財源については、確かに政府案に余り詳しくは書いてありませんが、これは、せんだって御党と自民党と我が党の間で合意をした中で、政調会長同士で合意をされた中で、御党の考え方も我が党としても共通な考え方でやっていきたい、このことを申し上げておりますので、政府案としては入っておりませんけれども、党としてはそうした考え方を持っております。」(第177回国会(衆)東日本大震災復興特別委員会会議録 第2号28頁)
| 政府案 | 自民党案 | 公明党案 | 基本法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本理念 | 被災地域の復興の基本理念 ・災害復旧にとどまらない抜本的な対策推進 ・人類共通の課題解決に資する先導的取組 |
東日本大震災からの復興再生の基本理念 ・二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿の実現 |
東日本大震災からの復興の基本理念 ・一人一人に光を当てた「人間の復興」 ・原子力災害被災地域の復興への配慮 |
東日本大震災からの復興の基本理念 ・災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を者に入れた抜本的な対策 ・一人一人の復興、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿の実現 ・人類共通の課題解決に資する先導的取組 ・原子力災害被災地域の復興への配慮 |
|
| 責務等 | ・国、地方公共団体による必要な措置の実施 |
・国の復興再生基本計画、自治体の復興再生計画の策定 ・国、自治体による必要な施策の実施 ・国民の互助 |
・国の復興基本指針、自治体の復興計画の策定 ・国民の互助 |
・国の復興基本方針の策定 ・国、地方公共団体による必要な措置の実施 ・国民の互助 |
|
| 財源 | - | ・復興再生債の発行 |
・復興債の発行 |
・復興債の発行 |
|
| 特区 | - | - | ・別法で特区の指定 |
・別法で特区制度の整備 |
|
| 組織 | ・東日本大震災復興対策本部 |
・東日本大震災復興再生院 |
・東日本大震災復興庁 |
・東日本大震災復興対策本部(復興庁設置時に廃止) |
・復興庁(別途法律で設置) |
| 所掌 | ・基本的方針の企画・立案、総合調整 ・関係行政機関の復興施策の実施の推進・総合調整 |
・復興再生に関する企画・立案、総合調整 ・施策の実施 |
・復興に関する企画・立案、総合調整 ・施策の実施 |
・復興基本方針の企画・立案、総合調整 ・関係行政機関の復興施策の実施の推進・総合調整 |
・復興に関する施策の企画・立案・総合調整 ・施策の実施 |
| 体制 | ・本部長:内閣総理大臣、副本部長:内閣官房長官及び復興対策担当大臣 |
・広く行政組織の内外から人材を登用 |
・復興庁を所管する専任担当大臣任命 ・幅広く人材を登用 |
・本部長:内閣総理大臣、副本部長:内閣官房長官及び復興対策担当大臣 |
- |
| 現地 | ・現地対策本部 |
・地方復興再生事務所 |
・地方支分部局 |
・現地対策本部 |
(復興対策本部から引継ぎ) |
| 会議等 | ・東日本大震災復興構想会議 ・原子力災害被災地域の復興に関する合議制の機関 |
・東日本大震災復興再生委員会 |
・東日本大震災復興委員会 |
・東日本大震災復興構想会議 ・原子力災害被災地域の復興に関する合議制の機関 |
(復興対策本部から引継ぎ) |
| 現地 | ・復興庁の設置について法律施行後一年以内を目途に必要な法制上の措置の実施 |
・復興再生院の所掌事務及び権限について、被災した県及び市町村に段階的に移譲 |
|||
(3) 法概要・措置内容
1) 概要・目的
基本法は、東日本大震災からの復興の迅速な推進と、活力ある日本の再生に向け、復興に当たっての基本理念及び組織の在り方、資金確保などの基本となる事項を定めたものである。また、上述のとおり、政府案と自民党案及び公明党案との調整が図られた結果、民主党・自由民主党・公明党が共同で提出した起草案によるものである。
具体的には、東日本大震災復興対策本部の内閣への設置、これを引き継ぐ復興庁の設置に関する基本方針、別に法律で定めるところによる復興債の発行や復興特区の創設等に係る規定が盛り込まれている。
2) 基本理念・国の責務等
法第2条において、東日本大震災からの復興の基本理念として、
① 単なる災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を視野に入れた抜本的な対策及び一人 一人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる施策の推進により、新たな地域社会の構築、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと
② 国と地方公共団体との適切な役割分担・連携協力、全国各地の地方公共団体の相互の連携協力の確保とともに、被災地域の住民意向が尊重され、女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見の反映されるべきこと
③ 被災者を含む国民一人一人の連帯・協力を基本とすべきこと
④ 人口減少や国境を越えた社会経済活動の進展への対応等の我が国が直面する課題や、食料問題・エネルギーの利用制約や環境負荷等の人類共通の課題の解決に資する先導的な施策に取り組まれるべきこと
⑤ 安全な地域づくり・雇用創出と社会経済の再生・地域の文化振興と絆の維持強化及び共生社会の実現のための施策が推進されるべきこと
等が掲げられた。
また、法第3条から第5条において、
・ 国の責務として東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針を定め、必要な措置を講ずること
・ 地方公共団体の責務として当該方針を踏まえ必要な措置を講ずること
・ 国民は、相互扶助と連帯の精神に基づき、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとすること
が規定された。
3) 基本的施策
a. 復興のための資金の確保
法第7条において、国は、復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る歳出の削減、財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること等により、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとされた。
また、第8条において、国は、別に法律で定めるところにより、復興債を発行するものとされ、復興債については、その他の公債と区別して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとされた。
なお、これらの規定に基づき、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定・同年8月11日改定)等も踏まえて、東日本大震災の復興財源についての法制化を目的として、税外収入に関する措置及び復興特別税の創設、復興債の発行等の措置等を規定する「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布・施行された。
b. 復興特別区域制度の整備
法第10条において、政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(復興特別区域制度)を活用し、地域の創意工夫を生かした東日本大震災からの復興に向けた取組を推進することとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとされた。
なお、当該規定に基づき、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定・同年8月11日改定)等も踏まえて、復興特別区域制度を具体化する東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)が平成23年12月14日に公布、同月26日に施行された。
4) 東日本大震災復興対策本部の設置
法第11条から第23条において、東日本大震災復興対策本部の設置をはじめ、その所掌事務や組織等について以下のとおり規定された。
・ 内閣に、東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
・ 本部は、法第3条に規定する東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針の企画・立案、総合調整に関する事務等を司る。
・ 本部長は内閣総理大臣、副本部長は内閣官房長官及び東日本大震災復興対策担当大臣とする。
・ 本部員は次の者とする。
- 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣
- 内閣官房副長官、関係府省の副大臣もしくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指名する者
・ 本部の地方機関として、所要の地に現地対策本部を置き15、関係府省の副大臣、大臣政務官等のうちから、内閣総理大臣が指名する者を現地対策本部長とする。
・ 本部の諮問機関として、被災地域の復興に関する重要事項を調査審議する東日本大震災復興構想会議を設置するとともに16、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で規定する合議制の機関を設置する。
なお、東日本大震災復興対策本部については、1章2節及び2章2節もあわせて参照のこと。
- 15 現地対策本部の名称、位置及び管轄区域は政令で定めることとされており、平成23年6月24日に公布・施行された東日本大震災復興対策本部令(平成23年政令第182号)により、岩手現地対策本部、宮城現地対策本部及び福島現地対策本部が設置された。
- 16 東日本大震災復興構想会議は、「東日本大震災復興構想会議の開催について」(平成23年4月11日閣議決定)に基づき、基本法の制定前から開催されていたが、同法の施行により法定の審議会となった。
5) 復興庁の設置
法第24条において、復興庁の設置に関する基本方針として以下のとおり規定された。
・ 別に法律で定めるところにより、内閣に、期限を限って、復興庁を設置する。
・ 復興庁は、東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に加え、その実施に係る事務を司る。
・ 本部は、復興庁設置の際に廃止し、本部及び本部に置かれる組織の機能は、復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれる。
・ 復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、必要な措置について検討し、可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずる。
なお、当該規定に基づき、所要の検討を経て、復興庁設置法(平成23年法律第125号)は、平成23年12月16日に公布、平成24年2月10日に施行された。
(下線部は主な相違点)
| 政府案 | 基本法(制定時) |
|---|---|
(目的) 第一条 この法律は、東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において未曽有の災害であることに鑑み、被災地域の復興についての基本理念を明らかにするとともに、東日本大震災復興対策本部の設置等を定めることにより、被災地域の復興を迅速に推進して被災地域の社会経済の再生及び生活の再建を図り、もって現在及び将来の世代にわたって国民経済を健全に発展させ、及び国民生活を向上させることに寄与することを目的とする。 |
第一章 総則 (目的)第一条 この法律は、東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、東日本大震災からの復興のための資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めること等により、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図ることを目的とする。 |
| (基本理念) 第二条 被災地域の復興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 一 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており、かつ、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国各地における企業活動や国民生活に支障を及ぼしている等その影響が広く全国に及んでいることを踏まえ、国民一般の理解と協力の下に、単なる災害復旧にとどまらない抜本的な対策が推進されるべきこと。この場合において、行政の内外の知見が集約され、その活用がされるべきこと。 |
(基本理念) 第二条 東日本大震災からの復興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 一 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており、かつ、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国各地における企業活動や国民生活に支障を及ぼしている等その影響が広く全国に及んでいることを踏まえ、国民一般の理解と協力の下に、被害を受けた施設を原形に復旧すること等の単なる災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を視野に入れた抜本的な対策及び一人一人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる復興のための施策の推進により、新たな地域社会の構築がなされるとともに、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと。この場合において、行政の内外の知見が集約され、その活用がされるべきこと。 |
二 国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力並びに全国各地の地方公共団体の相互の連携協力が確保されるとともに、被災地域の住民の意向が尊重されるべきこと。この場合において、被災により本来果たすべき機能を十全に発揮することができない地方公共団体があることへの配慮がされるべきこと。 |
二 国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力並びに全国各地の地方公共団体の相互の連携協力が確保されるとともに、被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと。この場合において、被災により本来果たすべき機能を十全に発揮することができない地方公共団体があることへの配慮がされるべきこと。 |
三 国民の相互の連帯を基本とし、国民、事業者その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと。 |
三 被災者を含む国民一人一人が相互に連帯し、かつ、協力することを基本とし、国民、事業者その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと。 |
四 少子高齢化及び人口の減少への対応等の我が国が直面する課題や、エネルギーの利用の制約、環境への負荷等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと。 |
四 少子高齢化、人口の減少及び国境を越えた社会経済活動の進展への対応等の我が国が直面する課題や、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと。 |
五 次に掲げる施策が推進されるべきこと。 イ 何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策 ロ 被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策 ハ 地域の特色ある文化の振興並びに地域社会の絆の維持及び強化を図るための施策 |
五 次に掲げる施策が推進されるべきこと。 イ 地震その他の天災地変による災害の防止の効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策 ロ 被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策 ハ 地域の特色ある文化を振興し、地域社会の絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策 |
六 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。 |
六 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。 |
| (国の講ずる措置) 第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、被災地域の復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずるものとする。 |
(国の責務) 第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針(以下「東日本大震災復興基本方針」という。)を定め、これに基づき、東日本大震災からの復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずる責務を有する。 |
| (地方公共団体の講ずる措置) 第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、被災地域の復興に必要な措置を講ずるものとする。 |
(地方公共団体の責務) 第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。 |
| (国民の努力) 第五条 国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。 |
|
| 第二章 基本的施策 (復興に関する施策の迅速な実施) 第六条 国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第三条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。 |
|
| (資金の確保のための措置) 第七条 国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。 一 復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。 二 財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること。 |
|
| (復興債の発行等) 第八条 国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。 2 国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。 |
|
| (復興に係る国の資金の流れの透明化) 第九条 国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。 |
|
| (復興特別区域制度の整備) 第十条 政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(以下「復興特別区域制度」という。)を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。 |
|
(東日本大震災復興対策本部の設置) 第五条 内閣に、東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を置く。 |
第三章 東日本大震災復興対策本部 (設置) 第十一条 内閣に、東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を置く。 |
| (東日本大震災復興対策本部の所掌事務) 第六条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 被災地域の復興のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 二 関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる被災地域の復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務 三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務 |
(所掌事務) 第十二条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 二 関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務 三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務 |
| (東日本大震災復興対策本部長) 第七条 本部の長は、東日本大震災復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 |
(東日本大震災復興対策本部長) 第十三条 本部の長は、東日本大震災復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 |
| (東日本大震災復興対策副本部長) 第八条 本部に、東日本大震災復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東日本大震災復興対策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、被災地域の復興のための施策の推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 |
(東日本大震災復興対策副本部長) 第十四条 本部に、東日本大震災復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東日本大震災復興対策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 |
| (東日本大震災復興対策本部員) 第九条 本部に、東日本大震災復興対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣 二 内閣官房副長官、関係府省の副大臣若しくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者 |
(東日本大震災復興対策本部員) 第十五条 本部に、東日本大震災復興対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣 二 内閣官房副長官、関係府省の副大臣若しくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者 |
| (幹事) 第十条 本部に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。 |
(幹事) 第十六条 本部に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。 |
| (現地対策本部) 第十一条 本部に、第六条(第一号を除く。)に規定する事務の一部を分掌させるため、地方機関として、所要の地に現地対策本部を置く。 2 現地対策本部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 現地対策本部に現地対策本部長を置き、関係府省の副大臣、大臣政務官その他の職を占める者のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。 4 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。 5 現地対策本部に現地対策本部員を置き、国の関係地方行政機関の長その他の職員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。 |
(現地対策本部) 第十七条 本部に、第十二条(第一号を除く。)に規定する事務の一部を分掌させるため、地方機関として、所要の地に現地対策本部を置く。 2 現地対策本部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 現地対策本部に現地対策本部長を置き、関係府省の副大臣、大臣政務官その他の職を占める者のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。 4 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。 5 現地対策本部に現地対策本部員を置き、国の関係地方行政機関の長その他の職員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。 |
| (東日本大震災復興構想会議の設置等) 第十二条 本部に、東日本大震災復興構想会議を置く。 2 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 本部長の諮問に応じて、被災地域の復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。 二 被災地域の復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。 3 東日本大震災復興構想会議は、議長及び委員二十五人以内をもって組織する。 4 議長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 |
(東日本大震災復興構想会議の設置等) 第十八条 本部に、東日本大震災復興構想会議を置く。 2 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 本部長の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。 二 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。 3 東日本大震災復興構想会議は、議長及び委員二十五人以内をもって組織する。 4 議長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 |
| (原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関) 第十三条 前条第一項に定めるもののほか、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない。 |
(原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関) 第十九条 前条第一項に定めるもののほか、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない。 |
| (資料の提出その他の協力の要請) 第十四条 東日本大震災復興構想会議及び前条に規定する合議制の機関(以下「東日本大震災復興構想会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。 2 東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 |
(資料の提出その他の協力の要請) 第二十条 東日本大震災復興構想会議及び前条に規定する合議制の機関(以下「東日本大震災復興構想会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。 2 東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 |
| (事務局) 第十五条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。 2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。 3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 4 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。 5 事務局に、現地対策本部に対応して、事務局の所掌事務のうち当該現地対策本部に係るものを処理させるため、現地対策本部事務局を置く。 |
(事務局) 第二十一条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。 2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。 3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 4 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。 5 事務局に、現地対策本部に対応して、事務局の所掌事務のうち当該現地対策本部に係るものを処理させるため、現地対策本部事務局を置く。 |
| (主任の大臣) 第十六条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 |
(主任の大臣) 第二十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 |
| (政令への委任) 第十七条 第五条から前条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 |
(政令への委任) 第二十三条 この章に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 |
| 第四章 復興庁の設置に関する基本方針 第二十四条 別に法律で定めるところにより、内閣に、復興庁(第三項に規定する事務を行う行政組織をいう。以下同じ。)を設置するものとする。 2 復興庁は、期間を限って、置かれるものとする。 3 復興庁は、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する国の施策に関し、次に掲げる事務をつかさどるものとし、当該事務の効率的かつ円滑な遂行が確保されるよう編成するものとする。 一 東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関する事務 二 東日本大震災からの復興に関する施策の実施に係る事務 三 その他東日本大震災からの復興に関し必要な事務 4 本部は、復興庁の設置の際に廃止するものとし、本部並びに現地対策本部、東日本大震災復興構想会議等及びその他の本部に置かれる組織の機能は、復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとする。 5 復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、前各項に定めるところにより、復興庁を設置するために必要な措置について検討を行い、可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずるものとする。 |
|
| 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 |
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 |
| (検討) 第二条 政府は、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、被災地域の復興のための施策を推進するための行政組織の在り方を見直し、復興庁(東日本大震災により被害を受けた特定の地域の復興のための行政各部の施策の統一を図るため必要となる事項の企画及び立案並びに総合調整を行う行政組織をいう。以下同じ。)を設置すること、復興庁の設置についてはその期間を限るものとすることその他復興庁に関し必要な事項について総合的に検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後一年以内を目途として必要な法制上の措置を講ずるものとする。 |
(4) 改正経過・概要等
平成24年2月10日に施行された復興庁設置法附則第8条により、本部について規定された法第3章(第11条から第23条まで)が削除された。あわせて、政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない旨を定める法第10条の2の規定が追加された。
(5) 適用実績
本法律の適用実績については、1章2節を参照のこと。
2. 復興庁設置法(平成23年法律第125号)
2章2節で記載。
3. 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)
(1) 東日本大震災復興特別区域法
1) 立案経緯・制定趣旨
平成23年6月24日に公布された東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号。以下「復興基本法」という。)第10条において、「政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに法律上の措置を講ずるものとする」と規定された。さらに、東日本大震災復興構想会議による提言(平成23年6月25日)においても、被災地のまちづくりや被災地経済の再生のため、「特区」手法を活用することが有効と提言された。
東日本大震災からの復興の基本方針(平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定)においては、地域が主体となった復興を強力に支援するため、オーダーメードで地域における創意工夫を生かし、旧来の発想にとらわれず、区域限定で思い切った規制・制度の特例や経済的支援などの被災地からの提案を一元的かつ迅速に実現する復興特区制度を創設すること、及び地方公共団体が自ら策定する復興プランの下、復興に必要な各種施策が展開できる使い勝手のよい自由度の高い交付金を創設することについて位置付けられた。
2) 国会審議等
a. 国会審議、公布・施行経緯
東日本大震災は、これまでにない未曽有の被害を各地域にもたらしたものであり、その復興を加速させるためには、前例や既存の枠組みにとらわれず、地域限定で思い切った措置をとることが必要とされていた。また、被災状況や復興の方向性が地域により様々であることから、地域の創意工夫を生かしたオーダーメードの仕組みが必要であり、あわせて、被災した地方公共団体の負担を極力減らし、迅速な対応を可能とするため、規制・手続の特例や税制、財政、金融上の特例をワンストップで総合的に適用する仕組みが必要とされた。
このような考え方に立ち、東日本大震災復興特別区域法案は、平成23年10月28日に国会に提出された。同法案は、衆議院東日本大震災復興特別委員会において審査を行う中で、修正に向けた議論が行われ、新たな規制と特例措置等に関する提案に関する事項、国と地方の協議会における協議結果の尊重義務に関する事項、復興交付金に関する事項等についての修正を内容とする修正案が、11月29日に民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、国民新党・新党日本及びたちあがれ日本の議員により提出された。修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも委員会、本会議において全会一致で可決され、参議院に送付された。参議院においては、11月30日の本会議で趣旨説明及び質疑を行った後、東日本大震災復興特別委員会で趣旨説明聴取、質疑を行い、採決の結果、全会一致で可決された。12月7日の本会議においても全会一致で可決・成立した。
《国会における審議経過》
・ 平成23年11月18日 衆議院本会議において審議
・ 平成23年11月18日 衆議院東日本大震災復興特別委員会において趣旨説明聴取
・ 平成23年11月21日、11月22日、11月24日、11月25日 衆議院東日本大震災復興特別委員会において審議(議案修正前)
・ 平成23年11月29日 衆議院東日本大震災復興特別委員会において3件の修正案が提出。民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、国民新党・新党日本及びたちあがれ日本の5会派共同提案による修正案及び修正部分を除く原案が可決(全会一致)。併せて、7項目の附帯決議が付された(全会一致)。
・ 平成23年11月29日 衆議院本会議において修正議決
・ 平成23年11月30日 参議院本会議において審議
・ 平成23年11月30日 参議院東日本大震災復興特別委員会において趣旨説明聴取
・ 平成23年12月1日 参議院東日本大震災復興特別委員会において審議
・ 平成23年12月2日 参議院東日本大震災復興特別委員会において修正案が提出され、賛成少数により否決。衆議院で修正された議案を可決(全会一致)。併せて、8項目の附帯決議が付された(全会一致)。
・ 平成23年12月7日 参議院本会議において議了処理
・ 平成23年12月14日 公布
・ 平成23年12月26日 施行
b. 法概要
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)の施行時における全体概要は、以下のとおりである。
第一に、政府は、復興基本法の基本理念に則り、かつ、東日本大震災からの復興の基本方針に基づき、復興特別区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が実施すべき施策等を内容とする復興特別区域基本方針を定めなければならないこととされた。
第二に、被災地域(222市町村(平成24年2月からは227市町村))の地方公共団体は、単独で又は他の地方公共団体と共同して復興推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることができるものとするとともに、その認定を受けたときは、各種規制・手続の特例措置、税・金融上の支援措置の適用を受けることができるものとされた。
また、地域における創意工夫を生かして復興を推進していくため、被災地域の地方公共団体は、新たな規制の特例措置その他の措置について、政府に対し提案をできることとされ、国と地方の協議会が組織されている場合は、当該協議会における議題とすることとされるほか、国会に対しても復興特別意見書を提出することができることとされた。
第三に、被災地域の市町村であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業等を実施する必要がある地域をその区域とするものは、単独で又は都道県と共同して復興整備計画を作成することができるものとするとともに、復興整備計画が所要の協議等の手続を経た上で公表されたときは、土地利用基本計画等の変更や土地利用に係る許認可等がなされたものとみなす等の特別の措置の適用を受けることができるものとされた。
第四に、被災地域の市町村は、単独で又は都道県と共同して、東日本大震災により相当数の住宅等に著しい被害を受けた地域の復興のために実施する必要がある事業に関して復興交付金事業計画を作成し、内閣総理大臣に提出することができるものとするとともに、国の予算の範囲内で、提出された計画に係る事業等の実施に要する経費に充てるための復興交付金の交付を受けることができるものとされた。
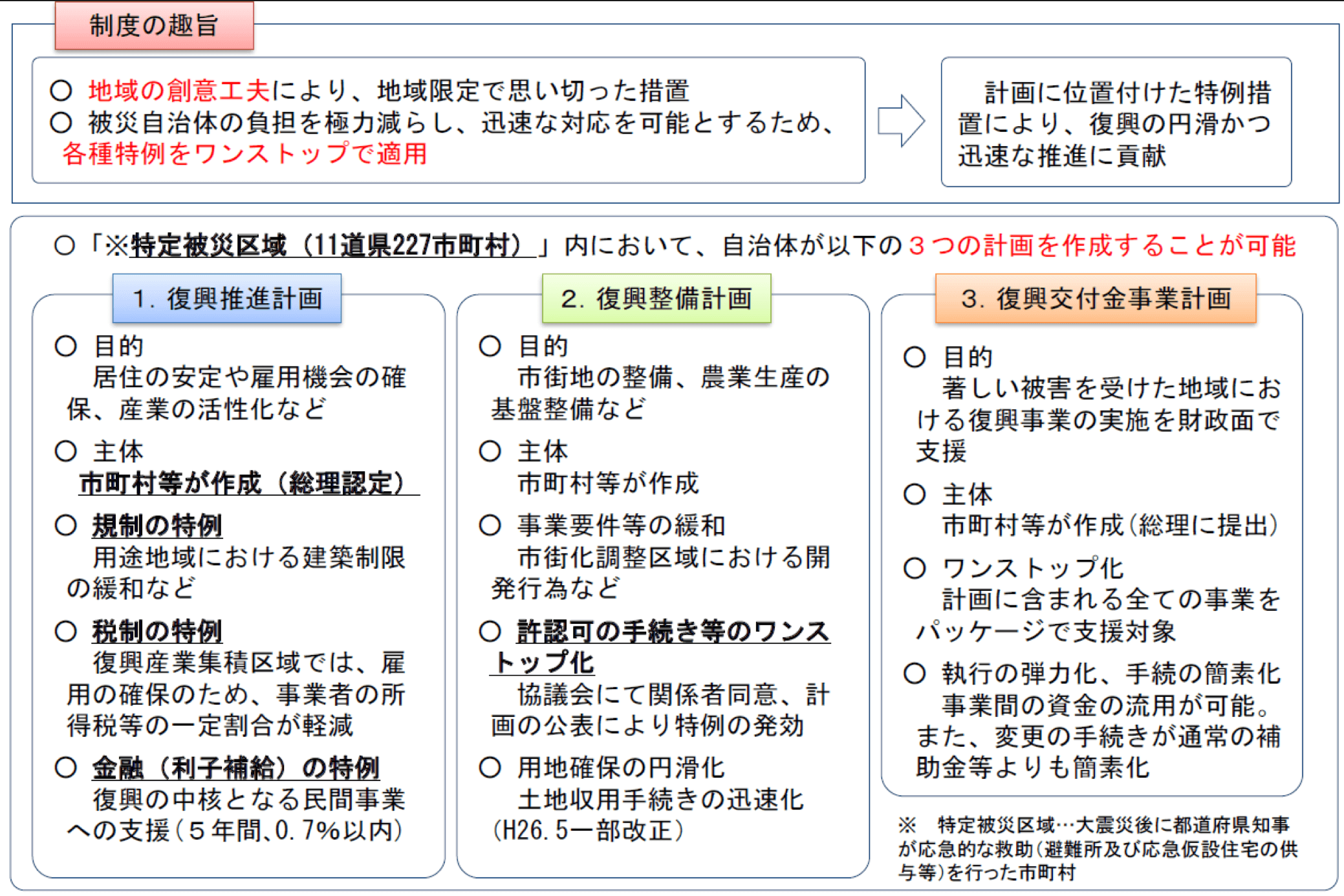
c. 国会審議における主な論点及び議員修正
復興特区法の審議においては、国と地方の協議会の実効性の確保、漁業法に係る規制の特例措置を設けた理由、復興交付金の使途等について質疑が行われた。
衆議院において、法案の修正がなされた主な内容は以下のとおりである。
① 認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等について、国会に対して復興特別意見書を提出できること、国会が当該意見書の提出を受けた場合に必要があると認められるときは、所要の法制上の措置を講ずることに関する規定が追加された。
② 復興に関する施策の推進に関して協議を行うための国と地方の協議会において、協議がととのった場合に必要があるときは、内閣総理大臣等は、速やかに所要の法制上の措置等を講じなければならないこと、内閣総理大臣は、同協議会の協議結果を国会に報告するとともに、国会は当該報告を受けた場合に必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずることに関する規定が追加された。
③ 復興交付金事業計画に記載する事項のうち、いわゆる効果促進事業に、基幹事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業等を含めるとともに、国は必要があると認めるときは、特定地方公共団体等が講ずる措置であって、原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができることに関する規定が追加された。
3) 改正経過・概要
復興特区法は、平成26年の復興特区法改正及び令和2年の復興特区法等改正において、実質的な改正がなされてきた。以下において、令和2年の復興特区法等改正における対象地域の重点化について、概要を示す。なお、平成26年の復興特区法改正については、(5)復興整備計画で詳述する。
未曽有の複合災害であった東日本大震災による被害に対し、前例のない支援等を実施したことにより、復興は大きく前進し、地震・津波被災地域では復興の総仕上げの段階に入り、原子力災害被災地域においても、復興・再生が本格的に始まっている等の状況を踏まえ、「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針(令和元年12月20日閣議決定)においては、復興特区法について、「規制の特例、復興整備計画、金融の特例について、これまでの復興状況や必要となる事業の見込みも考慮しつつ、対象地域を重点化した上で、必要な支援を継続する」、「復興特区税制について、津波被害が甚大な地域には、人口や働く場等の減少が著しいにもかかわらず、区画整理事業等による基盤整備に時間を要し、企業立地等が進んでいない地域が残ると見込まれることから、著しい被害を受けた地域が引き続き、着実に産業復興に取り組めるよう、復興特区法を改正し、対象地域を重点化した上で、適用期限の延長等を行うことについて検討する」と位置付けられた。
こうしたことを受け、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、第1期復興・創生期間後の復興を支える仕組み、組織及び財源について必要な法律上の手当てを盛り込んだ令和2年復興特区法等改正法が成立した。令和3年4月に施行された同法においては、特例措置を活用することのできる対象地域の重点化等がなされた。
具体的には、復興特区法第4条第1項において定められる、復興推進計画を作成できる地域については、これまでの復興状況や事業の見込み等を踏まえ、復興の課題が引き続き集中している地域に重点化することとされ、岩手県沿岸部の12市町村の区域、宮城県沿岸部の15市町の区域及び福島県の59市町村の区域とされた(具体的には、復興特区法施行令にて規定)。
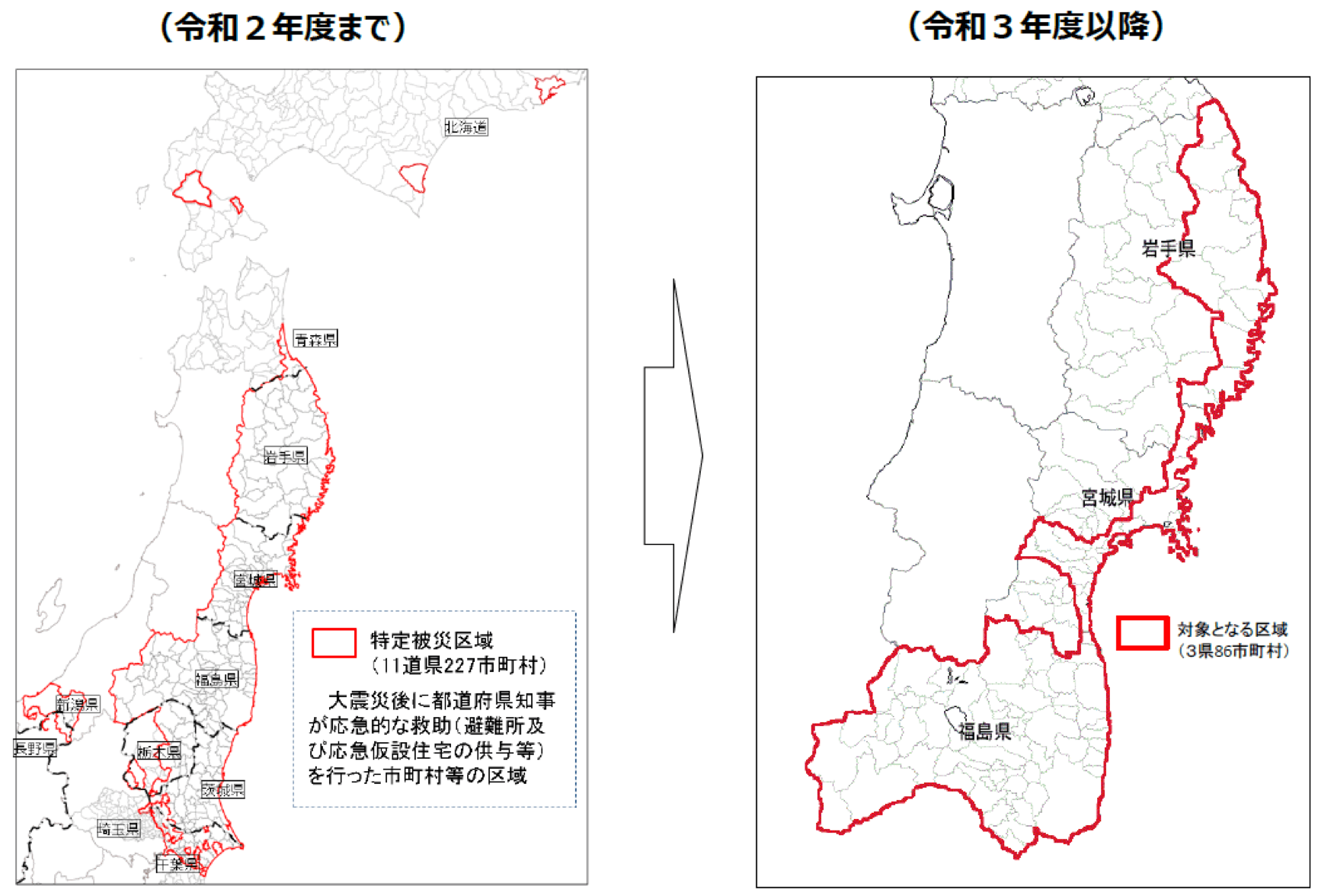
4) 適用実績
これまでに、復興推進計画は、令和4年9月時点で、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県の7県の管内で、307計画が作成されている。
また、復興整備計画は、令和4年9月時点で、岩手県、宮城県及び福島県の3県の管内の1,034地区において、当該計画に位置付けられた事業が施行されている。
復興推進計画や復興整備計画については、被災地の産業復興や、復興まちづくりの目標の実現に貢献している。例えば、令和4年9月時点の集計では、税制上の特例の適用を受けるために指定を受けている者は延べで6千を超え、また、指定を受けた者による投資も延べで4兆円を超えている。また、金融上の特例の適用を受けた案件における総投資額は1兆円を超えている。
以下において、新たな規制の特例措置等の提案制度について言及した後、規制の特例、金融上の特例、復興整備計画の各特例の概要、適用実績及び効果等について記述していく。なお、復興特区税制については2章4節で、復興交付金については3章1節で詳しく取り上げることとし、本節では取り扱わない。
(2) 新たな規制の特例措置等の提案制度
復興特区制度については、被災地域の住民の意向を尊重するとともに、地域における創意工夫を生かして推進していく必要がある。このため、復興特区法第11条において、特定地方公共団体等は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置等を提案できることとしている。
また、復興特区法第12条により、内閣総理大臣、内閣総理大臣が指定する国務大臣及び認定地方公共団体等の長は、都道府県の区域ごとに、新たな規制の特例措置等の整備等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとしている。
新たな規制の特例等の提案による国と地方の協議会は、令和4年までに以下のとおり2回開催された。
a. 宮城県における国と地方の協議会
平成24年8月7日、内閣総理大臣並びに宮城県知事及び宮城県内34市町村の長は、宮城県における国と地方の協議会を設置し、宮城県から提出された新たな規制の特例措置等の提案について協議を行った。
宮城県からの提案は、①特別控除の適用による防災集団移転促進事業の推進のための特例(防災集団移転促進事業の移転先の土地売却について、5,000万円控除を適用)、②45フィートコンテナ利用促進のための特例、③保育サービス確保のための保育所整備の補助対象の拡大、④復興特区における税制上の特例措置の期間延長、適用要件の緩和の4点であった。
①については、宮城県の提案を踏まえ、平成25年度税制改正要望が行われ、税制上の措置が実現した。②、③については、現行の交付金制度や補助制度、既存税制の活用等により対応が可能なことから、宮城県においてこれらの活用を検討してもらうこととし、平成25年度予算概算要求は行わなかった。④については、復興特区法第40条に基づく新規立地促進税制における適用要件の緩和措置が実現した。
b. 岩手県における国と地方の協議会
平成25年9月11日、内閣総理大臣及び岩手県知事は、岩手県における国と地方の協議会を設置した。さらに同月17日、同協議会を開催し、岩手県から提出された新たな規制の特例措置の提案について協議を行った。
岩手県からは、再生可能エネルギー(風力・地熱)を活用した自立・分散型エネルギー体制の確立のための特例措置について提案があった。同県の提案は、再生可能エネルギーによる発電事業を定めた復興推進計画について認定を受けたときは、優良農地の確保に支障を生じないことを前提に、農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定により許可を受けるべきものに対し、これらの許可があったものとみなすこととしてほしいといった内容であった。
その後、平成25年11月15日、第185回臨時国会において「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」が成立し、再生可能エネルギー発電設備の整備に係る農地転用許可制度上の取扱いについて、全国的な制度として実現した。
(3) 規制の特例
規制の特例については、復興特区法第14条から第36条までに規定されており、法制定時、計20の特例が定められた。
令和4年3月末時点で、規制の特例については、計42の復興推進計画が認定されている(青森県1、岩手県8、宮城県18、福島県6、茨城県6、栃木県1、千葉県2)。なお、復興推進計画には複数の特例を盛り込むことが可能なため、1計画に複数の規制特例が盛り込まれている場合も多く見られる。
以下、条文の順に規制の各特例の概要及び適用実績等について記述していく。
1) 特区区画漁業権免許事業(復興特区法第14条)
a. 概要
復興特区法第14条に基づく措置である。漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正漁業法」という。)により、特例の対象となる規定が廃止されたため規定削除となった。
改正漁業法による改正前の漁業法(昭和24年法律第267号。以下「旧漁業法」という。)においては、沿岸の一定区域の漁場を占有し、生け簀やいかだの敷設等により行う水産動植物の養殖の事業について、漁業の安定的な利用の観点から、都道府県知事によって免許される漁業権に基づき行うこととされており(漁業法第9条及び第10条)、この知事の免許は「優先順位をよつてする」と規定されていた(漁業法第15条)。水産動植物の養殖の事業を対象とする「特定区画漁業権」については、自ら漁業を営まない地元の漁協が第1順位として法定され(漁業法第18条)、実態的にはそのような漁協がほぼ全ての免許を取得していた。
三陸地域が全国の一大生産拠点となっている養殖業については、養殖施設の壊滅的な被害に加えて、多数の漁業者が犠牲となり、担い手の確保の見通しも立たなくなるなど未曾有の被害を受け、自力での復興が困難な地域が存在していた。こうした養殖施設や人材確保等が困難で、地元漁業者のみでは養殖業の再開が困難な地域では、外部の企業等と連携して支援を得ながら再建を図る等の取組の推進が課題となっていた。
本特例では、地元漁業者主体の法人に対して県知事が直接免許を付与することを可能とすることとし、地元漁業者のみでは養殖業の再建が困難と認められる地元地区に係る特定区画漁業権の免許を事業内容として定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、地元漁業者主体の一定の法人であって経済的基礎や漁業との協調等に係る審査基準を満たすものについて、漁業権の優先順位規定の適用を除外し、第一順位として免許することができるものとした。
なお、法制定時の国会審議においては、地元漁民を7割以上含む法人又は地元漁民を7人以上含む法人に対しても、第一順位として県知事が免許をすることができる旨の特例が設けられたことに対し、浜の秩序の崩壊や地元漁民が職を失うことについての懸念が示された。これに対し、当時の農林水産大臣は、知事が直接免許を付与できる法人の要件として、他の漁業者と協調すること、経理的基礎を有すること等の法定基準を満たしたものとすることとするなど、漁業者の懸念に応える規定を設けている旨の見解を示した。
b. 適用実績・効果
本特例について策定された復興推進計画は1件である。宮城県において、当該地区における漁業生産の増大、地元漁民の生業の維持及び雇用機会の創出を目的として、特定区画漁業権免許事業に係る宮城県復興推進計画が作成され、平成25年4月23日、内閣総理大臣の認可を受けた。
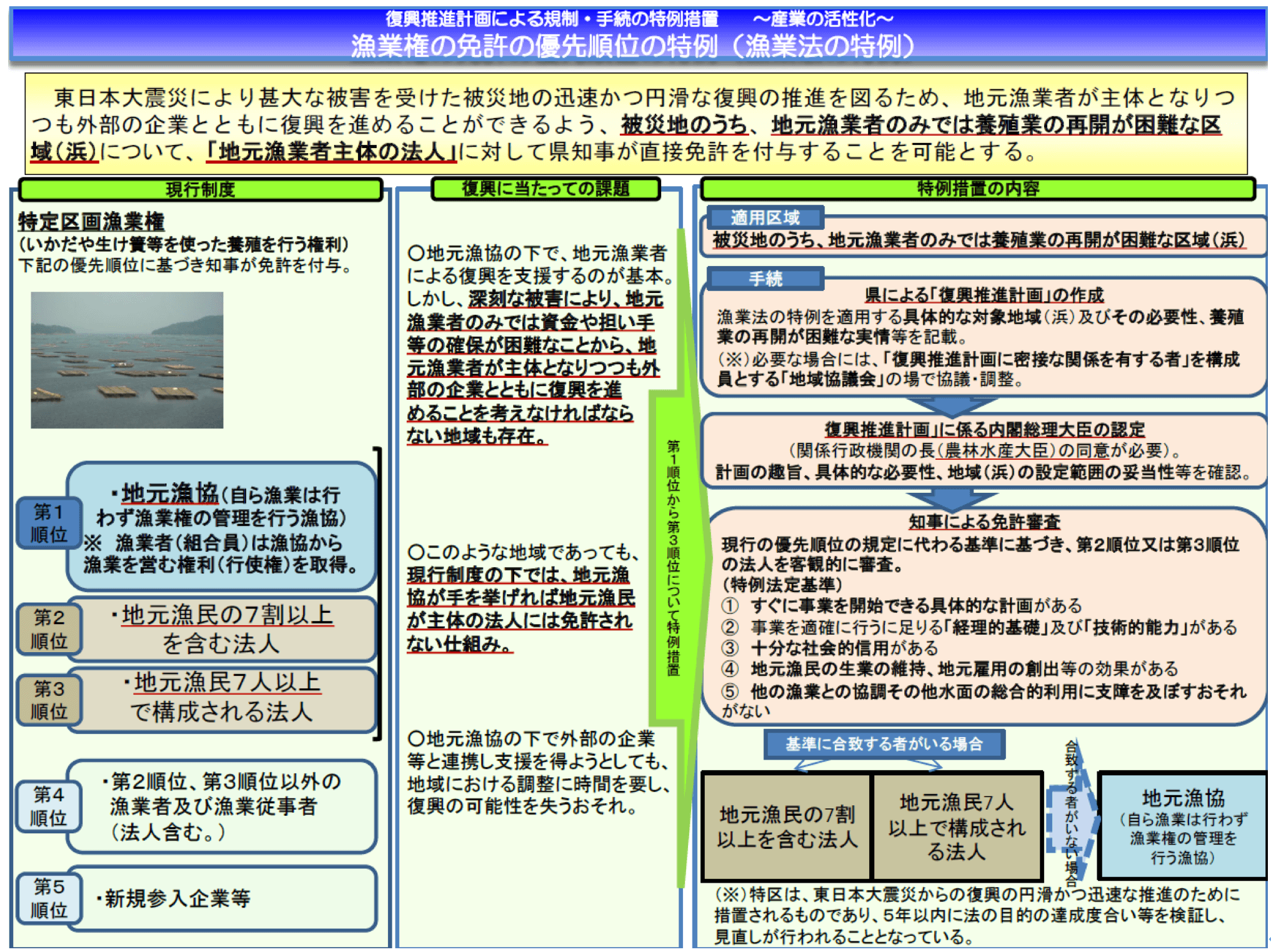
2) 復興建築物整備事業(復興特区法第15条)
a. 特例の概要
本特例は、復興特区法第15条に基づく措置であり、土地の利用方針や建築基準法により定められた建物以外の建物を建築できるようにするものである。
通常制度では、建築基準法第48条及び別表第2において、都市計画として定められている用途地域に応じて建築できる用途の建築物等を規定しているが、第48条第1項から第13項までのただし書きにおいて、特定行政庁の許可を受ければ、各用途地域で制限されている用途の建築物を建築し、又は用途を変更することができることとなっている。
本特例において、復興建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めた復興推進計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合は、特定行政庁が当該建築物の整備に関する基本方針への適合を認めて許可することにより、用途制限の緩和を行うことができるものである。
b. 適用実績・効果
令和5年3月までに、9の復興推進計画が認定され、6の自治体で活用がなされた。
岩手県内自治体では、①岩手県釜石市(平成24年8月認定。工業専用地域において商業施設の整備を可能としたもの)、②岩手県陸前高田市(平成30年3月認定。第一種住居地域の一部において、床面積の合計が3,000㎡を超える建築物の整備を可能としたもの)、③岩手県陸前高田市(令和3年2月認定。商業地域の一部において、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超える建築物の整備を可能とするもの)が活用した。
宮城県内自治体では、①宮城県七ヶ浜町(平成24年9月認定。町内中心部の高台地区(第一種中高層住居専用地域)において、第二種中高層住居専用地域と同様の一定規模の事務所の建築を可能とするもの)、②宮城県女川町(平成24年11月認定。第二種住居地域及び商業地域の一部区域において、漁業関連施設や水産加工施設等の建築を可能とするもの)、③宮城県南三陸町(平成25年10月認定。第二種住居地域の一部において、水産加工工場等の立地を促進するために用途制限の緩和を行ったもの)、④宮城県女川町(平成26年9月認定。第一種・第二種中高層住居専用地域の一部において、ホテル・事業所の建設を促進するもの)、⑤宮城県名取市(平成26年11月認定。閖上地区の第一種住居地域の一部において、水産加工施設の整備を可能にするもの)、⑥宮城県南三陸町(平成27年12月認定。地元企業の速やかな工場立地を促進するための土地利用制限の緩和)が活用した。なお、福島県内の自治体での活用はなかった。
平成27年までの活用が多く見られたが、発災から10年が経過した令和3年においても、岩手県陸前高田市で活用事例があるなど、復興期間を通して活用が認められた。
特例の効果について、自治体からは、「地元購買率が震災前の平成20年度には78.7%だったものが、特例の活用により、新規店舗が立地した後の平成26年度には91.8%になった」、「制度の活用により用途地域の変更を待たず早期の建設が実施できたことで、施設をオープンすることができた。オープンから1か月間で約4,000人が施設を訪れており、年間数万人がこの施設を訪れる試算となっており、他の市内店舗等への流入も期待できることから、市の賑わいの創出に貢献している。」等の評価があった17。
本特例は、上述のとおり複数の自治体で活用され、被災地の復興まちづくりに貢献することができた。
- 17 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。
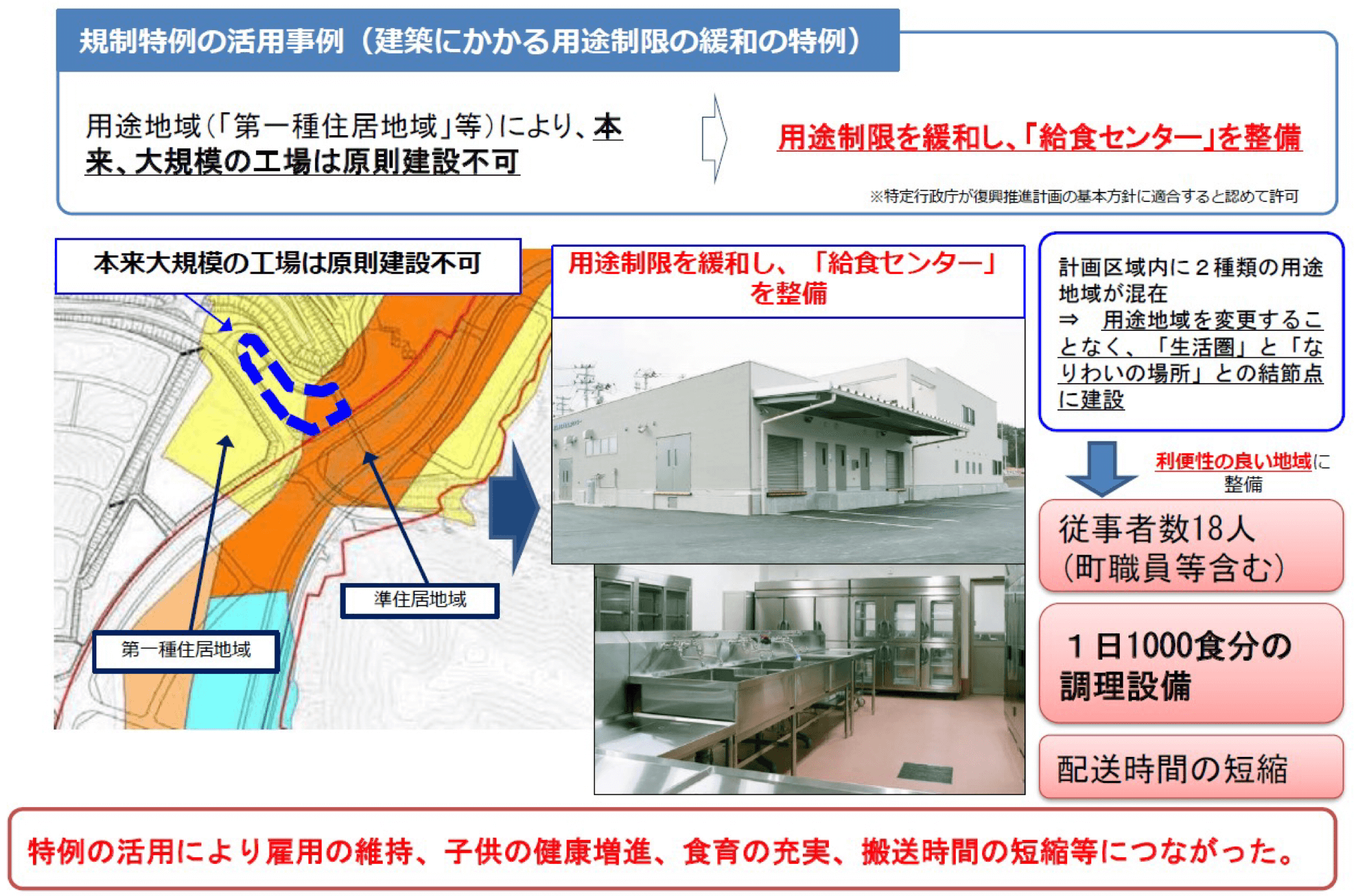
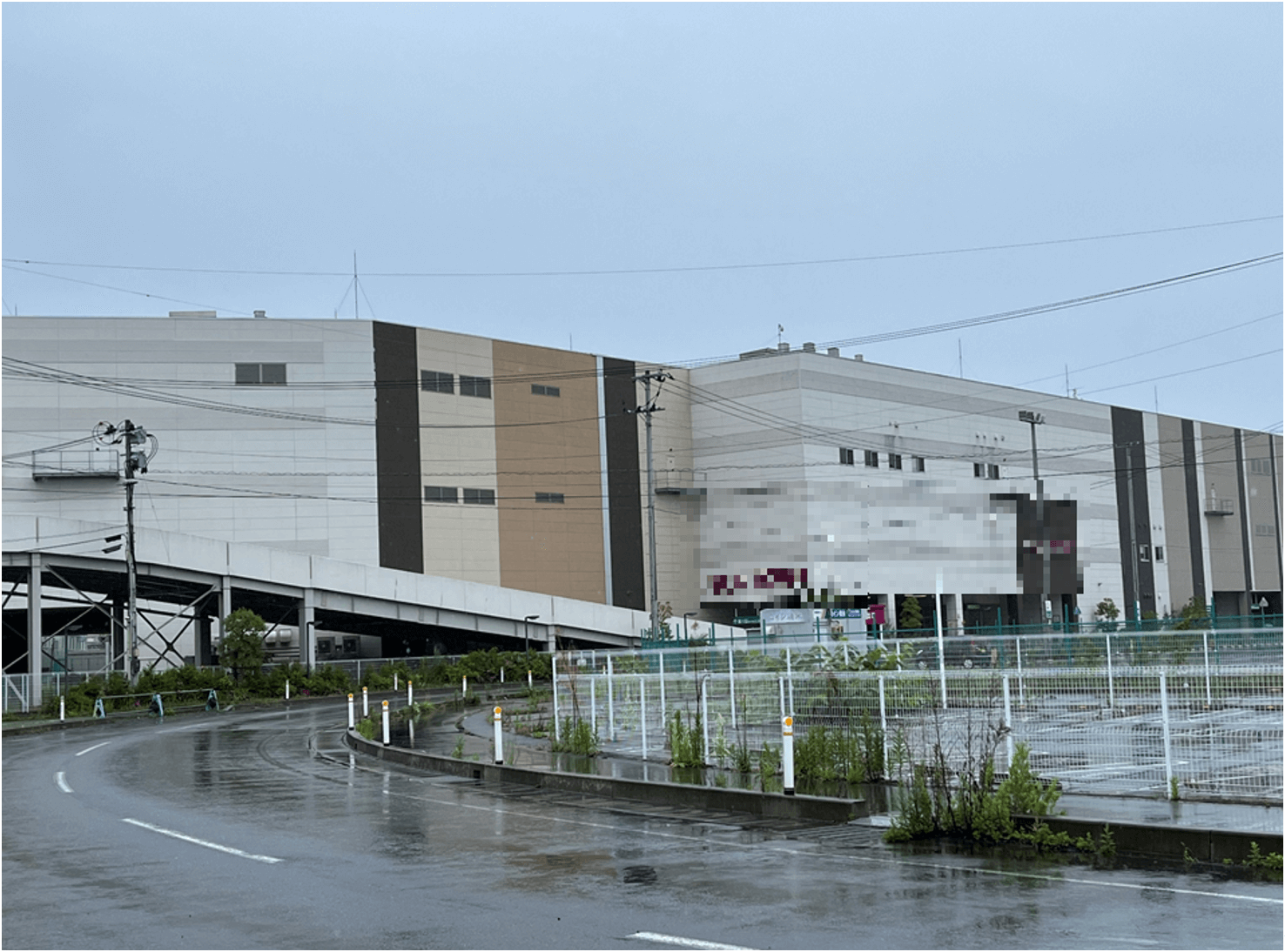
3) 特別用途地区復興建築物整備事業(復興特区法第16条)
a. 特例の概要
復興特区法第16条に基づく措置である。
建築基準法第49条第1項では、用途地域の指定を補完するものとして、都市計画に定められる特別用途地区において、当該指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定を地方公共団体の条例で定めることができることとしている。
本特例は、建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で定めようとする建築物の用途制限の緩和の内容を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、当該認定を同法第49条第2項の承認とみなして、建築基準法上の国土交通大臣承認の手続を不要とするものである。
b. 適用実績・効果
本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。
特例が活用されなかった理由として、本特例は、国土交通大臣承認自体を完全に省略することが可能となるわけではなく、手続の簡素化であり、実体的に何らかの規制が緩和されるわけではないことから、特例の効果が小さく、したがってニーズがなかったことが考えられる。また、そもそも特別用途地区の規制を緩和するような事業の事例がなかったことや、被災地では震災後に特別用途地区の建築を制限する条例を制定している自治体もあったことも理由として考えられる。
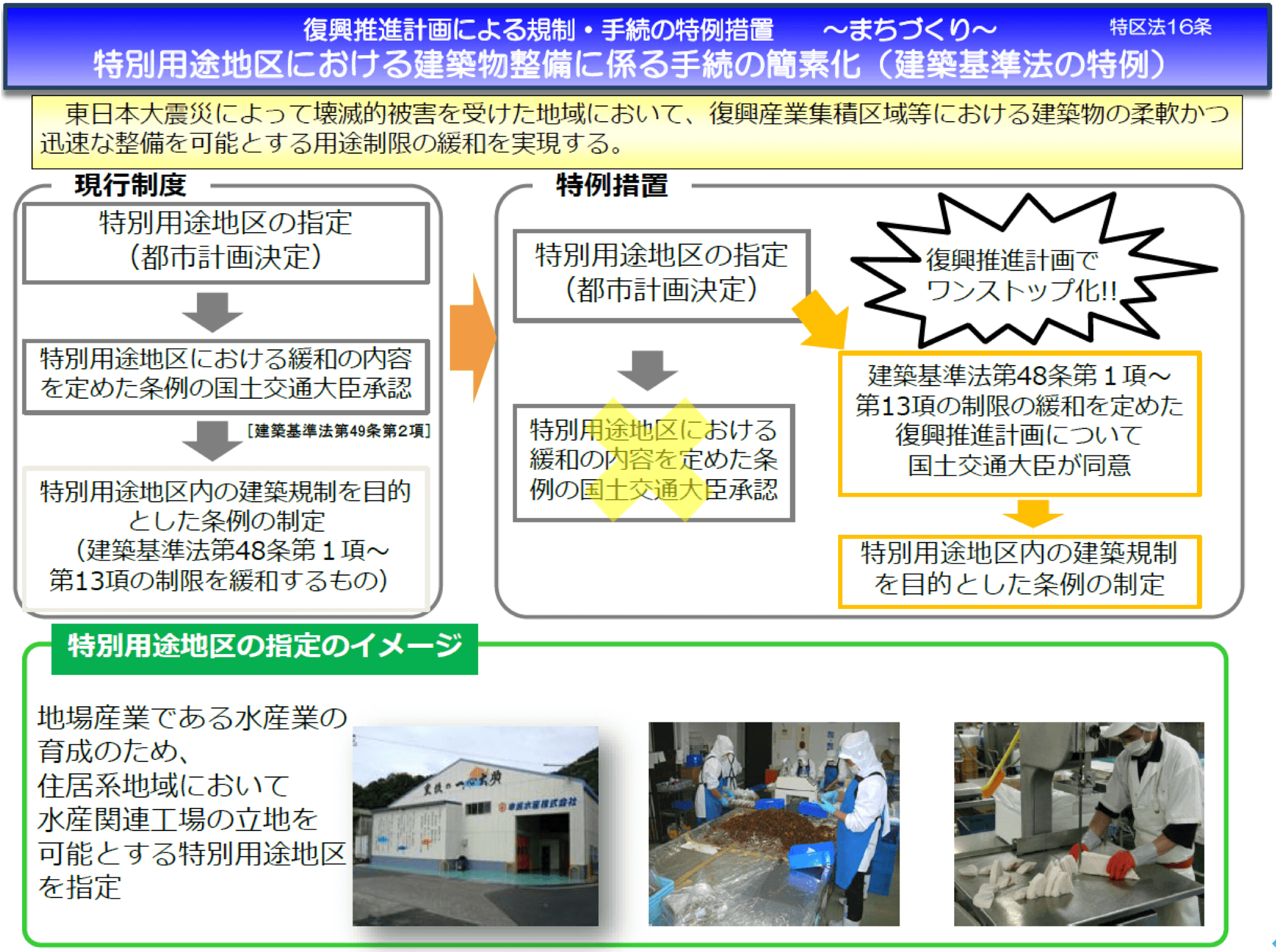
4) 応急仮設建築物活用事業(復興特区法第17条)
a. 概要
建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第2項により災害があった場合に建築される応急仮設建築物については、建築確認手続や一定の技術基準が除外される一方、その存続期間は2年3か月とされている(同条第3項・第4項)。東日本大震災では、地域の重要な社会基盤である店舗、工場、学校、社会福祉施設等が損壊した。津波浸水区域が広範囲にわたったことによる用地不足等の実情や復興の進捗状況に鑑み、2年3か月以内に建築基準法に適合した恒久的な建築物が必要数建築されることが困難と考えられる区域が存在していたことから、本特例が設けられた。本特例は、2年3か月を超えて存続させようとする建築基準法第85条第2項の応急仮設建築物(住宅を除く)の所在地、用途、存続させようとする期間を定めた復興推進計画が、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、当該応急仮設建築物について、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めることで、当該期間内で1年を超えない期間、存続を延長することができるものとされ、これをさらに延長しようとする場合も同様とされた。
なお、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号。第12次地方分権一括法。)により、令和4年5月31日に建築基準法の一部改正が施行され、応急仮設建築物の存続期間の延長に係る被災地特例が全国展開されたことから、復興特区法第17条の本特例は削除となった。
b. 適用実績・効果
本特例は、各県・市町村で復興推進計画が作成され、延べ700以上の建築物に特例が適用されるなど、復興特区法に基づく規制の特例の中でも最も活用された特例となった。
復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第8号(平成25年5月認定、令和4年2月まで12回の変更認定)、②宮城県復興推進計画第21号(平成25年4月認定、令和3年3月まで7回変更認定)、③宮城県石巻市復興推進計画第24号(平成25年4月認定、令和3年3月まで9回変更認定)、④宮城県塩竃市復興推進計画第26号(平成25年9月認定、平成27年3月変更認定)、⑤仙台市復興推進計画第33号(平成26年1月認定)、⑥宮城県岩沼市復興推進計画第51号(平成27年6月認定)、⑦福島県南相馬市復興推進計画第5号(平成24年7月認定、令和4年3月まで7回変更認定)、⑧福島県復興推進計画第18号(平成25年7月認定、令和4年2月まで19回変更認定)、⑨茨城県復興推進計画第3号(平成25年1月認定、平成28年3月変更認定)、⑩茨城県水戸市復興推進計画第10号(平成25年5月認定、平成27年11月変更認定)、⑪茨城県石岡市復興推進計画第17号(平成27年3月認定、平成29年12月変更認定)、⑫栃木県高根沢町復興推進計画第1号(平成24年11月認定)の12の計画が認定され、各計画で認定された応急仮設建築物に特例が適用された。
適用された建築物の用途は幅広く、役場の仮庁舎、郵便事業等の事務所、公共交通機関の事務所、職員宿舎、仮設校舎、仮設事務所、高齢者等施設、仮店舗、仮設作業場等、公共建築物から民間の事業活動にまで適用され、復旧・復興期間における生活に必要なサービス等の安定的な供給に貢献した。特に、他都道府県からの職員派遣を受けた自治体が多く、市中の多くの宿泊施設が被災していたことから、仮設の職員寮が必要な状況であり、本特例が積極的に活用された。発災から10年が経ってもなお、心のケアや地域コミュニティの再生などのソフト事業のための職員派遣は続いており、本特例が引き続き活用されることとなった。
また、福島県においては、原子力災害に起因する廃棄物焼却処理施設(がれき等の災害廃棄物を破砕・選別処理、中間貯蔵施設へ移送する前の灰を保管等)、除染検査施設(帰還困難区域を通過する場合に車両等のスクリーニングを実施する等)等の仮設施設が多数建設され、2031(令和13)年までの計画が認定されるなど、長期にわたり存続している。
特例を活用した自治体からは、「特例の活用により住民サービスの安定的な提供が可能になった。」、「被災事業者が特例の活用により本復旧までの期間をつなぐことができた。」「教育施設は特例の活用により、地域を支える学校として存続でき大きな役割を果たした。」との声があった18。
本特例は、令和4年に全国展開されるまで、上述のとおり非常に多くの被災自治体で活用され、被災地の産業活性化等に貢献することができた。
- 18 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。
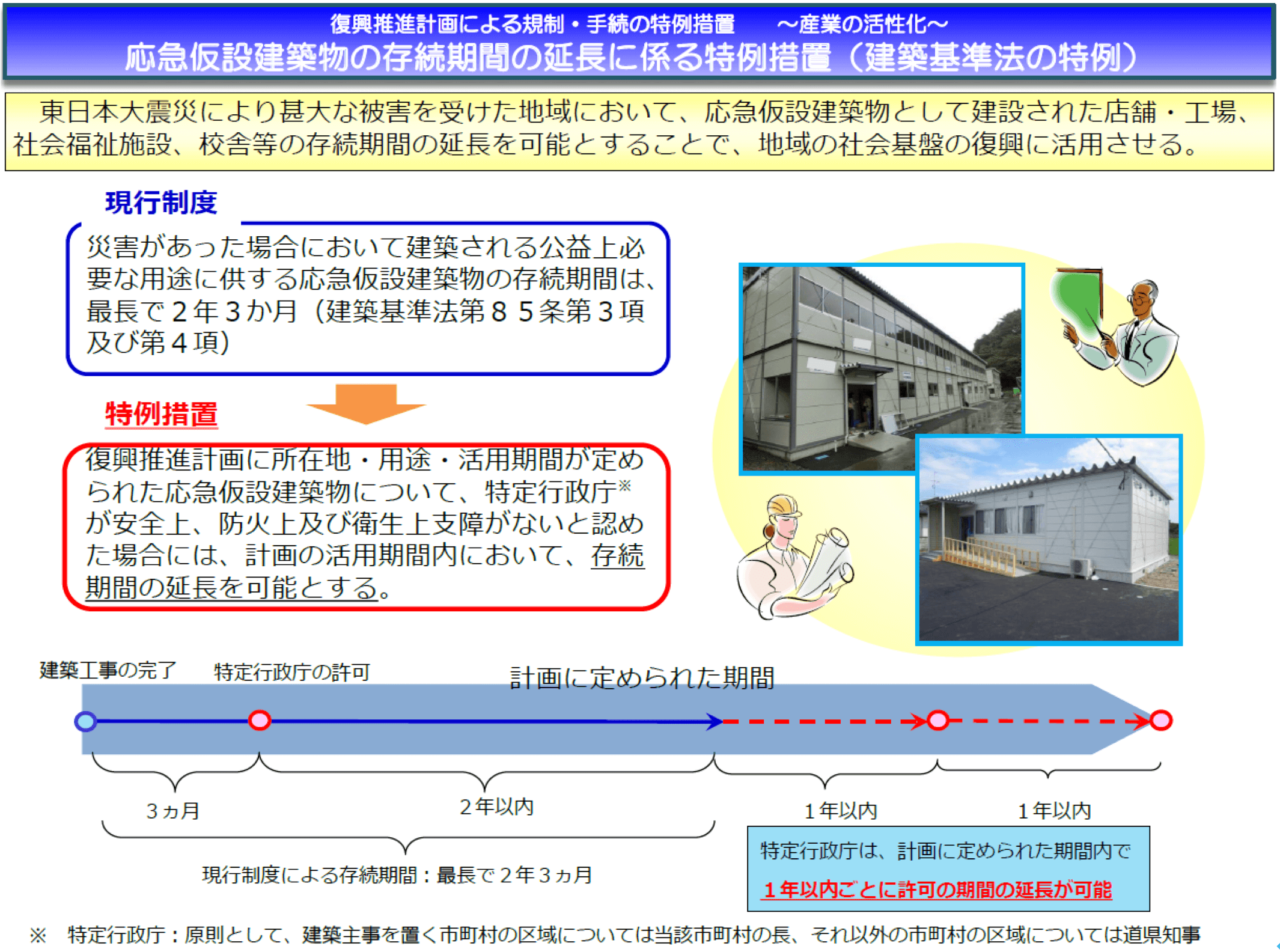

5) 被災区域道路運送確保事業(復興特区法第18条)
a. 概要
復興特区法第18条に基づく措置である。本特例は、一般乗合旅客自動車(バス)運送事業に係る事業計画の認可等の特例である。
道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項により、一般乗合旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、路線、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数などの事項に関する事業計画等の申請書を国土交通大臣に提出し、許可を受けなければならない。
一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた者は、事業計画を変更しようとするときは、同法第15条第1項の規定により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
東日本大震災により甚大な被害を受けた被災地では、仮設住宅と生活施設等とを結ぶ生活交通の確保が課題となり、一般バス路線の見直し等について被災地のまちづくり施策と一体として議論がなされた。
本特例では、被災区域道路運送確保事業が定められた復興推進計画について、国土交通大臣の同意を得て内閣総理大臣の認定を受けたときは、当該復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業のうち、道路運送法第15条第1項の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定により届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなすものである。
b. 適用実績・効果
本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。
震災後、国土交通省が道路運送法に基づく通常の手続処理期間を短縮して迅速に対応していたことが複数の自治体から挙がっており、これにより被災地におけるバス路線等の柔軟な運航の実現につながったことで、本特例の活用につながらなかったと考えられる。
6) 罹災者公営住宅等供給事業(復興特区法第19条から第21条まで)
a. 概要
復興特区法第19条から第21条までに基づく措置である。
公営住宅法(昭和26年法律第193号)は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を賃貸すること等を目的としており、地方公共団体が公営住宅等の整備を行う場合には国庫補助が行われる。このため、収入要件等の入居者資格を定めるとともに、一定期間公営住宅としての社会的便益を発揮させるため、公営住宅の譲渡期間を設け、譲渡の対価の使途も公営住宅等の整備等に限定している。
東日本大震災の被災地では、甚大な住宅被害に加え、第一次産業従事者をはじめとする失職者が相当数に上っており、今後、短期的に大量の災害公営住宅を整備することにより、被災者が地元地域での生活再建を行えるよう環境を整えることで、復興を進める必要があった。
また、短期的には震災被害による住宅不足から、一定の収入がある者等本来の入居者資格を有しない者まで住宅に困窮することが想定されたため、被災地域においては、住宅困窮者に広く公営住宅の入居を認めていく必要があった。
一方で、被災地域では将来的な人口減少が見込まれており、一定期間経過後に平時では想定し得ない公営住宅の需給ギャップ(空き家)が発生し、事業主体が負担する管理コストの増大が予想されていた。
災害公営住宅の大量供給を進めるに当たっては、事業主体の懸念を払拭すべく、災害公営住宅の建設後、公営住宅の需給状態等に応じて弾力的に譲渡処分を行い得る環境を整える必要があった。
上記状況を踏まえ、罹災者公営住宅等供給事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、公営住宅等に係る入居者資格の緩和、財産処分制限期間の短縮及び譲渡対価の使途制限の緩和に係る特例措置が適用されることとなった。
特例の適用内容は、①東日本大震災により住宅を失った者等が、入居者資格要件のうち住宅困窮要件を満たせば、他の要件も満たす者とみなすこととする(復興特区法第20条)。②公営住宅等の譲渡制限期間を耐用年限の「4分の1」から「6分の1」に短縮するとともに、譲渡対価の使途を公営住宅等の整備等のみならず、地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する費用にも充てることを可能とした。
なお、①については、復興特区法で期限を、発災から10年の平成33(令和3)年3月11日としており、期限到来により規定削除となった。
b. 適用実績・効果
本特例は、各県及び市町村で復興推進計画が作成され、多くの公営住宅に特例が適用されるなど、復興特区法に基づく規制の特例の中でもよく活用された特例となった。
復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第10号(平成25年8月認定、令和2年3月まで2回の変更認定)、②宮城県復興推進計画第28号(平成25年10月認定)、③福島県復興推進計画第17号(平成25年7月認定)、④茨城県復興推進計画第12号(平成25年9月認定、平成26年6月変更認定)、⑤千葉県旭市復興推進計画第1号(平成25年2月認定)、⑥千葉県香取市復興推進計画第2号(平成25年8月認定)の6の計画が認定された。
平成31年3月時点において、岩手県1,910世帯、宮城県5,714世帯、福島県1,076世帯、茨城県13世帯が適用された。また、譲渡期間の短縮については、平成30年、福島県南相馬市で震災後初となる譲渡(木造:7.5年を5年に緩和)がなされたのをはじめ、被災3県では令和4年3月までに120戸が譲渡処分された。
なお、耐火構造の場合は通常17.5年であり、緩和されても11.7年後になることから、発災10年以降にニーズが出てくる特例となっている。
特例を活用した自治体からは、「本来公営住宅に入居できない被災者を救うことができた。また、仮設住宅の解消にもつながった。」、「入居事前登録に係る資格審査が簡素化され、スムーズな建設戸数の確定や工事着手につながった。」との声があった19。
本特例は、上述のとおり数多くの自治体で活用され、被災地の住宅の確保に貢献することができた。
- 19 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。
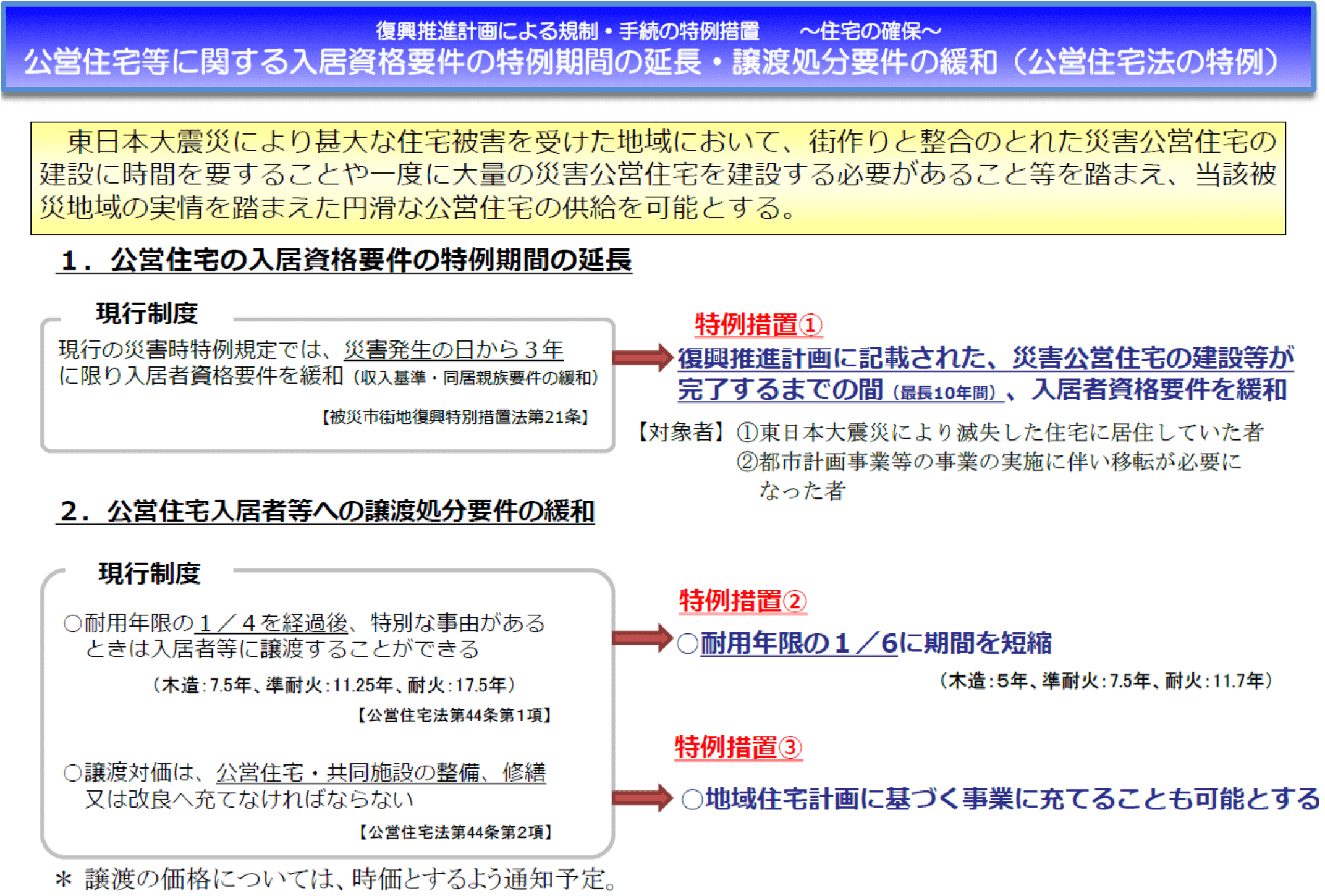



7) 復興推進公営住宅等管理等事業(復興特区法第22条)
a. 概要
公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を賃貸すること等を目的としており、公営住宅の建設に対して国は国庫補助をするものとされている。
また、①公営住宅等が災害による損壊等の事由により修繕しても供用し続けることが困難で用途廃止する場合、②公営住宅を社会福祉事業のグループホームに使用させる場合、③公営住宅等事業の実施主体を変更する場合、国土交通大臣の承認を必要としている。
加えて①~③の承認に当たっては、市町村が申請する場合には都道府県を経由することとされており、また、①、③については厚生労働大臣に協議することとされている。
本特例は、特定地方公共団体が、復興推進計画において復興推進公営住宅等管理等事業を盛り込み、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、上記①~③に係る国土交通大臣の承認を受けたものとみなすものである。
b. 適用実績・効果
本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。
特例が活用されなかった理由として、本特例は、国土交通大臣承認を省略することが可能となる、手続の簡素化であり、実体的に何らかの規制が緩和されるわけではないことから、特例の効果が小さく、用途廃止の手続については本法の方で柔軟な運用が図られていることと相まって、復興特区法を活用するニーズがなかったことが考えられる。
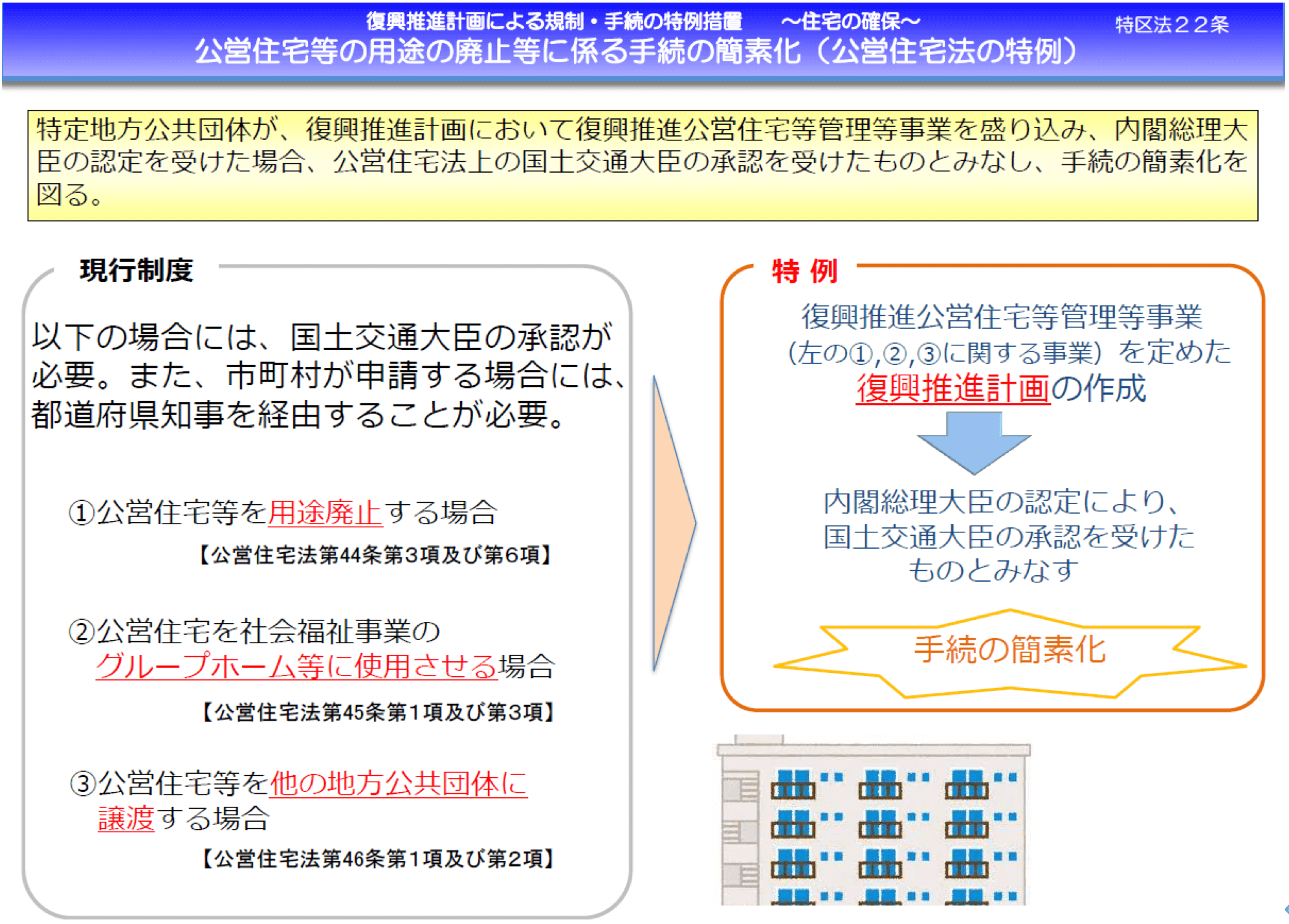
8) 食料供給等施設整備事業(復興特区法第23条から第27条まで)
a. 概要
東北地方太平洋沖の津波による被害を受けた地域では、基幹産業である農林水産業について、農地のみならず、加工施設等の関連施設についても大きな被害を受けた。このため、被害を受けた農林水産物の加工施設等の食料供給等施設を早急に復旧することにより、被災地域の食料供給機能を回復させ、また地域の農林水産業の復興を行うことが、被災地の迅速な復興のために重要であった。
一方、被災地域では津波災害リスクを低減するため、沿岸部から内陸部へ施設を移転整備させていたが、内陸部では施設用地がもともと限られている上、仮設住宅等の建設が優先され、内陸部に多く存在する農地や森林が施設用地として求められている。しかし、農地法(昭和27年法律第229号)上、優良農地の農地転用許可が制限されており、水産業関連施設等は原則転用が認められなかった。また、各種制度により、農地転用や林地開発について、個別の施設ごとに許可申請を行う必要があり、迅速な復興の観点から支障になりかねない状況であった。
こうした事情に鑑み、本特例は、津波による被害を受けた市町村が、食料供給等施設整備事業(食料の安定供給の確保又は地域の農林水産業の復興に資する施設(食料供給等施設)を当該市町村の区域内において整備する事業)を定めた復興推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けたときは、当施設の整備について、地域協議会での協議を通じた農地転用や林地開発に係る手続の一元化を図るとともに、非代替性等の一定の要件を満たす場合に限って優良農地であっても整備を認めることとした。
さらに、内閣総理大臣の認定を受けた復興推進計画を作成した市町村は、食料供給等施設整備事業の実施計画を、地域協議会において、農地転用許可及び林地開発許可の手続に関与する主体(知事、都道府県農業会議、森林及び林業に関する学識経験者等)と協議の上、作成することとなる。
一連の手続により、計画に位置付けられた食料供給等施設については、農地の転用許可基準の緩和を行うとともに、農地転用許可及び林地開発許可の手続をワンストップ化することができる。
b. 適用実績・効果
本特例に関しては、宮城県石巻市において、乾燥調製貯蔵施設の迅速な整備を図るため、復興推進計画が作成され、平成24年3月23日、内閣総理大臣の認定を受けた。策定された復興推進計画はこの1件である。なお、石巻市では上記計画を作成したものの、結果として本特例を活用した規制緩和等は行われなかった。
石巻市の当該復興推進計画は、石巻市北上地区及び河北地区を計画区域として、復興整備計画の土地利用方針と整合を図りつつ、これらの農業生産基盤整備事業によるほ場の大区画化及び担い手への農地の利用集積の促進を図り、併せて共同乾燥調製貯蔵施設等を整備することにより、基幹産業としての農業の再興を図るとともに、地域の活性化とコミュニティの再生に資することを目的として計画された。石巻圏域の食料供給基地として重要な役割を担っていた同地区は、被災により農業用設備が流出するなど大きな被害があったところ、乾燥調製機をはじめとする農業機械の整備を個々の担い手が対応することとなれば、営農意欲を維持することが困難になることから、より多くの収量を一括して乾燥調製貯蔵することで、農業経営の効率化などの効果が期待できるものと計画された。
結果として本特例が活用されなかったことについて、本特例を活用するためには、復興推進計画が認定された後に、地域協議会における協議、食料供給等施設整備計画の作成、同計画の県への協議といった一連の手続が必要とされており、本則である通常の農地法による手続と負担感が大きく変わらなかったものと考えられる。
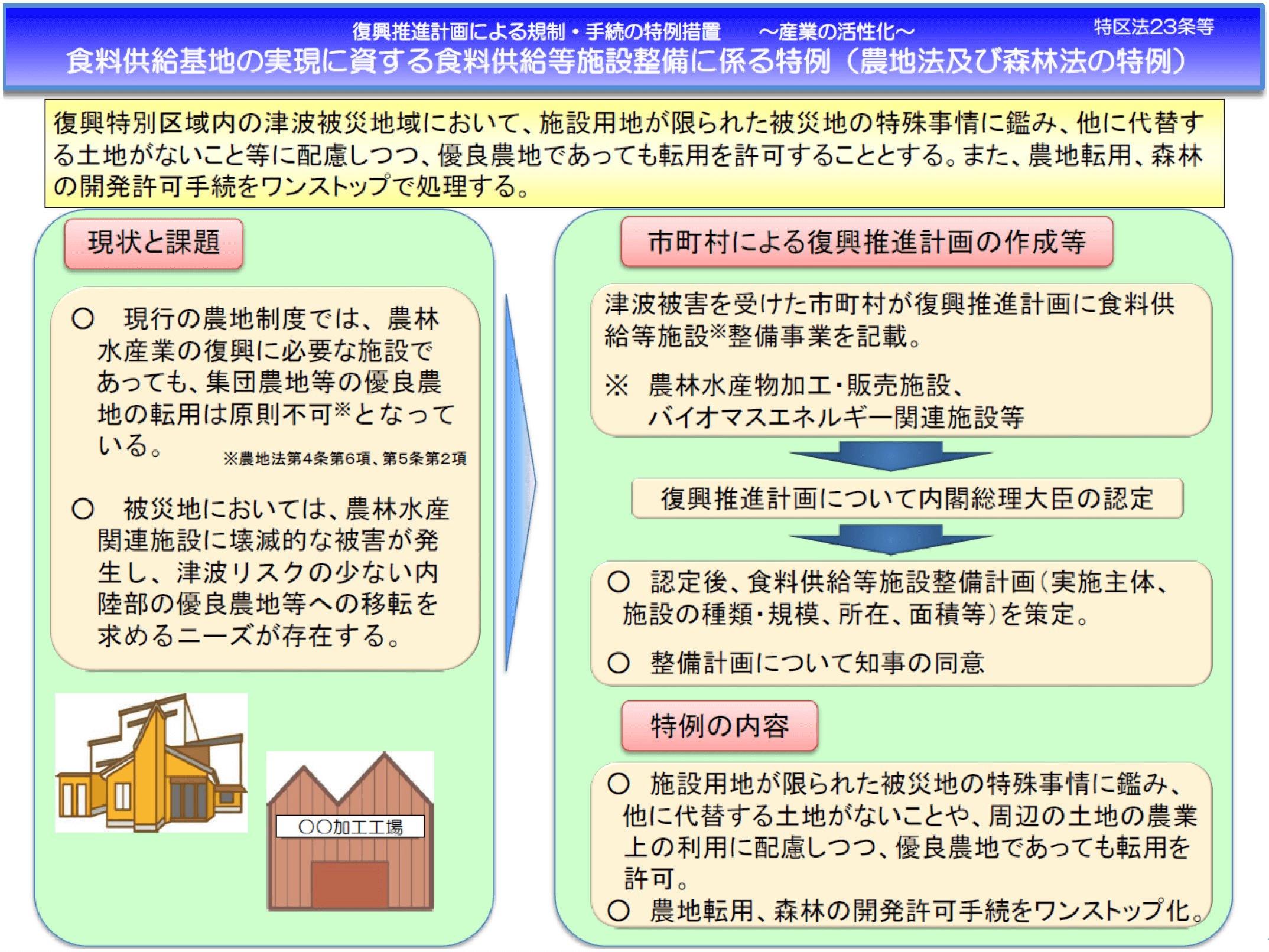
9) 復興産業集積事業(復興特区法第28条)
a. 概要
本特例は、復興特区法第28条に基づく特例であり、工場立地法等に基づく緑地面積等の割合よりも、自治体が独自の低い緑地割合を設定できるものである。
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、国による工場の緑地面積等に係る準則の公表、準則に適合しない一定規模以上の工場等に対する市町村長(特別区の区長を含む。)による勧告、変更命令等を定めている。
また、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)では、地域の特性を活用して高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進する観点から、工場立地法による準則に代えて適用できる準則を、条例で現行の土地利用のあり方ごとに国が定める基準の範囲内で定めることができる特例措置を講じている。
復興特区法に基づく復興推進計画に、東日本大震災の津波等により、特に甚大な被害を受けた地域で雇用確保の観点等から特に産業集積の形成及び活性化を進める必要がある地域を記載し、内閣総理大臣の認定を受けた場合には、当該計画を作成し認定を受けた市町村においては、現在の土地利用のあり方に関わらず、地域の復興の実情にあわせて当該地域で適用できる緑地面積率等の基準を条例で定めることができる旨の特例措置が講じられた。
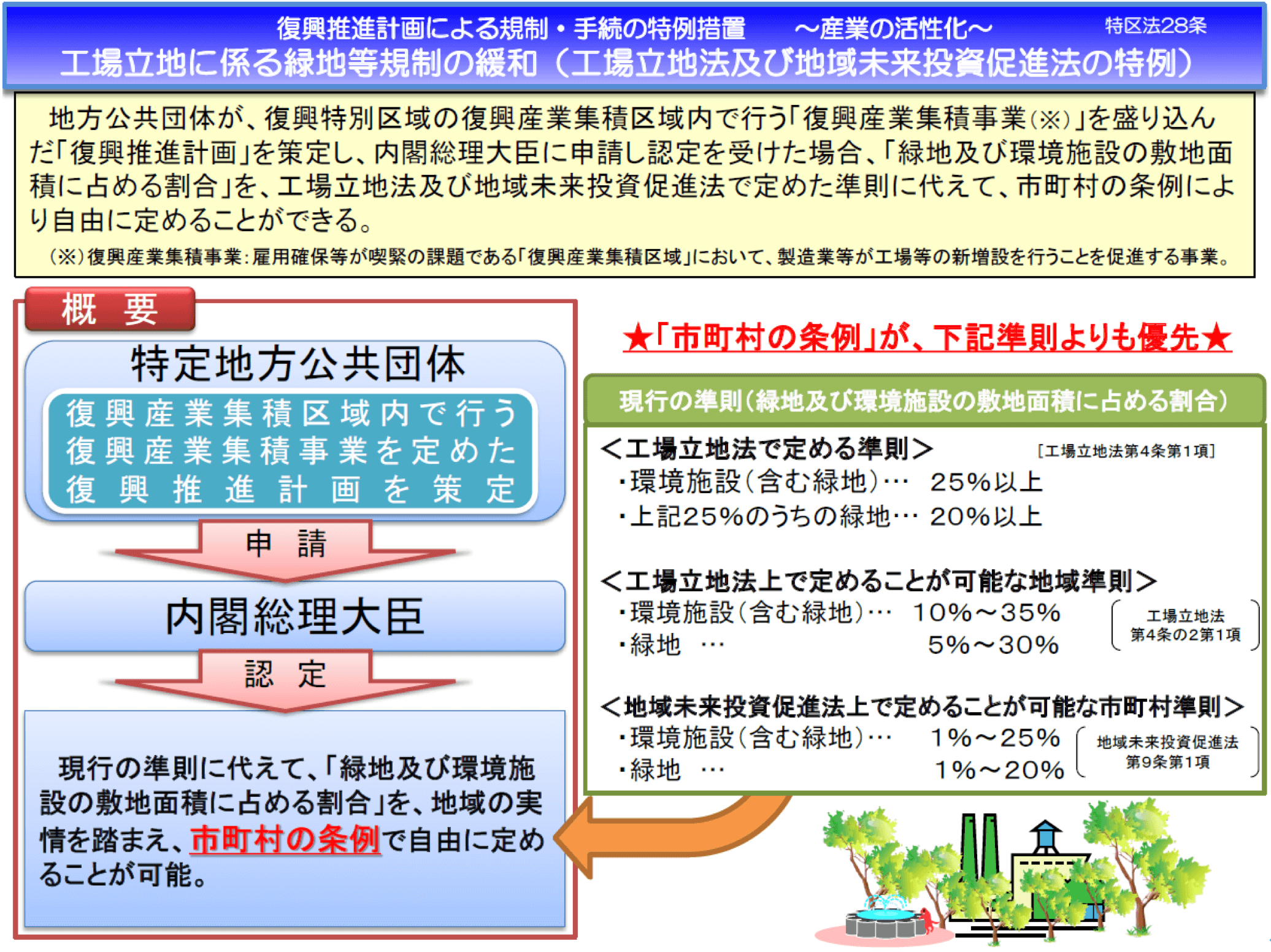
b. 適用実績・効果
本特例は、各県で復興推進計画が作成され、150以上の事業に特例が適用されるなど、復興特区法に基づく規制の特例の中でも多く活用された特例となった。
復興推進計画は、①青森県復興推進計画第1号(平成24年3月認定)、②宮城県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和3年4月まで7回変更認定)、③茨城県復興推進計画第1号(平成24年3月認定、平成24年9月変更認定)の3計画が認定され、各市町村において条例が定められ、工場等の立地等に当たり特例が適用された。
上記3県においては、本特例はいずれも税制上の特例とセットで復興推進計画が策定されており、作成時期も平成23年度内と早いものとなっている。中でも活用の多かった宮城県では、発災から10年が経過しても、新規立地に伴う特例の活用が複数自治体で検討されている。
なお、岩手県及び福島県では、本特例に係る復興推進計画が策定されていない。震災以前から、工場立地法及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)において、市町村が条例による基準を定めることで、要件を緩和することができる特例措置が設けられており、既に複数の市町村が条例を設けていたことなどが考えられる。
本特例を活用した自治体からは、「緑地造成費用等を一定程度抑えることができたことで、企業の負担が軽減され、立地しやすい環境づくりに貢献した」、「緑地面積の緩和がなければ立地困難な案件もあった」、「震災により流出した企業の早期再開につながった」「復興特区制度の特例措置が決め手の一つとなり立地が決まった」などの評価があった20。
本特例は、上述のとおり多くの自治体で活用され、企業の負担が軽減されることで立地しやすい環境をつくり、被災地の産業の活性化に貢献することができた。
- 20 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。
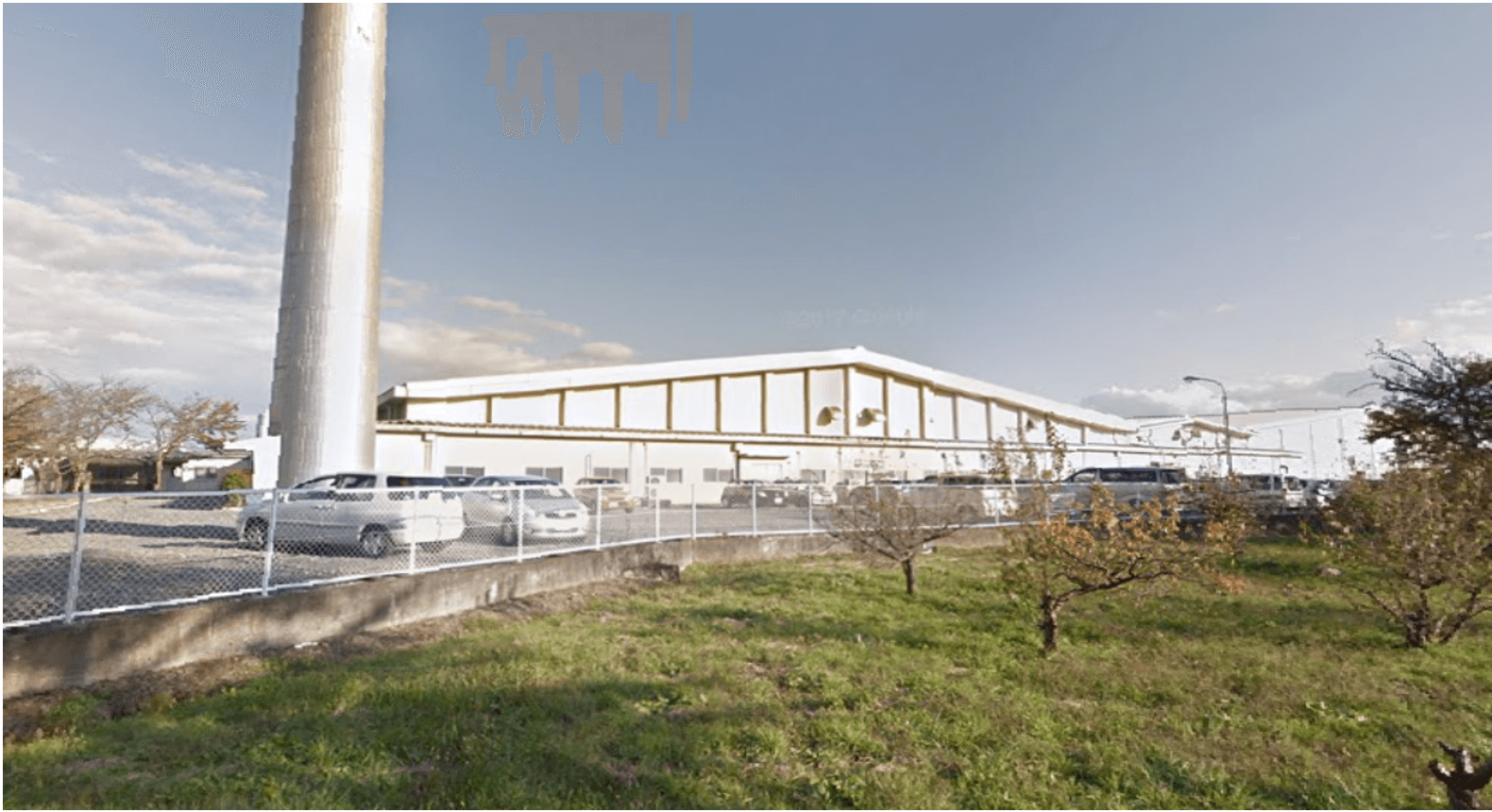
10) 特定水力発電事業(復興特区法第29条から第32条まで)
a. 概要
復興特区法第29条~32条に基づく特例措置である。
河川法(昭和39年法律第167号)では、国土交通大臣等が水利使用に関する許可の処分をしようとするときは、河川の適正な管理の観点から、①関係行政機関の長との協議、②関係地方公共団体の長の意見の聴取、③水利使用の申請のあった場合の通知、④国土交通大臣の認可等の手続が義務付けられている。また、電気事業法(昭和39年法律第170号)では、発電水力のための水利使用に関する許可の申請を受けた都道府県知事等に対して、経済産業大臣への意見聴取等が義務付けられている。
本特例は、被災地域における小水力発電の導入の促進を図る観点から、これらの手続の簡素化等に関する特例措置を講ずることとした。
特定地方公共団体が、特定水力発電事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣申請に対する処分をしようとするときは、関係行政機関の長に協議することを要しないこととする等の特例を講じた。
なお、本特例の全国展開に伴い、平成25年法律第35号により規定が削除となった。
b. 適用実績・効果
本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。
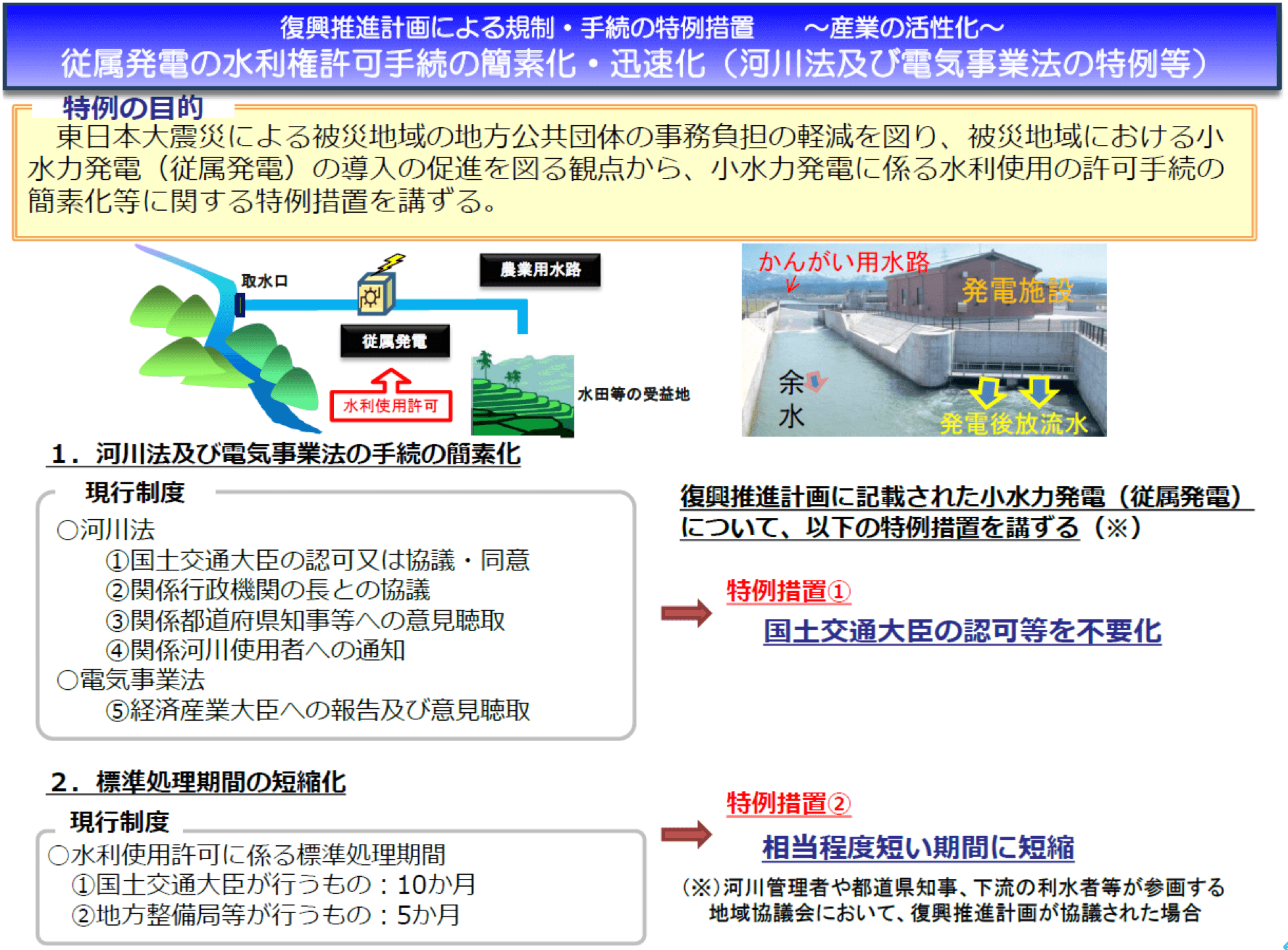
11) 被災鉄道移設事業(復興特区法第33条)
a. 概要
復興特区法第33条に基づく措置である。
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の規定により、鉄道事業を経営しようとする者は、事業の基本となる事項に関する計画等を国土交通大臣に提出し、許可を得なければならないこととされている。さらに、鉄道事業の許可を受けた者(鉄道事業者)は、事業基本計画を変更しようとするときは、同法第7条第1項の規定により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
本特例は、被災鉄道移設事業を定めた復興推進計画について、国土交通大臣の同意を得て内閣総理大臣の認定を受けたときは、計画に定められた被災鉄道移設事業のうち、鉄道事業法第7条第1項の許可を受け、又は届出をしたものとみなすものである。
b. 適用実績・効果
本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。
現状路線で復旧したケースが多く、通常の鉄道事業法で手続が迅速に進められたためと考えられる。
12) 地域振興事業(復興特区法第34条)
a. 概要
復興特区法第34条に基づく措置である。
確定拠出年金制度は、老後の所得確保を目的とした制度であることから、60歳到達前の中途での脱退は原則として認められていないが、退職時等については、資産が少額の場合には、例外的に脱退一時金の支給が認められている(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)附則第2条の2、第3条)。
被災地の復興の推進を図るには、それぞれの地域の特性を生かした地域振興事業を促進していくことが重要であり、そのような事業の取組に当たっては、公的な支援だけでなく、民間や地域住民の主体的な参加が必要不可欠である。
確定拠出年金の資金は、本来、老後の年金の原資に充てるものであるため、中途での引き出し(脱退一時金として支給)には規制が設けられているが、本特例措置は、この規制を緩和し、震災により職を失ったものが自助努力により積み立てた確定拠出年金の資金を復興に向けた取組(地域振興事業)に活用できるようにすることとしている。これは、被災地住民の自己資金を活用した復興への主体的な参加を促すことにつながるものである。
本特例では、地方公共団体が特区計画において位置付ける復興のための取組(水産業の再生、雇用機会の創出、観光資源の再建等)において、事業主体への出資や事業への参加等に活用することが見込まれる者について、確定拠出年金の脱退一時金の支給要件を緩和する(脱退一時金を支給する)ものである。
復興特区法規定の期限が令和3年3月11日となっており、期限到来により規定削除となった。
特定地方公共団体が、地域振興事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、平成23年3月11日において、復興推進計画の区域内に住所を有していた者が、平成28年3月31日までの間、脱退一時金の支給を請求し、地域社会の活性化等の活動に活用するものである。
b. 適用実績・効果
復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第7号(平成25年4月認定)、②宮城県復興推進計画第20号(平成25年3月認定)、③福島県復興推進計画第6号(平成24年8月認定)、④茨城県復興推進計画第2号(平成24年10月認定)の4計画が認定され、適用された。
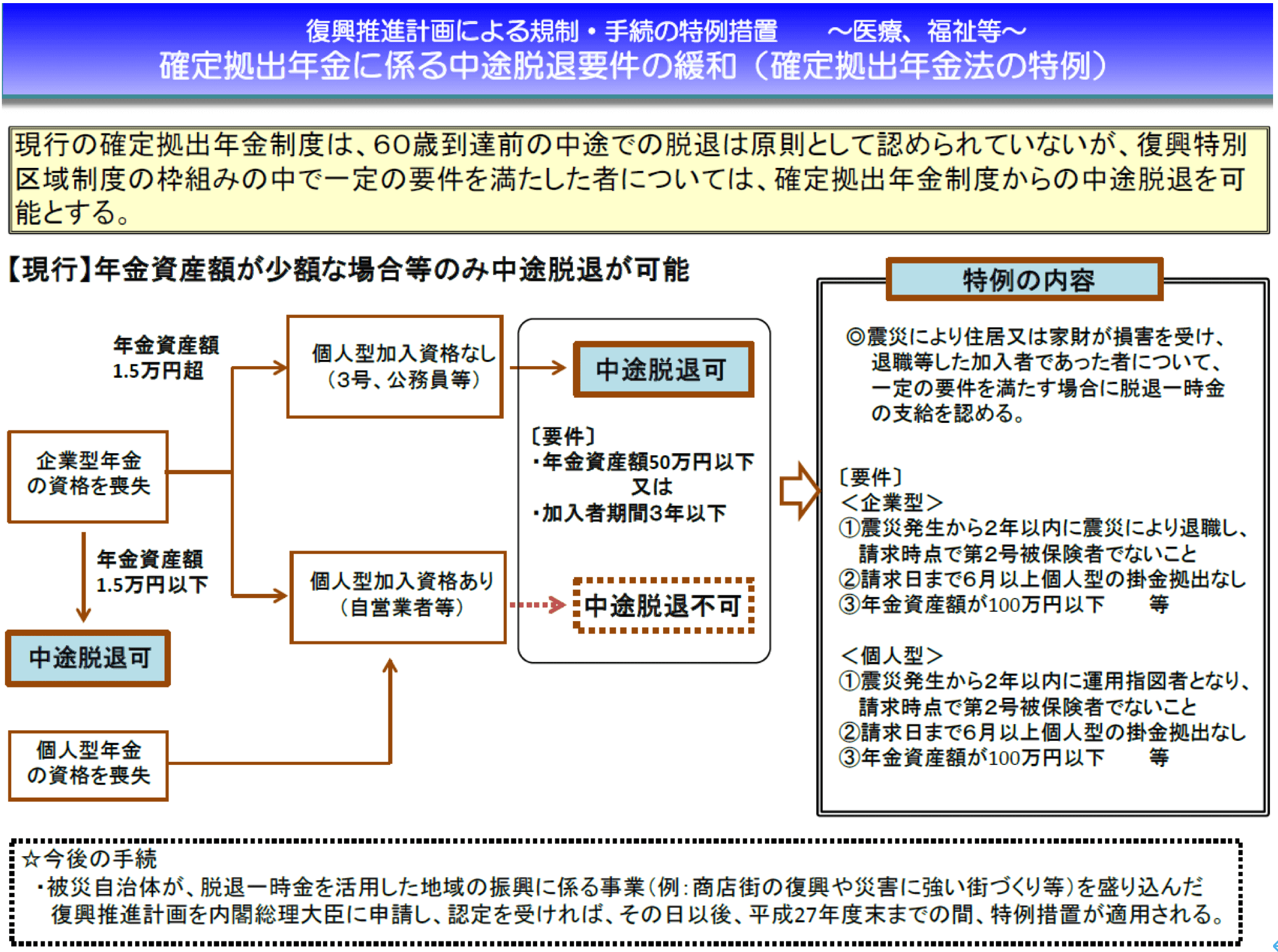
13) 復興仮設占用物件設置事業(東日本大震災復興特別区域法施行令(平成23年政令第409号)第4条)
a. 概要
本特例は、仮設店舗等についての都市公園法の占用に関する制限の緩和の特例である。
都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)により、都市公園の占用は、①許可申請に係る物件又は施設が、都市公園法第7条各号に掲げる物件又は施設(極めて公共性の強いもの、それを設けることが都市公園本来の利用法にやや類似するもの、それを設けることによって都市公園の効用を著しく阻害することのないもの等)に該当する、②都市公園の占用が、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ないと認められる、③都市公園の占用が政令で定める技術的基準に適合する場合に許可される。
東日本大震災により、多くの店舗・工場等が滅失・損壊等したが、地域の円滑かつ迅速な復興のためには、地域住民の生活や地域経済の活性化のために必要な施設を早急に整備する必要があった。しかし、こうした施設を再建又は新規に設置するための土地も不足している地域が存在した。本則では、応急仮設住宅以外の応急仮設店舗等は、条例で定めなければ専用物件とはならず、また条例で専用物件として定めた場合でも、建ぺい率の上限等、都市公園の利用上の制限が設けられている。
こうした事情に鑑み、本特例は、地域住民の生活に必要な物件又は施設を設置するために必要な土地が不足している区域において、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な仮設店舗等を復興仮設占用物件として都市公園内に設置する事業が盛り込まれた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、当該物件又は施設を都市公園の占用物件として許可しうるものとしている。
b. 適用実績・効果
本特例に関して、自治体で復興推進計画は作成されず、活用事例はなかった。
震災以降、仮設店舗は客の利便性、駐車場、電気・ガス等の引き込みの容易性などから場所を選定しており、都市公園内ではそれらを有効に確保できないことが多く、特例を活用するニーズがなかったものと考えられる。
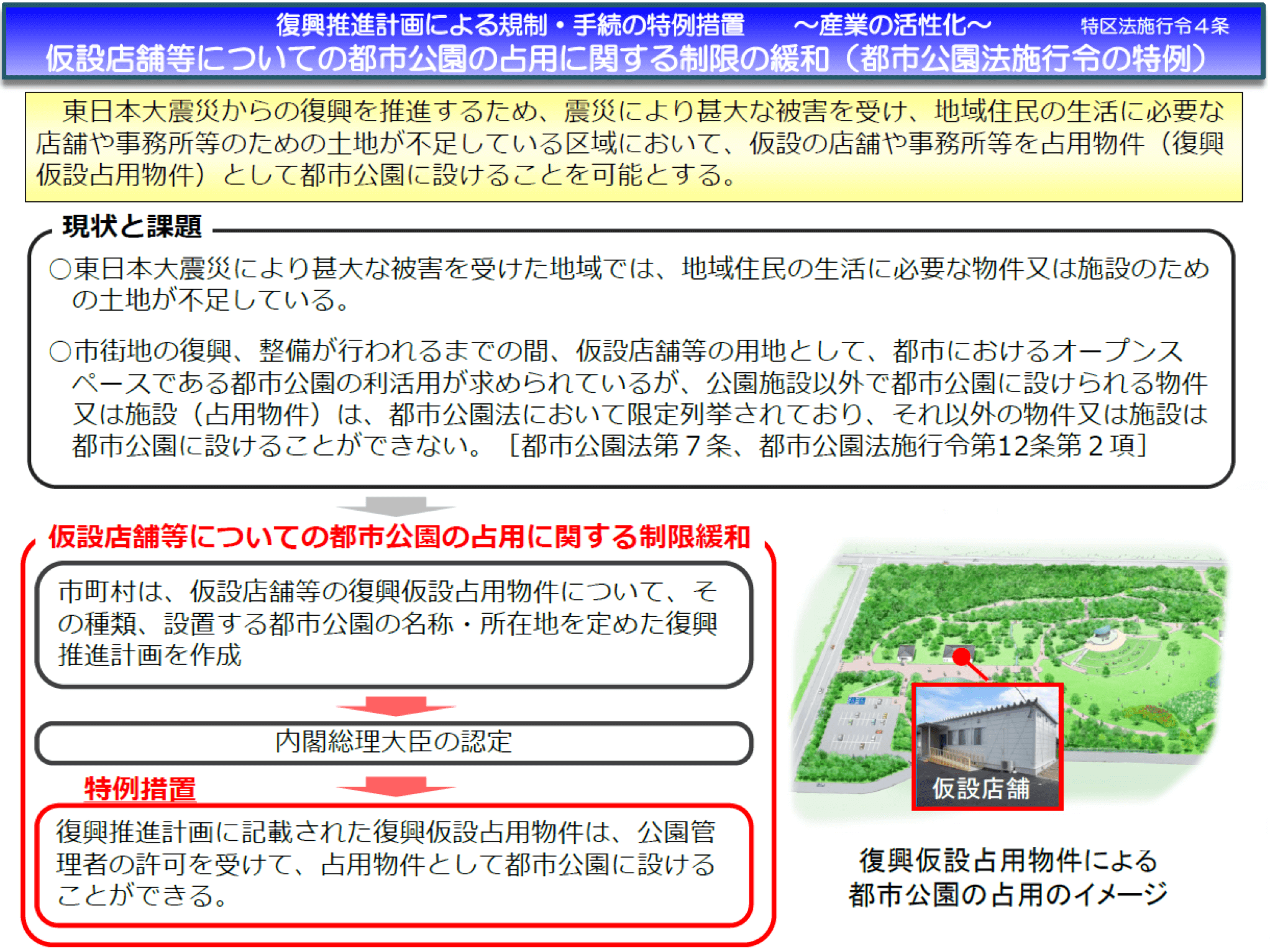
14) 地域医療確保事業(厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令(平成23年内閣府令・厚生労働省令第9号。以下「厚労省令特例命令」という。)第1条)
a. 概要
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第19条第5項及び第50条では、病院について、前年度の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数の平均値に基づき計算される医療従事者数を配置しなければならないとしている。
本特例では、県が復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な医療を担う病院を確保する事業及びその事業の期間を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、区域内の病院のうち、一定の申請書等を踏まえ県の知事が必要と認めるものについて、①配置すべき医療従事者数の計算に当たり、入院患者数等については、地域の実情に応じ、妥当な方法により計算された数を用いることができること、②医師配置基準については、他の医療機関との連携等を条件に、通常の90%相当に緩和すること(ただし3人は下回らないものとする)を可能とした。
b. 適用実績・効果
本特例は、各県で復興推進計画が作成され、復興特区法に基づく規制の特例の中でも多く活用された特例となった。
復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和2年2月まで2回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)、③福島県復興推進計画第3号(平成24年3月認定、令和3年3月まで3回変更認定)の3計画が認定され、認定された各県において特例が適用された。
各県の復興推進計画により、宮城県で2施設、福島県で9施設が医師等の配置基準の緩和を受けた。
宮城県では、県全域で、平成24年4月から平成29年3月までの期間で計画が認定された。
2病院が、患者数の増加や医療従事者の確保が困難であることを理由に、一時的に医療機関としての設置基準を満たせない状態が生じていたことから、平成24年度に特例を活用し、県民が必要な医療を受けられる体制が整えられた。
福島県では、平成24年に計画が認定され、4回の延長を経て、令和5年においても計画は継続している。同県では、6市町の9病院が、平成24年度以降特例を活用した。平成27年度に活用を終えた施設が多かったが、最も長い施設で平成29年3月まで特例を活用した。
なお、岩手県では計画が認定されたものの、実際には必要な医師数を確保することができたことなどにより、活用に至らなかった。
活用した自治体からは、「医療復興の過程で一時的に医療機関として配置基準を満たせない事態が生じていたが、特例により、病院が患者の受入れを積極的に行えるようになり、住民が必要な医療を受けられる体制が整えられた」といった評価があった21。
- 21 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。
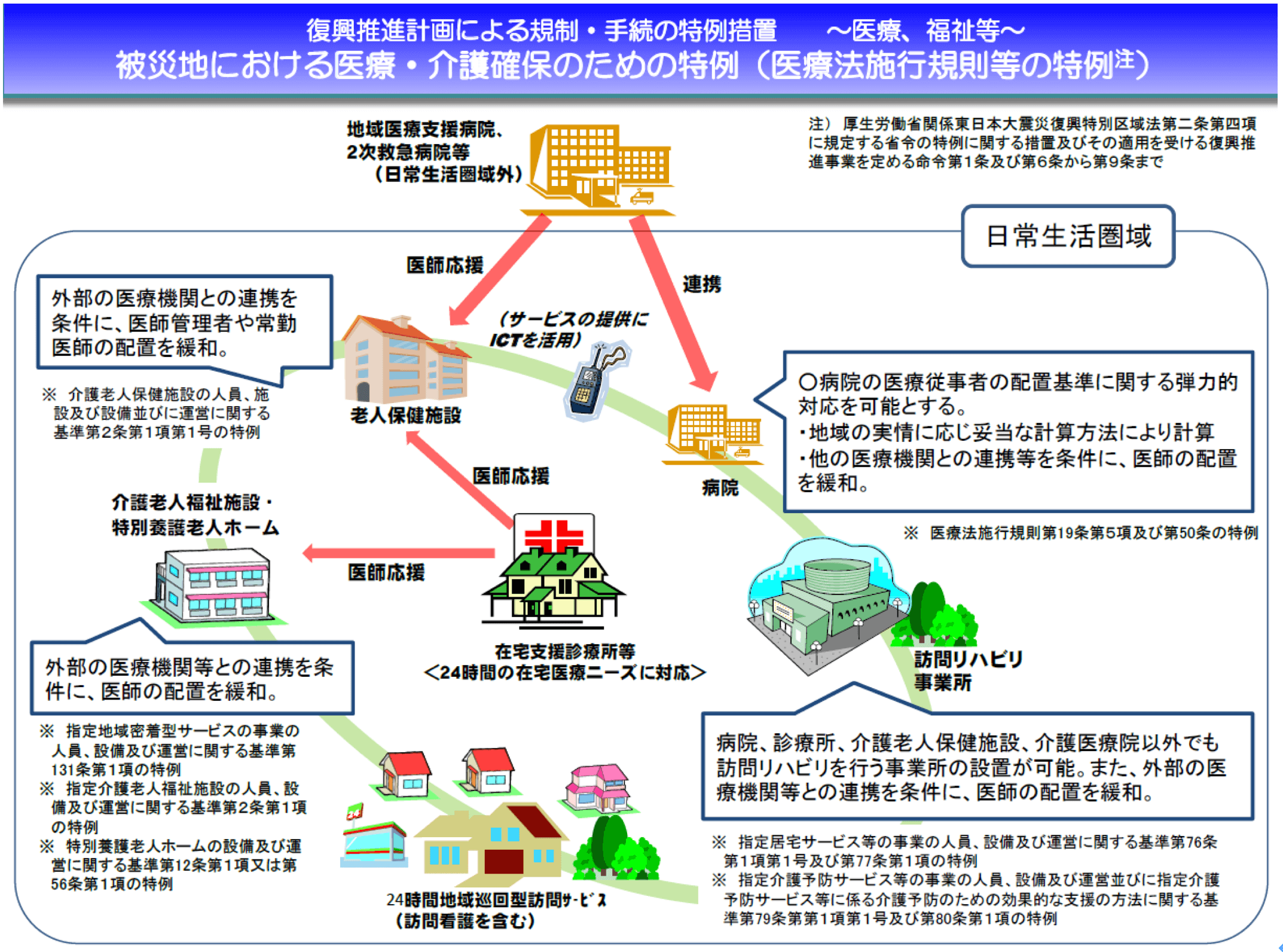
15) 医療機器製造販売業等促進事業(厚労省令特例命令第2条及び第3条)
a. 概要
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)においては、医療機器の製造販売業者は「医療機器等総括製造販売責任者」を、製造業者は「医療機器責任技術者」を置かなければならないとされており、それらの資格要件の一つとして、実務経験の要件(3年)が規定されている。
県が医療機器製造販売業等促進事業及びその事業の期間を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合には、医療機器の総括製造販売責任者及び責任技術者の資格要件の一つである実務経験の要件(3年)に関する基準を緩和し、県が復興推進計画に定める基準(品質管理上、保健衛生上等の観点から、現行の基準に相当する基準)を適用することとした。
b. 適用実績・効果
復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第2号(平成24年3月認定、令和3年4月まで5回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)、③福島県復興推進計画第1号(平成24年3月認定)の3計画が認定され、認定された各県において特例が適用された。
岩手県では、産業再生復興推進計画として、税制特例とともに計画された。
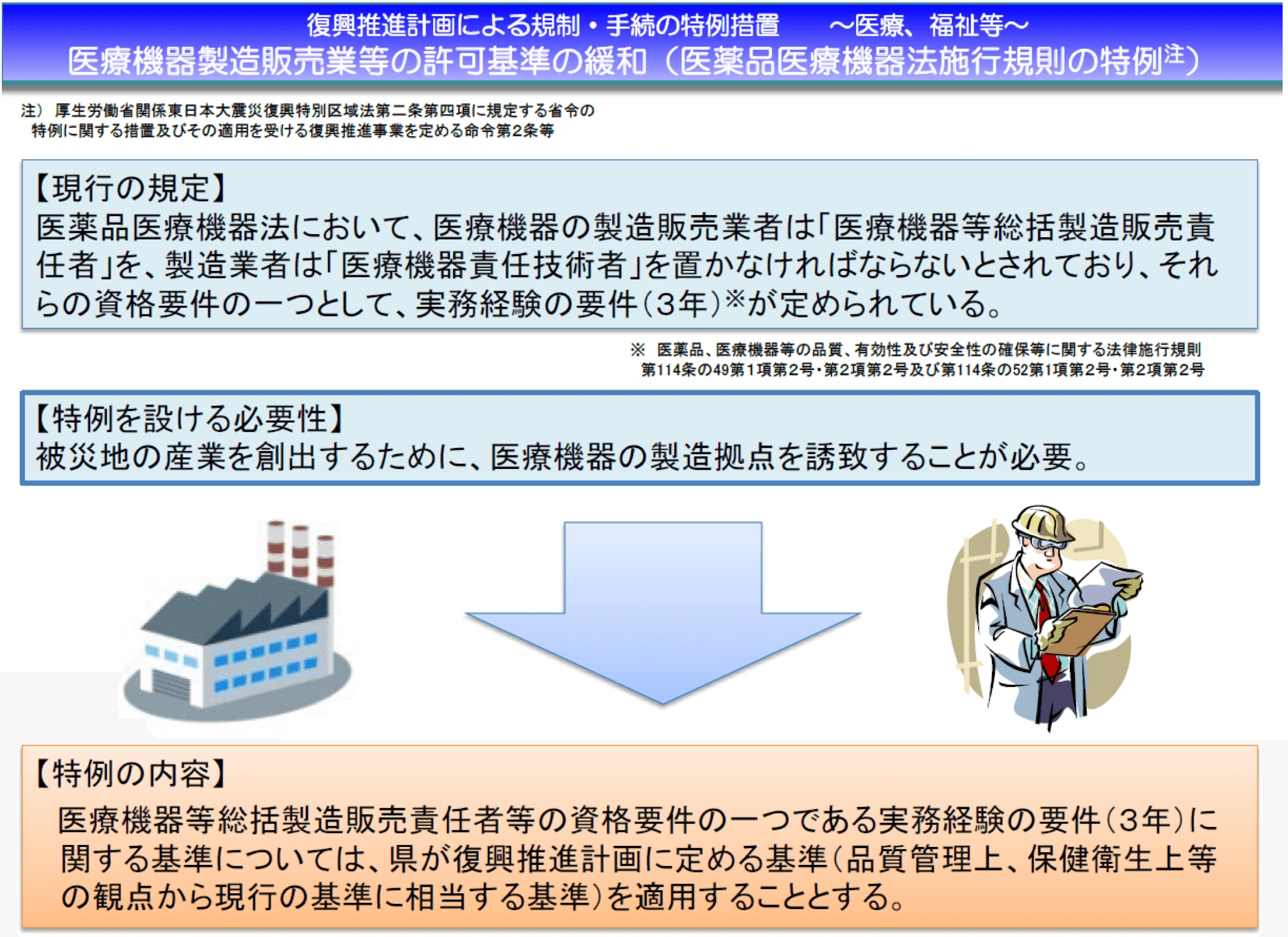
16) 薬局等整備事業(厚労省令特例命令第4条及び第5条)
a. 概要
薬局及び一般用医薬品を販売する店舗等の構造設備の基準を定めた薬局等構造設備規則には、薬局及び一般用医薬品を販売する店舗の面積に関する基準、リスクの高い一般医薬品を陳列するために必要な設備に関する基準等が規定されている。
県が、薬局等整備事業及びその事業の期間を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合は、薬局等整備事業に係る薬局等のうち、面積に関する基準を満たさないものであって、その所在地の県知事等が保健衛生上支障を生ずるおそれがないと認めたものについては、面積に関する基準等を適用しないものとした。
b. 適用実績・効果
復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和2年2月まで2回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)の2件が認定された。
計画が認定されたものの、実際には本来の面積基準を満たす薬局等が整備されたなどの理由により、結果的に活用実績はなかった。
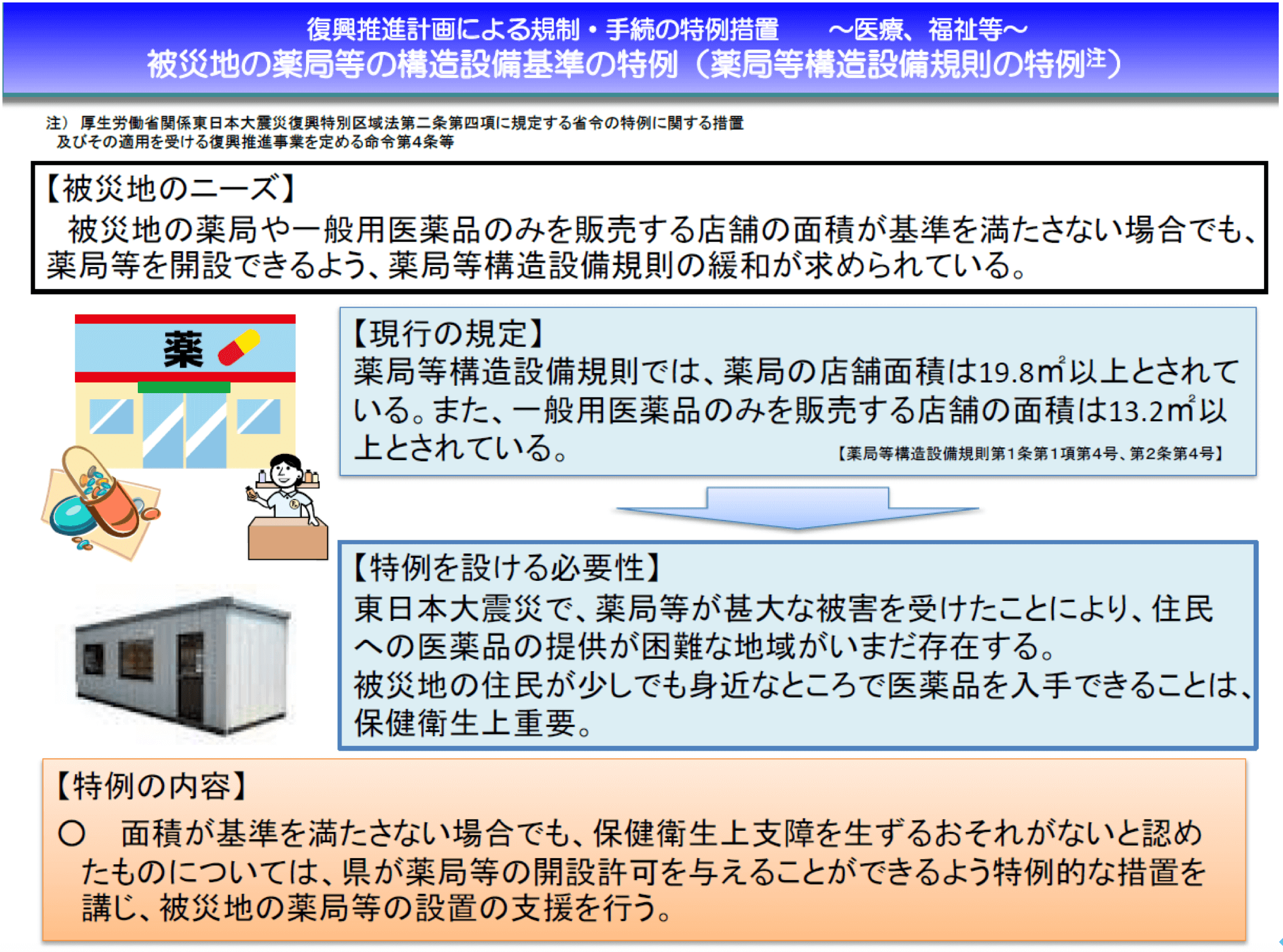
17) 訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(厚労省令特例命令第6条)
a. 概要
指定訪問リハビリテーション事業所の開設主体は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に限定されている。また、同事業所ごとに指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数の医師を置くこととしている。
本特例は、県が、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所の整備を推進する事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院との密接な連携を確保し、指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の県知事が認めるものについて、指定訪問リハビリテーション事業所の開設要件及び同事業所ごとに置くべき医師の員数を緩和するものである。
b. 適用実績・効果
復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和2年2月まで2回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)、③福島県復興推進計画第3号(平成24年4月認定、令和5年3月まで4回変更認定)の3計画が認定され、認定された各県において特例が適用された。
いずれの県も、平成24年の早い段階での計画策定を行っている。また、いずれも変更認定にて適用期限の延長を行っている。
岩手県で6事業所、宮城県で3事業所、福島県で4事業所が特例を活用し、利用登録者は合計910人(令和元年6月末時点)であった。
福島県では、令和3年11月まで、2自治体に所在する4事業所が本特例を活用した。特例活用終了後は、訪問看護ステーションに移行する等の移行措置がとられた。
自治体からは、「訪問リハビリテーション事業所の開設のため若くて意欲的な人材が集まり地域が活性化するとともに、若者の雇用の場が生まれた」、「町民の在宅サービスの選択肢が増え、在宅介護の充実が図られた」との声があった22。
本特例の活用により、被災地に必要な介護体制の確保につながった。
- 22 復興庁復興特区班が実施した自治体アンケート結果による。
18) 介護老人福祉施設等整備推進事業(厚労省令特例命令第7条)
a. 概要
老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)においては、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数の医師を配置しなければならないこととしている。
本特例は、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な介護老人福祉施設等の整備を推進する事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、区域内の特別養護老人ホーム等であって、病院や介護老人福祉施設等との密接な連携を確保し、入所者に対する健康管理及び療養上の世話を適切に行うと所在地の県知事(地域密着型介護老人福祉施設にあっては、市町村長)が認めるものについては、医師の配置基準について、弾力的な対応を可能とするものである。
b. 適用実績・効果
復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和2年2月まで2回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)、③福島県復興推進計画第3号(平成24年4月認定、令和5年3月まで4回変更認定)の3計画が認定された。計画は認定されたものの、実際には必要な医師数を確保することができたことなどにより、いずれの県においても活用実績はなかった。
19) 介護老人保健施設整備推進事業(厚労省令特例命令第8条)
a. 概要
介護老人保健施設については、医師を常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上配置しなければならないこととしている。
本特例は、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な老人保健施設等の整備を推進する事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、区域内の介護老人保健施設であって、病院若しくは診療所又は介護医療院との密接な連携を確保し、入所者に対する看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を適切に行うとその所在地の県知事が認めるものについて、医師の配置基準の弾力的対応を可能とするものである。
b. 適用実績・効果
復興推進計画は、①岩手県復興推進計画第1号(平成24年2月認定、令和2年2月まで2回変更認定)、②宮城県復興推進計画第6号(平成24年4月認定、令和2年1月まで2回変更認定)、③福島県復興推進計画第3号(平成24年4月認定、令和5年3月まで4回変更認定)の3計画が認定された。
宮城県において、1事業所が本特例を活用した。同事業所は、平成27年4月から7月までの間、特例を活用したが、8月以降に常勤の医師が確保され、その後は特例を活用していない。岩手県及び福島県は、計画を策定したものの、実際には必要な医師数を確保することができたことなどにより、活用実績はなかった。
20) 介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(厚労省令特例命令第9条)
a. 概要
指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の開設主体は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に限定されている。また、同事業所ごとに指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数の医師を置くこととしている。
本特例は、県が、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の整備を推進する事業を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、区域内の指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院との密接な連携を確保し、指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の県知事が認めるものについて、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の開設要件及び同事業所ごとに置くべき医師の員数を緩和するものである。
b. 適用実績・効果
17)訪問リハビリテーション事業所整備推進事業と同様である。
(4) 金融上の特例(復興特区法第44条)
1) 概要
復興推進計画の区域における雇用機会の創出その他の東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼす事業のうち、復興推進計画の目標を達成する上で中核となる事業を行う際に金融機関が必要な資金を貸し付ける場合に、利子補給金(復興特区支援利子補給金)を支給している。
復興特区支援利子補給金は、平成24年11月以降、公募の仕組みを導入し、平成25年度以降、毎年度3回の公募を実施してきている。また、令和3年度以降は復興状況等に鑑み、対象区域の重点化を実施したほか、福島県内陸部における案件においては、雇用機会の創出に寄与する事業について、公募時の要件における金融機関による融資合計額の水準を3億円から10億円に引き上げ、絞り込みを行った。
2) 認定事業の実施状況
a. 全体の実施状況
これまでに、金融の特例(利子補給)に係る復興推進計画は、令和3年度末時点で、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の5県の管内で、225計画が作成されている。被災地の地方公共団体においては、税制上の特例や金融上の特例の活用はもとより、必要に応じ、応急仮設建築物活用事業、復興産業集積事業等の規制の特例も活用している。
また、金融上の特例の適用を受けた案件における投資額は、延べで1兆円を超えている。
対象融資額は初年度がもっとも大きく、認定件数は平成26年度がもっとも多い。
復興が進むにつれ、件数・融資額ともに減少にある中、令和3年度はコロナ禍も実績減少に影響している。
県別では福島県の案件が約半分を占めており、宮城県が2割ほど、続いて茨城県、岩手県、青森県となっている。
b. 地域別の実施状況
ア) 青森県の実施状況
青森県の認定件数は令和元年度末までの累計で11件。三沢市、八戸市、おいらせ町の3市町村で実施がなされた。
投資見込額は総額237億円、融資見込額112億円となっている。
また、新規雇用予定者数は515人である。投資規模が小さく、制度利用状況も限定的となっている。
イ) 岩手県の実施状況
岩手県の認定状況は平成30年度末までの累計で20件(沿岸北部5件、沿岸南部9件、内陸南部6件)。
投資見込額は総額431億円であり、沿岸北部137億円、沿岸南部151億円、内陸部143億円となっている。融資見込額は288億円であり、沿岸北部51億円、沿岸南部114億円、内陸部123億円となっている。
また、新規雇用予定者数は1,119人である。沿岸南部の認定件数が全体の4割以上を占めるが、復興の進展もあり、平成30年度の認定が最後となっている。
ウ) 宮城県の実施状況
宮城県の認定件数は令和3年度の実績はなく、令和2年度末までの累計で53件(沿岸北部10件、沿岸南部25件、内陸部18件)。
投資見込額は総額2,636億円であり、沿岸北部353億円、沿岸南部1,702億円、内陸部580億円となっている。融資見込額は総額937億円であり、沿岸北部131億円、沿岸南部387億円、内陸部419億円となっている。
また、新規雇用予定者数は2,545人である。認定件数、投資見込額は沿岸南部が最大、融資見込額は内陸部が最大となっている。沿岸北部の認定は平成30年度が最後であり、令和元年度以降は沿岸南部の認定が多い(認定事業7件のうち5件が沿岸南部)。
エ) 福島県の実施状況
福島県の認定件数は令和3年度末までの累計で119件(県西部13件、県央部60件、沿岸部46件)。
投資見込額は総額4,378億円であり、県西部239億円、県央部1,476億円、沿岸部2,663億円となっている。融資見込額は総額2,109億円であり、県西部173億円、県央部806億円、沿岸部1,130億円となっている。
また、新規雇用予定者数は3,901人である。総じて、沿岸部においては設備投資が高い水準で推移している。
オ) 茨城県の実施状況
茨城県の認定状況は令和元年度末までの累計で22件。投資見込額は累計で3,226億円、融資見込額765億円となっている。
また、新規雇用予定者は1,091人である。認定は、復興初期の緊急的投資が多くを占めており、累計22件のうち6件が令和24年度の認定となっている。その後は復興の進展によって認定件数が減少しており、令和元年度2件の認定が最後となっている。

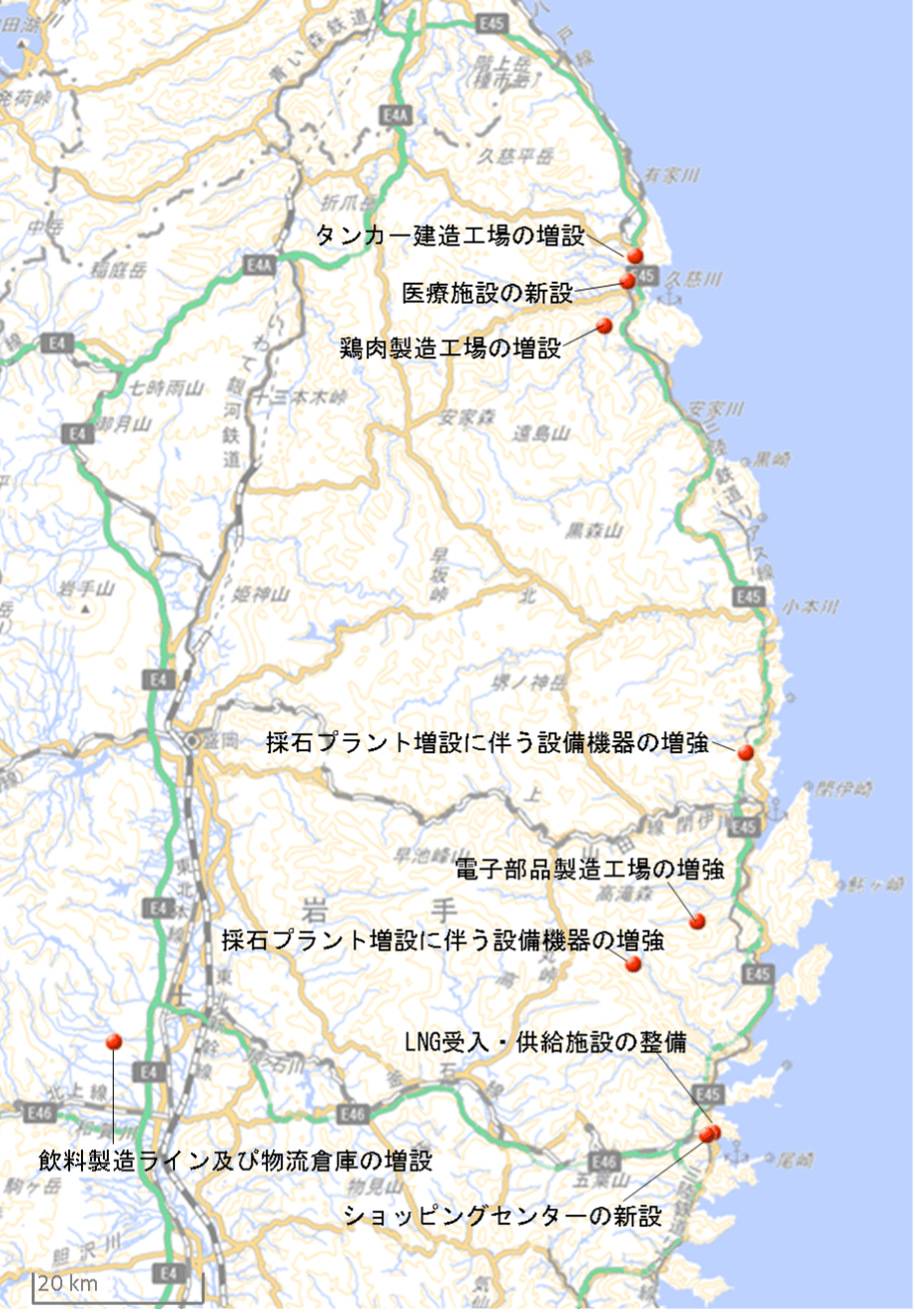


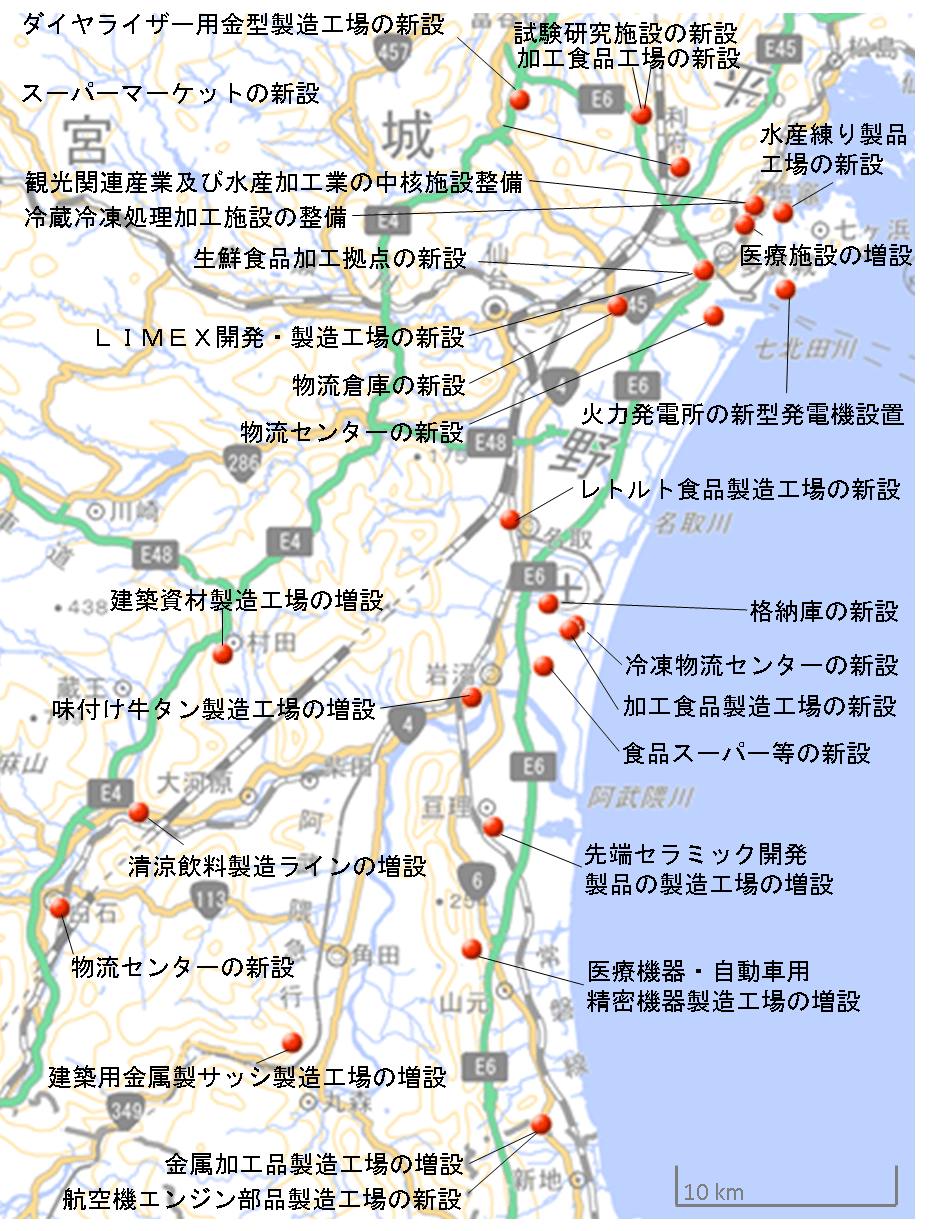

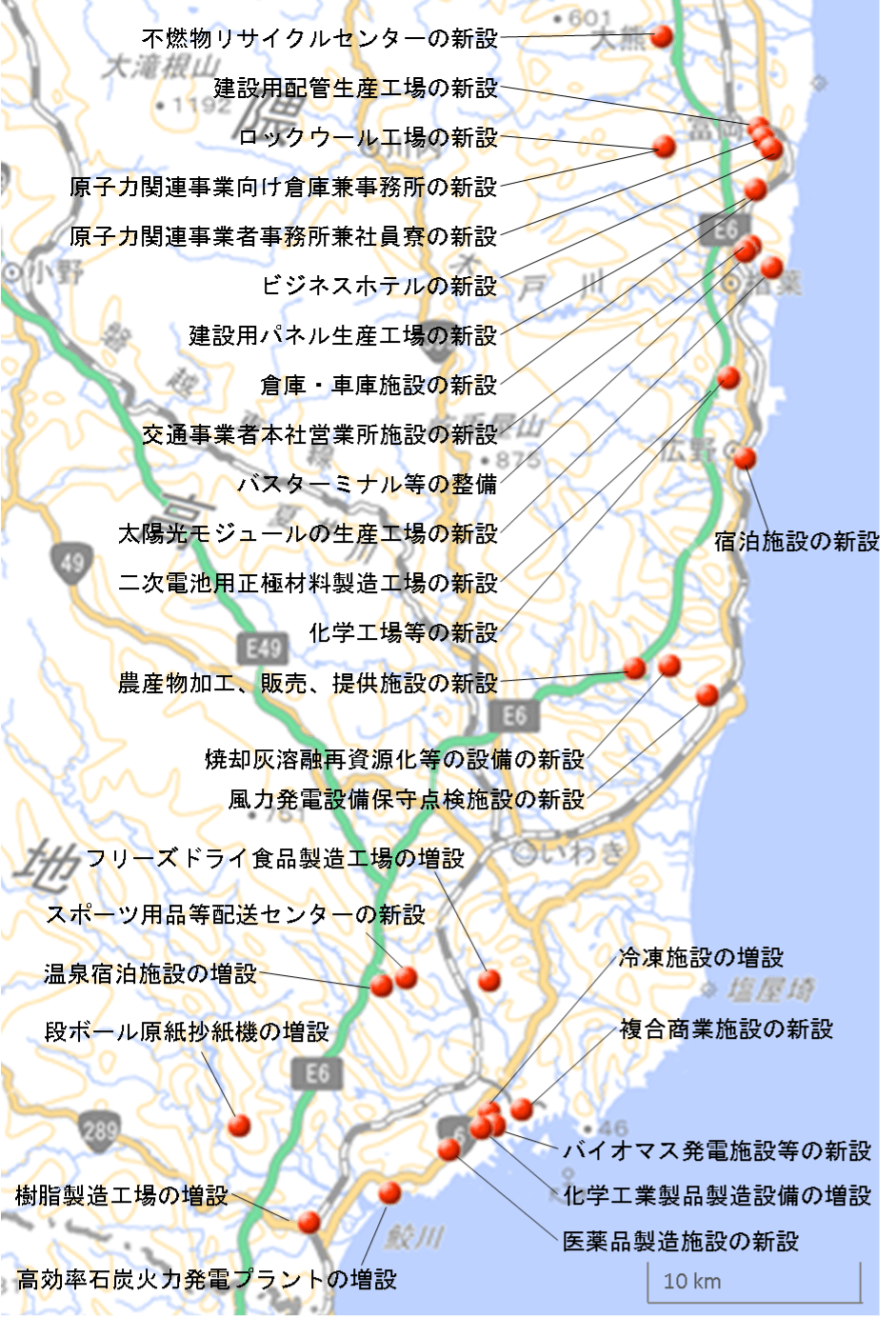
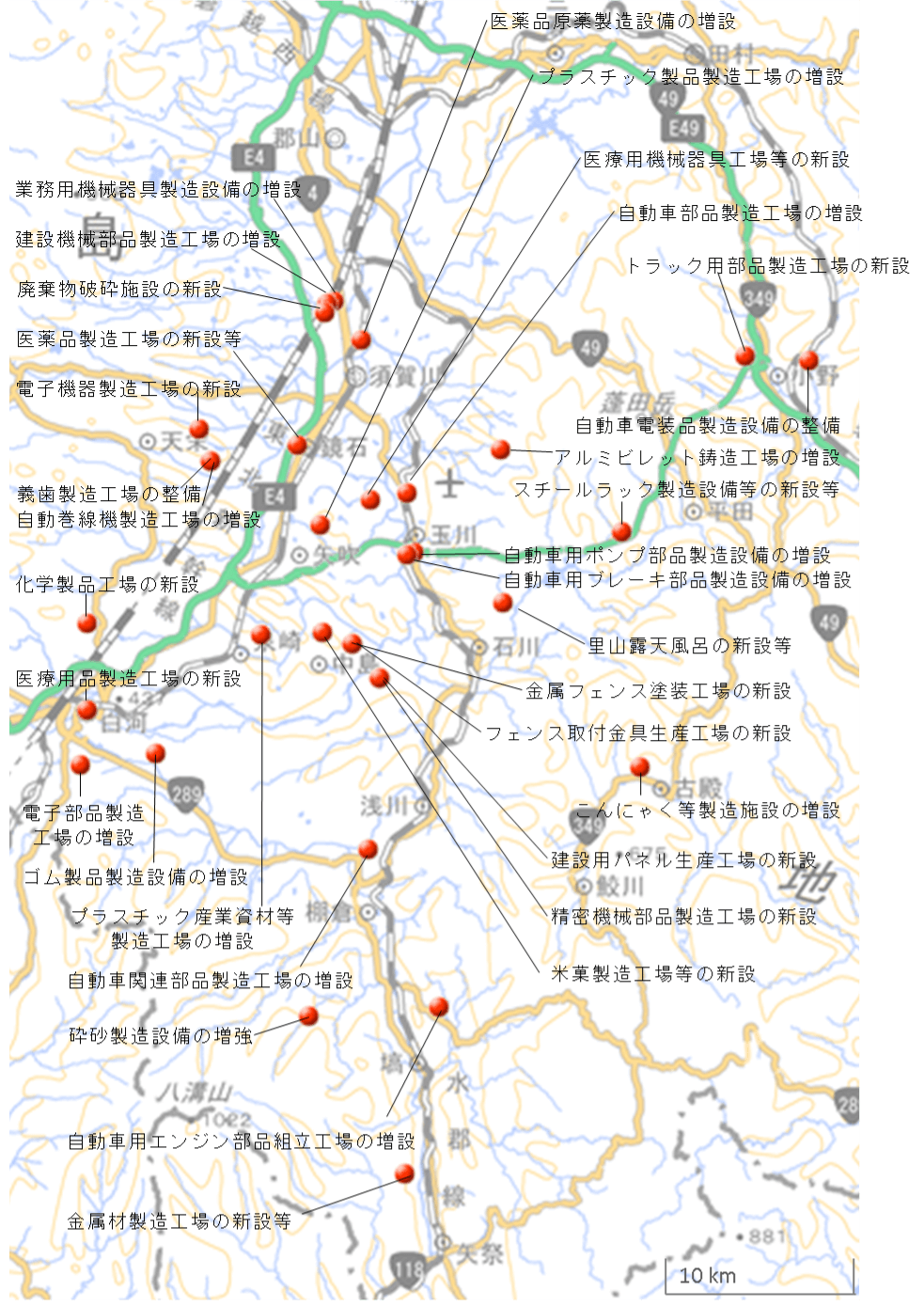

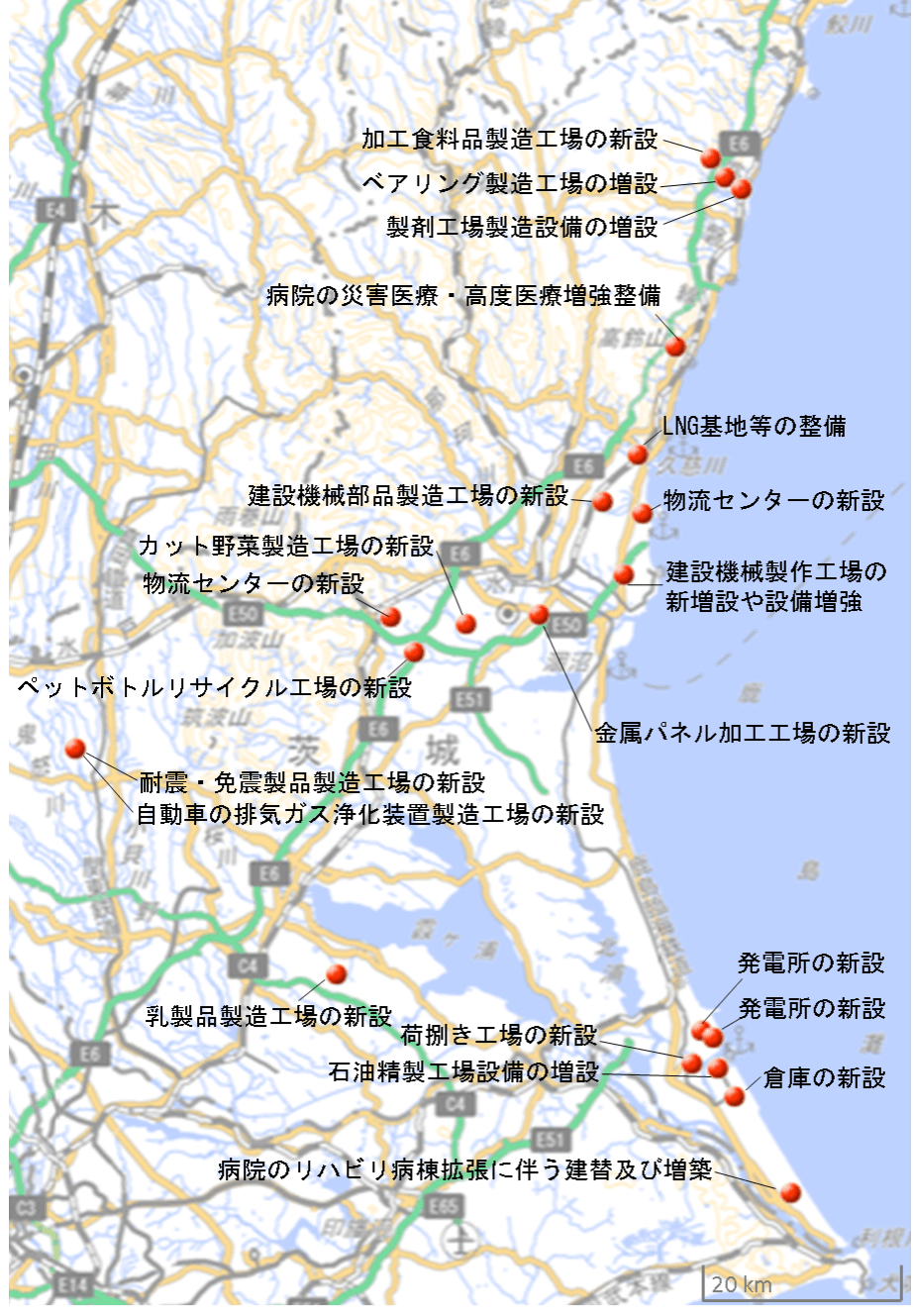
c. 実施状況の小括
融資見込額は初年度がもっとも大きく、認定件数は平成26年度がもっとも多い。復興が進むにつれ、件数・融資見込額ともに減少傾向にある。
投資規模別にみた場合、青森県、岩手県は1件当たりの融資見込額、投資見込額とも比較的小さく、茨城県がもっとも大きい。1件当たりの新規雇用予定者数は、茨城県がもっとも多く、福島県がもっとも少ない。
青森県は認定件数がもっとも少なく、投資規模も小さい。
岩手県は沿岸北部、内陸部は元々認定件数が少なく、沿岸南部においても復興が進むにつれ、案件が減少している。
宮城県は内陸部より沿岸部の認定件数が多く、全体の6割強が沿岸部である。但し、沿岸部の認定件数のうち7割は沿岸南部となっており、沿岸北部での認定件数は減少傾向にある。
福島県は県西部の案件は少なく、県央部の認定件数が5割を占める。投資規模は沿岸部が大きく、投資見込額の6割、融資見込額の5割を沿岸部が占める。
茨城県は復興当初の緊急的投資がピークであり、その後は復興の進展によって認定件数も減少している。
産業別にみた場合、製造業が全体の6割を占めており、卸売業・小売業が続く。1件当たりの事業規模は、電力・ガスが非常に大きい。製造業の中では、化学工業、パルプ・紙、輸送用機械、食料品といった業種が多くを占める。
このことから制度は地域における基幹産業の復旧・復興に貢献したものと思料される。
融資額100億円以下の産業では総事業費における利子補給対象融資額の割合が高く、地域における中核的企業の復興に役立っているものと思料される。
3) 他の災害復興に向けた補助制度との比較
a. 阪神・淡路大震災
ア) 阪神・淡路大震災と東日本大震災における利子補給制度の比較
阪神・淡路大震災では、復興特区支援利子補給金事業のような地域の中核企業や地域外の大企業の企業立地等を支援する目的で実施された利子補給制度は存在していなかった。
なお、阪神・淡路大震災の復興における中小企業向け利子補給制度に相当する今般震災の中小企業対策としては、政策金融機関において「東日本大震災復興特別貸付」や「東日本大震災復興緊急保証」等の新たな制度融資や信用保証制度を創設し、復旧・復興の段階や地域・業態等に即して各種資金ニーズに対応した。
また、阪神・淡路大震災復興基金による利子補給金事業の一覧と実績は、図表2-3-38のとおりである。
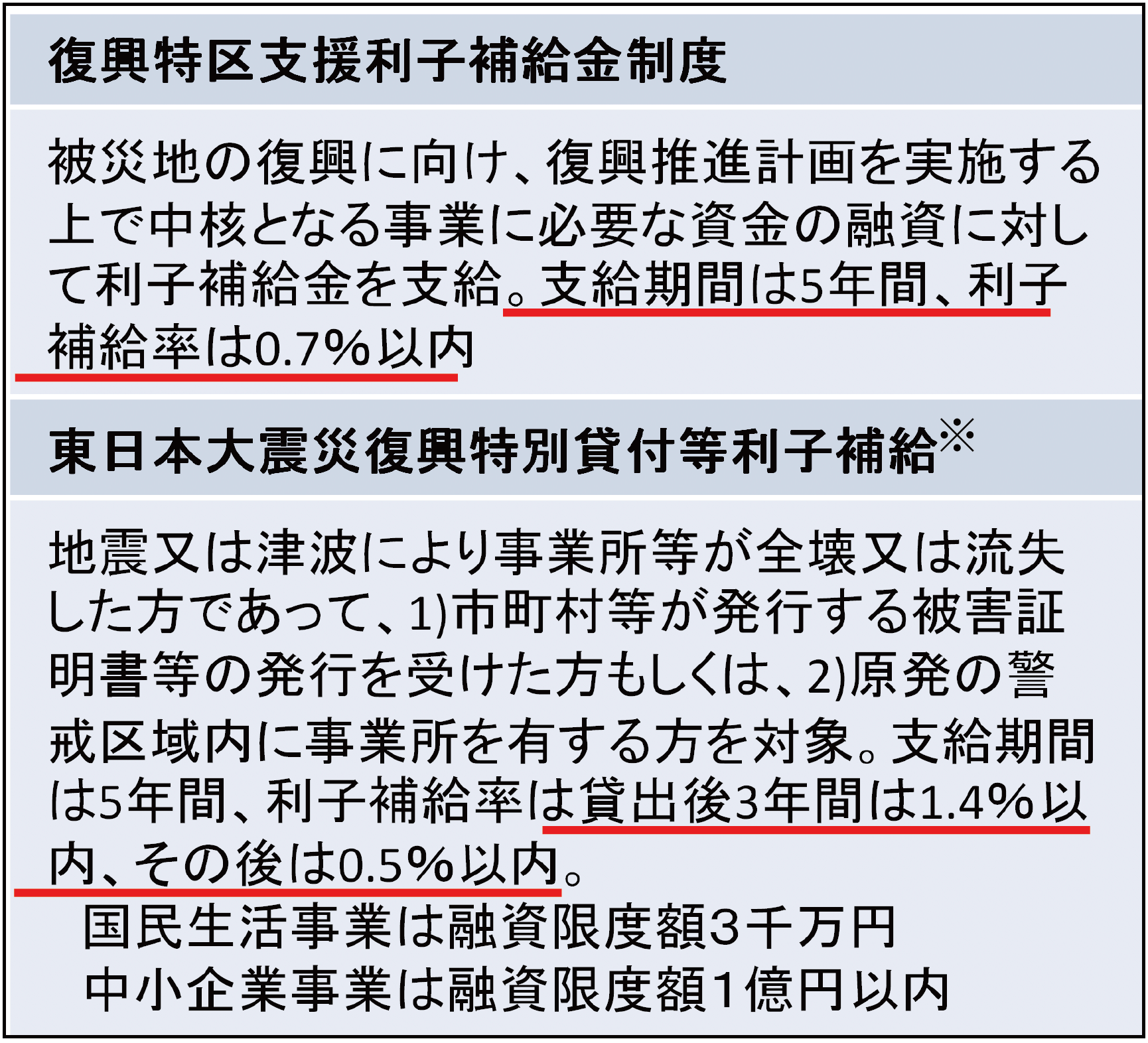
出所)復興庁作成
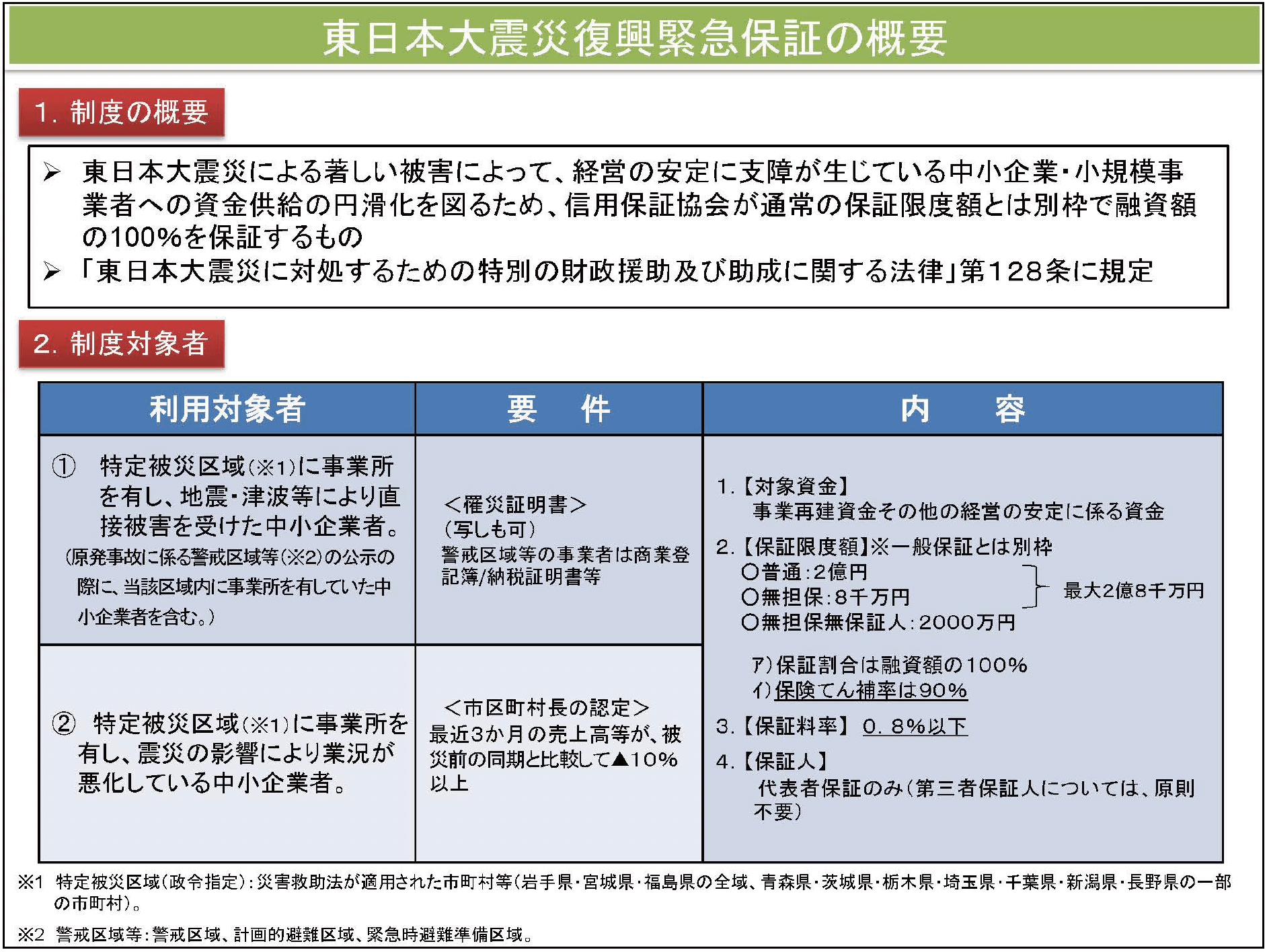
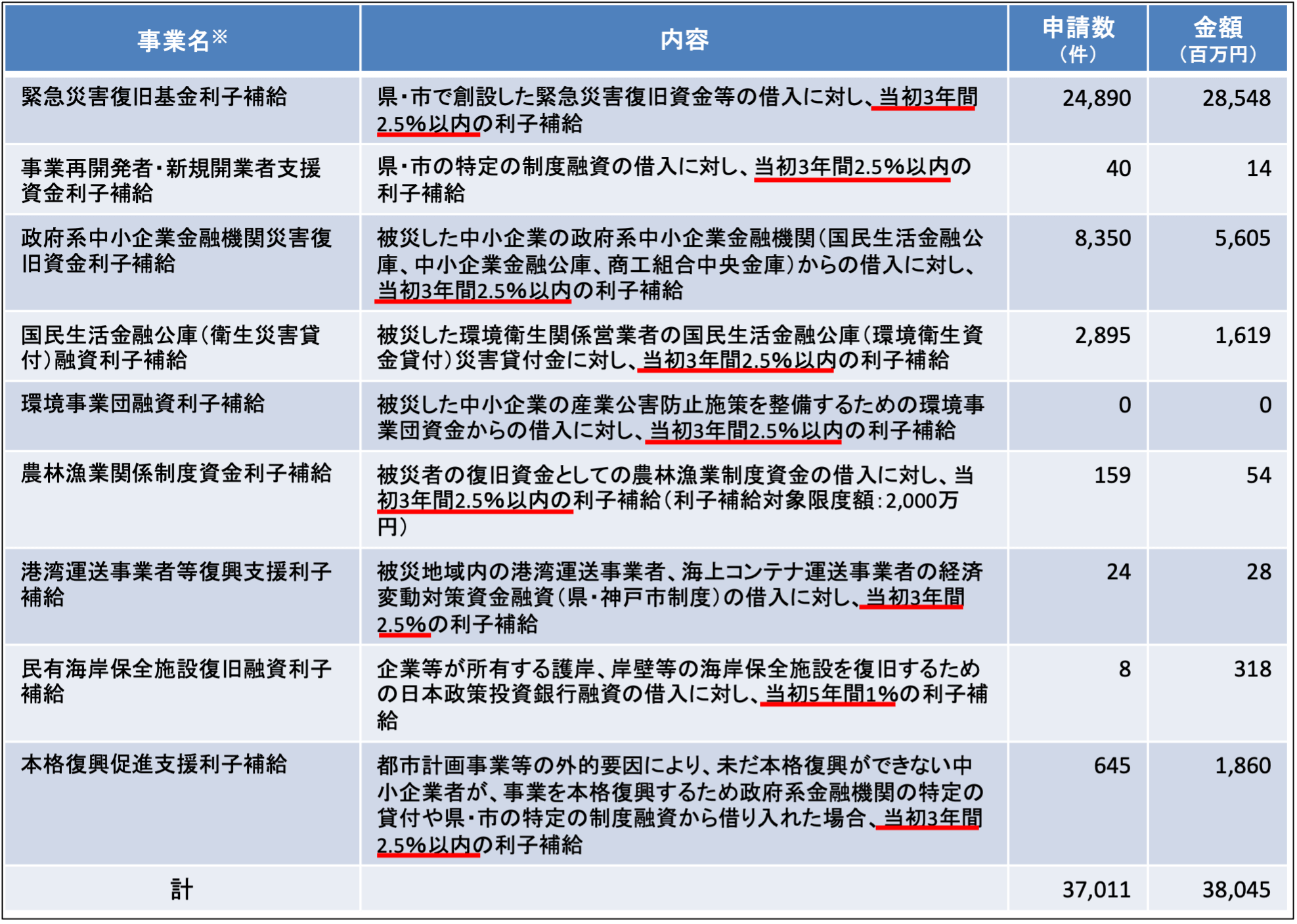
出所)内閣府「阪神・淡路大震災で実施された主要施策一覧」
イ) 阪神・淡路大震災の復興事業と比較しての、有識者等からのコメント
大学教授をはじめとした有識者、復興基金実務担当者等にヒアリングを行ったところ、次のとおりであった。
〇 阪神・淡路大震災と比較した東日本大震災復興事業の評価事項
・ 東日本大震災では、復興特区支援利子補給金事業及び東日本大震災復興特別貸付等利子補給において、阪神・淡路大震災の2倍を超える規模での支給が実施されている。
・ なお、補助金の適用利子率が阪神・淡路大震災の当時は2.5%前後、東日本大震災では0.7~1%であるため、利子補給制度が対象とする投資金額では東日本大震災の方が3倍以上になっているものと思料される。
・ 震災後に神戸に入ってきた有力企業はない。東北は企業誘致の面で相当頑張っていると思う。
〇 教訓事項
・ 阪神・淡路大震災の時は被災事業者への直接的な支援は実施されず、産業対策のメニューがほとんどなかった。
・ 阪神・淡路大震災の被災者はほとんどがサラリーマンだったので当時、経済支援の必要性はないとされ、個人事業主の救済が優先された。その結果、地場産業が落ち込んで大阪のベッドタウンになってしまい、自立した経済圏でなくなってしまった。
・ 製鋼、ゴム、ケミカル、港湾機能など国際競争力に晒される産業は災害に直面すると確実にやられる。一度離れた顧客はなかなか戻らないため、適切な支援がないと二度と競争力を取り戻せないということが阪神・淡路大震災の教訓である。
・ 産業支援は十分に資金をつぎ込まないと成果が上がらない。復興庁の取組は資金規模も大きく、十分に貢献しているものと考えられる。
b. その他参考(米国の例)
米国の経済復興に関わる金融支援の特徴を見てみると、我が国の利子補給制度とは異なり、災害時に事業者に対して提供される金融支援の中心は低金利融資であり、その他に被災自治体に補助金が提供され、これは経済復興支援にも活用可能である。
ただし、これらの金融支援は長期の産業復興を目的とする日本の金融支援とは異なり、中小企業の緊急的な資金ニーズに対する救済措置としての役割を担っている。
また、災害融資では金融機関を挟まずに直接審査・融資を行い、デフォルトリスクは連邦政府が負っている。そのため、借入には最低収入の要件と返済能力、信用履歴に関する審査があり、ハリケーン・サンディ時の融資承認率は42%にとどまるなど 、災害時の緊急的な資金ニーズを十分に満たしているとは考えにくい。
4) 総括
a. 利子補給制度による経済効果
令和3年度末時点においては、支給認定事業者数は累計225件、本制度を活用した融資見込額は4,000億円以上、それに伴い創出された新規雇用予定者の規模は9,000人以上となっている。投資額でみると、延べで1兆円を超えている。
b. 評価・課題
平成30年度に復興特区支援利子補給金事業の検証調査を実施したところ、各関係機関等に対するヒアリング調査、及び事業者に対するアンケート調査への主な回答は次のようなものであった。
ア) 評価事項
・ 利子補給制度の経済効果の計算方法について、利補支払額ではなく対象融資額とした計算の考え方は妥当である。利補支払金の分だけだと過小評価である。投資が喚起された部分を評価する必要がある。
・ 被災地における7,000人の新規雇用の意味は非常に大きいと思われる。神戸の場合は大阪が無事だったので雇用の問題はあまり起こらなかった。
・ 人手不足の状況の下では、新規雇用7,000人は地域にクラウディングアウトを引き起こした可能性がある。もちろん地域全体の経済効果としてはマイナスということはないが。
イ) 課題事項
・ 若い人がすぐに辞めてしまう。
・ 雇用を増やしたいがなかなか来てくれない。必然的に、派遣や外国人技能実習生に頼らざるを得ない。
| 制度の投資意思決定への影響有無 | 影響あり:75% |
| 借入の心理的しやすさへの影響有無 | 影響あり:86% |
| 投資規模拡大への影響有無 | 影響あり:60% |
| 投資時期前倒しへの影響有無 | 影響あり:54% |
| 制度活用事業の目的 | 事業の強化・拡大:62% |
| 現在の事業場の問題点 | 人材確保:91% |
上記をまとめると、投資の意思決定や借入金の増額など、制度が事業者の投資決定に一定の影響を与えていることが見受けられたところである。
なお、地方金融機関からは、東日本大震災からの復興政策10年間の振り返りに関する有識者会議(第4回)において、復興特区の利子補給制度を活用するためにはどの地域であっても融資額が3億円以上であることを要するというのは現実的ではなく、より小口の融資においても活用できる制度であれば活用事業者が増えるので検討いただきたいとの旨の意見があった。
また、行政経験者によるヒアリングにおいて、被災周辺部や在京大企業の誘致よりも、三陸沿岸などの被災者・地元中小企業者などに重点化すべきとの旨の意見があった。
(5) 復興整備計画
1) 概要
東日本大震災の被災地域では、津波による浸水をはじめとして、地盤の液状化や崩落等も含め、広範囲にわたって市街地、農地に甚大な被害が発生した。また、地域によっては、山間部が多く平地が少ないという地理的特性から、現地での再建が困難な箇所では、周辺の農地や森林等を含め、土地利用の再編を図りながら、復興に向けたまちづくり・地域づくりを進める必要があった。復興に向けたまちづくり・地域づくりを円滑かつ迅速に進めるには、各自治体が、それぞれ一つの計画の下で、都市計画法、農地法等の個別法による許認可、ゾーニング等の各種手続を一括して迅速に処理するとともに、市街地と農地の一体的な交換・整備や集落単位での住居の集団移転等、被災地域の実態に即した事業を展開していくことが必要となる。
復興整備計画は、このようなニーズに応えるために創設された制度であり、復興に向けたまちづくり・地域づくりを進めていくために必要となる市街地の整備や農業生産基盤の整備等の各種事業を対象に、許認可やゾーニングに係る手続のワンストップ処理、これら許可に係る基準の緩和、宅地と農地の一体的な交換・整備のための新たな事業手法の活用等、事業の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な各種の特例を講ずるものとなっている。
2) 復興整備計画の作成(復興特区法第46条)
復興整備計画は、被災地域の復興に向けたまちづくり・地域づくりのための計画として地域の様々な意見を考慮して作成するものとなっており、必要となる市街地の整備や農業生産基盤の整備等のための各種事業(以下「復興整備事業」という。)が記載されたものである。復興整備事業を復興整備計画に記載することによって、その円滑かつ迅速な実施をサポートするための各種の特例措置(手続の一元化、代行、迅速化、許可基準の緩和等)が適用されることになる。このことから、復興に向けたまちづくり・地域づくりを進めていく上で、このような特例措置を受ける必要がある場合には、各自治体が中心となって復興整備計画を作成するものとなっている。
復興整備事業は、復興に向けたまちづくり・地域づくりのための事業であり、構想から実施に至るプロセスを地域の住民の意向を反映しながら、順次進めていくものとなっている。
このため、復興整備計画は、復興整備事業による特例措置に応じた手続を経て、それらの事業の進み具合に応じた記載事項の追加等による変更が弾力的にできるものとなっており、必要な特例措置を柔軟に組み合わせて適用することによって、復興整備事業の円滑かつ迅速な実施を推進するものとなっている。
復興整備計画には、以下の基本的な事項を記載することとなる。
・復興整備計画の区域
・復興整備計画の目標
・土地利用方針
・復興整備事業に関する事項
・復興整備計画の期間
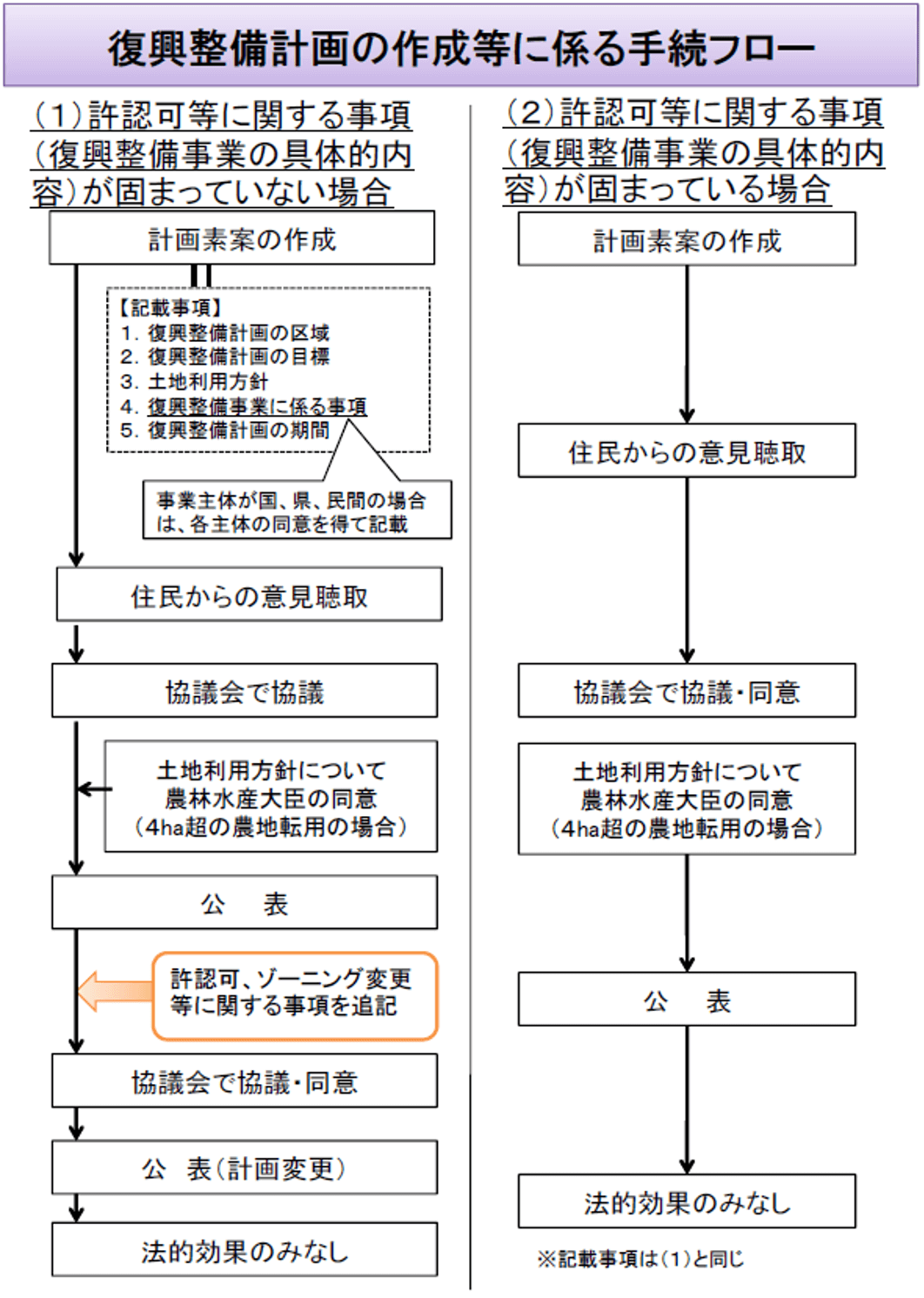
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/02manual_sankouyoushiki.pdf (令和5年7月14日閲覧)
3) 復興整備協議会の役割(復興特区法第47条)
復興整備計画を実効あるものとして作成・実施していくためには、幅広い関係者の意見を集約して、計画に反映させるための仕組みが必要となる。また、復興整備計画を活用して個別法の手続(許認可、ゾーニング、事業計画等)をワンストップ(一度に一堂に会して意思決定を行う事務処理)で処理するためには、当該手続に係る関係者が一堂に会し、実質的な調整を行うための場を設けることが必要になる。
このような事務処理を行うため、復興整備計画の作成主体となる市町村又は県は、復興整備協議会を組織することができるものとした。
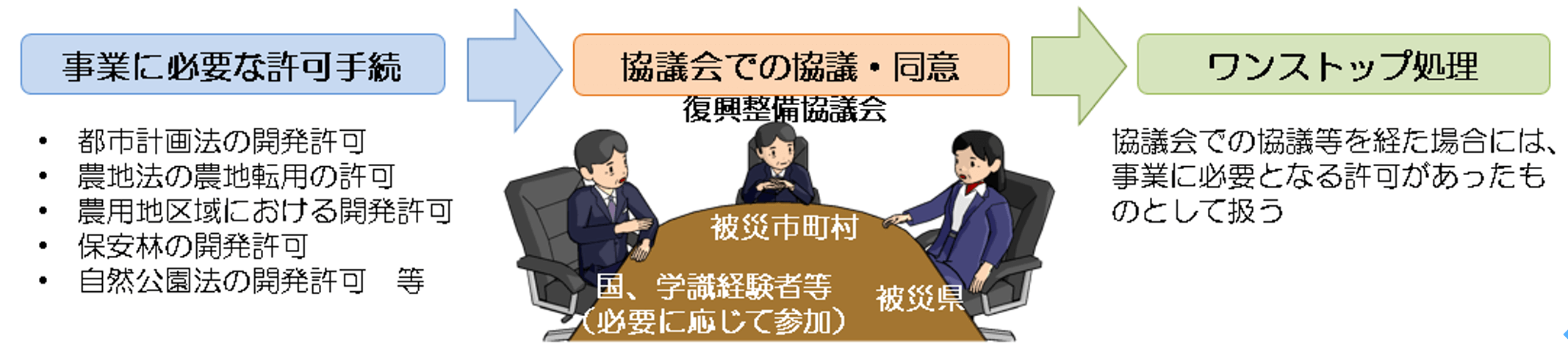
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/2206_setsumeishiryou.pdf (令和5年7月19日閲覧)
復興整備協議会は、以下の事項を協議する場となっており、その内容に応じて必要とする構成員を組み合わせて行うものとなっている。
・復興整備計画の作成・実施に関し必要な事項
・許認可、ゾーニング(法による指定区域)の変更、事業計画の作成に関する事項(ワンストップ処理に関する事項)
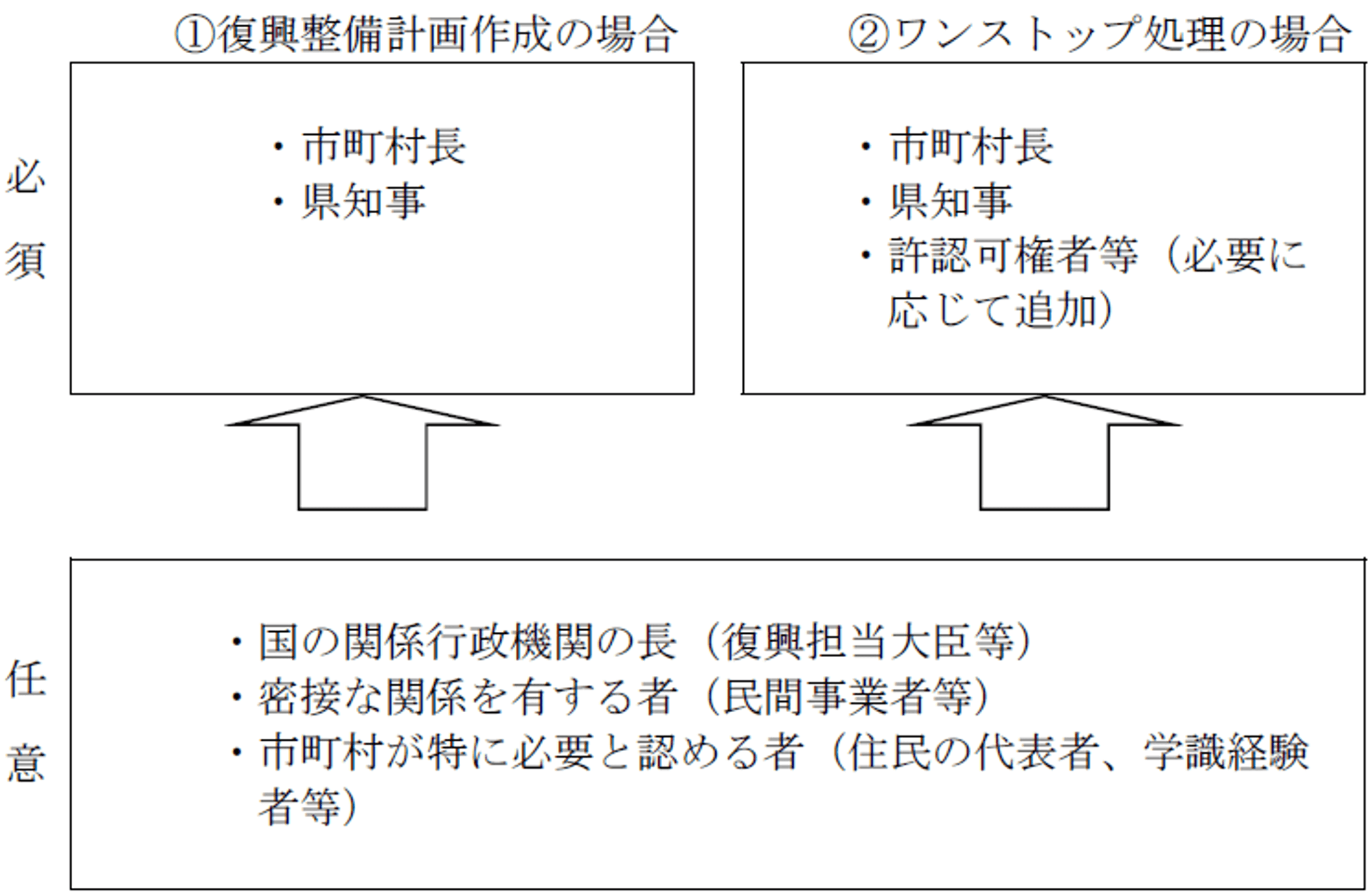
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/01manual_honbun.pdf (令和5年7月19日閲覧)
このように事務処理を行うことによって、各種窓口との協議、段階的な許認可等の手続が、一斉に事務処理されるものとなったため、打合せや関係機関との協議の回数が減ることとなり、また、年1回開催の審査会等に係る許可案件について協議会が毎月開催されることにより最大11か月の事務処理期間の短縮が図られたものがあったものの、作成書類の量については従前から大きな変化がないとの意見があった。
4) 主な法改正(平成26年法律第32号)
復興整備事業の円滑かつ迅速な推進には、その前提として事業に必要な用地の確保が不可欠となっているところであるが、被災地においては、様々な所有者不明土地が多数存在していたため、このことが、用地取得に当たっての隘路となり、復興の妨げとなっていた。このような状況を踏まえ、用地取得の加速化を図る必要があることから、財産管理制度、土地収用制度の活用、業務の外注の促進、実務支援等を図ることとした「用地取得加速化プログラム」の策定が行われ、その成果が具体的に現れ始めていた。
そのような中、被災地の現状としては、多数共有地、休眠担保、所有者不明土地等の件数が膨大にあり、また、土地収用法の適用対象外の事業も多く、さらに、自治体職員のマンパワーが圧倒的に不足していたことから、課題に対する適切な対応をできる状況にはなく、当該プログラムの効果が十分に機能できないとして、土地収用制度とは大きく異なる土地を収用するための特例制度の法整備の要望がなされていた。
このような要望を受けたこともあって、土地収用制度を更に活用するとともに、用地取得の一層の迅速化を図り、復興整備事業の工事着工の更なる早期化を図るためには、法制度の面から、土地収用制度に関する手続の期間短縮、緊急使用制度の活用促進等のための改正が必要となり、以下の内容のとおり法改正が行われることとなった。
ア 土地収用法による事業認定手続に当たって、「3月」以内に事業認定を行う努力義務を「2月」以内に短縮し手続の迅速化が図られた(法第73条の2)。
イ 土地収用法による裁決申請手続に当たっては、土地調書の添付が必要となっているものの、申請時においては、裁決申請書の記載事項の内、「収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。)」、「土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所」及び「土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積及びその内訳」の記載、土地調書の添付を省略することができることとした(法第73条の3)。
ウ 土地収用法による緊急使用のための工事着手の要件として、「東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」が明記されるとともに(法第73条の2)、損失補償額を供託する場合の弁済者の要件が「過失」から「重大な過失」に緩和された(法第73条の5)。
エ 土地収用法による緊急使用の期間を「6月」から「1年」に延長するとともに(法第73条の2)、裁決に要する期間をできる限り「6月」以内に行うものとされた(法第73条の4)。
オ 都市施設として認められる一団地の住宅施設の要件である「50戸以上」の集団住宅が、「5戸以上50戸未満」の集団住宅も小規模団地住宅施設整備事業として、都市施設としてみなされることとなった(法第54条の2)。
5) 実績
a. 復興整備計画の公表状況
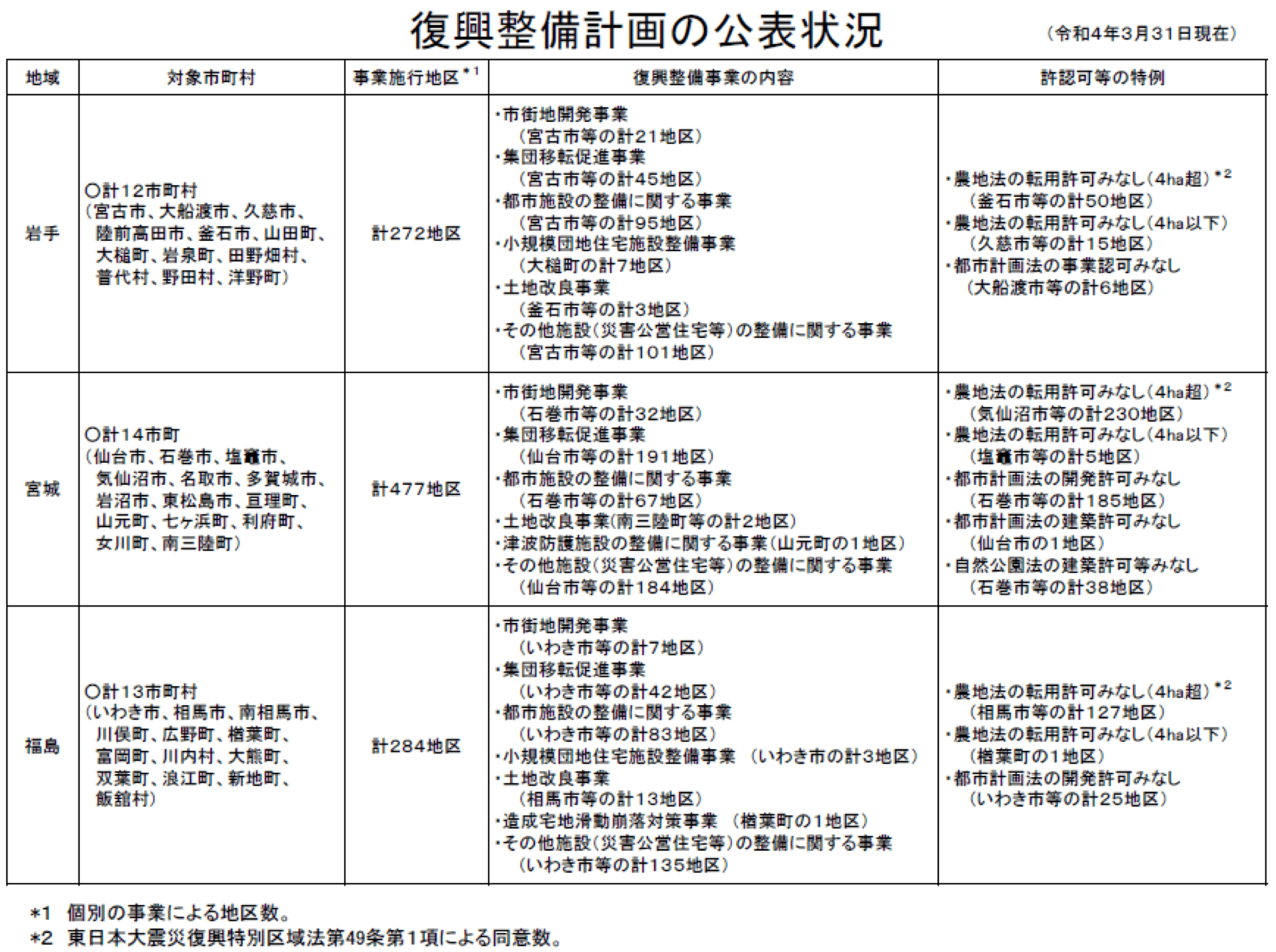
b. 復興整備事業の実施状況
ア) 岩手県
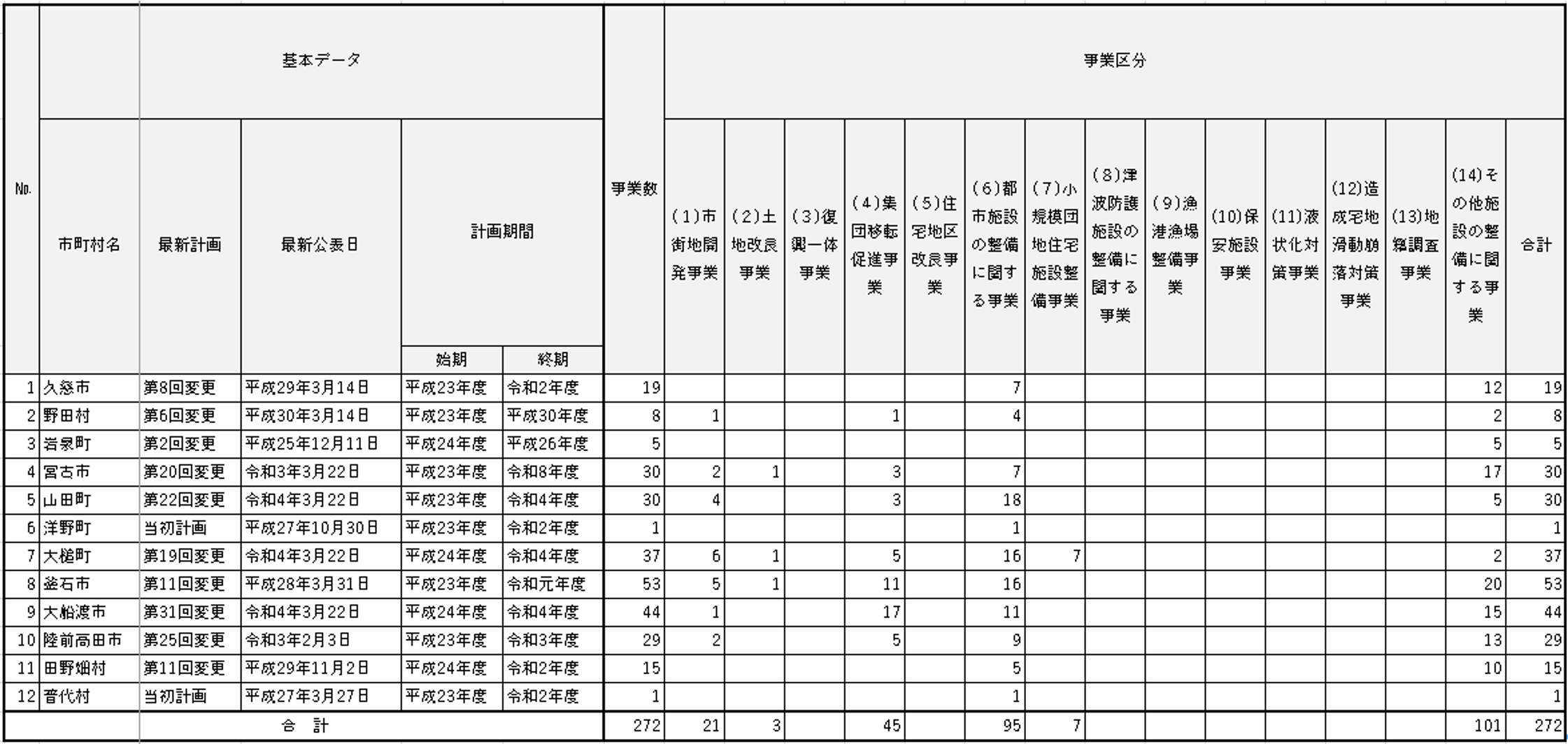
イ) 宮城県
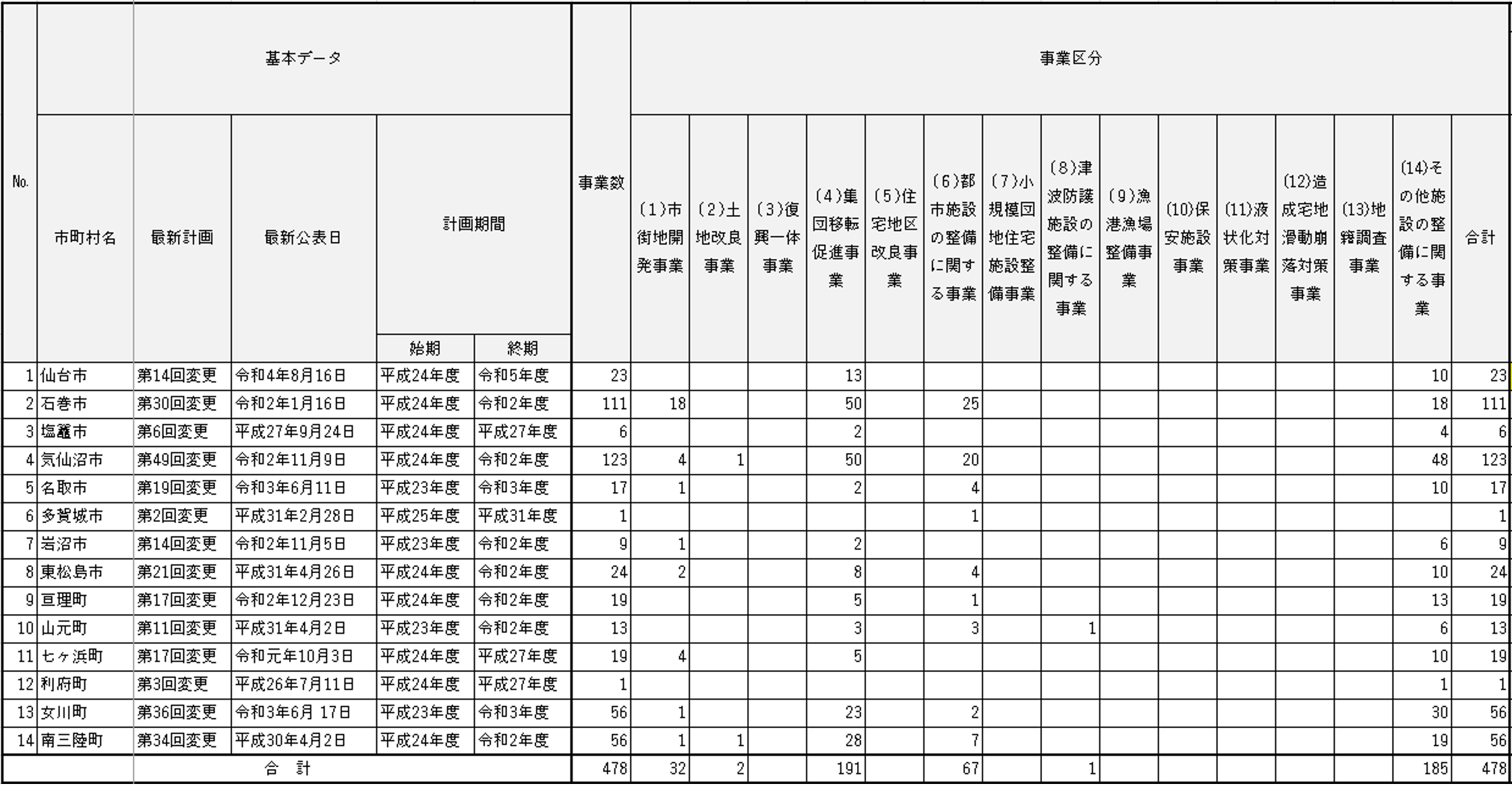
ウ) 福島県
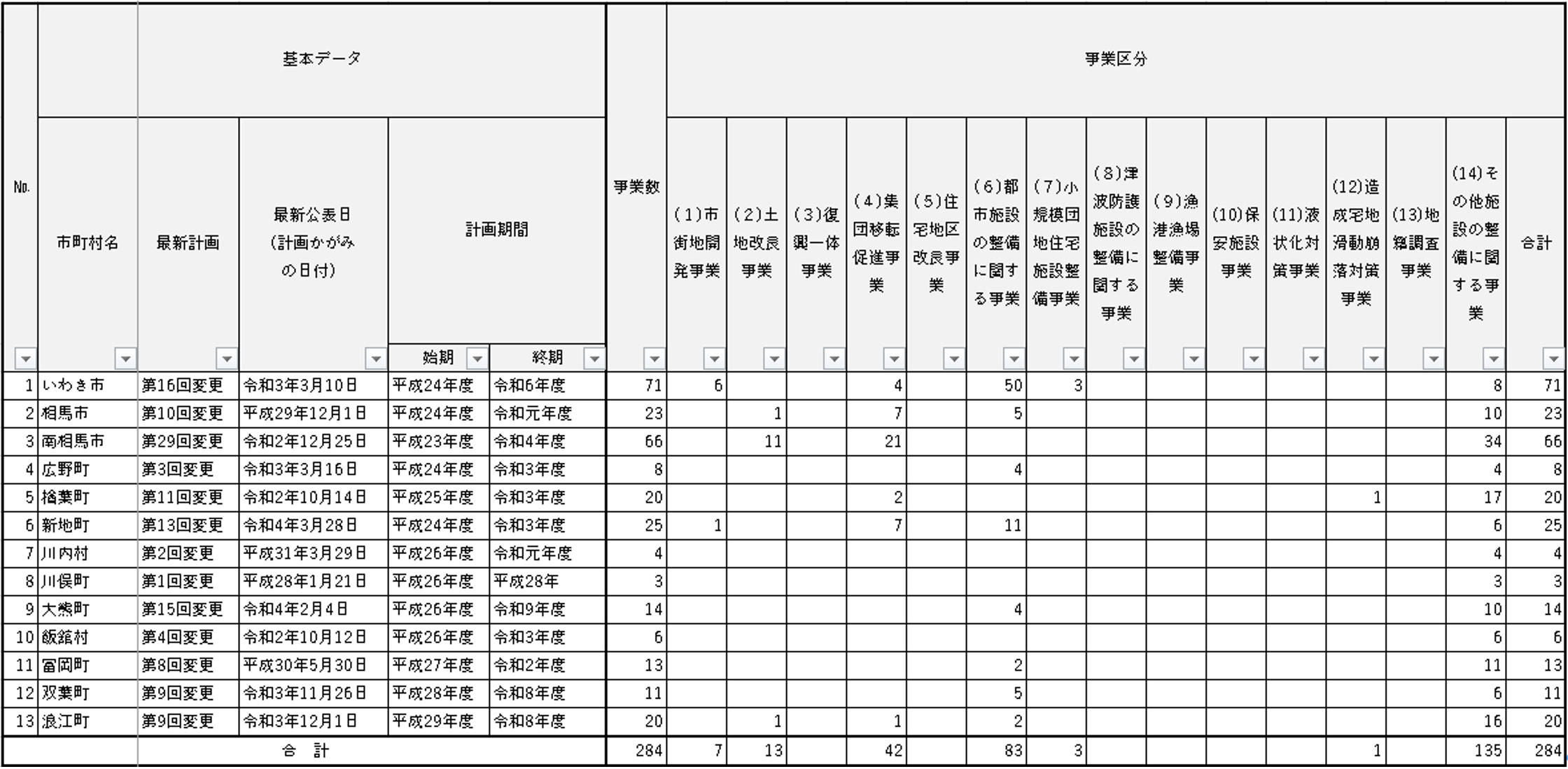
6) 土地利用基本計画に係る特例(ゾーニングの変更)(復興特区法第48条)
a. 概要
東日本大地震による被害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等においては、従来のゾーニング(各種法制度により指定がなされた区域)が大きく変更等される可能性が高いものとなる。
復興整備事業の実施に当たって、ゾーニングの変更等が生じる場合は、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法等の法手続に則って処理する必要があるものの、それぞれの法律に係る縦覧期間・意見聴取の手続等が区々であり期間を要するものであること、被災市町村によっては行政機能が著しく低下していたため、関係する法律の手続にそれぞれ拠っていては、地域の円滑かつ迅速な復興に支障を来たすおそれがある。
そのため、ゾーニングの変更等をワンストップで処理することができるものとした。
土地利用基本計画の変更等に関する事項は、以下のものとなっており、第5号以外は、都道府県知事が指定等権者となっているため、共同作成の場合に限り記載することができるものとなっている。また、それぞれの指定等に関する内容とその件数は以下のとおりとなっている。
| (令和4年3月末現在) | ||
| 1 | 土地利用基本計画の変更(国土利用計画法) | 147件 |
| 2 | 都市計画区域の指定、変更又は廃止(都市計画法) | 0件 |
| 3 | 都市計画の決定又は変更(都市計画法) | 172件 |
| 4 | 農業振興地域の変更(農業振興地域の整備に関する法律) | 7件 |
| 5 | 農用地利用計画の変更(農業振興地域の整備に関する法律) | 17件 |
| 6 | 地域森林計画区域の変更(森林法) | 150件 |
| 7 | 保安林の指定又は解除(森林法) | 58件 |
| 8 | 漁港区域の指定、変更又は指定の取消し(漁港漁場整備法) | 0件 |
なお、上記第3号又は第5号から第7号までの事項については、土地に関する権利に相当な制約が加わるものとなることから、当該事項を復興整備計画に記載しようとする場合においては、公告・縦覧に供するものとし、当該事項の案に対して提出された意見書の要旨については、その議をそれぞれ経なければならないこととなっている。
また、復興整備計画に上記第3号に定める事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続きの例によることとなる。
b. 効果
復興整備事業の実施に当たっては、主に、集団移転促進事業における住宅団地用地として、津波の影響が及ばない高台が選定されたことから、土地利用基本計画における森林地域の面積が591.01ha縮小するものとなり、また、被災地においては、被災者の住宅再建を図るため、市街地開発事業などが多く行われたことから、市街地の新たな形成を図るものとして、土地利用基本計画における都市地域は、1,263.3haの増加となった(令和4年3月末日現在)。
特に、土地利用基本計画の変更、都市計画の決定又は変更、地域森林計画区域の変更及び保安林の指定又は解除については、復興整備事業におけるまちづくりを行うに当たって、市街地開発事業、集団移転促進事業、都市施設の整備に関する事業などが多く行われたことから、件数が多いものとなった。また、被災自治体においては、復興整備事業を迅速に進めるという風潮が、許認可等の円滑な手続を後押しするものとなったようである。
都市計画区域の指定、変更又は廃止の件数は0件となっているが、復興整備計画を作成している市町村が40ある中、都市計画区域の定めのない町村は7となっており、概ね都市計画区域の指定がなされていたこと、そもそも、都市計画区域が広域に設定されていることなどから、変更する必要がなかったことによるものと考えられる。
農用地利用計画等の変更については、農地転用が先行して実施されていたこともあり、土地改良事業等の終了後に個別法により行われるものが通常となっていたことから、復興整備計画に事業を位置付ける際に、併せて農用地利用計画等の変更を行うもの又は復興整備事業の実施中若しくは終了後に特例により行われるものは少数となった。
漁港区域の指定、変更又は指定の取消しにおける件数は0件となっているが、海岸における復旧作業は、用地に関する問題が比較的生じなかったことから、東日本大震災復興特別区域法の施行を待つことなく、被災3県による早期の復旧の取組が実施されたことによるものと考えられる。岩手県においては、平成23年8月11日に「岩手県東日本大震災津波復興計画」、宮城県においては、同年10月18日に「宮城県震災復興計画」がそれぞれ策定され、また、福島県においては、今後の復興に当たっての基本理念や主要な施策を定めた「福島県復興ビジョン」を同年8月11日に策定し、その後、同ビジョンに基づく10年間における具体的な取組や主要な事業を示す「福島県復興計画(第1次)」が同年12月28日に策定された。これらの計画をもとに、東日本大震災直後から始まった各地の水産関係者の絶え間ない努力と実務の積み重ねによって成し遂げられてきた各種水産関連施設等の復旧・復興は速やかに実施され、平成24年4月18日時点における漁港の復旧状況は、以下のとおりとなっており、早期の復旧対応が図られるものとなった。
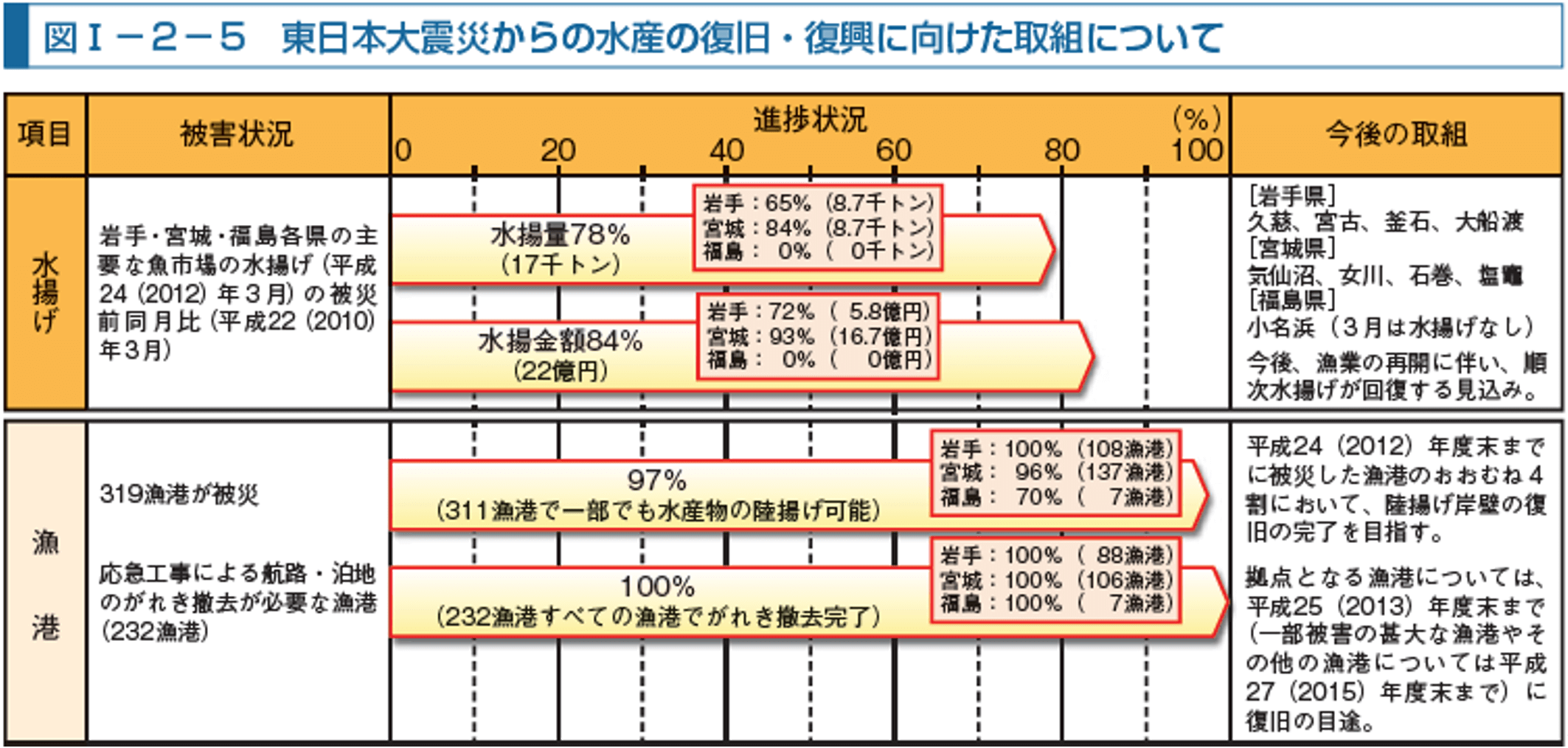
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h23/pdf/03_dai1shou.pdf (令和5年7月19日閲覧)
7) 復興整備事業に係る許認可等の特例(復興特区法第49条及び第50条)
a. 概要
東日本大地震による被害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等においては、復興整備事業を実施するに当たって、都市計画区域等における開発行為等の許可、農地転用の許可、農用地区域における開発行為の許可、地域森林計画における開発行為の許可など、個別法(それぞれの手続について定められた法律)の手続にそれぞれ拠ることとしていては、地域の円滑かつ迅速な復興に支障を来たすおそれがある。
そのため、復興整備事業の実施に当たり、それぞれの個別法による許可をワンストップで処理することができるものとした。
復興整備事業に係る許認可等の特例に関する事項及びそれぞれの許可等に関する件数は以下のとおりとなっている。
| 1 | 農地法第4条第1項及び第5条第1項に係る農林水産大臣の同意(4㏊超) | 390件 |
| 2 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可 | 210件 |
| 3 | 都市計画法第43条第1項の許可 | 1件 |
| 4 | 都市計画法第59条第1項から第4項までの認可又は承認 | 6件 |
| 5 | 農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可(4㏊以下) | 21件 |
| 6 | 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の許可 | 0件 |
| 7 | 森林法第10条の2第1項の許可 | 0件 |
| 8 | 森林法第34条第1項又は第2項の許可 | 0件 |
| 9 | 自然公園法第20条第3項の許可又は同法第33条第1項の届出 | 38件 |
| 10 | 漁港漁場整備法第39条第1項の許可 | 0件 |
| 11 | 港湾法第37条第1項の許可又は同法第38条の2第1項の規定による届出 | 0件 |
・ 4㏊超の農地転用が行われる場合においては、農林水産大臣の許可を得ることが必要となっており、また、農用地区域内の農地においては、農地転用が原則不許可となっているため、農用地区域内の農地を復興整備計画区域に位置付ける場合、事業の進捗に支障が生じるものとなる。そのため、復興整備計画の計画区域内において4㏊超の農地転用が行われる場合においては、事業を円滑かつ迅速に実施する必要があるため、農林水産大臣は、復興のため、必要かつ適当であり、農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合には同意するものとし、農用地区域内における農地転用を可能なものとした。
さらに、農地一筆毎に審査をすることなく、復興整備計画の計画区域内を一括して審査することができるものとした。
・ 市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされているものの、被災地域の円滑かつ迅速な復興又はこれらの地域の住民の生活の再建を図るためには、市街化調整区域内に施設等の整備を実施しなくてはいけない場合が生じることがある。そのため、被災関連都道県知事は、市街化調整区域内における開発行為の許可及び建築の許可に当たっては、復興整備計画に基づく復興整備事業として位置付けられた事業については、当該復興整備事業の実施区域の全部又は一部が市街化調整区域に含まれるものであっても、開発許可等の基準に適合するものであれば、同意をするものとした。
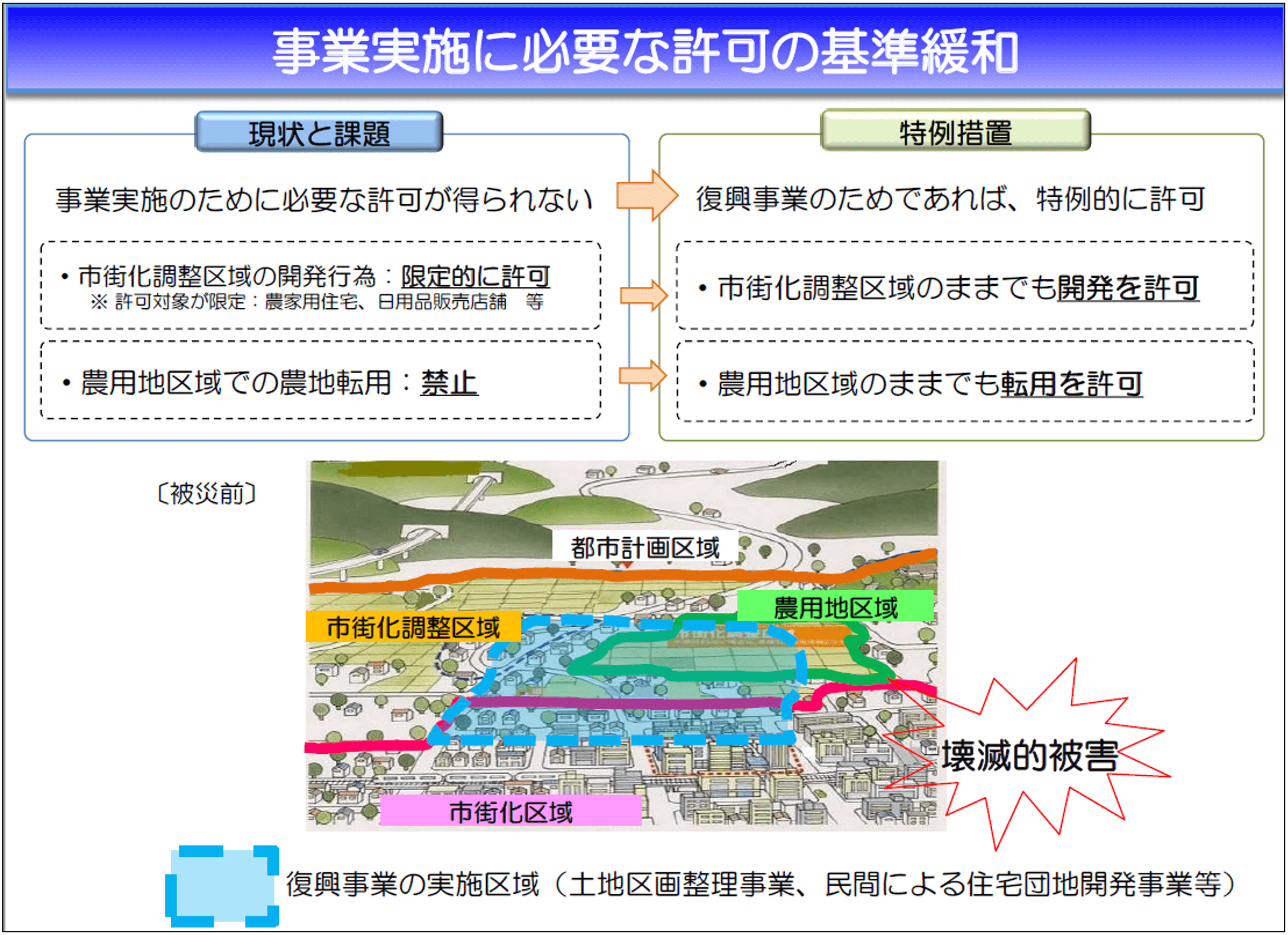
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/2206_setsumeishiryou.pdf (令和5年7月19日閲覧)
・ 岩手県上閉伊郡大槌町における一団地の住宅施設整備事業(赤浜地区)においては、都市計画の決定と都市計画事業の認可が、段階的にではなく、同時にワンストップで処理されたことから、期間の大幅な短縮(同時並行によるもの)が図られるものとなった。
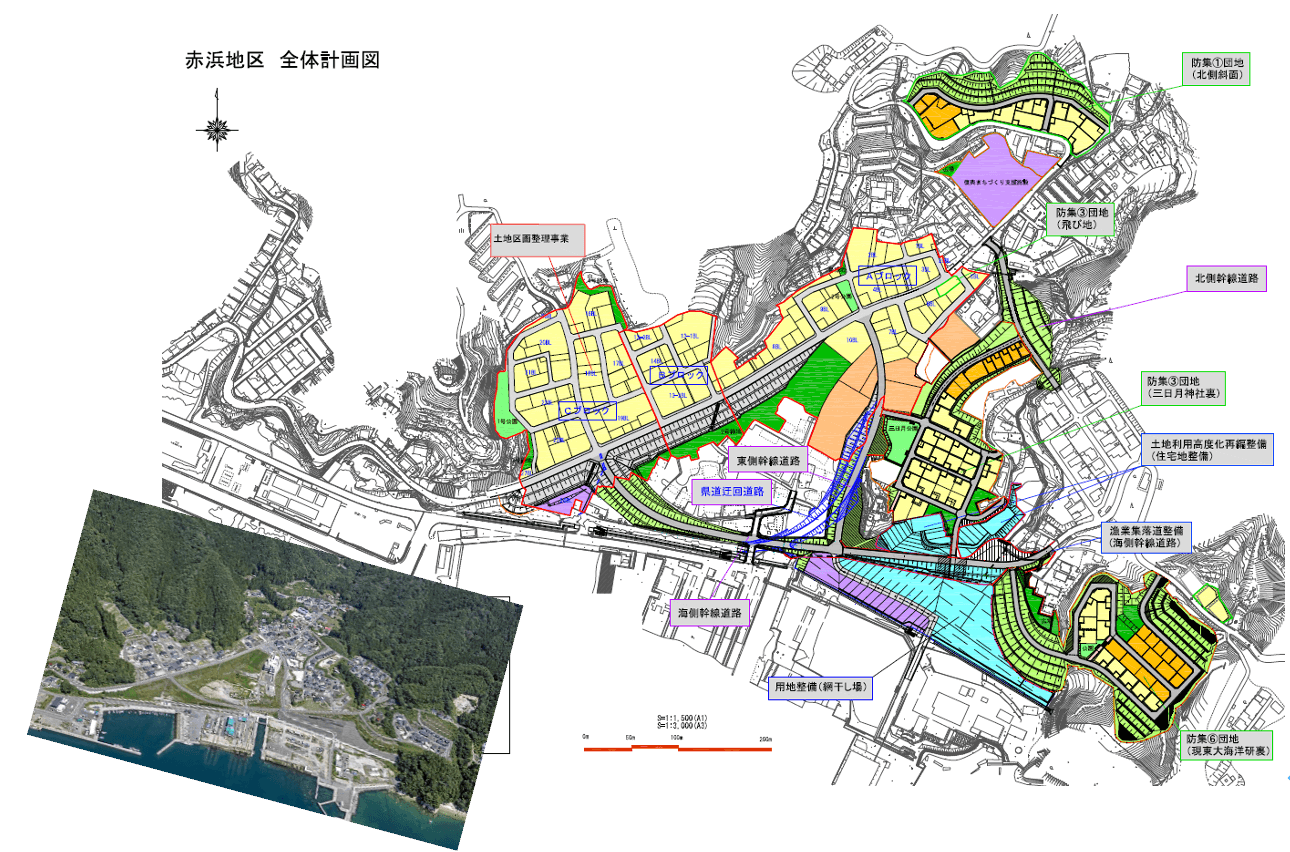
b. 効果
・ 被災自治体から、農地転用については、許可基準が復興特例となり、審査がまとめて行われるようになったことから、通常の手続に比べて、協議回数、作成書類など大幅に負担が軽減されたとの声があり、当該特例は多く活用されるものとなった。
当該特例が多く活用されることとなった背景として、農業振興地域内の農用地区域の除外手続には3~6か月程度の期間を要し、さらに、農地転用許可手続に当たっては3~6か月程度の期間を要し、通算概ね半年から1年程度の期間を要するものとることから、農地転用の手続は時間を要するものとなっている。そのため、被災地においては、迅速な復旧が望まれていたことから、東北農政局において発出した「平成 23 年東北地方太平洋沖地震災害に対応した農地転用手続の迅速な対応について」(平成23年3月18日付け事務連絡)により、農用地区域の除外及び農地転用の手続が同時並行的に行われることとなり、また、復興特区法により農地転用の特例が定められたことから、その手続に最短で2か月程度に期間が短縮されたことによるものとなっている。
また、宮城県内の年間の農地転用許可件数については、平成22年度までは約1,000件前後で推移していたものの、被災後の平成23年度は1,753 件、平成25年度は2,380件と震災前の倍の件数に大幅に増大するものとなった。
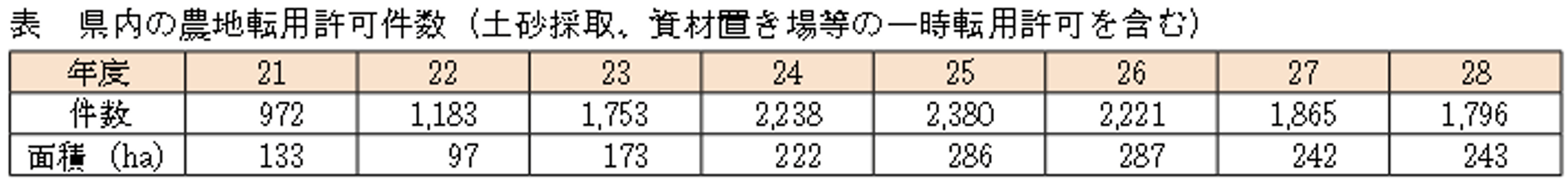
https://www.pref.miyagi.jp/documents/18704/648826_1.pdf (令和5年7月19日閲覧)
・ 開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可)については、被災を受けた箇所の復興に向けた一団のまちづくりを相当数進めていく必要があったことから、許可件数が210件に及ぶものとなった。なお、岩手県においては、岩手県権限移譲等推進計画により、平成20年に開発行為許可等に関する事務処理が市町村に移譲されていたこともあり、また、当該許可に当たっては、市町村における復興整備事業の進捗に支障のない期間による許可が可能であったことから0件となった。
・ 市街化調整区域内における建築物の新築等の許可(都市計画法第43条第1項)については、宮城県仙台市におけるその他施設の整備に関する事業による跡地利活用事業(新浜地区 地域コミュニティ広場トイレ整備事業)において行われた。当該事業箇所は、名取川・七北田川間の仙台東部道路から東側の地域となっており、仙台市における区域区分において市街化調整区域に指定されている区域となっている。事業の実施に当たっては、災害危険区域に指定された地区を市街化区域に編入するよりは、当該特例を活用することにより市街化調整区域にトイレの整備を行うこととしたものとなっている。
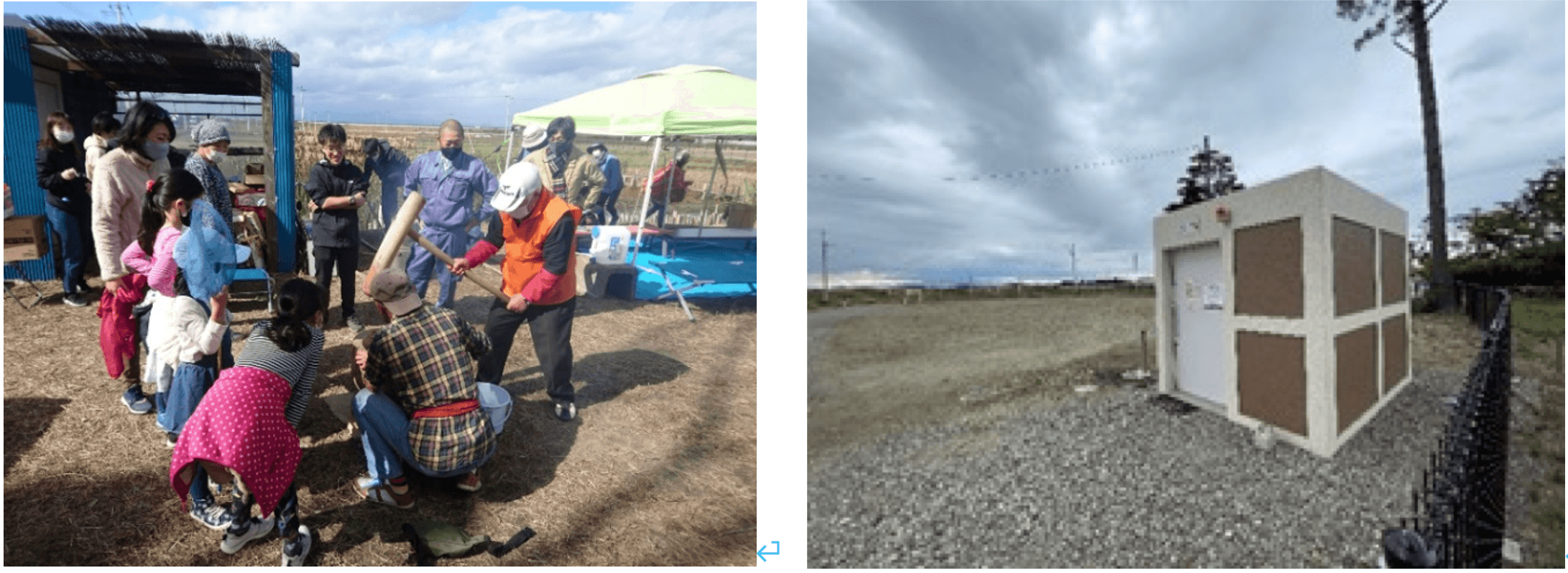
・ 事業認可(都市計画法第59条)については、岩手県大船渡市における「大船渡都市計画都市施設学校事業1号赤崎小学校及び附帯事業」及び「大船渡都市計画都市施設学校事業2号赤崎中学校及び附帯事業」並びに「一団地の住宅施設整備事業(安渡地区)」及び「一団地の住宅施設整備事業(赤浜地区)」の6件(事業統合により最終的に4件)となった。これらは、土地収用手続を見据えて、事業認可の手続が行われたものとなっており、都市計画の決定と都市計画事業の認可が、同時にワンストップで処理され、事務処理期間の短縮が図られたとともに、復興整備事業による土地収用法の特例による効果を得ることができるものとなった。
なお、事業認可(都市計画法第59条)の特例については、6件のみとなった理由として、被災自治体から、復興特区法による手続の理解に当たって復興事業を急ぐあまり時間的に対応が及ばなかった、また、個別法による通常の手続の迅速化が図られていたことから、あえて当該許認可等の特例を受けるまでには及ばなかったとの意見があった。
・ 農用地区域内における開発行為の許可(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項)、地域森林計画の対象となっている民有林における開発行為の許可(森林法第10条の2第1項)、及び保安林における立木の伐採の許可(森林法第34条第1項又は第2項)については、0件となった。この理由として、被災自治体から、個別法による通常の手続の迅速化が図られていたことから、あえて復興整備事業に係る許認可等の特例を受けるまでには及ばなかったなどの意見があった。
・ 自然公園法における特別地域等内において、同法第20条第3項の許可(工作物を新築し、改築し、又は増築すること、木竹を伐採すること等の行為に関するもの)又は同法第33条第1項の届出(高さ13m又は延べ面積1,000m2の建築物を新築し、改築し、又は増築すること、土地の形状を変更すること等の行為に関するもの)に関する許可等については、防災集団移転促進事業等の実施に当たって、特に津波被害が大きかった地域においては、高台への住宅移転が進められてきたことから、活用件数が多いものとなった。
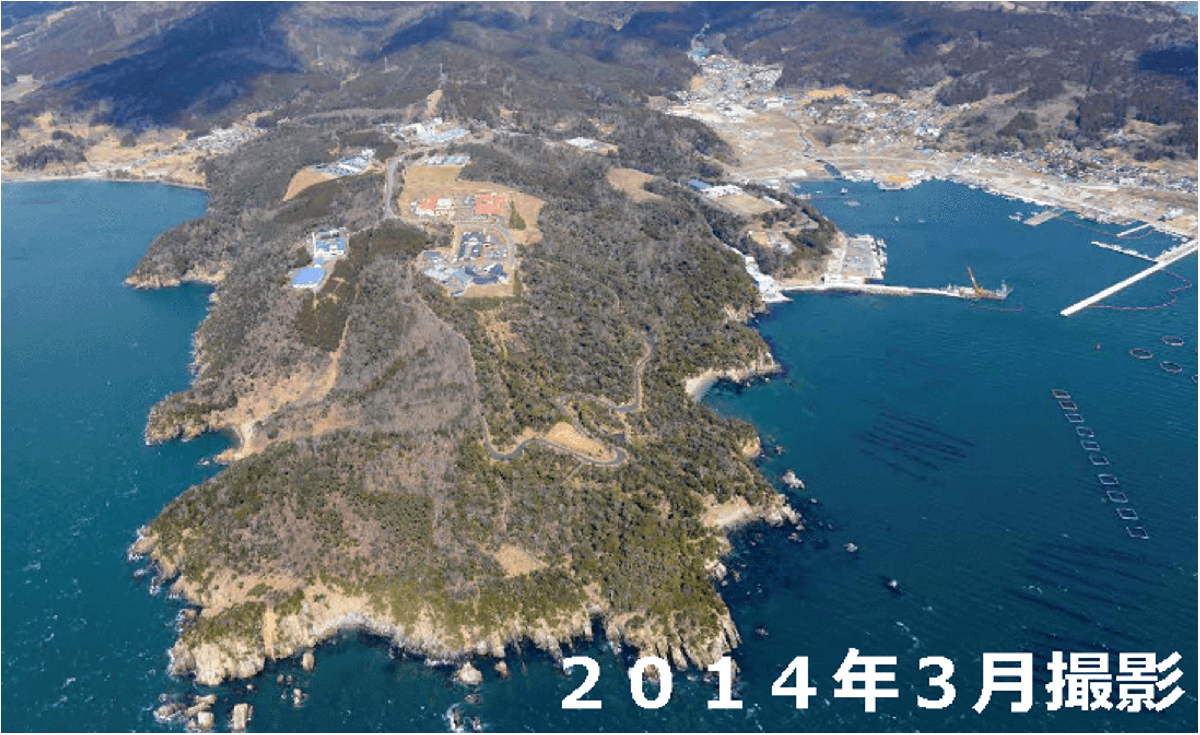
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat15/aerial/20200626_sorakaramiru3.pdf (令和5年7月19日閲覧)
・ 漁港の区域内の水域又は公共空地における工作物の建築、土地の掘削等に関する漁港管理者の許可(漁港漁場整備法第39条第1項)に当たっては、上記6)土地利用基本計画に係る特例(ゾーニングの変更)(復興特区法第48条)に記載のあるとおりとなっており、その活用はないものとなった。
・ 港湾区域内の工事等に関する港湾管理者の許可又は臨港区域内における行為に関する港湾管理者への届出(港湾法第37条第1項又は同法第38条の2第1項)については、震災発生直後の初動、応急復旧による航路啓開が実施され、災害復旧工事を早期に着手し、岸壁の供用が震災経過1年を待たずにして再開される箇所があるなど、復興整備計画の作成以前に復旧事業が既に行われていたことなどから、事例は生じないものとなった。
8) 各種事業に関する特例
a. 区画整理事業に関する特例
ア) 復興一体事業
復興一体事業とは、次に掲げる事業を一体的に施行する事業である。
① 土地区画整理事業
② 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理又は変更
③ 客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業
当該事業は、農地と市街地が混在している地域などにおいて被害を受けた場合、市町村が、復興一体事業として市街地の整備と農業生産基盤の整備を一体的に施行できるものとなっており、事業計画の作成に当たっては、施行地区(市街化調整区域においても定めることができる。)、事業の概要、事業施行期間及び資金計画を記載するものとし、これを県知事等に提出することによって、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができるものとなっている。
また、住宅や学校、病院等の公益的施設が広範に被害を受けた場合には、再度災害の防止又は軽減のための措置、例えば、盛土、嵩上、高台切土等による措置を講じた土地に住宅及び公益的施設を集約させることができるものとし、このように供すべき区域を津波復興住宅等建設区として施行地区内に定めることができるものの、当該区域の決定に当たっては、住宅及び公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設)の建設を促進する上で、効果的な位置に相当な規模の面積によるものとする必要があり、この場合、事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者である場合において、当該宅地に係る換地に住宅又は公益的施設を建設しようとするものは、当該宅地に係る換地を津波復興住宅等建設区域内に定めるべき旨の申出をすることができる。
さらに、市町村は、県に対して農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができることになっており、また、農業用用排水施設等に関する事業又は客土、暗渠排水等に関する事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設を管理するものとなっている。
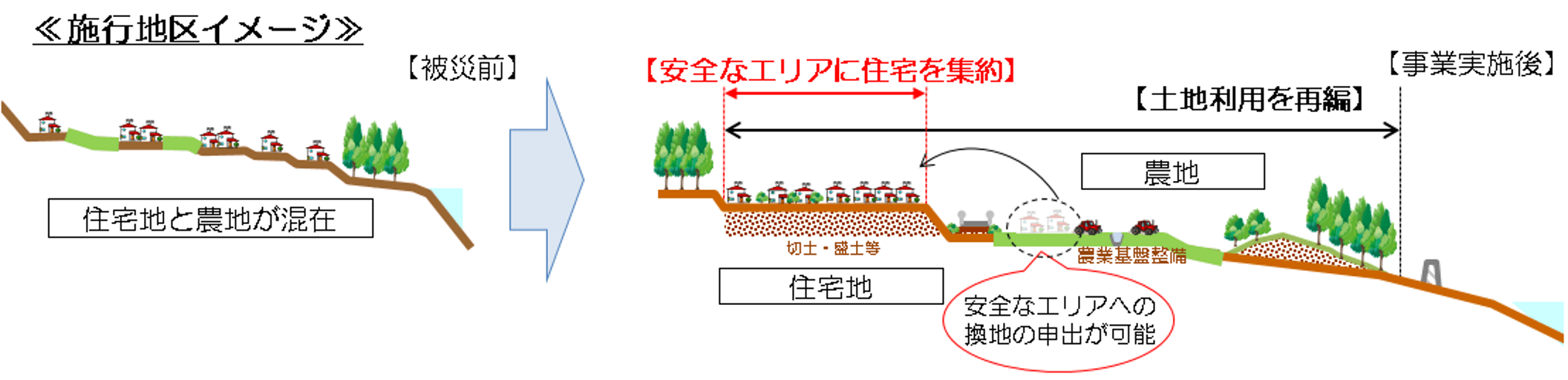
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/2206_setsumeishiryou.pdf (令和5年7月19日閲覧)
当該事業は復興特区法において新たに創設された事業となっているものの、被災自治体から、被災箇所から津波の被害が回避可能な高台への住宅の移転は、防災集団移転促進事業において多く実施されたこと、新たな事業への取組は不慣れなことから緊急時において負担が大きくなること、また、それぞれの事業区域が離れていること等の意見があり、当該事業は行われなかった。
なお、復興一体事業とは異なるものの、防災集団移転促進事業と連携した農業農村整備事業が行われており、高台への集団移転と併せた移転元地を含む農地整備事業が10市町15地区で行われた(令和2年1月末現在)。
特に、石巻市の北上地区では、農業農村整備事業により移転跡地等の集約化を図り、移転先の造成団地の住民が利用する多目的広場を計画するなど、効率的な土地利用の実現に向けた農地整備の推進が行われた。さらに、造成団地から発生する残土を農地整備に活用することによって、双方の事業費の縮減が図られるものとなった。
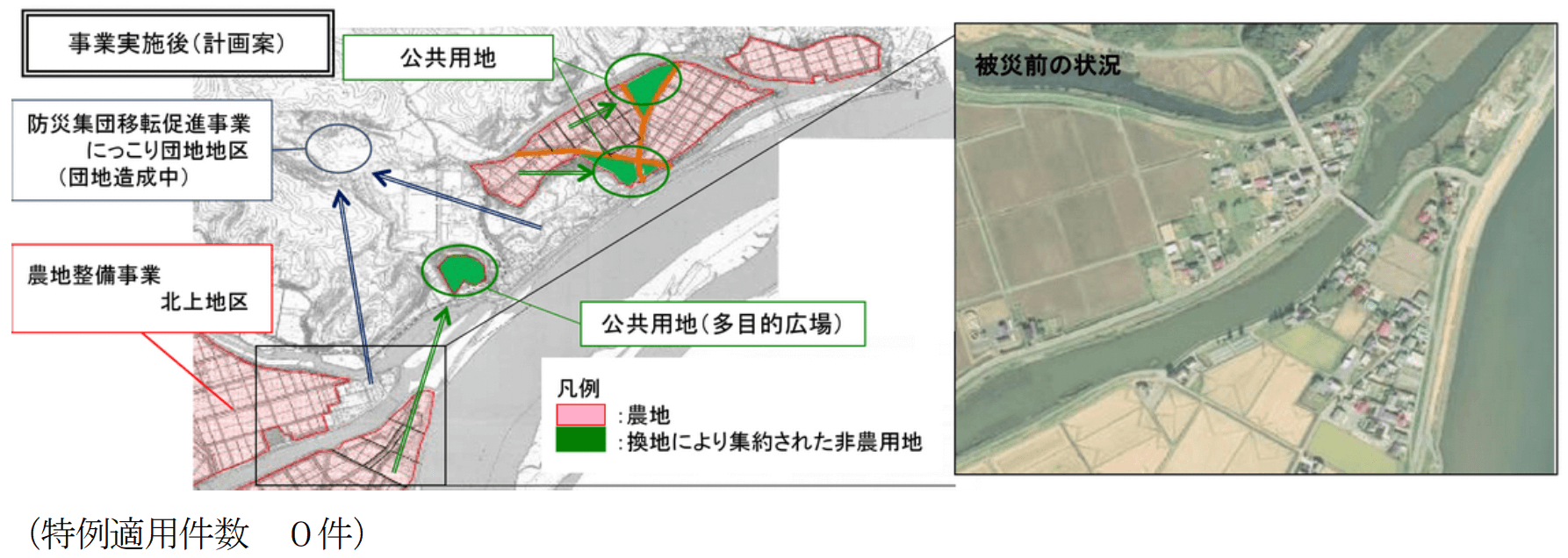
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20160708_sesakusyu.pdf (令和5年7月19日閲覧)
イ) 土地区画整理事業の特例(復興特区法第51条)
土地区画整理法及び都市計画法において、地方公共団体は、市街化調整区域において土地区画整理事業を実施できないこととされているものの、被災地域の円滑かつ迅速な復興のためには、市街化調整区域においても土地区画整理事業に関する復興整備事業の実施が必要となる場合がある。
そのため、次の①から③までに掲げる地域内に市街化調整区域が含まれる場合であっても、復興整備計画に市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業又は復興一体事業に関する事項を記載することができるものとしている。
① 東日本大震災による被害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域
② 東日本大震災の影響により多数の住民が避難し、若しくは住所を移転することを余儀なくされた地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域(①の地域を除く。)
③ ①②の地域と自然、経済等において密接な関係が認められ、かつ、①②の地域の住民の生活再建を図るための整備を図ることが適切であると認められる地域
当該特例の活用状況は、岩手県の沿岸地域においては、区域区分の定めがなかったことから0件となっているものの、宮城県については8件、福島県については3件となった。
宮城県女川町においては、市街地のほとんどの箇所が浸水したことから、女川町中心部の高台などでまちづくりが行われることとなり、復興整備事業(女川町被災市街地復興土地区画整理事業)の実施に当たっては、市街化調整区域を選択せざるを得ないものとなった。
当該特例を活用することによって、まちづくりに当たり、柔軟な立地計画を実施できるものとなった。
また、当該土地区画整理事業の実施に当たっては、仮換地指定の前であっても、損失補償が行われる場合を除き、土地区画整理事業の工事実施に関する地権者の同意(起工承諾)を得られた箇所から工事が可能との周知があったことから、工事着手が21か月前倒しで実施されるものとなった。
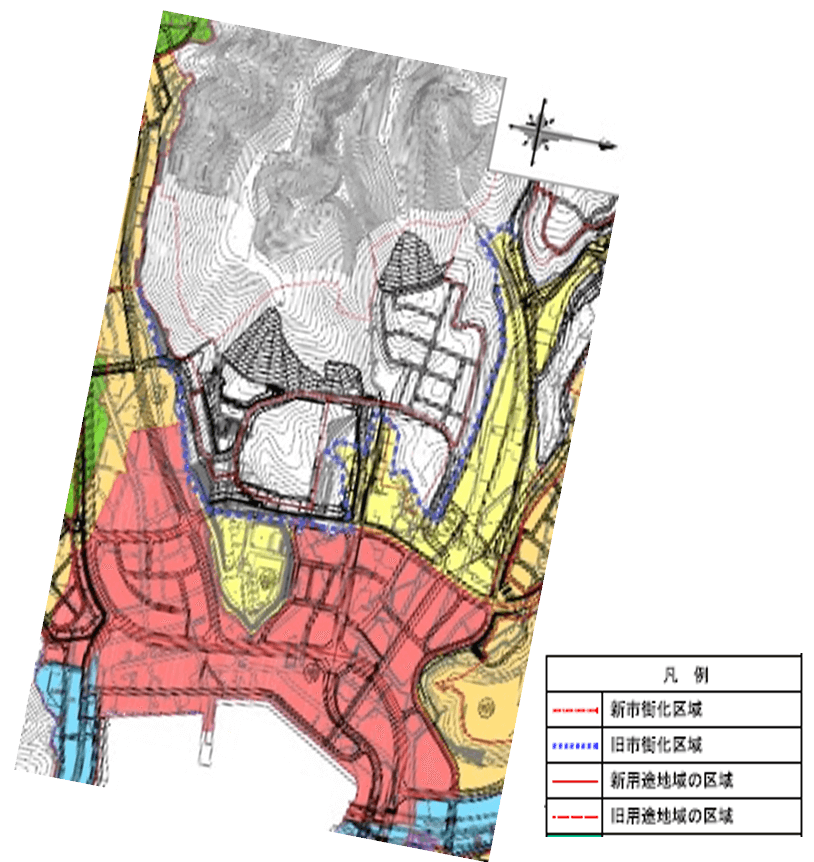

(特例適用件数 11件)
b. 住宅等施設に関する特例
・ 集団移転促進事業の特例(復興特区法第53条)
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「集団移転促進法」という。)においては、集団移転促進事業計画の策定主体が、市町村に限定されているものの、東日本大震災による被害により被災地の行政機能は低下している状況にある。このような状況を踏まえ、市町村から集団移転促進事業に係る集団移転促進事業計画の策定が困難である旨の申出を受けた場合には、都道県がその作成を行うことができるものとした。
この場合、都道県は、国土交通大臣に対する協議の同意、市町村に対する意見の聴取等を行う必要があり、手続に時間を要し、円滑かつ迅速な復興に支障が生じることとなるため、協議会が組織されている場合においては、集団移転促進事業計画をワンストップにおいて処理するものとし、集団移転促進事業に関する事項が記載された復興整備計画が公表されたときは、公表の日に当該事項に係る集団移転促進事業計画が集団移転促進法第3条第1項の規定により同項の同意を得て定められたものとみなすものとした。
ただし、被災自治体から、現状においては、市町村職員が、地域のコミュニティの維持、住民の意思など、被災の早い段階で、各地区を回って意思確認を行う必要があり、その作業は、地域のコミュニティの事情に精通している市町村の職員の対応が必然と考えられていたことから、県にお願いするというのは想定すらしていなかったとの意見もあり、都道県による集団移転促進事業については0件となった。
また、被災市町村では、多数の施設に深刻な被害を受けたことから、都市機能を完全に喪失しているものもあるため、集団移転促進事業については、住宅のみならず、移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用地取得及び造成経費についても補助の対象とした。
さらに、被災地においては、防災に対応しうる平地の移転適地が少ないことから、安全性確保を考慮した場合、高台への移転が余儀なくされている。その場合、大規模な造成が必要となるため経費が多大となり、当該造成された土地の適正な時価を上回ることが想定されるため、取得及び造成に要する経費を譲渡により回収することができないものとなる。そのため、現行制度では、取得及び造成後に住宅団地の用地を譲渡する場合は、当該宅地に係る用地費及び造成費は補助の対象とはなっていないものの、復興整備計画に記載された事業については、譲渡に係る対価の額が用地の取得及び造成に要した経費の額以上となる場合を除き、補助の対象とすることにした。ただし、分譲する住宅敷地等については、市場価格で譲渡した場合の譲渡収入を超える部分が補助対象となる。
c. 住宅地区改良事業の特例(復興特区法第54条)
住宅地区改良法においては、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地を、改良地区として指定することができるものとされているが、この場合の「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものとされている。
津波等により著しい被害を受けた住宅には、基礎が崩れて土地に定着していないものがあるなど、建築物とは言えないものが多数有り、住宅地区改良法上不良住宅に該当しないものとなっている。
このことから、申出地区(住宅地区改良法第4条第2項の申出に係る地区)として復興整備計画に記載することによって、地区内において主として居住のように供されていた建築物であったもので、著しい被害を受け損壊したため、建築物でなくなったものについても、当該居住者が保安、衛生等の危険性に現にさらされているものとして、それらが存する区域を含み申出地区とすることができるものとなっている。この場合、都市計画区域内において実施する事業に関しては、あらかじめ、施行者に応じて、関係市町村又は都道府県都市計画審議会の議を経る必要がある。
また、住宅地区改良法においては、施行者は、国土交通大臣による改良地区の指定後、国土交通大臣に協議の上、事業計画を定める必要があり、また、事業計画を定める際には、あらかじめ、公共施設の管理者等、地区施設の設置について許可、認可その他の処分の権限を有する行政機関との協議の上、住宅地区改良事業の具体的な実施内容等を記した事業計画を定め、事業を実施するものとされていることから、この場合手続に期間を要することになるため、関係地域の円滑かつ迅速な復興に支障を来たすおそれがある。そのため、申出地区及び事業計画に関する特例をそれぞれワンストップで処理することにより、住宅地区改良事業に関する事項が記載された復興整備計画が公表されたときは、公表の日に当該事項について定められたものとみなすものとなっている。
なお、住居の再建に当たっては、かさ上げも可能である土地区画整理事業や被災した地区において多数の事業が行われ、ノウハウが得られやすい市街地開発事業、防災集団移転促進事業により多くの整備が行われたこと、また、被災を受けた箇所は、災害危険区域に指定されることとなり、住居の多くは高台で再建される場合が多かったことから、当該事業が実施されることはなかった。
(特例適用件数 0件)
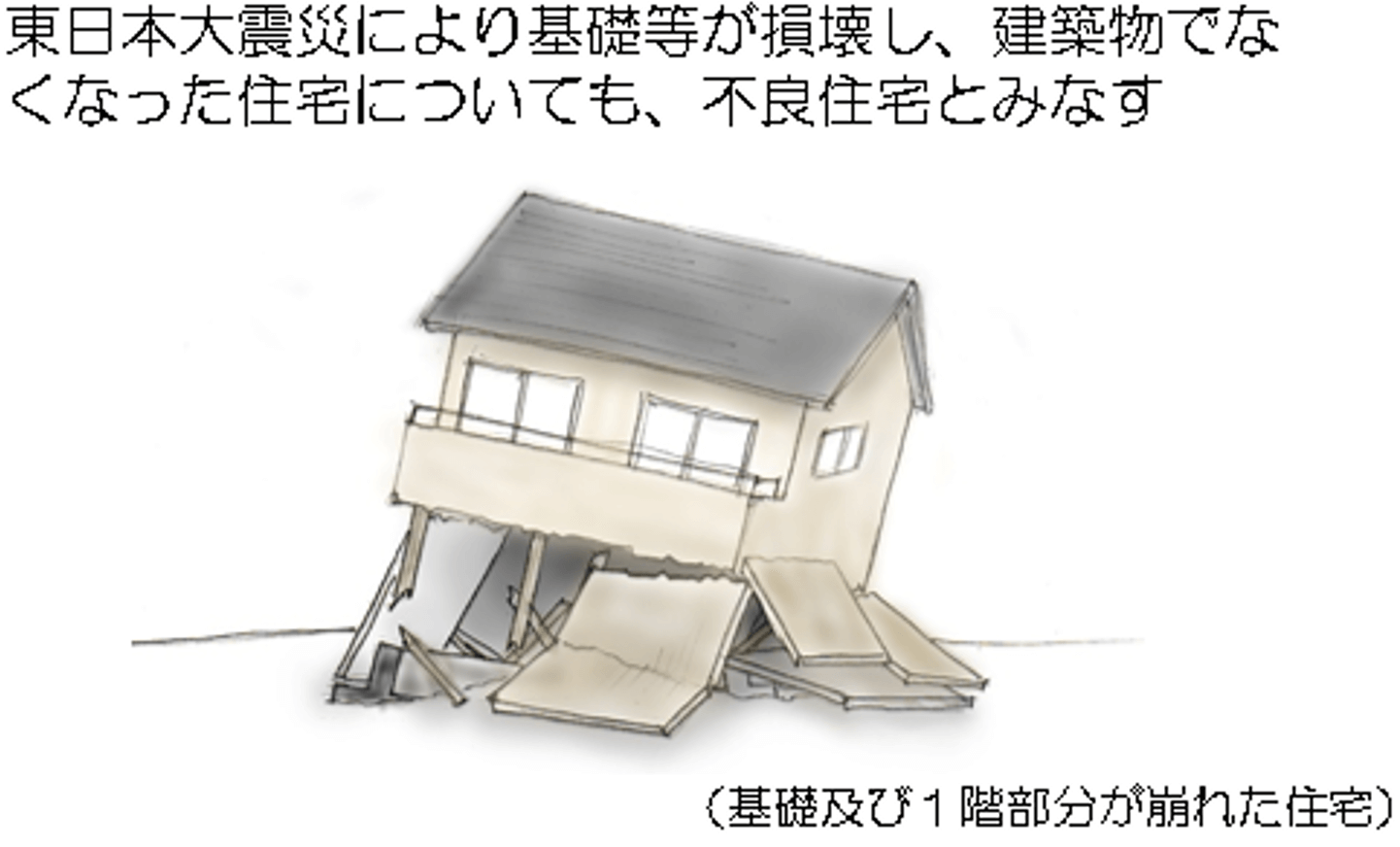
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/2206_setsumeishiryou.pdf (令和5年7月19日閲覧)
d. 小規模団地住宅施設整備事業の特例(復興特区法第54条の2)
都市計画法第11条第1項第8号においては、都市施設として、「一団地の住宅施設(一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)」と定められている。
被災地沿岸については50戸以上の規模の集落は少なく、小規模な集落が多く存在していることから、被災地域の実情を踏まえ、復興整備事業に小規模団地住宅施設整備事業(一団地における5戸以上50戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。)を加え、復興整備計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業については、都市計画法に規定する一団地の住宅施設とみなすものとし、これらの整備のための事業については、都市施設としての整備及び土地収用制度の活用を可能にするものとした。
当該事業については、岩手県大槌町及び福島県いわき市において行われた。大槌町においては、用地加速化支援隊の実務支援を受けていたこともあり、土地収用制度の活用を可能とするため、当該特例を活用したものであるが、被災地全体としては、用地取得が難航した場合には移転先地の変更が多数行われた。いわき市においては、多数の避難者により高まった住宅用地の需要に対応する必要があったため、開発許可に準じる手続き(いわき市の審査)を経ることにより、民間事業者を施行予定者とする「一団地の住宅施設」の都市計画決定及び事業認可が行われ、以下の3事業が実施された。
当該事業の民間事業者による実施によって、迅速かつ機動性のある民間活力の活用が可能となり、自立再建を目指す者の住環境の早急な改善が図られるものとなった。また、当該事業は都市計画事業として実施されるため、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の特例の適用が受けられるものとなり、円滑な用地取得の確保に資するものとなった。
(特例適用件数 10件)
| 地区名 | 事業名 | 実施主体 |
| E-1地区 | 平中山一団地の住宅施設事業 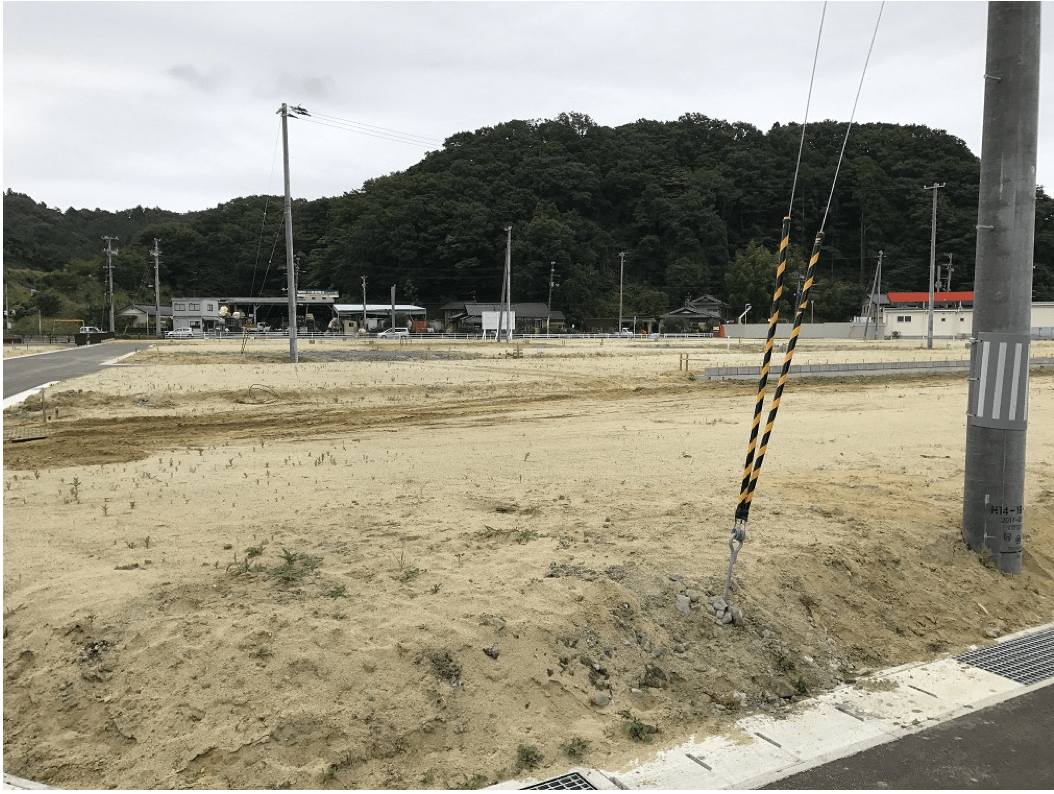 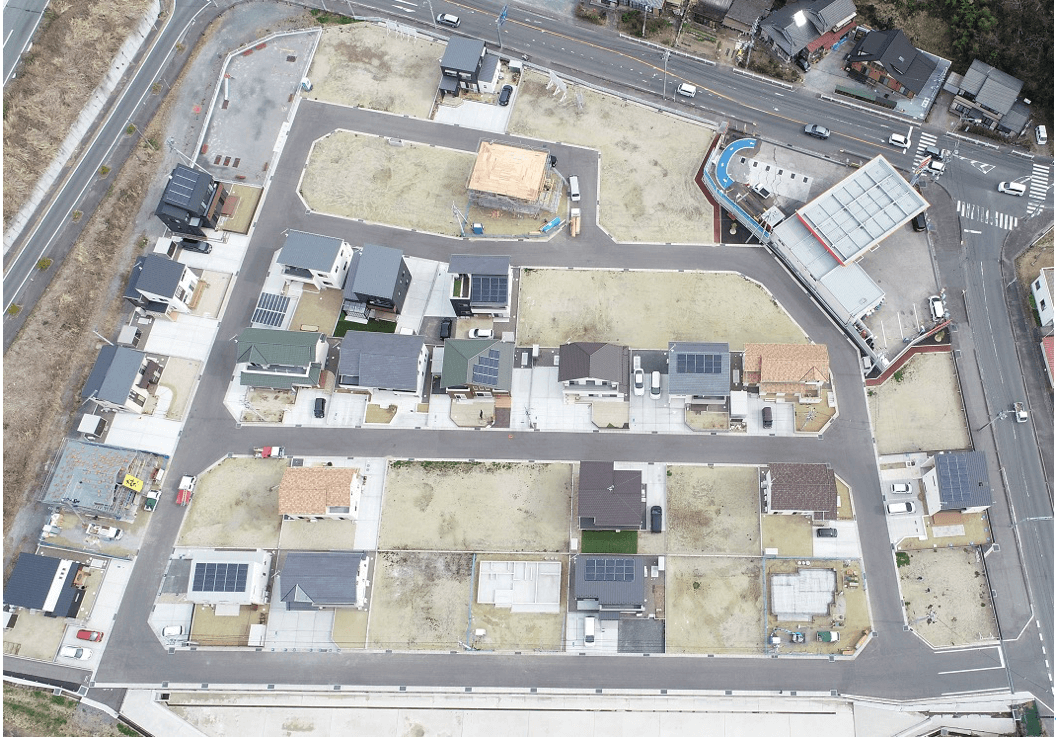 出所)株式会社 渡辺組 |
株式会社 渡辺組 |
| E-2地区 | 四倉町上仁井田一団地の住宅施設事業  出所)復興庁 |
株式会社ファーストホーム |
| E-3地区 | 常磐上矢田町一団地の住宅施設事業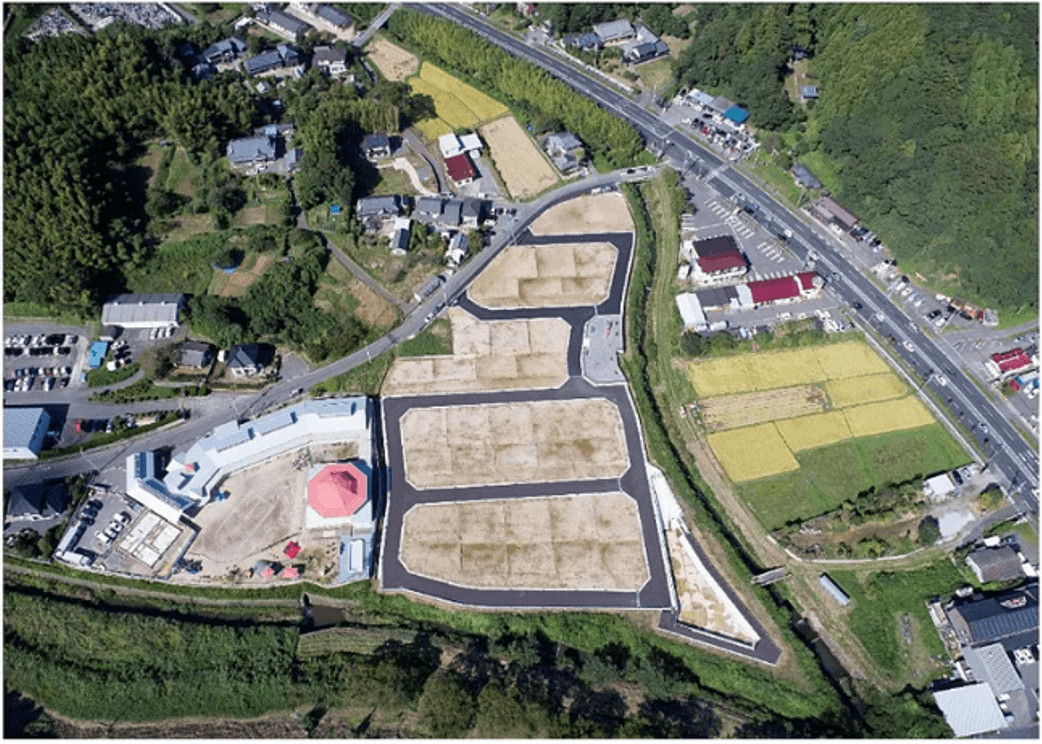 出所)株式会社アドマック  出所)復興庁 |
株式会社アドマック |
9) 施設整備事業に関する特例
a. 土地改良事業の特例(復興特区法第52条)
被災地域における農業生産活動は、地域経済・国民への食料の安定供給の面において、重要な役割を果たしており、緊急に復興させる必要がある。
このため、原則、農業者の申請を要件として実施される土地改良事業について、農業者の申請によらず、県の発意で、区画整理・農用地造成等の事業を行うことができるものとした。
釜石市大船渡・釜石地区(下荒川工区)において、県施工による土地改良事業が実施された。当該事業の実施箇所の選定に当たっては、岩手県内被災沿岸市町村一体となり、農地の復旧、復興をどのように実施するかという協議を進める中で、当該地区が、従前から狭隘な農地が多く、大区画化するための換地の強い要望があったことから選ばれたものとなっている。また、当該地区は、8㏊と施工規模が小さく、通常は県による施工とはならないものの、土地改良事業の施工実績がなく、また、被災対応により土地改良事業にまで手が回る状況になかったことから、市の依頼もあり、復興特区法の特例を活用して、県による施工となったものとなっている。
これらの結果、農地の復旧が区画整理事業により実施されることとなり、生産効率の向上や農地集積・集約化が図られた。
また、地域における話し合いの結果、釜石市初の本格的な営農組合が設立され(唐丹地区営農組合)、当組合の中心経営体である農業者4経営体により農地利用が担われることとなり、集落内の農地は、効率的に管理されるものとなった。
同地区においては、区画整理事業をきっかけに、区画拡大による作業の効率化や、個人には負担の大きい農業機械の導入などを営農組合で補完する仕組みができたことにより、被災後において営農再開が可能になった例となっている。
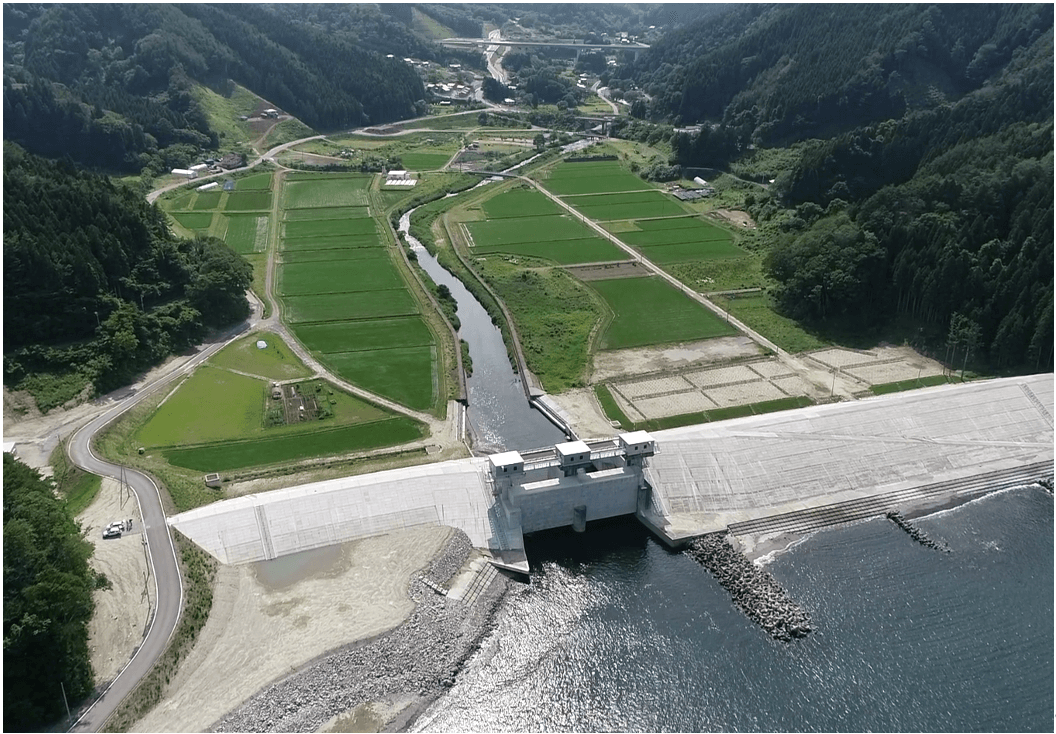
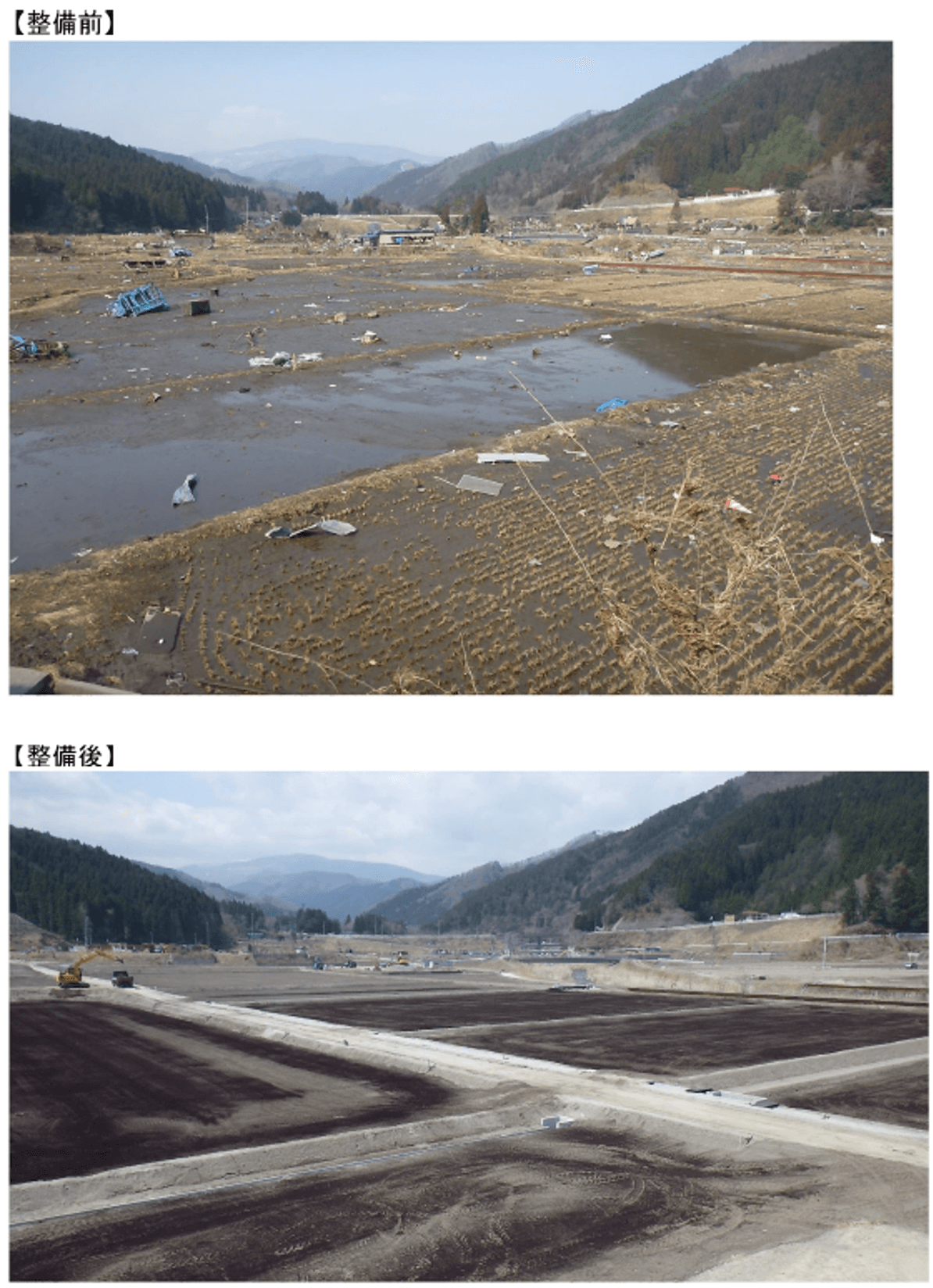
なお、福島県においては、原子力災害により被害を受けた農地が多くあったことから、農地除染を行うとともに、ほ場を大区画化し、担い手への農地集積・集約化を推進することで、農業競争力強化を図ることを目的とした区画整理事業を実施する土地改良事業が多く見受けられた。
(特例適用件数 6件)
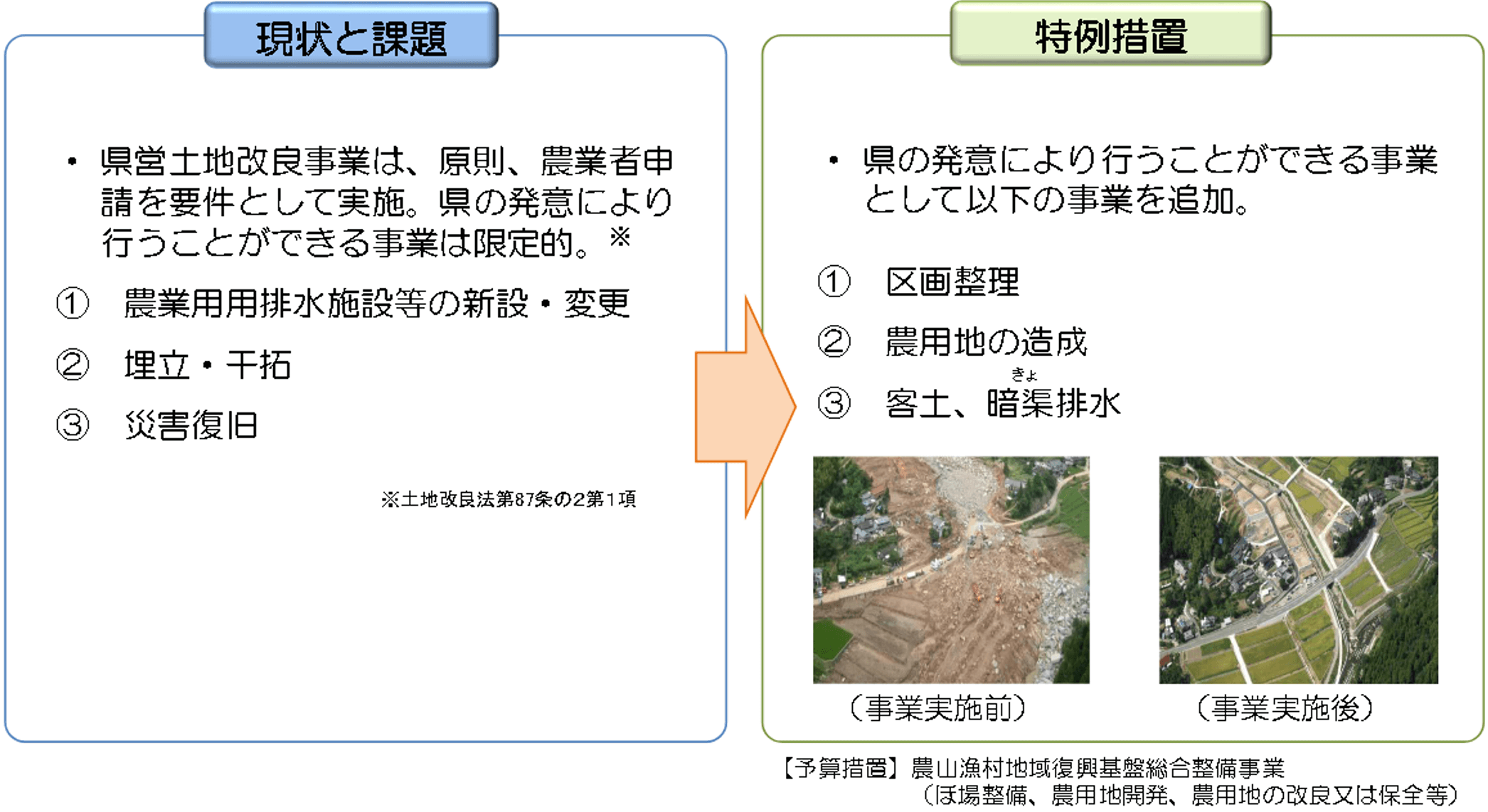
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/2206_setsumeishiryou.pdf (令和5年7月19日閲覧)
b. 漁港漁場整備事業の特例(復興特区法第55条)
漁港漁場整備事業は、漁港施設の新築、魚礁の設置等を行うことを目的とする事業である。
漁港漁場整備法に基づいて事業を行うこととした場合、関係地方公共団体及び関係漁港管理者との協議並びに概ね20日間の縦覧期間を経る必要があることから、事業の円滑かつ迅速な施行に支障を来たすおそれがある。
そのため、漁港漁場整備事業に関する事項を復興整備計画に記載しようとするときは、ワンストップで処理することとし、農林水産大臣の同意を得て、当該事項が記載された復興整備計画が公表されたときは、公表の日に同法第17条第1項における特定漁港漁場整備事業計画が定められ、かつ、当該計画について同項に規定する届出及び公表がされたものとみなすこととされた。
なお、特定漁港漁場整備事業計画に係る縦覧手続については、復興整備計画作成に当たっての公聴会の開催等住民の意見を反映させる機会に行うことが可能なものとなっている。
漁港漁場整備事業の実施については、上記6)土地利用基本計画に係る特例(ゾーニングの変更)(復興特区法第48条)にあるとおりとなっており、早期に漁港の復旧が図られたことから、当該特例の活用は行われなかった。
(特例適用件数 0件)
c. 地籍調査事業の特例(復興特区法第56条)
地籍調査とは、主に市町村が主体となり、一筆(土地の所有権等を公示するために、人為的に分けた区画のことであり、土地は「筆」(ひつ)という単位でカウントされる。)ごとの土地の所有者、地番及び地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査となっている。
被災地では、津波により土地の境界標が流失するなど、土地の境界が不明確となっている箇所があるため、復興に向けた事業等が円滑かつ迅速に進まない状況が生じている。この場合、速やかに、境界を復元する必要があるものの、地方公共団体では被災により行政機能が低下し、地籍調査の実施体制の確保が極めて困難な状況になっている。
このような状況を踏まえ、国土交通省が行う地籍調査に関する事項が記載された復興整備計画が公表されたときは、地方公共団体に代わって国土交通省が当該地籍調査を行うものとなっている。
なお、地籍調査に関する事項を復興整備計画に記載しようとするときは、必要に応じてワンストップ処理を活用しつつ、所要の協議等をするとともに、①地籍調査が復興の円滑かつ迅速な推進を図るために必要であり、②地方公共団体が行うことが困難であると認められ、かつ、③その事務の遂行により国の事務に支障がないことの3つの要件に該当すると認められるものとして、国土交通大臣の同意を得なければならない。
この事業に要する経費は、国が1/2、都道県が1/4、市町村が1/4をそれぞれ負担するものとなっている。
地籍調査事業の特例については、事業を実施しない地区においては地籍調査を行う緊急性が低かったこと、事業を実施する地区においても、各自治体における復興事業の実施に当たって、国からの十分な財政支援が行われたためにコンサル等への外部委託等の十分な活用が可能となり、必要に応じて測量の実施の際に地籍調査が行われたことから、地方公共団体に代わって国土交通省に地籍調査の実施を要請する自治体はなく、件数は0件となった。
なお、東日本大震災の被災県を対象とする登記所備付地図作成作業が、平成27年度を初年度として3年間(2年目作業を算入すると4年間)において9平方キロメートルに及ぶ登記所備付地図の作成が行われた。また、東日本大震災の被災県では、震災復興型登記所備付地図作成作業を実施すべき地区がなお存在したことから、平成30年度を初年度として3年間(2年目作業を算入すると4年間)において各年度約3平方キロメートルに及ぶ登記所備付地図の作成が行われた。さらに、令和3年度を初年度とする3年間(2年目作業を算入すると4年間)の各年度約2平方キロメートルに及ぶ登記所備付地図の作成が行われている。
石巻市における地籍調査が完了していない中心市街地においては、その一部に地図混乱地域が含まれていたことから、復旧・復興事業の実施に当たって支障が生じていた。そのため、登記所備付地図作成事業が行われることとなり、事業の実施に当たっては、仙台法務局と石巻市が包括連携協定を締結して実施する全国初の取組みとなった。両機関が連携することによって、仙台法務局においては、石巻市が保有する情報の活用、地図作成作業の現地事務所を石巻市役所庁舎内に設置することで、地籍調査担当課への技術的支援・助言や土地所有者等の来所が容易となり、石巻市においては、復興の更なる前進や地籍調査の再開(東日本大震災により地籍調査が中止)などの市民のニーズに対応できるものとなった。また、通常、市において事業を実施しようとする場合、多額の費用と期間(3年)を要するものの、法務局が主体となって事業が実施されたことから、短期間(2年)で事業が完了するものとなり、地図混乱地域が解消されるとともに、その結果、地図の縄伸びが多く生じ、税収の増加にもつながるという効果がみられた。
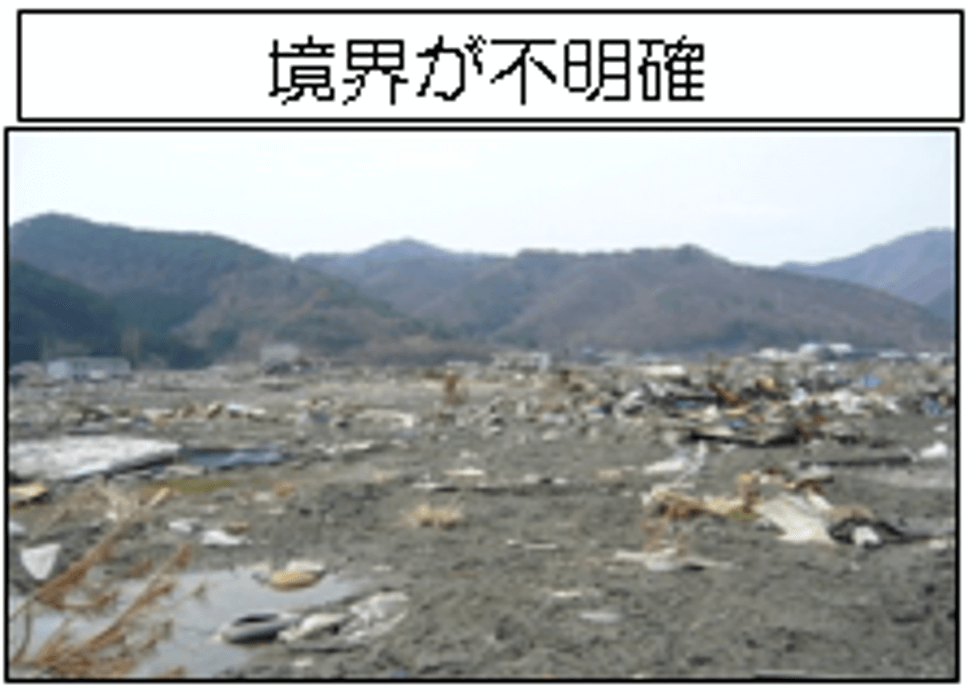
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/2206_setsumeishiryou.pdf (令和5年7月19日閲覧)
d. 法令等に関する特例
ア) 環境影響評価法の特例(復興特区法第72条)
環境影響評価法においては、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業について環境影響評価手続を義務付けているが、第52条の規定により、防災上の観点から緊急に行う必要があって被災区域において実施される事業については、環境影響評価法の適用除外としている。被災区域以外で行う事業は適用除外とはならないが、法に基づく手続を実施した場合、環境影響評価に必要な現地調査期間に加え、環境影響評価図書の公告・縦覧期間や行政機関及び住民等の意見提出期間等、長期間を要することとなり、被災住民の住居等の生活再建に係る事業が迅速に進められない懸念があった。
そのため、復興整備事業への迅速な着手と環境保全の両立を図るため、環境影響評価法の特例を設けることにより、復興整備事業のうち被災住民の居住地及び移動手段の確保に不可欠な事業である土地区画整理事業(面積75㏊以上)又は鉄道事業若しくは軌道事業(長さ7.5km以上)に限って、環境影響評価法を適用せず、当該特例に基づく特定環境影響評価を実施することとしたものである。
特例の内容は、以下の図のとおりとなっており、環境影響評価法に基づく通常の環境影響評価における方法書・準備書・評価書の手続を特定評価書という手続に集約するとともに、通常の環境影響評価で行われている通年又は四季にわたる現地調査を基本とせず、文献等の資料調査、専門家等へのヒアリング、現地の状況の確認等を基本とすることにより、事業着手前の手続に要する期間の大幅な短縮が図られたものとなっている。
<縦覧期間、意見提出期間の短縮>
・特定環境影響評価では、方法書、準備書、評価書を集約し、特定評価書を作成する。
・特定評価書の縦覧期間は2週間であり、縦覧方法は、被災地を離れている地元住民の利便性を考慮し、紙による縦覧に加えて、被災関連市町村等のウェブサイト等で公表。
・関係都道府県知事等の意見提出期間については、環境影響評価法に基づく手続における準備書についての意見提出期間(120 日)の半分の60 日。
・認可を行う者、環境大臣の意見の提出期間については、認可を行う者の意見提出期間は60日、このうち環境大臣の意見提出期間は30 日。
<調査期間の短縮>
特定環境影響評価手続では、通年又は四季にわたる現地調査を基本とせず、文献等の資料調査、専門家等へのヒアリング、現地の状況の確認等を基本とする。
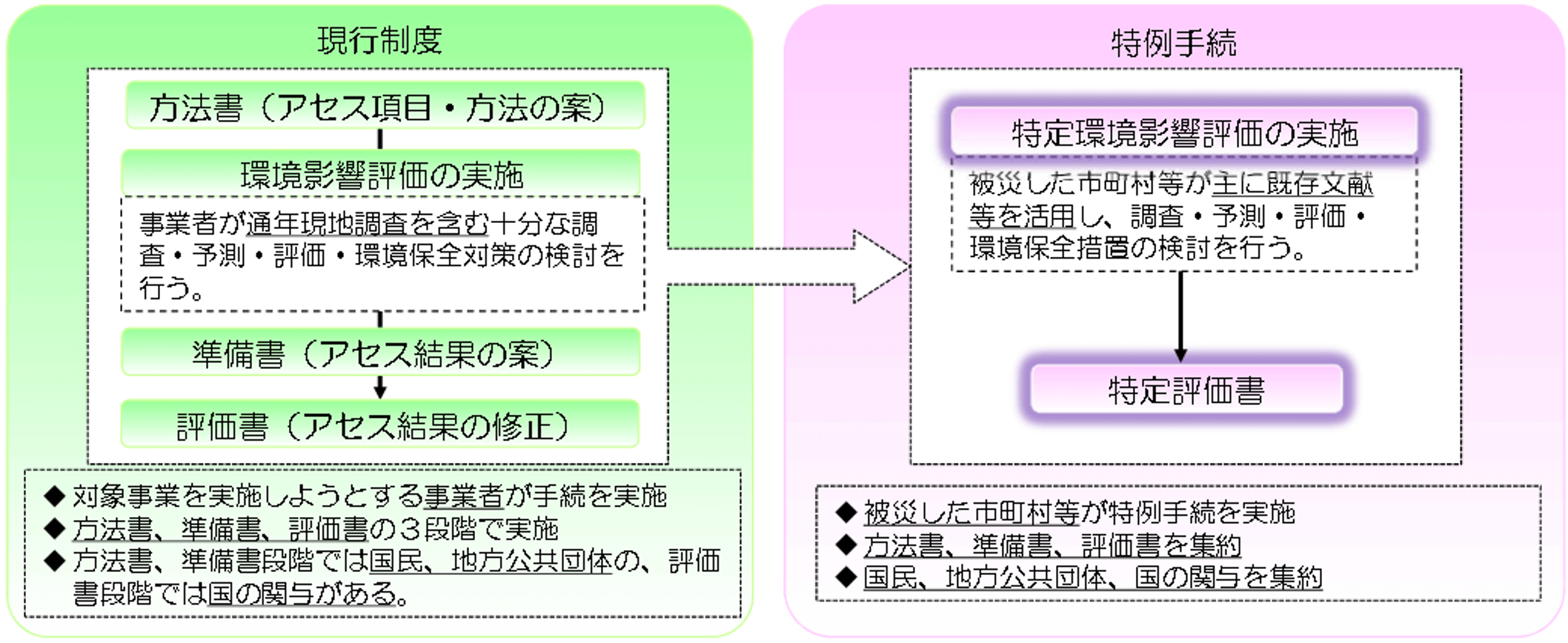
https://www.env.go.jp/council/02policy/y0212-01/900416831.pdf (令和5年7月19日閲覧)
特定環境影響評価は、以下の手続により行われる。
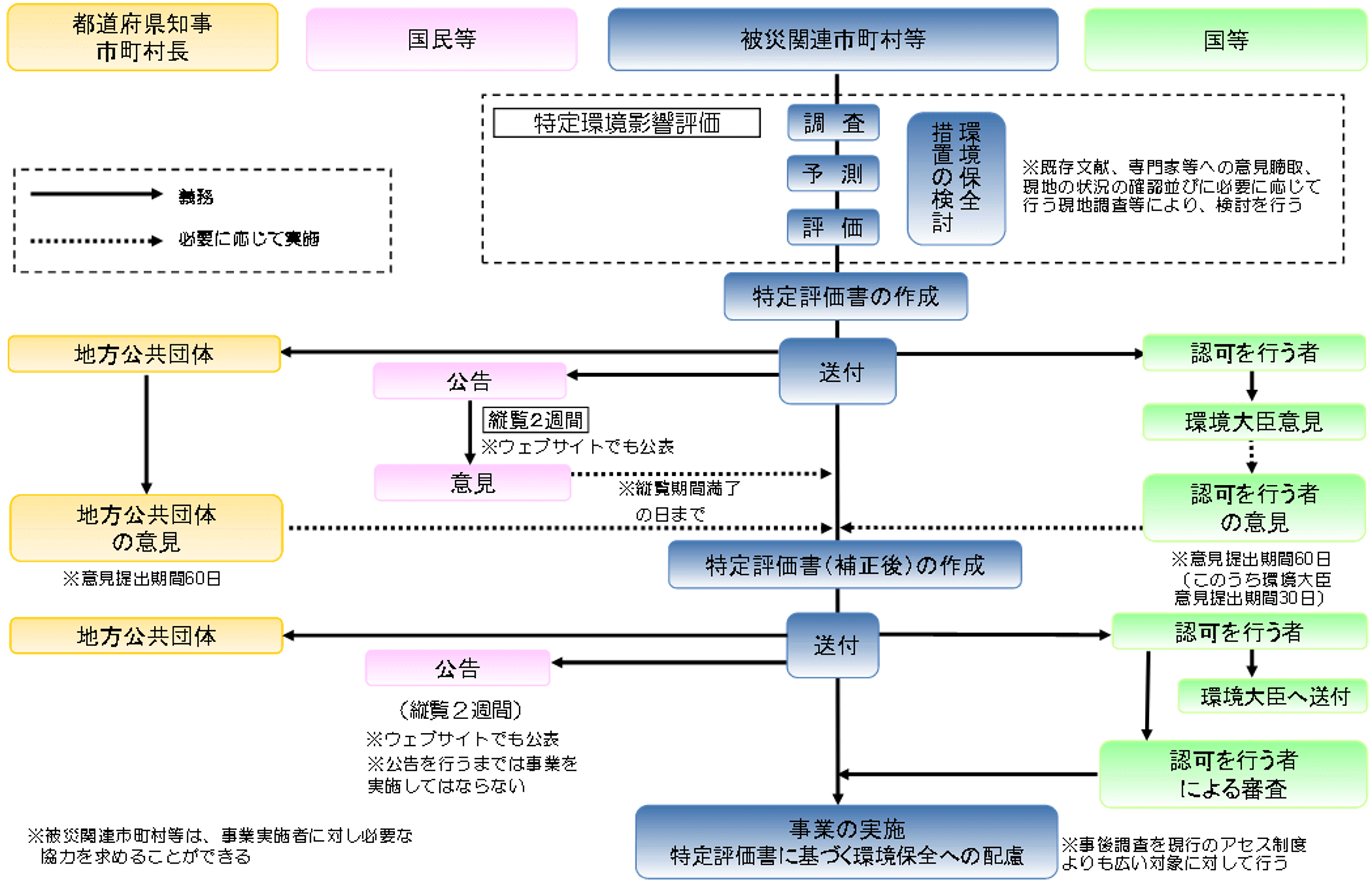
https://www.env.go.jp/council/02policy/y0212-01/900416831.pdf (令和5年7月19日閲覧)
当該特例に基づき以下の2事業(復興整備事業の件数6件)について特定環境影響評価手続が実施された。
石巻市新蛇田地区被災市街地復興土地区画整理事業(新蛇田地区(46.5ha)、新蛇田南地区(27.4ha)及び新蛇田南第二地区(13.7ha))
常磐線(駒ヶ嶺~浜吉田)復旧事業(山元町(12.01km)、亘理町(300m)及び新地町(2.49km))
特定環境影響評価手続が実施されたのは、土地区画整理事業と鉄道事業の1事業ずつにとどまったが、2事業とも約1年で特定環境影響評価手続を終了しており、通常の環境影響評価に比べて大幅に期間を短縮することができた。一方、 被災自治体から、特定環境影響評価は、事業者ではなく、被災関連市町村等が手続を実施するため、災害復旧時にもかかわらず市町村の負担が大きいとの意見があった。
(特例適用件数 2件(復興整備事業の件数 6件))
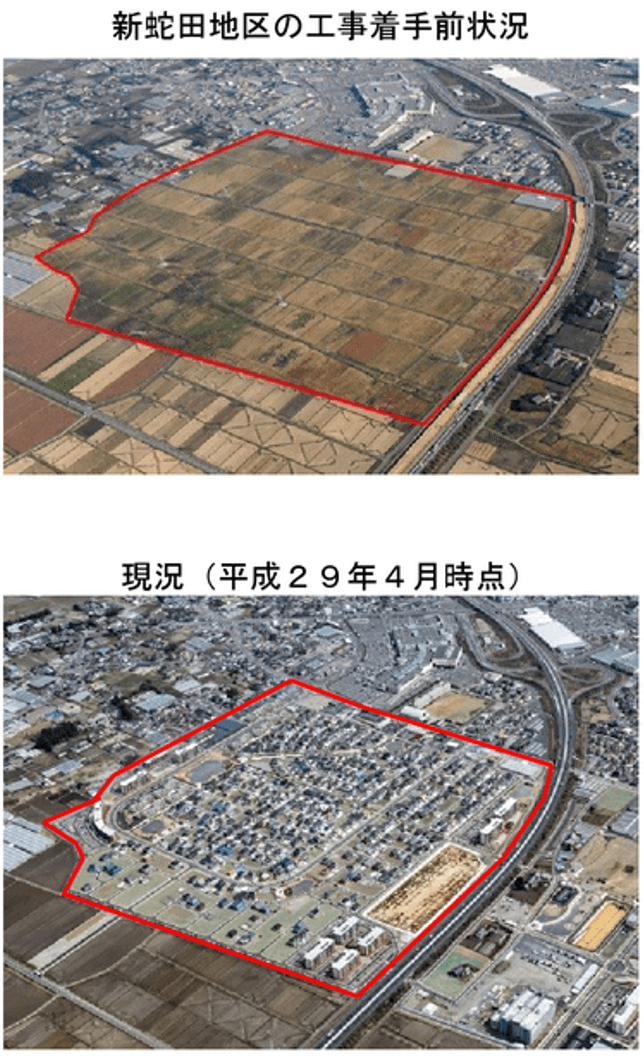
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10184000/501/01_sinhebita.pdf (令和5年7月15日閲覧)
 山下駅(山元町)
山下駅(山元町)
 坂元駅(山元町)
坂元駅(山元町)
 新地駅(新地町)
新地駅(新地町)イ) 不動産登記法の特例(復興特区法第73条)
筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度となっている。
用地の取得に当たっては、筆界の特定が不可欠となっているものの、被災地では、災害により、筆界を特定する上で参考となる杭や塀などの物的証拠及びその他の証拠書類が流失するなど、その特定が困難となっている状況が多く見受けられている。さらに、行方不明者、遠方への避難者も多数にのぼり、土地の所有者の所在が判明しないため筆界特定に支障が生じる状況も生じている。
そのため、事業の迅速な実施に支障が生じることのないよう、将来の所有者となり得る復興整備事業の実施主体が、筆界特定の申請を行うことができるものとなっている。
当該申請に当たっては、土地の所有者の承諾がある場合に限り行うことができることになっているものの、所有者の所在が判明しない場合には、その者の承諾を得なくても良いものとなっている。また、この場合における復興整備事業の実施主体の要件としては、土地収用法による事業認定の告示があった事業、公共用地の取得に関する特別措置法による特定公共事業の認定の告示があった事業又は都市計画法による都市計画事業の認可等の告示があった事業を行う者に限られたものとなっている。
不動産登記法の特例については、事業の実施主体の要件が限定されていること、東日本大震災の被災県を対象とする登記所備付地図作成作業が実施されたこと、また、各自治体における復興事業の実施の際に必要に応じて地籍調査が実施されたことから行われなかった。
(特例適用件数 0件)
ウ) 土地収用法の特例(復興特区法第73条の2~第73条の4)
土地収用制度とは、事業の実施主体が、任意の協議による土地の所有権の取得に向け最大限の努力を払ったにもかかわらず、その取得が困難な場合に、土地収用法に基づく一定の手続(事業認定手続及び収用裁決手続)を経ることによって、土地の所有権を強制的に取得するものとなっている。そのため、権利者保護に万全を期するという観点から、その手続に当たっては、当然厳正なものとなり、長期化する傾向が強いものとなっている。
被災地においては復興を迅速に進める必要があることから、復興整備計画に記載された復興整備事業について、土地収用法による事業の認定に関する処分を行うための努力期間を「3月」から「2月」に短縮し(第73条の2)、さらに、審理手続を短期に実施するため、収用裁決手続のうち明渡裁決に要する審理の期間を6月以内とする努力規定が設けられた(第73条の4)。
さらに、できる限り早期に裁決申請を行う必要があるため、裁決申請書に記載すべき事項は、「収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目」、「土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間」、「権利を取得し、又は消滅させる時期及び登記簿に現れた土地所有者及び関係人の氏名及び住所」を記載すれば足りるものとし、特に土地調書の作成は時間を要するものとなることから、申請時の添付の省略を可能とした(第73条の3)。
また、審理手続については、通常の場合6月あれば裁決は可能であるとされているものの、審理手続開始後、土地所有者が死亡する場合があるなど、審理に要する期間が突然の理由により延伸する場合も想定されることから、緊急に施行する必要がある事業のために土地を使用する際の使用期間を「6月」から「1年」に延長した(第73条の2)。
このことによって、法手続に要する期間の短縮が図られるとともに、早急に着手しようとする事業の継続的な施工を可能とするものとなった。
当該特例については、59件の申請があり、事業認定手続の短縮については97.6%、裁決申請手続については69.4%の効果が有った。
宮城県が起業者である主要地方道相馬亘理線道路事業においては、事業認定申請から告示までの期間が50日間、収用裁決申請から裁決日までの期間が78日間となり、最短の期間で収用手続が行われるものとなった。
(特例適用件数 59件)
エ) 民法の特例(復興特区法第73条の5)
復興整備計画に記載された復興整備事業のうち、土地収用制度による裁決申請に係る事業について、緊急に施工する必要があるため土地の使用が必要となる際に、土地所有者等から損失補償額の請求があった場合、自己の見積もった損失補償額を払い渡さなければならないこととされている。この場合、共有者の中に行方不明者がいるなど、権利者の氏名又は住所を確知することができないときは、損失補償額を供託することができるものとなっている。なお、供託に当たっては、民法第494条第2項により、確知するに当たって、過失がある場合には、供託ができないものとなっているものの、調査義務の軽減を図るため、民法の特例として、供託に当たっての要件を「過失」から「重大な過失」がある場合として要件の緩和を図ったものとなっている。
オ) 独立行政法人都市再生機構法の特例(復興特区法第74条)
独立行政法人都市再生機構(UR)は、委託に基づき業務を行う場合、大都市及び地域社会の中心となる都市の既成市街地以外の地域においては、原則として、本来業務の遂行に支障のない範囲内においてのみ受託業務を行うことができるものとなっている。
地方公共団体における復旧・復興業務が多岐かつ膨大にわたり、地方公共団体、地域の関係者のみでは市街地整備がなかなか進まないような場合、市街地整備に関する豊富な知識や高い業務遂行能力を有するURに業務を委託する選択肢を設けることは、被災地の迅速な復興を図る上で有用なものとなる。
実際、平成23年10月3日に岩手県沿岸市町村復興期成同盟会から国に提出された「東日本大震災からの早期復旧・復興に関する要望」において、「UR都市機構の体制強化(URによる設計から発注・工事監理までの事業実施や自治体毎の現地事務所設置など、長期にわたる支援を行うこと。)」が盛り込まれるなど、URの支援に対する被災自治体からの期待は非常に高いものがあった。
これに対しURは東日本大震災復興対策本部に、震災復興支援におけるURの取組方針について下記のとおり説明した。
1 基本的な考え方
・国交省の指導と調整の下、URとして出来るだけ支援
・受託を基本。人的支援も可能
・具体地区と時期は、国交省及び地方公共団体と協議調整
2 事業地区の想定
・体制の弱い、経験職員のいない、あるいは前記課題を複数抱えて自ら事業を実施することが困難な市町村
・鉄道、防潮堤、直轄事業等と関連して整備が必要な(大規模な)地区
・中心市街地など、優先度・困難性の高い地区
ところが、東日本大震災の被災地域は、独立行政法人都市再生機構法第3条の「大都市及び地域社会の中心となる都市」や同法第11条の「既に市街地を形成している区域」に該当しない都市や区域も多く、URが事業を実施するためには新たな法的位置付けが必要であった。
そのため、復興整備計画に記載された事業について、地方公共団体等からの委託によりURが事業を行うことを可能とするとともに、本特例措置に係る業務を同法第11条第2項に加えることとした。
URは、令和4年7月時点で26の被災自治体と協定等を締結し、当該自治体からの委託又は要請を受けて復興市街地整備事業(29地区)及び災害公営住宅の整備(要請戸数:5,932戸)を推進した。
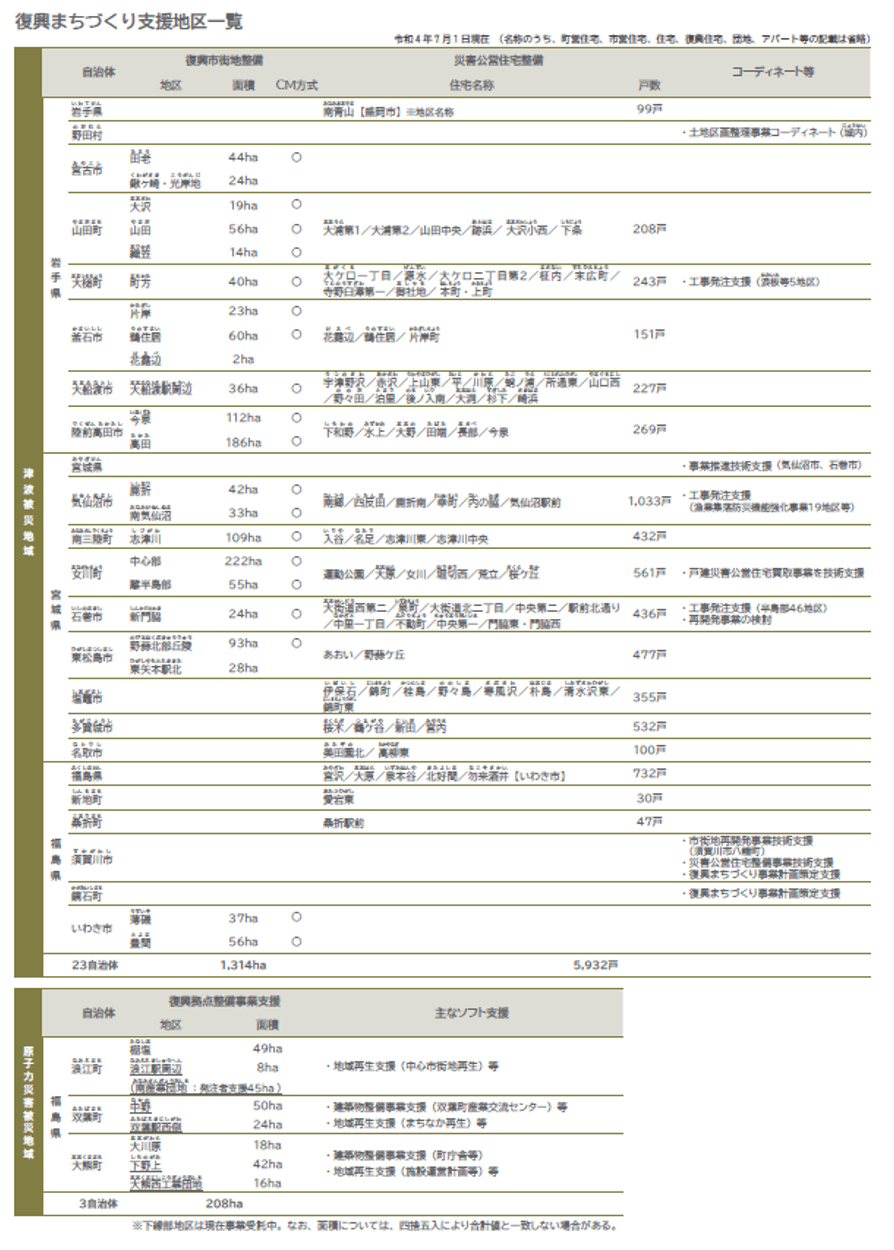
カ) 農業振興地域の整備に関する法律の特例(復興特区法第75条)
土地改良事業等を実施した農地については、農用地区域外に代替する土地がないこと、農用地の集団化、担い手への農地の利用集積、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと等(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項)及び土地改良事業の完了後8年が経過している土地であること(農業振興地域の整備に関する法律施行令第9条)の要件を全て満たした場合に、農用地区域内の土地を農用地区域から除外することができるとされている。
仮に復興整備事業として実施される土地改良事業又は復興一体事業実施区域内において、農用地区域からの除外が認められるとなると、復興整備事業の実施に支障が生じ、事業の達成が困難となるおそれがある。
このため、復興整備事業として実施される土地改良事業又は復興一体事業が施行された農地を農用地区域から除外するに当たっては、農用地区域の変更に係る要件を全て満たすほか、復興整備事業が満了した土地である場合に限り可能なものとしている。
(特例適用件数 0件)
キ) 津波防災地域づくりに関する法律の特例(復興特区法第76条)
津波防災地域づくりに関する法律第10条に基づく推進計画区域内において適用される津波防護施設の整備、指定津波防護施設の指定及び津波からの避難に資する建築物の容積率の特例は、被災地において、速やかに適用させることが早期復興に資するものとなるものの、津波による被害によって行政機能が低下していることから、復興整備計画と推進計画の2つの計画を作成する負担を軽減する必要がある。
そのため、被災関連市町村のうち津波による被害を受けた市町村が、一定の条件を満たす復興整備計画を作成した場合においては、津波防護施設管理者は、同法の規定にかかわらず、当該復興整備計画の計画区域内において、当該復興整備計画に即して、津波防護施設の新設又は改良を行うことができるものとし、当該復興整備計画の計画区域を推進計画区域とみなして、津波からの避難に資する建築物の容積率の特例及び指定津波防護施設の指定の規定を適用できるものとした。
この場合における復興整備計画が満たすべき一定の条件とは、推進計画区域と復興整備計画の計画区域を同等とみなすために必要な以下の条件となっている。
① 被災関連市町村のうち津波による被害を受けた市町村が、復興整備計画を定める場合であること
② 津波防災地域づくりに関する法律の基本指針に基づき、津波防災地域づくりの総合的な推進に関する基本的な方針に相当する事項を記載していること
③ 津波浸水想定に定める浸水の区域における土地の利用及び警戒避難態勢の整備に関する事項を記載していること
④ 津波による災害を防止し、若しくは軽減することを目的として実施する市街地開発事業、集団移転促進事業等に関する事項を定めること
なお、「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」を都市計画法における都市施設として定めることができることから、同施設の整備に係る事業を復興整備事業として復興整備計画に定めることにより、復興整備計画に係る都市計画法関係の特例を適用することができる。
主要地方道相馬亘理線道路事業は、宮城県が津波から内陸部を守る堤防を兼用する道路として施工されたものとなっており、山元町の復興整備計画においては、津波防護施設の整備に関する事業として位置付けられたものとなっている。当該事業は、山元町内の「山下駅~山元町山寺地区」の区間において、平成30年度以降、土地収用手続を実施する必要があったことから、土地収用法の特例を受けるため復興整備事業としたものとなっており、上記(ウ)土地収用法の特例にあるとおり、短期間で土地収用手続を完了するものとなった。
(適用事業件数 1件)
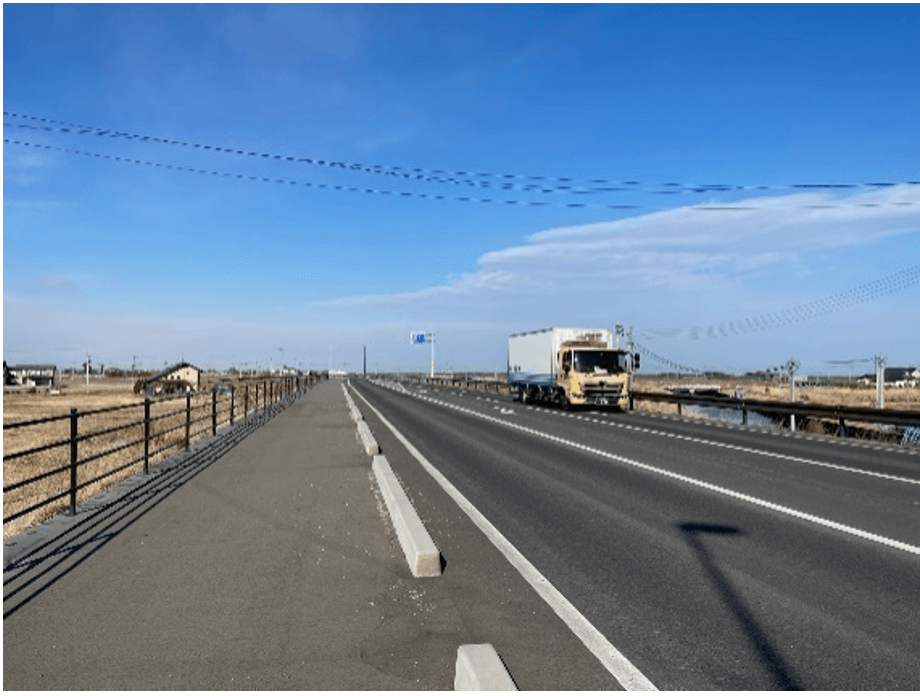

e. 届出等に関する特例
ア) 届出対象区域内における建築等の届出等(復興特区法第64条)
市町村長は、復興整備事業の実施区域で行われる当該事業以外の建築物の建築等について情報を収集することにより、必要があれば、当該事業と事業実施主体以外の者による行為との調整を図ることが必要になる場合がある。そのため、届出対象区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う者に対しては、行為に着手する前に、その旨を市町村長に届け出る必要があるものとし、市町村長は、当該行為が当該事業の実施に障害となるおそれがあると認める場合には、必要な措置をとるよう勧告することができるものとなっている。
この場合、市町村は、復興整備事業の実施区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができるものとし、その指定に当たっては、その旨及びその区域を公示することによってその効力が生ずるものとなっている。
届出対象区域内においては、建築物その他の工作物の新築等をしようとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類等を市町村長に届け出るものとし、また、変更に当たっても、同様に当該変更に係る行為に着手する日の30日前までに、その旨を届け出るものとなる。
市町村は、勧告をした場合においては、必要に応じて、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
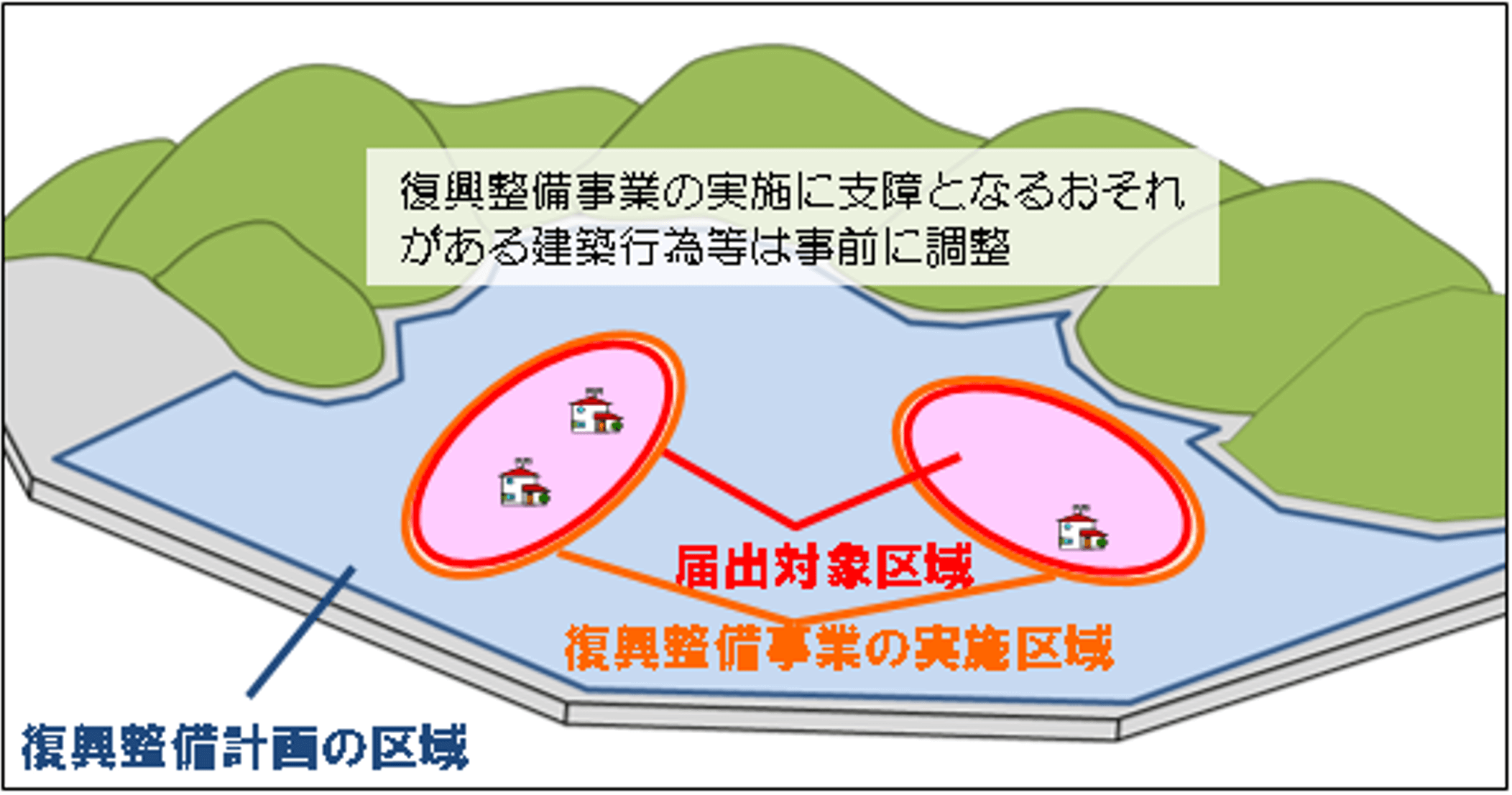
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/2206_setsumeishiryou.pdf (令和5年7月19日閲覧)
また、売買等の対象となる宅地(又は建物)については、届出対象区域に該当する場合、宅地建物取引業法に基づき、当該区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、原則として当該行為に着手する日の30日前までに当該市町村長に届け出なければならないこと、また、当該届出に係る事項を変更しようとするときも、原則として届出が必要であること等の事項について、重要事項として相手方に説明する必要がある。
宅地建物取引業者から、売買等の対象となる宅地(又は建物)を有する市町村が、届出対象区域に該当するか否かの問合せについて復興庁に対して頻繁に寄せられた。
さらに、防災集団移転促進事業により取得した移転元地を利用して復興整備事業を行うため、事業区域内の民有地と区域外の公有地との交換を行った場合に、民有地所有者に課税される所有権移転登記に関する登録免許税を免税とする特例がある。
この特例の適用に当たっては、被災市町村は、移転促進区域内の土地(移転元地)を利用する事業を記載した復興整備計画を作成し、復興整備事業の実施区域を届出対象区域に指定する必要がある。
当該特例を活用するため、仙台市における跡地利活用事業(荒浜地区 避難の丘)、(荒浜地区 公共利用ゾーン)、陸前高田市における私道長部線事業及び大船渡市における綾里地区漁業集落防災機能強化事業において、届出対象区域の指定が行われた。
(指定したことがある市町村数 3市4件)
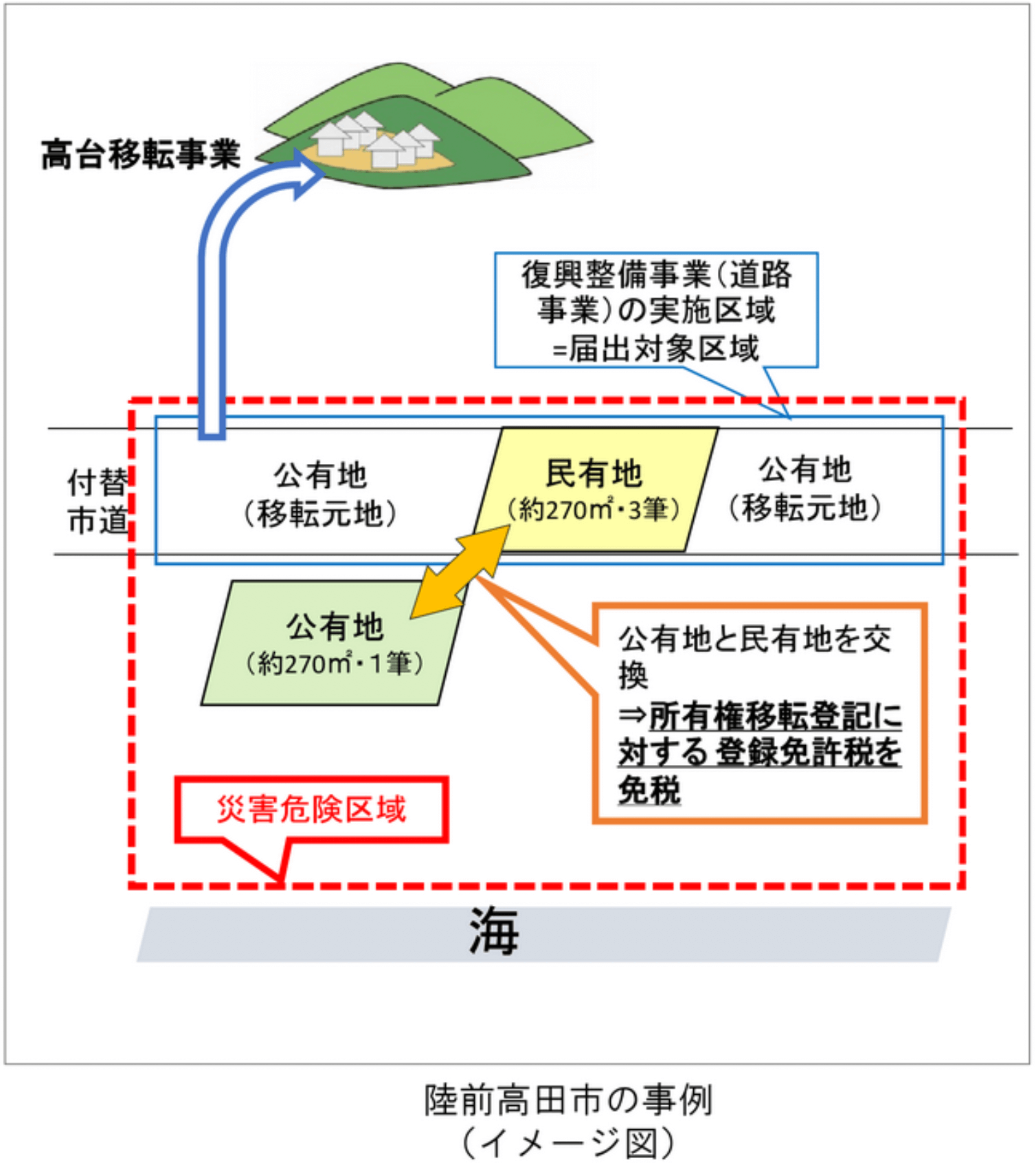
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20170630_motochijireisyu.pdf (令和5年7月14日)
イ) 復興整備計画のための土地の立入り等(復興特区法第65条)
市町村は、復興整備計画の作成又は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることを可能とするものとなっている。この場合、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知する必要があり、この際、土地の占有者は、正当な理由がない限り、立ち入りを拒み、又は妨げるようなことがあってはならない。また、建築物が存し、又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、立ち入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者にお知らせする必要がある。
なお、測量等に当たっては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、日出前及び日没後においては、当該土地への立ち入りが禁止されている。
ウ) 復興整備計画のための障害物の伐除及び土地の試掘等(復興特区法第66条)
復興整備計画の作成又は変更に当たって、その計画区域等の調査又は測量を実施するため、障害となる植物若しくは垣、柵等を伐除したり、当該土地に試掘若しくはボーリング又はこれらに伴う障害物を伐除したりする場合がある。この場合において、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、所有者等に事前に通知したにもかかわらず、その同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができるものとなっている。
また、当該障害物の所有者等がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができるものとし、この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者等に通知するものとしている。
エ) 復興整備事業のための土地の立入り等(復興特区法第67条)
市町村は、復興整備事業の実施の準備又は実施のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることを可能とするものとなっている。この場合、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知する必要があり、この際、土地の占有者は、正当な理由がない限り、立ち入りを拒み、又は妨げるようなことがあってはならない。また、建築物が存し、又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、立ち入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者にお知らせする必要がある。
なお、測量等に当たっては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、日出前及び日没後においては、当該土地への立ち入りが禁止されている。
オ) 復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等(復興特区法第68条)
復興整備事業の実施の準備又は実施に当たって、その事業の実施区域等の調査又は測量を実施するため、障害となる植物若しくは垣、柵等を伐除したり、当該土地に試掘若しくはボーリング又はこれらに伴う障害物を伐除したりする場合がある。この場合において、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、所有者等に事前に通知したにもかかわらず、その同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができるものとなっている。
また、当該障害物の所有者等がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができるものとし、この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者等に通知するものとしている。
カ) 証明書等の携帯(復興特区法第69条)
土地等への立入り等の行為に際しては、証明書及び許可証の携帯を義務付けるものとなっており、委託先等の職員においても同様に携帯を求めるものとなる。
復興整備計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施に当たって、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯するものとし、また、障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び管轄する地方公共団体の許可証を携帯するものとし、関係人からこれらの請求があったときは、これらを提示するものとしている。
キ) 土地の立入り等に伴う損失の補償(復興特区法第70条)
復興整備計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施に当たって、市町村等が、調査又は測量の実施により他人に損失を与えてしまった場合は、その損失を受けた者と協議を行った上で、通常生ずべき損失を補償するものとする。
なお、当該協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は収用委員会に土地収用法の規定による裁決を申請することができる。
f. その他
ア) 資料の提出その他の協力(復興特区法第71条)
復興整備計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施のため、土地等の所有者、占有者等の状況を把握する必要があるものの、これらの調査に当たっては、個人を識別する情報を含む場合があるなどの理由により、各行政機関等においては当該情報の収集目的以外の使用が困難な状況にあるため、被災地における十分な情報の活用がなされない状況が想定される。そのため、これらの調査に当たり、関係行政機関、関係地方公共団体の長、公私の団体に対して、それらの機関が有する当該情報に関する資料の提出その他必要な協力を求めることができるものとしている。
具体的には、固定資産課税台帳、選挙人名簿、自治会名簿等により、復興整備事業の実施の準備のための調査や用地買収に当たっての土地の所有者等を探索するための情報の提供を求めることなどが想定される。
なお、復興整備事業の実施主体には民間主体も含まれるが、本特例により関係行政機関等から情報提供を受けられるのは、国、都道県又は市町村の実施主体に限られたものとなっている。
4. 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
福島県においては、地震・津波被害に加えて、東京電力福島第一原発事故の放射性物質による環境の汚染が生じているという三重苦にあった。さらに、①警戒区域の設定等に伴いそもそも復旧作業すらできない地域も多く、それ以外でも空間放射線量が高い地域があり、まず除染が必要となる等復旧が著しく困難である、②放射性物質による汚染のおそれから住民に健康上の不安が生じている、③放射性物質の飛散に伴う風評被害により県産業全般の低迷に加え、人口や産業の県外流出が生じているといった特殊事情の下にあった。また、本来産業振興施策の主体である県において、長期避難者への対応等により、県単独では十分な施策を行うことが困難な状況にあるなど、県としての被害は甚大かつ多様であった。
東日本大震災からの復旧・復興に当たっては、平成23年12月に「東日本大震災復興特別区域法」が成立したほか、様々な立法措置がなされた。しかし、これらは主に地震・津波被災地域を対象としており、原子力災害被災地域について特に考慮したものとはなっていなかった。これらの法制度のみでは、上述の放射性汚染や風評被害、人口や産業の県外流出などの特殊な状況にある福島の復興を達成することが困難な状況にあった。
平成23年4月23日に開催された東日本大震災復興構想会議の第2回会議においては、委員である福島県知事が、現行法の既存の枠組みでは到底対応できないとの理由で特別法制定の必要性を訴えた23。また、同年6月18日の第10回会議でも福島県から福島被災地域の再生のための独自の特別法の制定を求める提案が行われた24。その中で福島県は、緊急の対応が必要な事項は個別の法改正等で迅速に対処しつつ、特別法では、中長期的に原子力災害の被災地域の再生に必要な恒久的措置を体系的に規定するという考え方を示した。特別な立法の必要性については、①福島県が、原子力災害による特殊かつ深刻なハンディキャップを多分野において長期的に負担することになるが、国策として進められてきた原子力による災害からの地域再生は全面的に国が責を負うべきこと、②放射線の影響からの住民の安全確保が、被災地域の再生と表裏をなす不可欠の前提であること、③原子力災害からの地域再生は分野が多岐にわたるため、総合的・体系的な再生の枠組みと省庁横断での対応が必要であること、④福島県民が、今後、新生ふくしま創造に向けて一丸となって臨むことのできる希望の旗印が不可欠、⑤国の威信をかけ、断固たる決意で福島の再生に取り組む姿勢と実績を国内外に発信することが必要といった点を挙げている。
こうした議論を踏まえ、同会議が同年6月25日に取りまとめた「復興への提言~悲惨のなかの希望」においても、「福島県は、地域の再生・復興を図る上で極めて困難な条件下に置かれる。原子力災害からの復興に対応する国の態勢の一元化や必要となる法整備を含め、長期的視点から、国が継続して、責任をもって再生・復興に取り組むべきである」とされた。
平成23年7月29日に東日本大震災復興対策本部で決定された「復興の基本方針」25においても、「国は、地方公共団体と調整を行い、できるだけ速やかに、原子力災害からの復興のための協議の場を立ち上げ、地域再生、損害賠償措置をはじめ復興に向けた十分な対策を講じるため、法的措置を含めた検討を行い、早急に結論を得る」と明記された。
このような中、平成23年8月から、東京電力福島第一原子力発電所における事故により甚大な被害を受けている福島県の復興再生に向けた対策等について、国と福島県が協議する場として「原子力災害からの福島復興再生協議会」(以下「協議会」という。)が設置された。同年8月27日の協議会第1回会合においては、福島県知事から、福島に特化した地域再生特別法の立法について、県や市町村との協議を通じて、国が責任と役割を担って立案・制定し、原子力災害からの福島の復興に万全を期すべきとの要望がなされ、平野復興担当大臣からも第2回会合において、特別法の策定を急ぐ旨発言があった26。
こうした中、東日本大震災復興対策本部事務局を中心に検討が進められ、平成23年12月10日に福島の復興再生のための特別法案の骨子が国から福島県に提示された27。翌年1月8日の協議会第3回会合では検討中の項目について28、同月23日の復興対策本部の第12回会合では法案の概要について29、翌月4日の協議会第4回会合でも同法案概要30と要綱案31について報告がなされた。その後、政府内及び与党との調整を経て、平成24年2月10日に主として以下の措置を内容とした福島復興再生特別措置法案が閣議決定された。
① 避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置
② 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置
③ 原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置
④ 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進のための措置
- 23 東日本大震災復興構想会議(第2回)議事要旨(平成23年4月23日)、佐藤福島県知事発言「また、今回の原子力災害は、被害が県内全域かつ長期にわたることや、一定地域の住民全員が避難せざるを得なかったこと、風評被害が県内全域、また多くの産業に及んでいることなどから、現行法では想定のできない甚大な被害を県内外にもたらしており、既存の枠組みでは到底対応できないと思います。新たな特別法立法の制定が不可欠であると考えています。」
- 24 「原子力災害による被災地域の再生に関する特別立法について」(平成23年6月18日、東日本大震災復興構想会議(第10回)福島県知事提出資料)
https://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou10/sato.pdf (令和5年7月15日閲覧) - 25 東日本大震災復興対策本部「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年7月29日)
- 26 第2回協議会議事概要 復興対策本部発言「別途知事から御要望のございます福島県に限りました特例法については、別途作業を進めているところでございます。」
https://www.reconstruction.go.jp/topics/2231017.html (令和5年7月19日閲覧) - 27 「福島の復興再生のための特別法案」東日本大震災復興対策本部、平成23年12月10日
https://www.pref.fukushima.lg.jp/download/1/kikaku_chosei_honbusiryo7.pdf.pdf (令和5年7月19日閲覧) - 28 「福島復興再生特別措置法案(仮称)について検討中の項目」第3回協議会資料、平成24年1月8日
https://www.reconstruction.go.jp/topics/2318.html - 29 「福島復興再生特別措置法案(仮称)概要(未定稿)」東日本大震災復興対策本部第12回資料、平成24年1月23日
https://www.reconstruction.go.jp/topics/000448.html (令和5年7月19日閲覧) - 30 「福島復興再生特別措置法案の概要」第4回協議会資料、平成24年2月4日
https://www.reconstruction.go.jp/topics/03-2_4houan.pdf (令和5年7月19日閲覧) - 31 「福島復興再生特別措置法案要綱案」第4回協議会資料、平成24年2月4日
https://www.reconstruction.go.jp/topics/03-3_4houan.pdf (令和5年7月19日閲覧)
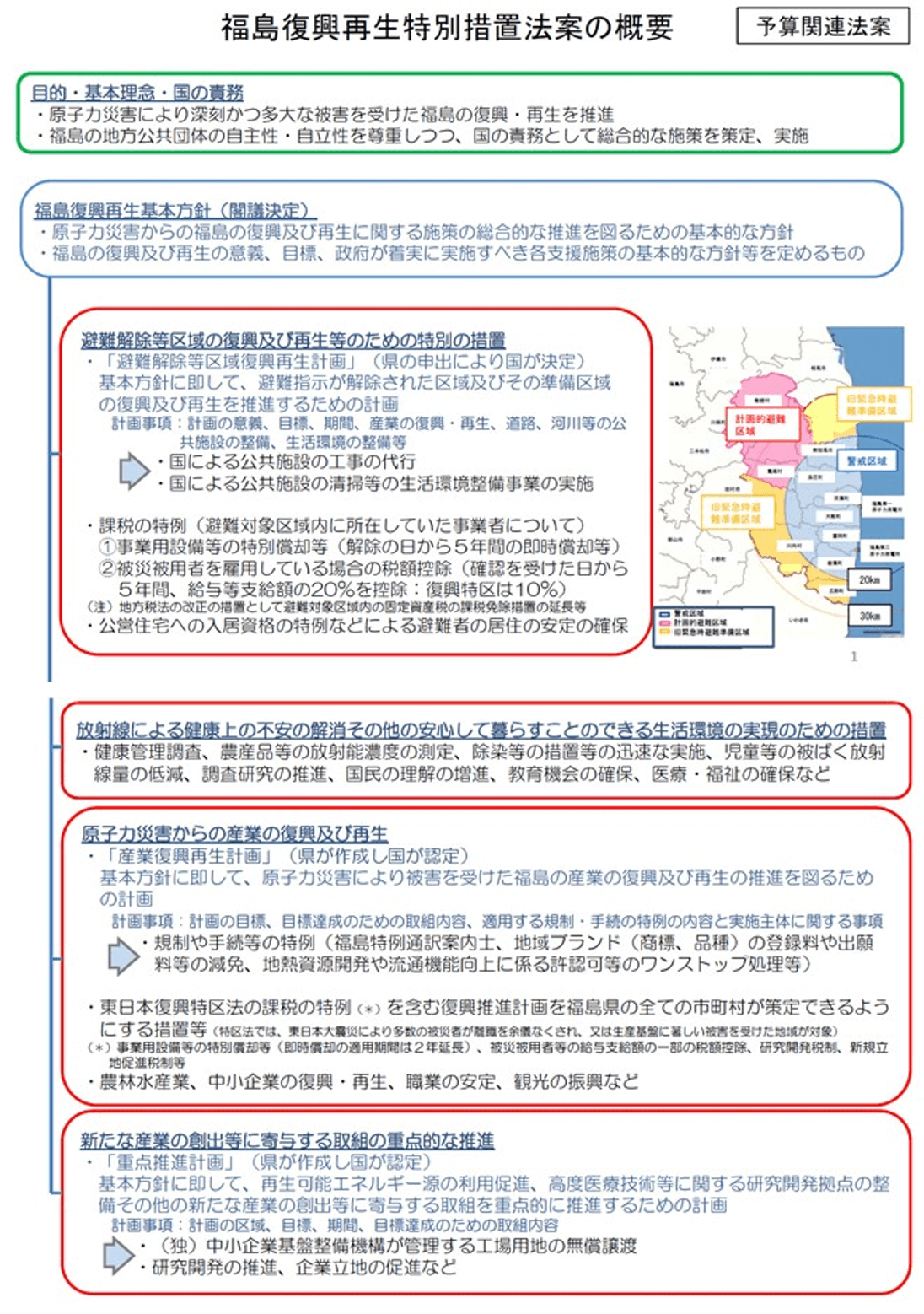
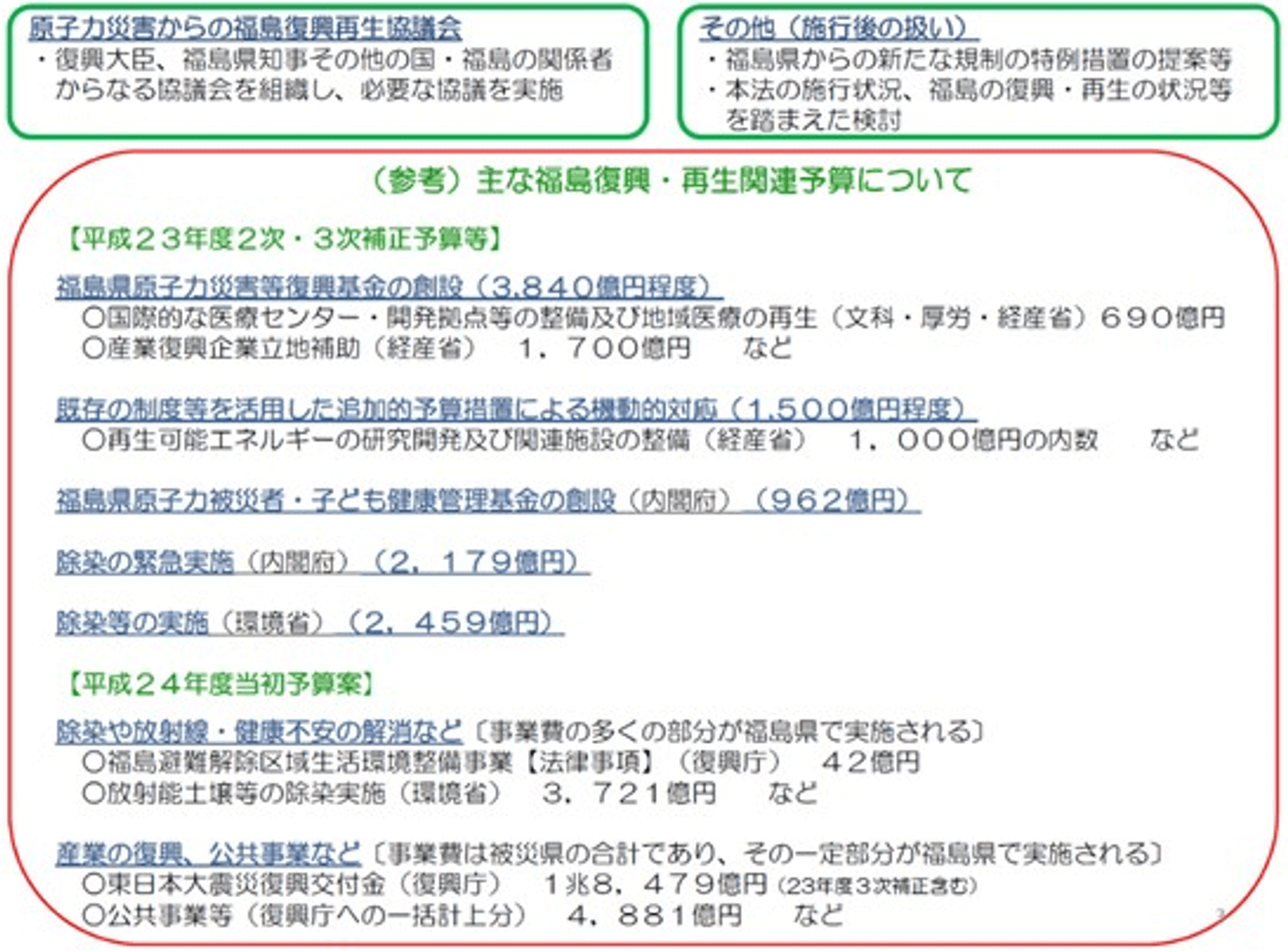
(2) 国会審議、公布・施行経緯
福島復興再生特別措置法案(以下「政府原案」という。)は、平成24年2月10日に閣議決定、国会に提出された。同年3月6日に(衆)東日本大震災復興特別委員会で提案理由説明がなされ、翌7日から質疑が開始されたが、政府原案では不十分な点があるとして、民主党、自由民主党、公明党の三党が中心になって修正協議が行われた。翌8日の同委員会に民主党、自由民主党、公明党等の6会派共同による修正案が提出され、修正案及び修正部分を除く政府原案が全会一致で可決されるとともに、附帯決議が付された。同日、修正後の本法律案は(衆)本会議において全会一致で可決された。
なお、主な修正としては、①目的規定への「国の社会的責任」の追加、②基本理念への「住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ること」の追加、③国による復興事業の直接施行が可能な工事対象の追加、④福島県による健康管理調査の内容の例示と財政的措置に係る規定の追加、⑤「生活の安定」など福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置の追加等が挙げられる。
その後、(参)東日本大震災復興特別委員会では、3月26日に政府原案の提案理由説明及び修正案の趣旨説明、27日及び28日に質疑、29日に質疑及び可決、附帯決議が付された。3月30日(参)本会議で全会一致により可決・成立、3月31日に公布され、同日施行(一部除く)された。
また、附帯決議には、各計画への市町村及び被災者意見の反映、復興及び再生の具体的な道筋の明確化と公表、除染等に必要な資機材の県内での調達、一日も早い事故終結と従事者の安全対策及び処遇改善、原子力災害起因の差別をなくす措置、分散避難した家族に対する格段の配慮、風評被害対策、中間貯蔵施設や最終処分施設のあり方についての自治体との協議などが盛り込まれた。
国会審議においては、主に以下の点について議論がなされた。
1) 福島の復興再生における国の責任
政府原案の目的規定には、国の責務は書かれているが、責任が明記されていないという指摘32が複数の委員からなされた。これに対して、平野復興大臣からは、「福島の復興再生は国が責任を持って推進すべきとの考え方に立って、『原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。』との規定を盛り込んだところでございまして、そこに我々の思いは入っているという認識でございました」と答弁された。しかし、「国が社会的責任を踏まえながら福島に対してより充実した支援を行う必要があるとの共通認識」に立つことを明確にする趣旨3334から、6会派共同での修正案において、第1条目的規定に、「これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ」との文言が盛り込まれることとなった。
- 32 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月7日)吉野正芳委員(自)発言「この法律第一条を読ませていただきました。国の責任が書いてありません。三条で国の責務は、一生懸命やりなさいという責務は書いてありますけれども、国の責任というのは書いていないんです。」
- 33 平成24年3月8日衆議院・東日本大震災復興特別委員会における「福島復興再生特別措置法案に対する修正案」の提出者の代表である吉野正芳議員(自)の趣旨説明。
- 34 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月8日)高木美千代委員(公)発言「国にこれまで原子力政策を推進してきた社会的な責任があるのは事実であり、今般の原子力災害による深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興再生につきまして、国がそのような社会的責任を踏まえて可能な限り最大限の措置を講ずるのは当然のことであるというのが趣旨でございます。」
2) 「住民一人一人の復興」の基本理念への追加
政府原案の基本理念では、福島の復興再生を図るために、「安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境」の実現をはじめ、福島が直面する課題を多様な住民の意見を尊重しつつ解決していく旨が規定された。これに対し、いわゆる自主避難者や、住民票を移したものの機会があれば福島に戻りたいと考えている県民なども含めて、全ての県民が同法律案の視野に入っているのかとの指摘があった35。平野復興大臣からは、同様の認識であるとの答弁があり、これらの議論を踏まえ、復興の基本理念として全ての福島県民一人一人の日常を取り戻すことを目指すべき36との意図で、修正案によって、基本理念に「福島の復興及び再生は、住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない」との文言が盛り込まれた。
- 35 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月7日)高橋千鶴子委員(共)発言「福島復興再生特別措置法は、いわゆる自主避難と呼ばれる方たちや、住民票を移したものの機会があれば福島に戻りたいと考えている県民にとっても再生なんだと、そういうことを確認したいと思うんです。」
- 36 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月8日)高橋千鶴子委員(共)発言「問われるのは、この基本理念が文字どおり具体化されるのか。原発事故により人生を大きく変えられ、家族がばらばらにされた全ての福島県民が主役であり、一人一人の日常を取り戻すためにこそ、この特別措置法が生きるということを期待します。」
3) 生活の安定
政府原案では、公共事業や産業の再生及び経済復興に対する特別措置に比して、原発事故によって避難を余儀なくされた方、風評被害等の被害者や失職した住民に対する生活再建支援が弱いのではないかとの指摘37がなされた。平野復興大臣からは、政府原案は原子力事故によって発生した風評被害、健康被害、精神的被害など様々な被害に対応したものである旨答弁がなされたが、修正案によって、避難指示区域からの避難者や避難指示の解除により避難解除区域に再び居住する者について、雇用の安定を図るための措置など生活の安定を図るため必要な措置を国が講ずるものとすることが盛り込まれた。
- 37 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月7日)吉泉秀男委員(社)発言「公共事業や産業の再生、経済復興に対する特別措置、これは講じられているわけでございますが、この特措法に、原発事故によって避難を余儀なくされた方々、風評被害等に苦しむ被害者、職場を失い収入の道を絶たれた住民に対する生活再建、この支援が全く触れられておりません。」
4) 健康管理調査の実施
放射線による健康上の不安を解消するとともに、安心して暮らすことのできる生活環境を実現するための健康管理調査の実施に関して、福島県がかねてから希望していた直接国費による18歳以下の医療費無料化が見送られたことに対する指摘38、福島県が健康管理調査等を実施するための基金に対する財政上の措置の必要性に対する指摘39があった。平野復興大臣からは平成23年度二次補正予算や平成24年度予算における基金への予算措置40を含め、法案修正があればその趣旨を踏まえて政府として対応していきたい旨答弁がなされた。これらの議論を経て、修正案によって、第68条を新設し、健康管理調査等のために福島県が設けた基金に対して国が必要な財政上の措置を講ずべきことが規定された。また、福島県が行うことのできる健康管理調査の内容として、子どもに対する甲状腺がんに関する検診が例示として明記された。
- 38 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月7日)太田和美委員(民)発言「県が強く求めていた十八歳以下の医療費無料化のことであります。子供たちの医療費無料化が見送られたこと、これはまことに残念であります。」「特措法六十八条において、国は、健康管理調査その他原子力災害から子供を初めとする住民の健康を守るための必要な事業を実施することを目的として地方自治法第二百四十一条の基金として福島県が設置する基金については、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講じるものとする(中略)修正が行われる予定だというふうに聞いております」
- 39 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月7日)高木美千代委員(公)発言「二十六条については、健康管理調査の実施に関し必要な措置ということで、「国は、福島県に対し、健康管理調査の実施に関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。」この「その他の必要な措置」というのは、私は、明らかにこれは財政上の措置というふうに読むわけですが、これはいかがでしょうか。
- 40 実際には、平成23年第二次補正予算による国から福島県への交付金781億円及び東京電力から平成24年1月に支払われた250億円の賠償金をもとに造成された「福島県民健康管理基金」の中で、福島県は全県民を対象とした健康管理調査、18歳以下の全県民を対象とした甲状腺検査等の健康不安対策の事業を行っている。
5) 将来的な住民の帰還を目指す区域の復興及び再生に向けた準備のための取組
政府原案には帰還先の地域の復興再生に向けた様々な取組は規定されているが、帰還困難、あるいは除染を終えなければ当分帰れない地域のことは規定されていない41との指摘がなされた。平野復興大臣からは、特別立法も含めて政府内で検討中との答弁があったが42、質問者からは一日も早く施策を提示すべきとの意見があり、これらの議論を踏まえて、修正案によって、避難解除等区域復興再生計画の計画事項に「将来的な住民の帰還を目指す区域における避難指示の解除後の当該区域の復興及び再生に向けた準備のための取組」が追加された。
- 41 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月7日)吉野正芳委員(自)発言「この法律を読むと、一番困っている、被害を受けた、戻れない地域の方々に対する施策は何かというと、復興住宅、公営住宅に入る資格がありますだけなんです。これは法改正しなきゃ入れないのは当たり前ですけれども、こんなことは当たり前なんです。復興住宅に入れる、公営住宅に入れる、これは当然、当たり前なんです。入って、ではどうするんだという、ここの支援策が全く書かれていないというのが、私がこの法律をずっと隅から隅まで読ませていただいて一番感じたところなんですね。」
- 42 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月7日)平野復興大臣発言「委員の問題意識は、非常に重要な問題提起をいただいておりまして、その問題については、繰り返しになって恐縮ですけれども、いろいろなテーマを設置して、今、鋭意政府内で検討中でございまして、その検討をさらに被災の自治体の方々と議論するためにも、先ほど議論になりました、先般ちょっと開催が成りませんでしたけれども、関係市町村との協議会、こういったことも今立ち上げたということでございます。いずれこの問題につきましては、非常に大きなテーマでございまして、個々のテーマ一つ一つが、大きな、慎重な、そしてまたかなりの細部にわたっての議論が必要でございます。最終的には、これに基づいての特別立法、別な法律が必要だということであれば、法律も場合によっては出すことも考えなければならないというふうに考えております。」
6) 再生可能エネルギーの導入
バイオマス発電や洋上風力発電の推進に係る意見43があり、修正案によって、国が「再生可能エネルギーの開発及び導入のため必要な財政上の措置、エネルギーの供給源の多様化のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずる」ことが追加された。
- 43 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月7日)石原洋三郎委員(民・無)発言「山林の除染を進めていくためにも、バイオマス発電を推進していくことが必要ではないかと考えます。」
第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月7日)吉泉秀男委員(社)発言「三次補正の段階で、福島県の復興シンボルとして、福島沖に六基の洋上風力発電を建設していく、そのためにまずは実証実験を行う、こういうことが決まりまして、公募をし、事業主体も決まって、そして県民、さらには国民の期待、これが大きく高まってきているわけでございます。世界で初めての浮体式の洋上風力発電でございます。しかし、この実証実験が、今、暗礁に乗り上げております。」
7) その他
復興交付金について国の精査が厳しいという指摘も踏まえて、福島の自治体の自主性、自立性を尊重すべき、地域のコミュニティに配慮すべき、放射線物質による汚染状況や健康影響については国が正確な情報を発信していくことが必要等の意見があり44、修正案によって、これらについては基本理念に追加された。
- 44 第180回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月7日)高木美智代委員(公)発言「交付金の活用について、復興庁から厳しい査定がという、査定庁とか悪口をいろいろ言われているようでございます」「例えば、我が党が主張してきました、人間の復興であるとか、福島の自治体に対する自主性、自立性の尊重であるとか、また福島の地域のコミュニティーの維持に配慮しなければならないとか、入れるべきと思っております。またあわせて、正確な情報を今後発信していくという、ここの留意というのは特に私は大事かと思っております。」
(3) 法概要・措置内容
制定時における具体的な内容は、以下のとおりである(以下、条番号や条文の内容は当時のものであり、現行法とは異なる場合がある。)。なお、本法に基づく措置の具体的な内容や適用状況等については、7章の各節も参照されたい(課税の特例については、2章4節3.参照)。
1) 概要・目的
原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の置かれた特殊な諸事情を踏まえ、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するため、福島復興再生基本方針の策定、避難解除等区域の復興及び再生並びに原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等について規定した法律である。
第1条において、本法の目的として、「原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、」と、国の社会的責任が冒頭に明記され、上記のような措置等によって「原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図り、もって東日本大震災復興基本法第二条の基本理念に則した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とする」ことが示されている。
2) 基本理念・国の責務
第2条において、基本理念として、原子力災害からの福島の復興及び再生では、原子力災害による住民の大量避難、復旧の長期化、放射性物質による住民の健康上の不安等に鑑み、安心できる生活環境の実現と社会経済を再生する必要が急務であるとして、それらの課題について、社会的弱者も含めて、「多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化を促進し、福島の地域社会の絆の維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならない」としている。
また、国会審議45を受けて、「原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民一人一人の復興を旨として行われなければならない」こと、「復興及び再生に関する施策は、福島の地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ講ぜられなければならない」こと、「福島の地域のコミュニティの維持に配慮して講ぜられなければならない」こと、「放射性物質による汚染の状況及び人の健康への影響、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況等に関する正確な情報の提供に特に留意されなければならない」ことも記されている。
また、第3条において、国は基本理念に則り、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有するとしている。
- 45 第180回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会(平成24年3月28日)高木美千代委員発言(公)「元の政府案に定められた基本理念は、その制作過程におきまして、福島県知事の御意見を踏まえることにより福島県民の思いを凝縮したものになったと伺っております。本修正はそうした思いが込められた基本理念を維持しつつも、私ども直接、議員も、県知事からも、また多くの県民の方たちからも御意見、また思いを伺ってまいりました。それを基に更に敷衍し、より一層本法案が福島の復興及び再生に資するものとなるよう、御指摘の四項目を追加したものであります。」
3) 福島復興再生基本方針
第5条において、政府は、福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本方針(以下「福島復興再生基本方針」という。)を定めなければならないこととされ、同基本方針には、福島の復興及び再生の意義及び目標や、避難解除等区域の復興及び再生の推進のための施策、生活や産業の再生のために必要な施策や計画等を定めることとされた。
4) 避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置
法第3章において、避難解除等区域46では長期にわたり地域コミュニティや産業の断絶が続き、他の地域に比べ著しく復旧・復興が困難なため、国の責任において避難解除等区域復興再生計画を策定し、国が自ら公共施設の整備や公共・公益施設の機能回復を行うこととした。また、避難解除区域における課税の特例、公営住宅法の特例等が設けられた。
① 避難解除等区域復興再生計画
第7条では、内閣総理大臣は、福島県知事の申出に基づき、避難解除等区域復興再生計画を作成し、復興及び再生のための取組を積極的に進めることとしている。避難解除等区域は、国が原子力災害対策特別措置法に基づき、地域住民に対して当該区域からの立退き及び立入りの制限等に係る指示を行った地域であり、長期にわたり地域コミュニティや産業基盤の断絶が生じ、他の地域と比べて特に復旧・復興が著しく困難となっていることから、国の責任においてその復興及び再生のための取組を実施する必要がある地域であるため、本計画は内閣総理大臣が作成することとされている。他方で、同計画には地域の復興・再生という福島県内の具体的な地域に密着した事項が盛り込まれることから、福島県知事が関係市町村長の意見を聴いた上での申出に基づくこととした。この際、県が具体的な計画のイメージをもって申出することを想定している。
② 国による県又は市町村の事業の直接施行
第8条から第16条まででは、計画区域において、国が県又は市町村に代わって、土地改良事業、漁港漁場整備事業、砂防工事、港湾施設建設・改良等の社会資本整備や農村地域整備に係る復興事業を直接行うことができることとするほか、一定の手続簡素化等を規定している。基本理念の通り、福島の復興再生は国の責任で行うことが基本であること、地元の行政機能が低下しており財政支援のみでは不十分であることに鑑みた措置である。
③ 生活環境整備事業
第17条では、避難解除等区域復興再生計画に基づく生活環境整備事業(学校、病院、公民館、市町村庁舎、市町村道、ガソリンスタンド等の公共・公益施設の清掃や軽微な修繕等)を国の負担で当該施設を管理する者の要請に基づいて実施できることを規定している。これは、避難解除等区域の公共施設等が、避難指示のために長期にわたって維持管理ができず、使用が困難となっている状況を受けた措置である。
④ 課税の特例
第18条及び19条では、避難解除区域において、一定の要件の下で設備投資や雇用に関する課税の特例が設けられている。
⑤ 公営住宅法の特例等
第20条から第22条まででは、避難指示区域内の住宅に震災時に居住していた者(以下「居住制限者」という。)に賃貸等するための公営住宅を建設等する場合の国の補助率の嵩上げや、入居者資格の特例、公営住宅の譲渡制限期間の短縮等を定めている。これは、原子力災害の避難者について、災害により住宅が滅失した者等と同様に救済するための措置である。また、第25条では福島県及び避難指示区域内の市町村は公営住宅等の建設事業者や民間賃貸住宅の管理主体等必要な関係者を加えた協議会を設置できることとする規定を設けている。
第23条及び第24条では避難者に対する住居の安定供給を確保するために独立行政法人都市再生機構(UR)と独立行政法人住宅金融支援機構(JHF)の業務の特例を設けている。
福島県の原子力災害被災地域は、独立行政法人都市再生機構法第3条の「大都市及び地域社会の中心となる都市」や同法第11条の「既に市街地を形成している区域」に該当しない都市や区域も多く、URが事業を実施するためには、東日本大震災復興特別区域法における特例と同様、新たな法的位置付けが必要であった。そこで、特定帰還者及び居住制限者に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限り、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同法11条3項各号の業務を行うことを可能としたものである(実績:大熊町大川原地区、大熊町下野上地区及び双葉町双葉駅西側地区等)。
- 46 福島復興再生特別措置法第4条第2号以下の規定により、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して内閣総理大臣等が行った避難指示が全て解除された区域(避難解除区域)及び当該避難指示が近く解除される見込みであるとされた区域を指す。
5) 放射線による健康上の不安の解消等
法第4章において、放射線による健康上の不安解消と安心して暮らせる生活環境実現のため、健康管理調査の実施その他の配慮規定について規定された。
① 健康管理調査の実施
第26条及び第27条では、福島県は、福島復興再生基本方針に基づき、平成23年3月11日時点での県への居住者に対し、健康管理調査(被ばく放射線量の推計、子どもに対する甲状腺がんに関する検診等)を実施できることや、調査対象者の同意のもと、特定健康診査等を実施した保険者から診査結果の提供を直接受けることができること等が規定された。また、第28条では、県による健康管理調査の実施について、国が技術的な助言や情報提供等の必要な措置を講ずることとされた。
② その他の配慮規定
第29条から第37条まででは、国が実施する措置として、健康増進等を図るための支援、農林水産物等の放射能濃度の測定等の実施の支援、除染等の措置等の迅速な実施等、児童等の被ばく放射線量の低減のための措置、放射線の人体への影響等に関する調査研究の推進等、国民の理解の増進、教育を受ける機会の確保のための施策、医療及び福祉サービスの確保のための施策等が規定された。
6) 原子力災害からの産業の復興及び再生
法第5章において、福島県の産業が原子力災害による被害を受け、また、風評被害等によって再生にも多大な困難を抱えていることを受け、福島県知事が原子力災害による被害を受けた産業の復興及び再生の推進を図るための計画(産業復興再生計画)を作成し、内閣総理大臣の認定を受けて、規制や手続の特例措置の適用を受けることとしている。
① 産業復興再生計画
第38条では、福島県知事が産業復興再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることにより、各種規制の特例措置を受けることができることとしている。具体的には、第40条から第50条までにおいて、福島特例通訳案内士育成等事業、商品等需要開拓事業、新品種育成事業など7事業の特例措置が規定された。
② 課税の特例(復興特別区域法の地域要件の緩和)
第51条及び第52条では、地震や津波による被災地域の事業者への支援を目的とした東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)の課税特例(同法第37条から第40条まで及び第43条)の適用対象となる地域要件を緩和し、福島県についてはその全域で事業用設備の取得や被災者雇用に伴う課税の特例を適用できることとした(令和3年度税制改正により廃止)。
③ 産業の復興及び再生に関する配慮規定
第53条から第57条まででは、国によるその他の支援措置として、農林水産業・中小企業の復興及び再生のための施策、職業指導等の措置、観光の振興等を通じた福島の復興及び再生のための施策、その他の産業の復興及び再生のための措置を定めている。
7) 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進
法第6章においては、福島県の地域特性や要望を踏まえ、風力、太陽光、バイオマス等の再生可能エネルギー関連産業や世界最先端のがん治療拠点構築をはじめとする医薬品や医療機器等の研究・開発拠点の整備等について、福島県が重点推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けて、国が一体的に推進することとしている。
認定を受けた計画の実施に関し、第60条では独立行政法人中小企業基盤整備機構による産業用地の無償譲渡等の特例措置を講じることとしたほか、第61条から第63条まででは国が研究開発の推進や企業立地の促進等のために必要な施策を講ずることとした。
8) 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置
法第7章では、上記の措置に加え、衆議院における修正によって、福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要なものとして、以下の措置が定められた。
・ 避難者の生活の安定を図るための措置(第64条)
・ 原子力発電所の事故に係る放射線による被曝に起因する健康被害が将来発生した場合における保健、医療及び福祉にわたる総合的な措置(第65条)
・ 再生可能エネルギーの開発等のための財政上の措置(第66条)
・ 復興交付金その他財政上の措置の活用(第67条)
・ 住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置(第68条)
・ 復興大臣による適切かつ迅速な勧告(第69条)
9) 原子力災害からの福島復興再生協議会
第70条では、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進に関し必要な協議を行うため、復興大臣、福島県知事及びその他の者からなる原子力災害からの福島復興再生協議会を組織するものとした。これにより、従来から開催されていた国と福島県の関係者からなる「原子力災害からの福島復興再生協議会」が法律上の協議会として位置付けられることとなった。
10) その他
第71条では、この法律の規定は、この法律に基づく措置の費用について、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)の規定により原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものを国が当該原子力事業者に対して求償することは妨げるものではないと明記された。
また、附則第2条では、法律の施行後3年以内に、福島の復興・再生の状況等を勘案し、住民の意向に配慮しつつ、課税の特例を含め、法律の規定について検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずることとされた。なお、「課税の特例を含め」は議員修正により追加されたものである。
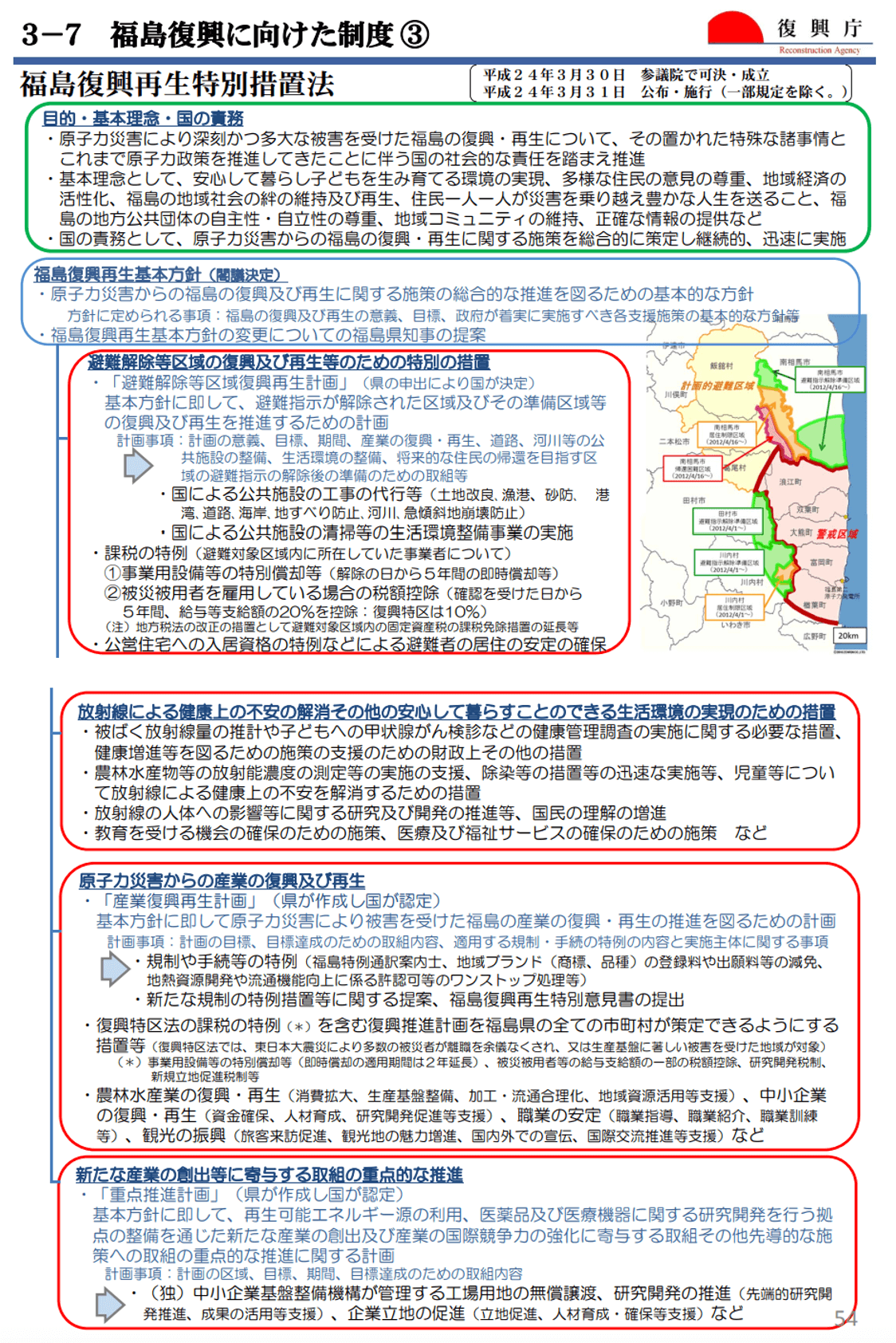
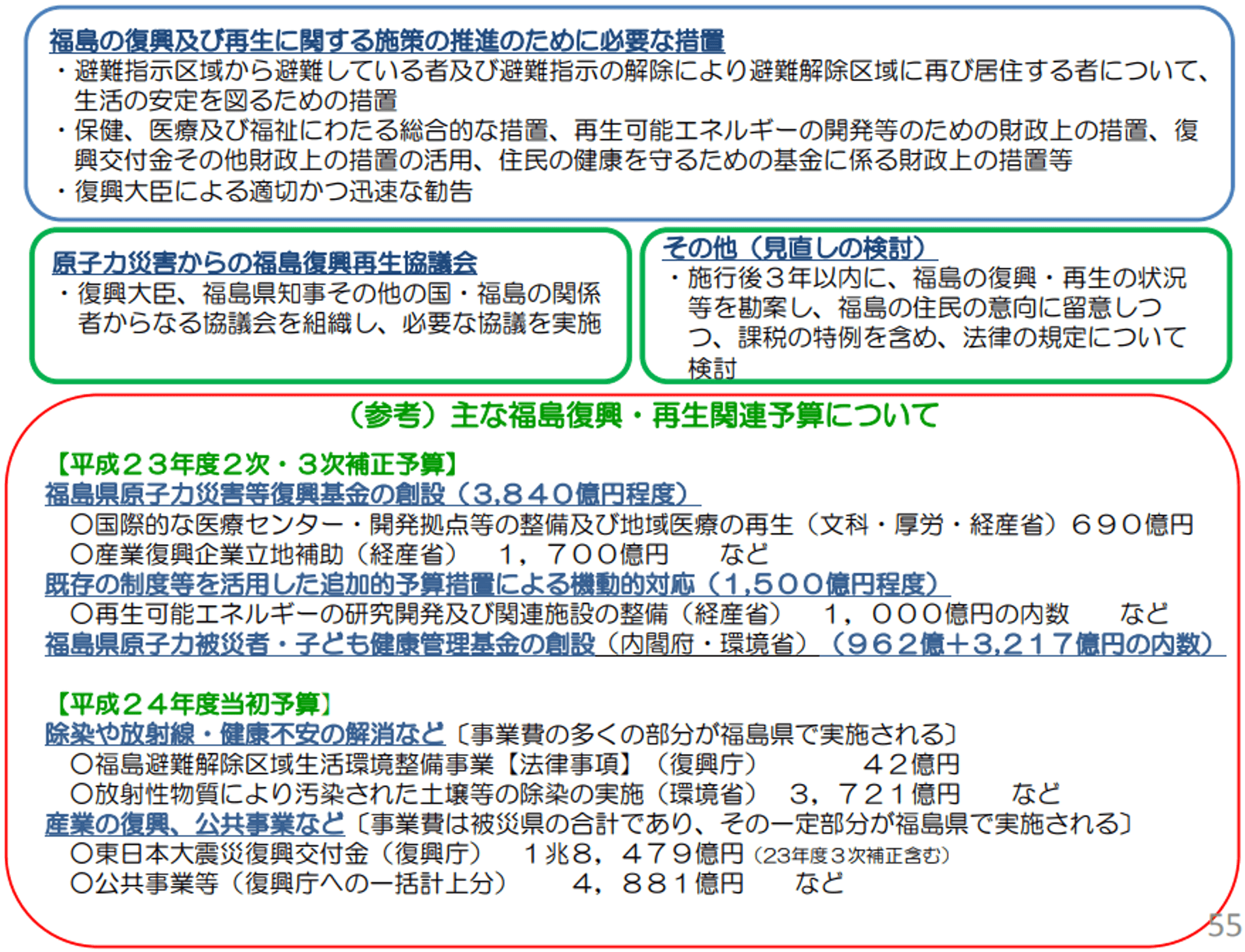
https://www.reconstruction.go.jp/topics/120611torikumitogenjo.pdf (令和5年7月14日閲覧)
(4) 改正経過・概要
1) 概要
福島復興再生特別措置法(以下「福島特措法」という。)は、第1期復興・創生期間が終了するまでに、平成25年改正法、平成27年改正法、平成29年改正法及び令和2年改正法において、実質的な改正がなされてきたところである。また、第2期復興・創生期間においては、令和4年6月に福島国際研究教育機構の設立に係る法改正がなされたほか、令和5年2月には、特定復興再生拠点区域外において、避難指示解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す「特定帰還居住区域」を設定できる制度の創設に係る改正法案が国会に提出された。
| 成立日 | 改正法 | 項目 |
| 平成25年 4月26日 |
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第12号) | ・長期避難者の生活拠点の形成(生活拠点形成交付金の創設) ・公共インフラの復興・再生(国による公共事業の代行対象区域の拡充) ・課税の特例等による企業立地の更なる促進(新規事業者を対象に追加等) |
| 平成27年 4月24日 |
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律第20号) | ・一団地の復興再生拠点整備制度の創設 ・帰還環境整備交付金の創設 ・事業再開を支援するための課税の特例(福島再開投資等準備金) |
| 平成29年 5月12日 |
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第32号) | ・特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制度の創設 ・官民合同チームの体制強化 ・「福島イノベーション・コースト構想」推進の法定化 ・風評被害払拭への対応 |
| 令和2年 6月5日 |
復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号) | ・帰還促進に加え、移住等の促進・営農再開の加速化 ・福島イノベーション・コースト構想の推進を軸とした産業集積の促進 ・風評被害への対応 ・福島県が福島復興再生計画を作成し、国の認定を受ける制度の創設 |
※ なお、本法に基づく措置の具体的な内容や適用状況等については、7章の各節も参照されたい(課税の特例については、2章4節3.参照)。
2) 平成25年改正法
a. 概要
平成25年5月10日に公布・施行された福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第12号)による主な改正内容は以下のとおりである。
① 長期避難者の生活の拠点を形成するため、公営住宅の整備をはじめとするインフラ整備と、生活環境改善やコミュニティ維持のためのソフト事業とを一体的に支援するための生活拠点形成交付金を創設した。
② 国による公共事業の代行や生活環境整備事業の対象地域を拡充し、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものについて、避難指示の対象となっている区域(警戒区域を除く)においても実施することができることとした。
③ 避難解除区域等内の区域であって雇用機会の確保に寄与する事業等を実施する企業の立地を促進すべき区域(企業立地促進区域)において、一定の要件の下で設備投資や雇用に関する課税の特例等を受けることができることとした。
b. 改正の背景・経緯
福島特措法が制定され、平成24年7月13日には福島復興再生基本方針が閣議決定された。また、平成25年2月13日には福島県知事から避難解除等区域復興再生計画の申出がなされ、平成25年3月19日に内閣総理大臣がこれを作成した。この間、平成24年9月4日には、復興庁から、福島県及び関係市町村からの要請を踏まえ、概ね10年後に向けた避難地域の復興に対する国の取組姿勢である「原子力発電所の事故による避難地域の原子力被災者・自治体に対する国の取組方針」(グランドデザイン)47が示されている。
これと並行して、避難指示区域の段階的な再編が行われ、緊急時避難準備区域については避難指示が解除されて帰還が可能となり、避難指示の対象となっている居住制限区域や避難指示解除準備区域についても事業の再開が認められる状況となった。このため、将来的な帰還に向けて、地域の社会インフラ整備と産業の復興を加速化させる必要があった。一方、避難指示区域の住民の避難は継続しており、避難先での安定的な生活確保や事故前の地域コミュニティ維持も課題となっていた。
こうした中、平成24年12月に第2次安倍内閣が発足し、「震災復興」が「経済再生」「危機管理」と並ぶ最重要課題として改めて位置付けられ、東日本大震災の被災地における復興の加速化、特に福島の復興・再生の加速化のための施策が進められた。平成25年2月1日には、復興大臣をトップとする「福島復興再生総局」が設置され、事務方トップクラスが総局に在勤するとともに、東京においても、復興大臣が関係省庁の局長クラスを直接指揮する「福島復興再生総括本部」が設置された。これにより、いわゆる「福島・東京2本社体制」が実現し、福島復興に係る政府の体制強化が図られた(この体制強化の詳細は、2章2節4.参照)。
復興関係予算についても、平成24年度補正及び平成25年度予算当初予算の両予算を一体として、被災地の復興のスピードアップ・加速化が図られることとなった。原子力災害からの復興再生のための予算としては、公共施設等の機能回復を支援する「福島避難解除等区域生活環境整備事業」、長期避難者を受け入れている自治体における災害公営住宅や道路・学校施設等の整備を促進する「長期避難者生活拠点形成交付金(仮称)」、子育て環境の整備(公的な賃貸住宅や屋内運動施設の整備、遊具設置等)を支援する「福島定住緊急支援交付金(仮称)」、住民の帰還に向けた区域の荒廃抑制・保全対策のための「福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業」等が計上され、除染や中間貯蔵施設の設置に向けた取組、営農再開や再生可能エネルギー支援、環境創造センターの設置、風評被害対策等も加えて、平成24年度補正予算には706億円が、平成25年度当初予算には7,264億円が、それぞれ計上された。
これらの福島の復興・再生への取組の加速や予算案及び税制改正大綱に盛り込まれた措置の実現のために福島特措法の改正が必要となり、平成25年2月17日の「原子力災害からの福島復興再生協議会」等における福島県への説明を経て、3月8日に「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出された。
- 47 復興庁記者発表資料「原子力発電所の事故による避難地域の原子力被災者・自治体に対する国の取組方針」(グランドデザイン) (平成24年9月4日)
https://www.reconstruction.go.jp/topics/20150203092246.html (令和5年7月19日閲覧)
c. 国会審議、公布・施行経緯
本法律案は、平成25年4月2日に(衆)東日本大震災復興特別委員会で提案理由説明、翌3日に質疑・採決、附帯決議が付され、翌4日、(衆)本会議において全会一致で可決された。4月19日に(参)東日本大震災復興特別委員会で提案理由説明、同月25日に質疑後、生活の党から提案された修正動議48は否決され、原案が全会一致で可決、附帯決議が付された。翌26日に(参)本会議において全会一致で可決・成立、5月10日に公布され、同日施行された。
附帯決議には、長期避難者と避難先住民との交流など地域との融和が進む施策を講じること、避難先市町村が公共インフラ・サービスを提供する負担への配慮、帰還困難区域等で作業する者の被ばく量への留意、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求権の消滅時効について必要な措置を講じること等が盛り込まれた。
国会審議においては、主に以下の点について議論がなされた。
- 48 事業者に対する課税特例の対象地域を避難解除区域に限定するとの修正案。
ア) 長期避難者の生活拠点形成交付金
長期避難者の避難先における生活拠点形成事業で整備可能な施設について質問があり49、根本復興大臣からは災害公営住宅、道路、学校施設、介護施設、子育て施設等が対象となる旨答弁があった。
- 49 第183回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号(平成25年4月3日)高木美智代委員(公)発言「本法案の生活拠点形成事業交付金につきまして、この計画に記載する項目として、第三十五条第二項の三に、「居住制限者の生活の拠点を形成する事業」として、「その他復興庁令で定める事業」とありますが、介護、子育て、医療などが考えられると思います。また、災害復興住宅の複合施設、同じ敷地内にそうした施設を設置することが可能なのかどうか、」等
イ) 公共事業の代行と生活環境整備事業の対象地域拡充
国による公共事業の代行や生活環境整備事業の対象地域を拡充することについて、拡充された地域で活動する除染作業者の活動の安全性に対する質問50があり、政府参考人からは、先行的に施設の除染を行って放射線量を下げることや作業員の線量の管理と結果を記録することなど安全が確保されるようなルールに従って作業を進めたい旨答弁がなされた。
- 50 第183回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号(平成25年4月3日)吉田泉委員(民)発言「基本的に、居住制限、人は住んじゃいかぬと言っているところですから、年間二十ミリシーベルト以上の地域ですよね。そこで、工事といいますか清掃はせねばならぬけれども、作業の安全性というのも確保せないかぬ、それをどうやって両立させるのかということについてお伺いしたいと思います。」
ウ) 企業立地の促進に関する課税優遇措置
課税の特例措置による居住制限区域等への一般事業者の誘導について、従業員等の安全性に問題はないのかという質問がなされた。政府参考人からは、一般事業者の事業活動については国の確認を得た上で例外的に市町村が許可することになっており、許可の条件として、年間積算線量が20ミリシーベルトを大きく超えない区域であり、その区域を優先的に除染し、屋内での作業を基本にするように求めることなどで、一般の事業者を危険にさらすことは回避されるとの答弁51があった。また、根本復興大臣からは、平成25年3月時点で被災事業者のうち既に22の事業所が居住制限区域で事業を再開しており、事業者を支援する必要があること、今後、復旧事業を進めるためにガソリンスタンドを補う必要がある旨の答弁があった。
- 51 第183回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号(平成25年4月25日)政府参考人発言「その許可の条件でございますが、例えば、年間積算線量が二十ミリシーベルトを大きく超えない区域であること、そしてその区域を優先的な除染をしていただくこと、また屋内での作業を基本にするように求めること、あるいは従業員の線量管理を徹底することと、このような一定の条件を付した上での許可でございますので、一般の事業者を危険にさらすことにならないと考えております」
d. 改正法の内容
ア) 概要・目的
福島の復興及び再生を一層推進するため、生活拠点形成交付金を創設するとともに、国による公共事業の代行及び生活環境整備事業の対象地域の拡充、避難解除区域における税制優遇措置の対象拡充等を行う。
(以下、条番号や条文の内容は当時のものであり、現行法とは異なる場合がある。)。
イ) 長期避難者の生活拠点の形成
長期避難者の生活の拠点を形成するため、福島県等による公営住宅をはじめとするインフラの整備と生活環境改善やコミュニティ維持のためのソフト事業を一体として財政的に支援する生活拠点形成交付金が創設された。
第35条では、福島県知事及び避難先市町村の長が共同して、避難先市町村の区域内における公営住宅の整備その他の居住制限者の生活の拠点を形成する事業に関する生活拠点形成事業計画を作成できることとされた。同計画では、公営住宅の整備又は管理に関する事業、居住制限者の生活拠点形成事業やこれらの効果を増大させる事業又は事務等を定めることとされた。
第36条では同計画に基づく生活拠点形成交付金事業と国による交付金の交付、第37条では拠点形成に当たっての居住制限者の生活の安定への配慮が定められた。
ウ) 公共インフラの復興・再生
避難解除等区域復興再生計画に基づく国による公共事業の代行や生活環境整備事業のうち、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要となるものについては、避難解除等区域だけではなく、避難指示の対象となっている区域(警戒区域を除く)においても実施可能とした。
エ) 企業立地促進計画及びこれに基づく措置等
避難対象区域内にあった事業者が避難解除区域で事業を再開する場合に適用された税制の特例措置について、避難指示解除準備区域及び居住制限区域で事業を再開する場合にも受けられることとした。
さらに、新規事業者がこれらの区域で事業を行う場合にも同様の税制の特例措置が受けられることとした。なお、対象となる新規事業者については、福島県が作成する企業立地促進計画に適合する事業実施計画を有する等、一定の要件を満たすとして福島県知事から認定を受け、雇用機会の確保に寄与する事業その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に資する事業を行う者とされた。
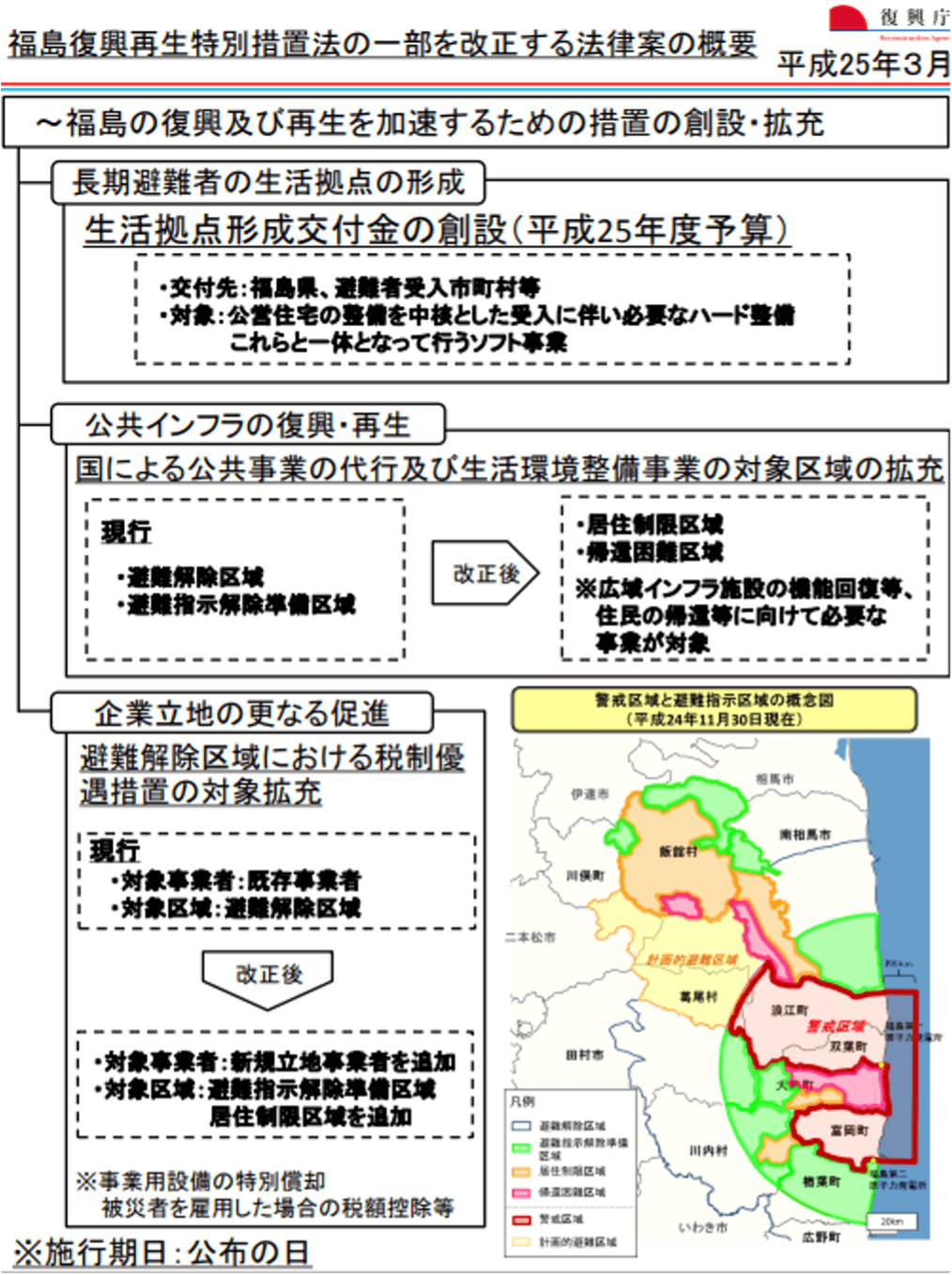
3) 平成27年改正法
a. 概要
平成27年5月7日に公布・施行された福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律第20号)による主な改正内容は以下のとおりである。
① 避難解除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地を形成することが必要であると認められるものについて、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設を定めることができるものとした。
② 土地区画整理事業、一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業その他の住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業等の実施に要する経費に充てるため、帰還環境整備交付金を創設するものとした。
③ 一定の避難指示の対象となった区域内に平成23年3月11日においてその事業所が所在していた個人事業者又は法人であって、避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕をするものは、当該施設の新設等に要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律で定めるところにより、課税の特例の適用を受けることができるものとした。
b. 改正の背景・経緯
平成25年5月の改正法の公布以降、平成25年12月20日には、国の福島復興の指針となる「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」(平成25年12月20日閣議決定)が策定され、①避難者の早期帰還と新生活開始の両面で福島を支える、②東京電力福島第一原発の事故収束に向けた取組を強化する、③国が前面に立って福島の再生を加速するとの方針が打ち出された。その中で、国は双葉郡をはじめとする避難指示区域の将来像について、中長期的かつ広域的な視点で検討を始めることとされた。そうした動きを受けて、福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会(座長:赤羽経済産業副大臣)が翌26年1月21日に立ち上げられ、同年6月23日には、浜通り地域の新たな産業基盤の構築や広域的視点でのまちづくりを目指した「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想」が、同研究会により取りまとめられ、翌24日の「経済財政運営と改革の基本方針2014について」(閣議決定)にも位置付けられた。また、同年12月には復興庁に「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」が設置され、2020(令和2)年を目標とした早期帰還可能な地域再生のための産業、医療、まちづくりなどの具体的なビジョンを含む地域の将来像についての検討が開始された。
この間、平成26年4月に田村市、同年10月には川内村の一部の避難指示が解除され、大熊町等の市町村においては、復興計画の策定作業が進められるなど、避難解除区域等への帰還の動きが進んできた。そうした中、法律の施行後3年以内の見直し時期を迎える平成27年3月を控え、平成26年11月27日に福島県から、避難地域の新たなまちづくりの加速化やふるさとでの事業再開に向けた福島特措法の改正が国に要望された52。要望では、大熊町の大川原地区をはじめ、ふるさとに帰還する住民の生活や地域経済再生のための拠点(町内復興拠点)の迅速な整備のための、新たな事業制度の創設や、地元企業の事業再開のための「福島再開投資等準備金」税制の実現が求められ、これらを踏まえて政府は検討を行い、平成27年2月17日に、一団地の復興再生拠点整備制度や帰還環境整備交付金の創設等の措置を講ずるため、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案が閣議決定、国会に提出された。
- 52 「福島復興再生特別措置法改正に関する緊急要望」平成26年11月27日、福島県知事内堀雅雄
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/374285.pdf (令和5年7月19日閲覧)
c. 国会審議、公布・施行経緯
本法律案は、平成27年3月26日には(衆)東日本大震災復興特別委員会で提案理由説明、4月2日に質疑・採決、附帯決議が付され、4月7日に(衆)本会議で可決された。その後、4月15日に(参)東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会で提案理由説明、4月22日に質疑・採決、附帯決議が付され、4月24日に(参)本会議で多数をもって可決・成立、5月7日に公布され、同日施行された。
なお、附帯決議においては、一団地の復興再生拠点整備制度を多くの市町村が活用できるような配慮、帰還環境整備交付金の柔軟な運用、住民の意向を尊重した帰還促進、平成28年度以降の復興支援の予算・人的資源の確保などの項目が盛り込まれた。
国会審議においては、主に以下の点について議論がなされた。
ア) 一団地の復興再生拠点整備制度のあり方
改正法案の一団地の復興再生拠点整備制度について、同案検討の際に既に復興再生拠点について検討を進める大熊町大川原地区を念頭に置いたとされることに対して、同地区以外での活用が難しいのではないか、との質問があり53、これに対して、竹下復興大臣から、大熊町以外の市町村における復興再生拠点制度の活用も念頭に置いており、やはり復興再生拠点の構想を持つ双葉町についても同制度活用を想定しているとの答弁があった。
- 53 第189回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号(平成27年4月2日)真山祐一議員(公)発言「一方、活用の念頭にある大川原地区以外での活用は難しいのではないか、こういった懸念の声もいただいております。そこで、この一団地の復興再生拠点整備制度をはじめ、帰還環境整備交付金の活用は、市町村のニーズを踏まえ、幅広い活用を認めるべきと考えておりますが、この帰還環境整備に向けた復興大臣の御所見をお伺いさせていただきます。」
イ) 住民の帰還に必要な環境の整備
一団地の復興拠点の想定人口が3,000人程度にとどまることや、避難住民の帰還意向が年々低下していることに関して、この程度の想定人口で本当に復興に成果が上がるのかとの質問54に対して、浜田復興副大臣からは、大熊町における住民意向調査では平成25年度の調査と比べて帰還希望世帯が、大川原の復興拠点への期待も含め約5%増えており、引き続き住民の意向を丁寧に把握したい、また復興拠点の事業化についてはニーズに合わせて段階的に進めていきたいとの答弁があった。これに対して、質問者からは地域の人口減少を踏まえて、広域的な帰還環境整備が必要との意見があった。
- 54 第189回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号(平成27年4月2日)小熊慎司委員(維)発言「この想定人口が三千人、町内の人が千人ということについて、私はなかなか、コミュニティーを再生するという意味では、今まで一万人、二万人という単位でいた町が、こういうことで本当に町が復活することになるのかという疑問をやはり消すことができないんですね。この想定人口、ある意味では、このぐらいで、これで本当に復興に成果が上がるのかどうか、この件について御所見をお伺いしたいと思います。」
ウ) 集中復興期間終了後の復興財源の確保
会期中の4月21日に福島県から、国の集中復興期間終了後の平成28年度からの5年間で、国と県、市町村分を合わせた復興事業費の総額が少なくとも3兆5,700億円に上るとする試算結果が公表されたのを受け、今後の予算確保を問う意見があったのに対して、竹下復興大臣より、必要な事業の必要な予算については財務大臣と交渉し、復興庁としてしっかり確保していきたい旨答弁があり55、附帯決議に盛り込まれた。
- 55 第189回国会 参議院 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会 第6号(平成27年4月22日)森まさこ委員(自)発言「福島県は昨日、国の集中復興期間終了後の平成二十八年度から五年間で、国と県、市町村分を合わせた復興事業費の総額は少なくとも三兆五千七百億円に上るとする試算結果を公表いたしました。被災地の自立ある復興のためにも必要な予算はしっかりと確保をしていただきたいと思います」
エ) 医療・介護・福祉人材の確保について
帰還支援を進める中で、障害者、高齢者をはじめとした要援護者が安心できる生活の場が重要であり、施設整備ができたとしても医療、介護、福祉のマンパワーが不足しているのではないかとの指摘があり56、厚生労働大臣政務官より引き続き厚生労働省としてしっかり取り組みたいとの答弁があった。
- 56 第189回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号(平成27年4月2日)金子恵美委員(民)発言「社会福祉施設等施設整備事業のお話もありましたが、そういう、いろいろなメニューの活用ということでありますけれども、施設整備ができたとしても、やはり医療、介護、福祉のマンパワーが不足しているということであります。」等
d. 改正法の内容
ア) 概要・目的
福島の復興及び再生を一層推進するため、一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画の制度及び住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業を行う地方公共団体に交付金を交付する制度を創設する等の所要の措置を講ずる。
(以下、条番号や条文の内容は当時のものであり、現行法とは異なる場合がある。)
イ) 一団地の復興再生拠点整備制度の創設
帰還する住民の生活再開、地域経済の再建の場となる復興再生拠点を円滑・迅速に整備するため、津波復興拠点制度(本節12.参照)に倣い、全面買収方式により新市街地を整備する事業制度を創設することとした。土地区画整理事業では換地計画の策定に要する時間等が懸念されたこと、避難解除区域等内の土地所有者の中には帰還の意思がなく土地の売却を希望する者も多く、換地を前提とした土地区画整理事業の施行には必ずしも馴染まない場合も想定されたこと、新住宅市街地開発事業では人口要件(概ね6,000人から1万人)に合致しないことが懸念されたことから、土地買収型の新たな市街地整備制度が必要となったものである。
第32条で、一定の条件を満たす避難解除区域等内の区域に、帰還する住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる「復興再生拠点市街地」を形成するため、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設(復興再生拠点市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設又は特定公益的施設及び特定公共施設)を定めることができることとした。
また、支援措置として、帰還環境整備交付金の予算措置と、土地等の提供者に対する税制上の特例措置を定めている。
ウ) 帰還環境整備交付金の創設
住民の帰還に必要な環境整備を加速化するため、第33条で、避難指示・解除区域市町村もしくは特定市町村57と福島県が単独・共同で、住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業に関する「帰還環境整備事業計画」を作成することができることとし、同計画を内閣総理大臣に提出することで、国から計画に位置付けられる事業が交付金を受けられることとした。これに伴い、福島再生加速化交付金(再生加速化)の支援対象事業に、面整備事業(土地区画整理事業、一団地の復興再生拠点整備事業)、道路(アクセス道路等)、下水道、公営住宅、公立学校等の基幹インフラ事業を追加するとともに、「帰還環境整備交付金」として法定化した。これにより、道路法等により補助率が法定化されているハードインフラへの充当が可能となり、本交付金の使い勝手が向上した。また、同交付金の対象としては、特定市町村における、放射線による不安を解消するための個人線量計の貸与に関する事業、相談員の育成、配置に関する事業等も規定された58。
- 57 避難指示・解除区域市町村以外の福島の市町村であって、その区域における放射線量その他の事項を勘案して復興庁令で定めるもの
- 58 第189回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号(平成27年4月2日)政府参考人発言「御指摘の法第三十三条第二項第二号ヘに掲げる事業でございますけれども、これは、放射線による不安を解消するための事業として個人線量計の貸与に関する事業、あるいは相談員の育成、配置に関する事業など、復興庁令により定めることといたしております。また、これらの事業を実施可能な特定市町村の範囲でございますけれども、いわゆる浜通り、中通りの市町村のうち、避難指示の対象となった十二市町村以外のところを定めることといたしております。」
エ) 事業再開を支援するための課税の特例
第25条で、避難指示解除区域や避難指示解除準備区域、居住制限区域における事業の再開に備え、事業者が事業再開に必要となる設備投資のために資金を積み立てた場合に、一定の要件の下、当該積立金が損金算入できる税制上の特例措置を創設した。
オ) その他の改正事項
新産業の創出等に向けて、福島県が作成する重点推進計画に定めることができる内容として、ロボットに関する研究開発拠点整備を通じた新たな産業の創出等に寄与する取組が追加された。また、住民の帰還促進のための配慮事項として、健康や帰還後の生活不安に対する相談体制の整備や、避難指示区域における鳥獣被害対策に係る規定が定められた。
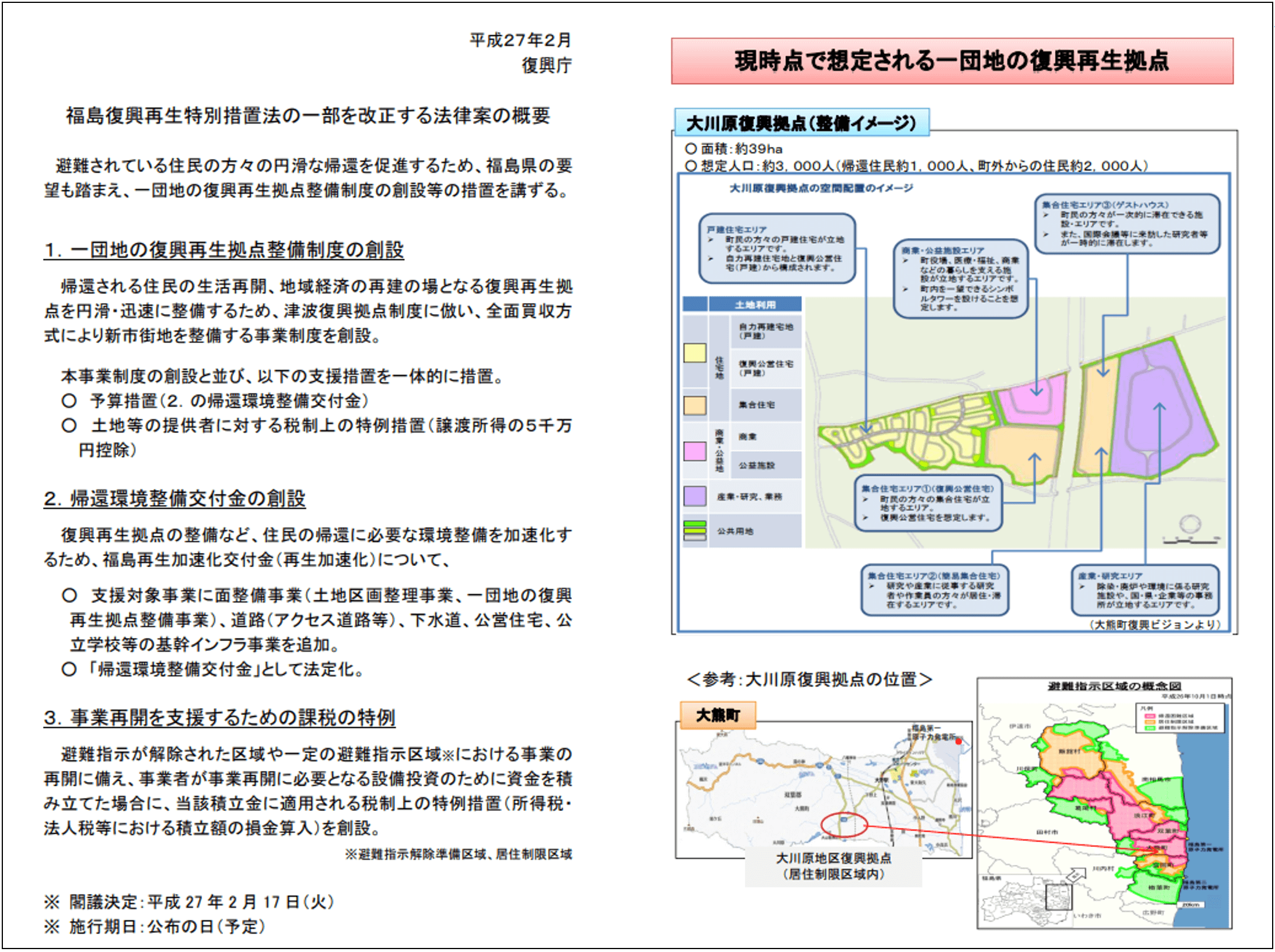
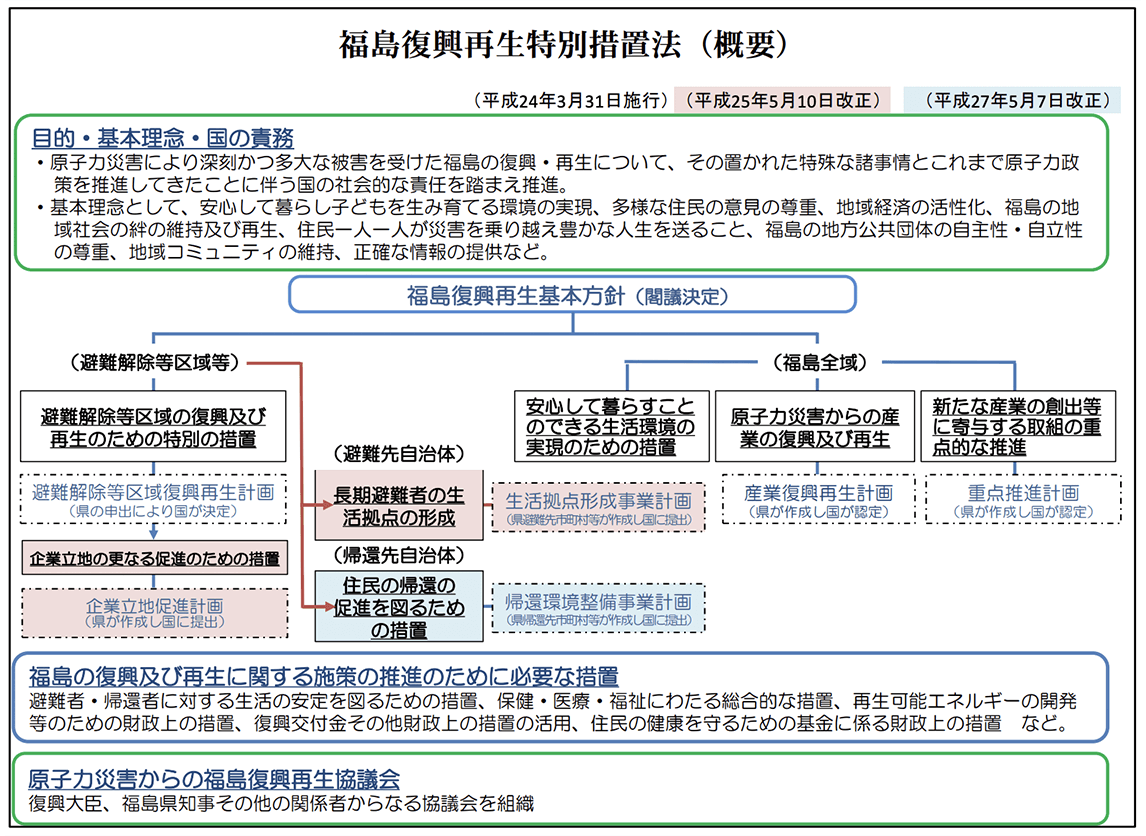
4) 平成29年改正法
a. 概要
平成29年5月19日に公布・施行された福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第32号)による主な改正内容は以下のとおりである。
① 帰還困難区域をその区域に含む市町村長は、福島県知事と協議の上、特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、土地改良事業等の国による事業代行や被災事業者の事業再開に必要な設備投資に係る課税の特例等を活用することができることとした。また、土壌の除染の措置や廃棄物の処理等を国の負担により行うことができることとした。
② 公益社団法人福島相双復興推進機構の要請に応じ、国の職員を、その身分を保有したまま当該機構に派遣し、その業務に従事させることができることとした。
③ 福島イノベーション・コースト構想に係る取組を推進する区域及び取組内容を重点推進計画に記載し、内閣総理大臣の認定を受けることで、中小企業者が行う研究開発に係る特許料等の減免等の特例措置が受けられることとした。
④ 風評被害の払拭等に向け、福島で生産された商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査や当該調査に基づく指導、助言等の措置を講ずるものとした。
b. 改正の背景・経緯
平成27年法改正後、楢葉町、葛尾村など4市町村で新たに避難指示解除が実現し、飯舘村、川俣町、浪江町においても平成29年3月の避難指示解除が決定されるなど、住民の帰還環境が整いつつあった。また「福島相双復興官民合同チーム」が発足し、被災事業者の事業再開等を支援する体制も整備されつつあった。さらに、浜通り地域においては、平成26年6月に取りまとめられた「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会報告書」を受けて、廃炉やロボットに関する研究・実証拠点の整備等、当該地域に新たな産業を創出するための取組が進められたが、一方で、福島産品に対する風評被害は依然として継続しており、福島県における復興の取組を一層加速させる必要があった。
平成28年12月5日、福島県知事から、避難指示解除といった復興の動きが着実に進む中、帰還困難区域の復興、福島イノベーション・コースト構想の早期実現などの課題があるなど、今後の福島復興の道筋をつける意味で同年が極めて重要な年であるとし、県が市町村と連携し復興に向けた取組を加速していくに当たり、復興をより確かなものとする必要があるとして、福島特措法改正の緊急要望が国に提出された59。要望書には、帰還困難区域内での復興拠点整備等に関する措置、官民合同チームの体制強化、福島イノベーション・コースト構想の更なる推進、避難地域12市町村のインフラ整備や福島県産農林水産物等の風評払拭の措置等が盛り込まれた。これらを反映した「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」が12月20日に閣議決定された60。翌平成29年1月28日に開催された第14回原子力災害からの福島復興再生協議会には、復興庁から、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案が提示され61、翌2月10日、同法案は閣議決定、国会に提出された62。
- 59 「福島復興再生特別措置法改正に関する緊急要望」平成28年12月5日、福島県知事内堀雅雄
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/195395.pdf (令和5年7月19日閲覧) - 60 「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針について」平成28年12月20日閣議決定
- 61 「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(概要)」第14回原子力災害からの福島復興再生協議会資料、平成29年1月28日、復興庁
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/20170128_kyougikai_2shiryo2.pdf (令和5年7月19日閲覧) - 62 「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案について」平成29年2月10日閣議決定
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/20170208104011.html (令和5年7月19日閲覧)
c. 国会審議、公布・施行経緯
本法律案は、平成29年4月4日に(衆)東日本大震災復興特別委員会で提案理由説明、同月6日から質疑が開始され、同月11日に可決、附帯決議が付され、同月14日の(衆)本会議で、同案は賛成多数で可決された。同月21日に(参)東日本大震災復興特別委員会で質疑が開始され、翌5月10日に可決、附帯決議が付され、同月12日の(参)本会議で賛成多数で可決・成立、5月19日に公布され、同日施行された。
なお、附帯決議としては、将来的な帰還困難区域全ての避難指示解除の実現、特定復興再生拠点区域の整備を国の負担の下で行うことについての丁寧な説明、帰還のための生活環境整備の加速、福島イノベーション・コースト構想への総合的な支援、いじめ、偏見、差別への対策などが盛り込まれた。
国会審議においては、主に以下の点について議論がなされた。
ア) 特定復興再生拠点区域の整備について
特定復興再生拠点区域の整備について、その意義、手法、今後の整備方針についての質問に対して、今村復興大臣からは、特定復興再生拠点となる区域を設定し、特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて除染、解体事業についてもインフラ整備等と一体的に実施することで、生活環境や働く場を整え、概ね5年を目途に避難指示を解除し、特定復興再生拠点への住民の帰還や事業者の立地を促進していきたい旨の答弁があった63。
また、特定復興再生拠点区域の除染費用を、東京電力に求償するのではなく国が負担することとした理由についての質問に対して64、今村復興大臣から、帰還困難区域の復興拠点整備は復興のステージに応じた新たなまちづくりとして実施するものであることから国費で負担する旨の答弁があり、政府参考人からは、除染とインフラ整備を一体的かつ効率的に実施するものであることといった様々な事情を勘案した上で、除染特措法ではなく福島復興再生特措法に基づいて実施することとし、国費で実施する方針との答弁があった。
また、特定復興再生拠点以外の除染費用の負担者についての質問に対しては、今村復興大臣から今後の検討課題である旨の発言があり、これらの整備を国負担で行うことの国民への丁寧な説明や、特定復興再生拠点区域以外の帰還困難区域における除染費用の負担のあり方についての国民的議論が必要なことが附帯決議に盛り込まれた。
- 63 第193回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号(平成29年4月6日)今村復興大臣発言「新たな制度のもとで特定復興再生拠点となる区域を設定し、特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて除染、解体事業についてもインフラ整備等と一体的に実施し、生活環境や働く場を整え、おおむね五年を目途に避難指示を解除し、特定復興再生拠点への住民の帰還や事業者の立地を促進してまいります。」
- 64 第193回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号(平成29年4月6日)岡田克也委員(民進)発言「今回、帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域の除染費用について、東電に求償することはしない、国が負担するということになりました。その理由が、私は、少なくとも法文上は全く書かれていないし、明らかでないというふうに思うわけです。」
イ) 福島イノベーション・コースト構想に係る取組
新たに法律上に位置付けられることとなった福島イノベーション・コースト構想について、今後どのように展開していくのかとの質問に対し、経済産業副大臣から、各種プロジェクトの実現に向けて着実に取り組んでいるところであるが、今後は、拠点を核とした産業集積の実現や周辺環境の整備、地元企業と域外企業との連携によるビジネスの創出等に向け、国有施設の低廉使用や中小企業の特許取得にかかわる経費低減によりロボットなどの研究開発を促進、関係閣僚級による会議体を創設等により、同構想を強力に推進し、浜通り地域に新たな産業基盤の構築を進めていく旨の答弁があった65。こうした議論も踏まえ、同構想について、政府全体での一層の連携強化や国・県及び産学官の連携推進、地元企業の参画促進、国内外の専門家の受入れ並びに人材育成などの各種取組等を進めるとともに、国内外の産業界、学術機関等への周知や協力要請、財政上の措置を含め総合的な支援措置を講ずることが、附帯決議に盛り込まれた。
- 65 第193回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号(平成29年4月6日)根本匠議員に対する高木経済産業副大臣答弁。なお、この質疑において、次のやりとりがある。根本議員「イノベーション・コースト構想は、振り返りますと、平成26年6月に取りまとめたものであります。当初は、あくまで現地対策本部の構想にすぎなかった。実は、そのときの骨太方針を策定するとき、私が佐藤雄平知事から骨太方針に書いてもらいたいと強い要請を受けました。しかし、これは閣議決定文書ですから、実は、本文には、イノベーション・コースト構想を地域経済の将来ビジョンとして抽象的に表現して、ここで読めるという話もいたしましたが、最後は、脚注の中にイノベーション・コースト構想というのを注書きで位置づけました。」、高木副大臣「まさに当初は、現地対策本部の提案というような形で、私の前の現地対策本部長の赤羽議員が中心となってやってまいりました。それがようやくこの法律に書き込まれるまでになった。その間、今委員御指摘のように、与党の方で、骨太の方針に対してしっかりと組み込む、そういう政府・与党一体となった動きの中でこの構想ができてまいりました。」
ウ) 原子力災害により避難している福島県の児童生徒等へのいじめ防止のための対策支援
新たに、原子力災害により避難している福島県の児童生徒等へのいじめの防止のための対策支援が盛り込まれたことについて、いじめが深刻化する現状に対し把握も対策も十分ではない旨の質問があり、文部科学大臣政務官からは、各教育委員会、学校に対して、被災児童生徒に対する心のケアなど日常的に格別の配慮を行うこと、児童生徒が科学的な知識を身につけられるようにするとともに、放射線に関する教育の充実に努めることなどの対応を求めており、引き続き、福島県教育委員会とも連携をして、いじめの防止に努める旨の答弁があった66。こうしたことを踏まえ、いじめ防止のための必要な対策を速やかに講ずることが附帯決議に盛り込まれた。
- 66 第193回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号(平成29年4月11日)田野瀬文部科学大臣政務官発言「文部科学省といたしましては、各教育委員会そして学校に対して、いまだ故郷に帰れず、不安の中過ごしておられる被災児童生徒に対して、心のケアなど日常的に格別の配慮を行うこと、そして、児童生徒が放射線に関する科学的な知識を身につけるとともに、理解を深めることができるよう、放射線に関する教育の充実に努めることなどの対応を求めておるところでございます。」
d. 改正法の内容
ア) 概要・目的
帰還困難区域内の復興・再生に向けた環境整備(特定復興再生拠点区域)、被災事業者の生業の復興・再生を担う組織の体制強化(福島相双復興推進機構)、浜通り地域の新たな産業基盤の構築(福島イノベーション・コースト構想)、福島県産農林水産物等の風評払拭等に必要な措置を講ずる。
(以下、条番号や条文の内容は当時のものであり、現行法とは異なる場合がある。)。
イ) 特定復興再生拠点区域復興再生計画制度
将来にわたって居住を制限することを原則としていた帰還困難区域の一部においても、放射線量の低下している地域がみられることや、帰還への地元の要望等があることを踏まえ、将来的な帰還に向けて、帰還困難区域を含む市町村が、一定の条件を満たす区域について、インフラ整備、除染等による新たなまちづくりに取り組むための「特定復興再生拠点区域復興再生計画」制度を創設した。
具体的に、第17条の2では、市町村長が、帰還困難区域のうち避難指示を解除し帰還者等の居住を可能とすることを目指す「特定復興再生拠点区域」について、復興及び再生を推進するための計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けた場合に、除染や廃棄物の処理の国による実施、道路の新設等のインフラ事業の国による事業代行、被災事業者の事業再開や新規事業者の立地促進に必要な設備投資等に係る課税の特例、一団地の復興再生拠点整備制度等が活用できることとした。
ウ) 官民合同チームの体制強化
平成27年8月に創設した官民合同チームは、商工事業者や営農再開の支援で大きな成果を上げていたが、国職員、福島県職員、公益社団法人福島相双復興推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構職員からなる複合的な組織であり、一元的な指揮命令を図ることが難しいなどの課題もあった。このため、第48条の2及び第48条の3において「福島相双復興推進機構」を法律上に位置付け、国職員がその身分を保有したままで派遣を可能にするなどして各主体の職員を官民合同チームの中核である同機構に集約することにより、組織の一元化や、国職員の持つ知見や人脈の一層の活用を図り、その機能を強化することとした。
エ) 「福島イノベーション・コースト構想」推進の法定化
浜通り地域における「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想」を一層推進するため、構想の取組を推進する区域(福島国際研究産業都市区域)や当該取組を重点推進計画に記載し、中小企業の研究成果に係る特許料等の減免やロボットの新製品・新技術の開発促進のための国有の試験研究施設の低廉使用ができることとした。
また、「原子力災害からの福島復興再生協議会」の下に分科会を創設し、同構想を関係機関等が連携・協力して推進するための枠組みを整備した。
オ) 風評払拭への対応
福島県産農林水産物等の風評被害については、震災以降、モニタリング検査、産業界への働きかけなどの取組が進められていたが、改正時点においてもなお風評被害による県産農産物価格の低迷等が続いており、一層の対策が求められていた。このため、風評被害の払拭に向け、国が、販売等の不振に関する実態調査や、当該調査に基づく販売者等への指導・助言等の措置を講ずることを法律に位置付けた。
カ) その他
避難指示等の対象となった12市町村においては、避難指示が長期化する中で、帰還意欲の低下や、避難者の所有家屋や土地の維持管理の課題が生じており、まちづくりのための人材も十分と言えない状況にあった。そうした中、住民の帰還環境整備に向けて、ハード・ソフト面からまちづくりに寄与する「まちづくり会社」等の活動事例もみられ、こうした組織を「帰還環境整備推進法人」として法的に位置付け、帰還環境整備事業計画の作成・変更についても提案できる制度を設けた。
このほかに、原子力災害により避難している福島県の児童生徒等へのいじめ防止のために福島県の教育委員会や学校が講じる取組等に対する支援施策、帰還した地域住民の交通手段の確保のための公共交通網形成についての国の指導・助言・情報提供等の支援措置も定められた。
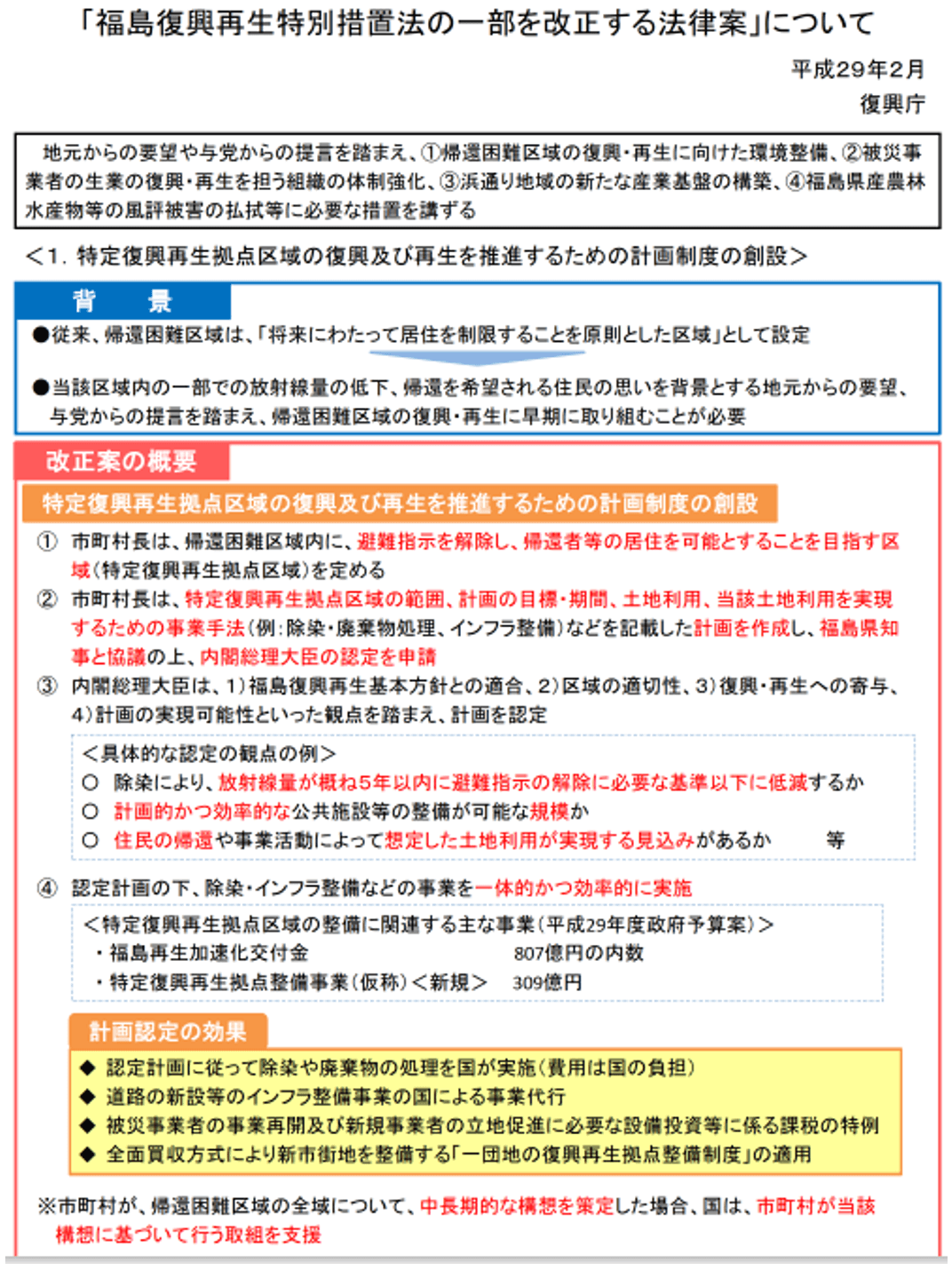
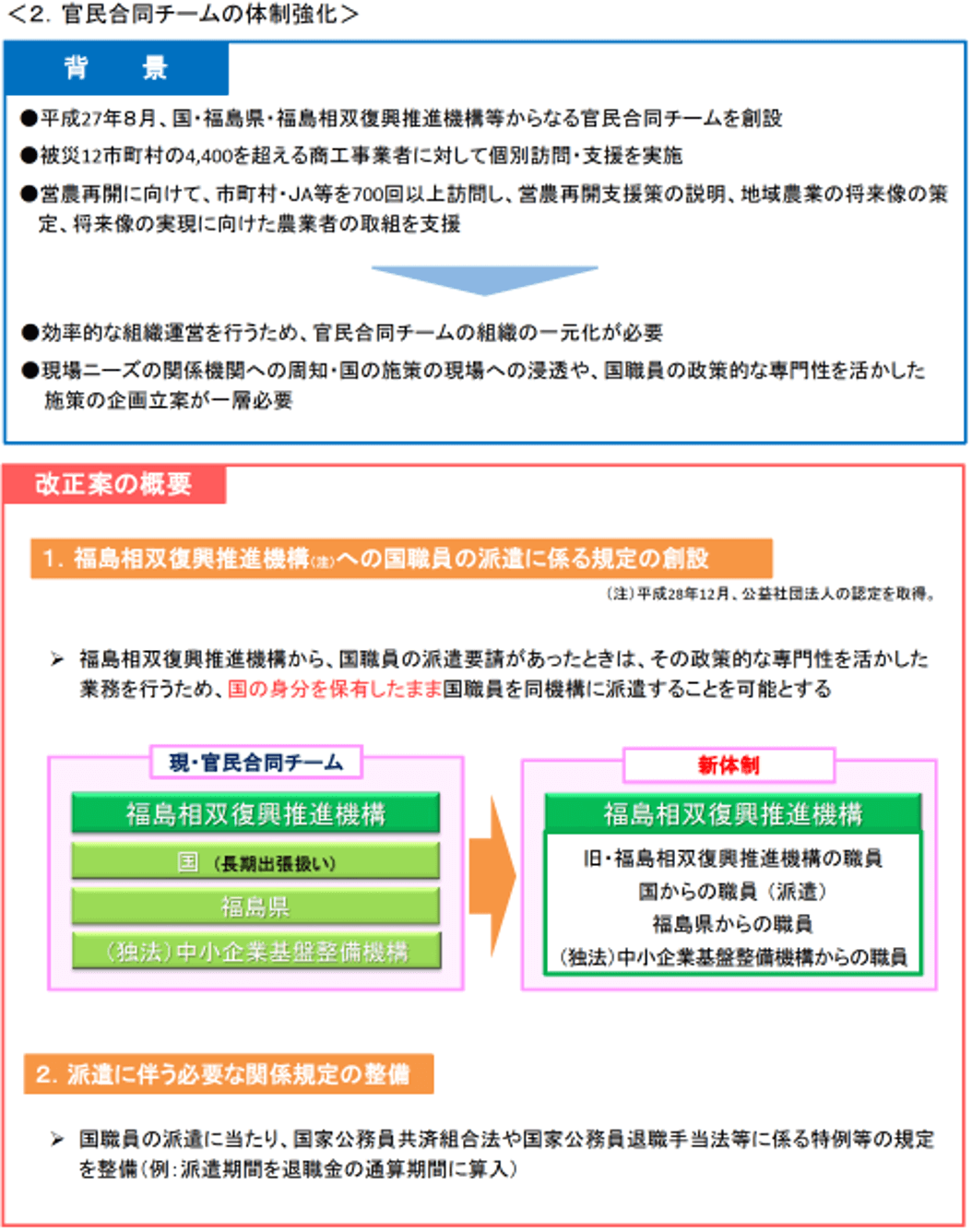
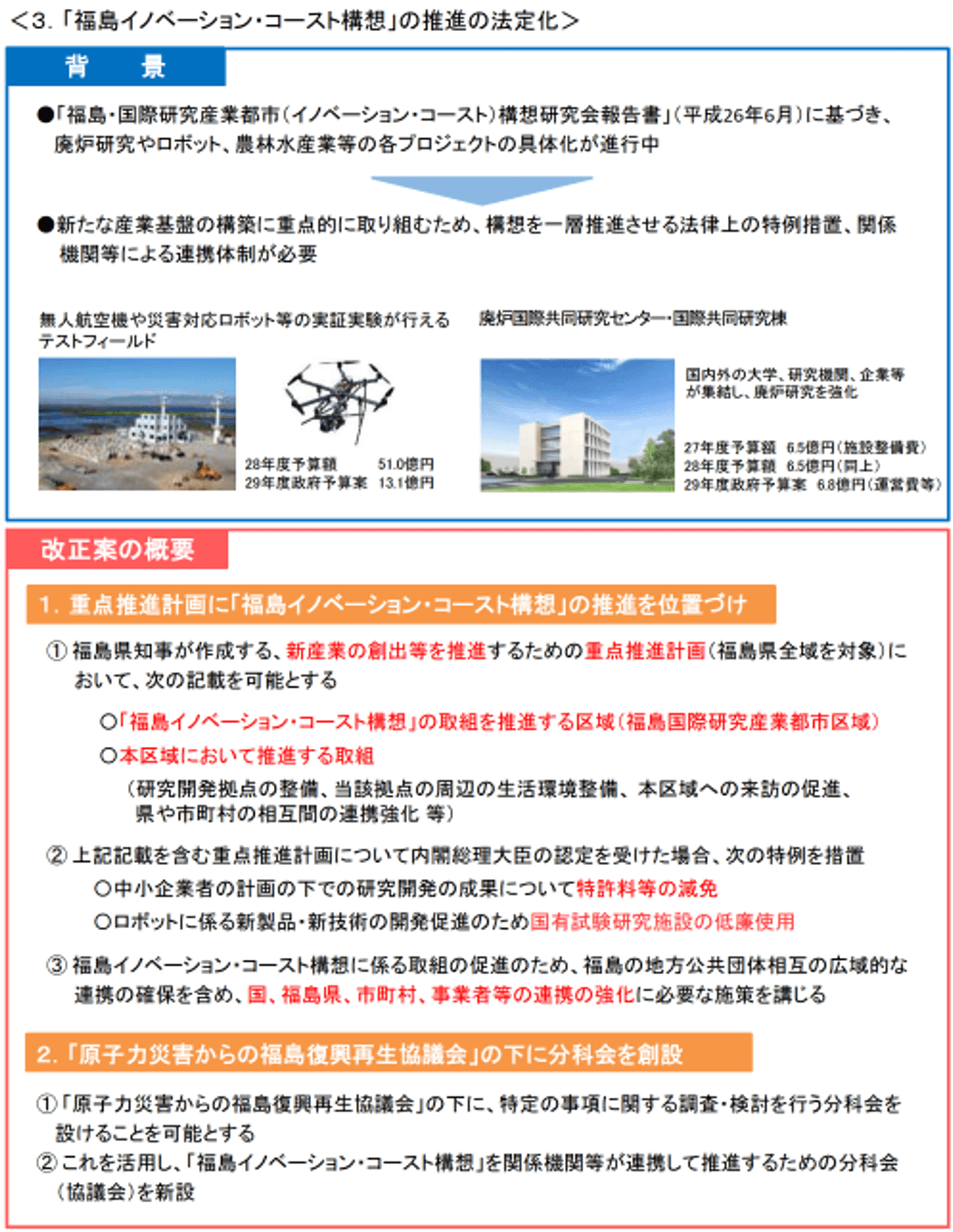
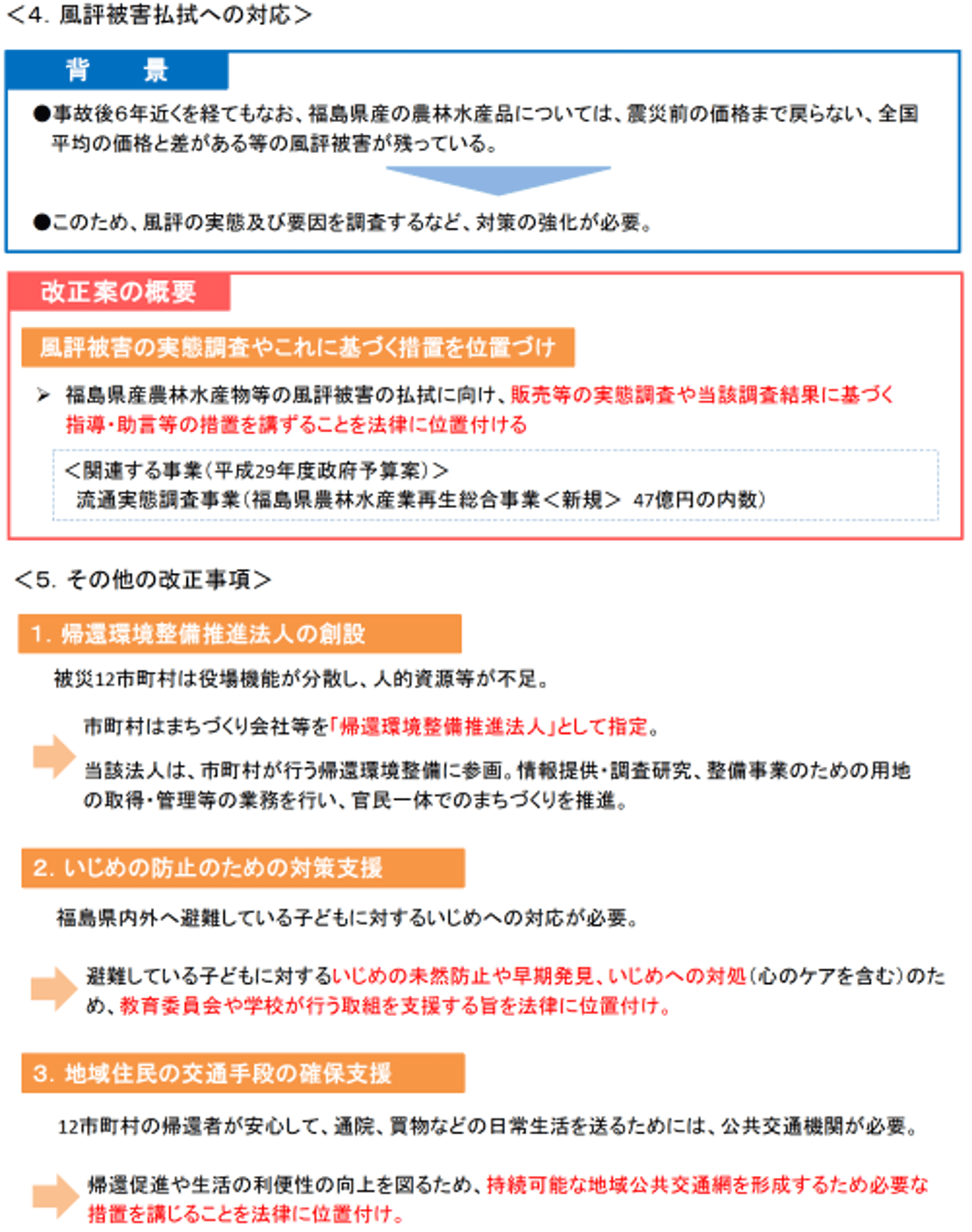
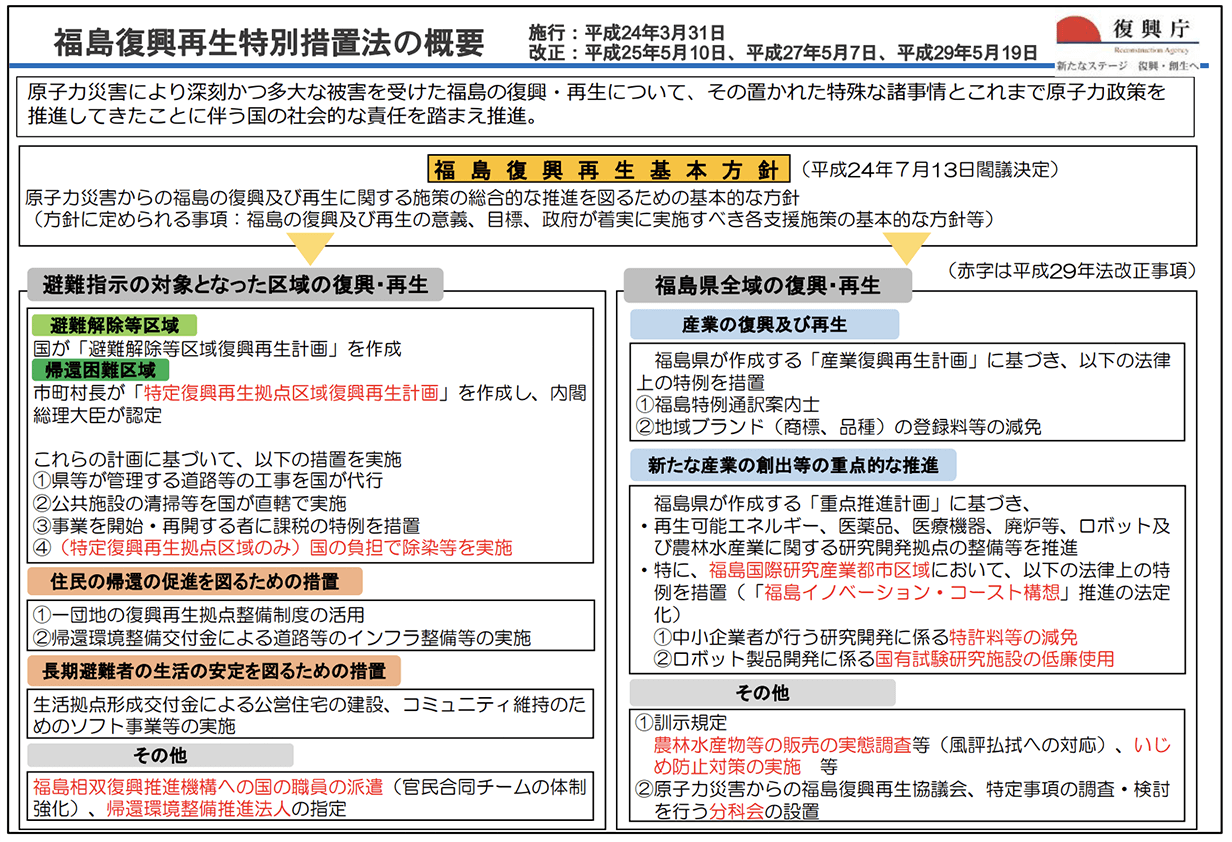
5) 令和2年改正法
a. 概要
令和2年6月12日に公布・一部施行された復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)による福島特措法の主な改正内容は以下のとおりである。
① 避難指示・解除区域の復興及び再生を推進するため、新たな住民の移住・定住の促進や交流人口・関係人口の拡大に資する施策を交付金の対象に追加するほか、農地の利用集積や6次産業化施設の整備を促進するための特例措置を設けることとした。
② 福島イノベーション・コースト構想の推進を軸とした産業集積を促進するため、同構想の推進に係る課税の特例の規定を設けるとともに、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構の要請に応じ、国の職員をその身分を保有したまま当該機構に派遣できることとした。
③ 風評被害が事業者の経営に及ぼす影響への対処に係る課税の特例の規定を設けることとするほか、政策課題ごとの3つの法定計画を1つに統合し、福島県が地域の実情を踏まえて福島復興再生計画を作成し、これを内閣総理大臣が認定する制度を設けることとした。
b. 改正の背景・経緯
被災から約10年が経過し、平成31年4月には、東京電力福島第一原子力発電所の立地する大熊町の一部地域で避難指示が解除され、また、平成29年の福島特措法改正により帰還困難区域に設けることが可能となった「特定復興再生拠点区域」においても、避難指示解除に向け、各町村で特定復興再生拠点区域復興再生計画が作成され、除染やインフラ整備等の事業が進められていた。また、浜通りにおいては、「福島イノベーション・コースト構想」に基づき、新産業の創出等に向けた取組が進められた。
一方で、避難解除等区域を区域内に持つ12市町村においては、住民の帰還が十分に進んでおらず、県内の産業の復興及び再生も依然として大きな課題となっていた。
「東日本大震災 復興加速化のための第8次提言」(令和元年8月5日 自由民主党・公明党)においても、移住の促進や関係・交流人口の拡大等による新たな活力の呼び込み、福島イノベーション・コースト構想の推進を基軸とした、中長期視点での地域再生や産業発展に向けた施策展開等が求められた。
こうした状況の中、福島県は令和元年11月7日、「ふくしまの復興・創生に向けた緊急要望」で、移住の促進、交流人口の拡大等の新たな活力の呼び込みや、営農再開の拡大に向けた農地の利用集積や6次化施設の整備促進等による避難解除区域等の復興・再生の加速化、福島イノベーション・コースト構想推進機構への国職員派遣のための制度整備等による構想の更なる推進、海外も含めた風評被害対策、さらには、これらを支える計画体系の見直しなどの措置を、福島特措法に盛り込むよう国に要望した。
一方、国は「東日本大震災からの復興の基本方針」に加え、新たに「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」を令和元年12月20日に閣議決定したが、その中では福島特措法に関して、移住の促進や交流・関係人口の拡大等の新たな活力を呼び込む施策の強化、営農再開加速、福島イノベーション・コースト構想の推進、風評払拭などの対応が盛り込まれた。さらに同基本方針では、「国が策定する基本方針の下、広域地方公共団体である福島県が地域の実情を踏まえて計画を作成することとするなど、計画制度の見直しを行う。」ことも示され、福島県知事が原子力災害からの復興に関する総合的な計画(福島復興再生計画)を作成し、これに基づき復興の取組を加速する方針が示された。
この基本方針の見直しを受けて、翌令和2年3月3日に、復興庁設置法、東日本大震災復興特別区域法等とあわせて福島特措法を改正する「復興庁設置法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出された67。
- 67 「復興庁設置法等の一部を改正する法律案の閣議決定」令和2年3月3日
https://www.reconstruction.go.jp/topics/20200303085910.html (令和5年7月14日閲覧)
c. 国会審議、公布・施行経緯
法律案は、令和2年5月14日に(衆)東日本大震災復興特別委員会で提案理由説明、同月19日より質疑が行われ、21日に可決、附帯決議が付され、翌22日に(衆)本会議で賛成多数で可決された。同月27日には、(参)東日本大震災復興特別委員会における提案理由説明、29日より議論が開始され、6月3日に賛成多数で可決、附帯決議が付され、同月5日には(参)本会議で可決、成立、6月12日に公布され、同日施行(一部)された。
なお、附帯決議のうち、福島特措法に関連する事項としては、特定復興再生拠点区域外における避難指示解除のための具体的な方針の明示、国際教育研究拠点の推進と福島ロボットテストフィールド等の拠点の活用などが盛り込まれた。
国会審議においては、主に以下の点について議論がなされた。
ア) 帰還困難区域の特定復興再生拠点外についての今後の対応
復興・創生期間後の対応として、帰還困難区域の特定復興再生拠点外についての対応が重要であり、これについては一律の避難指示解除基準を適用するのではなく、土地利用に応じた解除、類型を考えるという発想が大切なのではないかという質問68に対して、政府参考人から特定復興再生拠点区域外については、令和元年12月に閣議決定された「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」においても、地域の実情や、土地活用の意向や動向、地方公共団体の要望等を踏まえ、避難指示の解除に向けた今後の政策の方向性について検討を進めることとされており、各町村の具体的な要望を踏まえながら方向性を検討していきたい旨答弁があった。
- 68 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号(令和2年5月19日)根本匠委員(自)発言「帰還困難区域の特定復興再生拠点外について、一律の避難指示解除基準を適用するのではなく、土地利用に応じた解除、類型を考えるという発想が大切なのではないかと思います」
イ) 営農再開の支援
被災12市町村における営農再開に向け、農地の利用集積、6次産業化施設の整備促進のための計画制度等が盛り込まれたことを受け、その着実な実施と国の支援をお願いしたいという意見に対して、伊東農林水産副大臣から、農水省では4月から32名体制で12市町村に対して人的支援を行っていることに加えて、本改正で営農再開の加速化に関する特例を規定し、4月から派遣職員が核となって、福島県、JA、官民合同チーム等と一体となって、帰還者や移住者等による担い手づくり、集約化による営農基盤の確立に向けて全力で取り組む旨答弁があった69。
- 69 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号(令和2年5月21日)伊東農林水産副大臣発言「福島復興再生特別措置法の改正におきましては、営農再開の加速化に関する特例を規定するとともに、四月から、派遣職員が核となりまして、福島県あるいはJAまた官民合同チーム等と一体となって、この十二市町村でそれぞれ異なるニーズがあるものでありますから、現場のニーズをしっかり踏まえながら、帰還者やあるいは移住者等の促進による担い手づくり、集約化による営農基盤の確立に向けて全力で取り組んでまいりたいと思います。」
ウ) 風評被害対策としての課税の特例
農林水産業、観光業などでの風評被害の重大さに鑑み、引き続きの支援の継続と、県内全域を対象とした新しい税制の検討が必要ではないかとの質問に対し、菅家復興副大臣から、復興特区法の対象地域の見直しにより、復興特区税制の対象地域を沿岸部に重点化するに当たり、福島県については、農林水産業や観光業等の風評被害による深刻な影響が残る業種を踏まえて、県内全域を対象とする方向で課税の特例を検討していきたい旨の答弁があった70。
- 70 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号(令和2年5月19日)菅家復興副大臣発言「復興庁としては、今般、復興特区法の対象地域の見直しにより、復興特区税制の対象地域を沿岸部に重点化することに当たり、福島県については、農林水産業や観光業等の風評被害による深刻な影響が残る業種を踏まえて、県内全域を対象とする方向で課税の特例を検討してまいりたい、このように考えております。」
d. 改正法の内容
ア) 概要・目的
復興・創生期間後に生じる新たな課題や多様なニーズに対応し、本格的な復興・再生に向けた取組を加速するため、避難指示・解除区域の復興・再生の推進、福島イノベーション・コースト構想の推進を軸とした産業集積促進、風評被害への対応を進めるとともに、これまでの福島県の復興再生に関わる3つの計画を統合し、県が主体となって福島復興再生計画を作成する制度を導入する。
イ) 福島復興再生計画への統合
第7条では、福島の復興及び再生に関する従来の政策課題ごとの3つの法定計画(①国が作成する「避難解除等区域復興再生計画」、②福島県知事が作成する「産業復興再生計画」、③福島県知事が作成する「重点推進計画」)を統合し、国が定める福島復興再生基本方針に即して、福島県知事が「福島復興再生計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとした。これに伴い、それぞれの計画に位置付けられた特例措置についても統合された。
福島特措法の制定当時は、避難解除等区域は、地域コミュニティや産業基盤の断絶が生じ、福島県又は市町村の自助努力だけでは当該区域の復興及び再生は著しく困難な状況にあったため、国(内閣総理大臣)が計画の策定等も行うこととしていた。しかしながら、復興期間10年間の終了を見据える中、居住制限区域及び避難指示解除準備区域とされた区域においても避難指示の解除が進み、また、帰還困難区域においても特定復興再生拠点区域が設けられ除染やインフラ整備等の事業が進められる等、同区域の状況は福島特措法制定時から大きく変化してきており、従来内閣総理大臣が作成してきた避難解除等区域復興再生計画についても、福島県知事が中長期的かつ広域的な視点から立案が可能な状況となった。
また、福島県知事が避難解除等区域の計画を作成することは、避難解除等区域の復興の進捗状況に差異がある中、現地の実情を踏まえ、地元の視点でのきめ細かな対応が可能となるという点で大きな意義がある。
さらに、避難解除等区域復興再生計画についても福島県知事が作成することとすると、同計画の記載事項には産業の復興・再生が含まれており、産業復興再生計画及び重点推進計画との間で、記載事項の重複が生じることから、政策課題への対応を効果的かつ効率的に進める上で、これらの3計画を一体的に取扱う必要が生じた。
以上の状況の変化を踏まえ、3計画の作成主体がいずれも福島県知事となるこの機会を捉え、これらを統合し、福島復興再生計画とすることとしたものである。
ウ) 営農再開の促進のための効率的な農地利用の推進
第17条の19から第17条の33まで等では、営農再開の加速化のために、農地の利用集積の促進や、6次産業化施設整備の促進に向けた農地転用の促進措置、農業委員会の帰還が進まない場合の、農業委員会事務を市町村が行える特例措置等を設けた。
エ) 帰還環境整備交付金制度の見直し
第33条では、地域の活力向上のために交流・関係人口の拡大や地域外からの移住の促進を図るため、住民の帰還環境整備のための交付金の対象に、移住・定住促進、交流・関係人口拡大に資する施策を追加し、「帰還・移住等環境整備交付金」に名称変更した。
オ) 国内外における福島の風評被害への対策のための措置
第74条から第75条の5まででは、福島県産食品の消費停滞や外国人宿泊者数の低迷など、風評被害に悩む農林水産業や観光業等を対象に、福島県内全域において、一定の要件の下で、設備投資や雇用に関する課税の特例等を規定した。また、海外における輸入規制の撤廃・緩和に向けた外国との交渉等の措置や、福島県産農林水産物等に対する紹介・宣伝等の措置などを国が講ずる旨の規定を追加した。
カ) 福島イノベーション・コースト構想の推進を軸とした産業集積の促進
第84条から第85条の8まででは、福島イノベーション・コースト構想における重点分野(廃炉、ロボット、農林水産業等)の取組を支援するため、新産業創出等推進事業促進区域(※1)内において、一定の要件の下で、設備投資や雇用に関する課税の特例等を規定した。
また、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構へ国職員がその身分を保有したまま当該機構に派遣できるとする規定を整備し、同機構の機能強化を図ることとした。
※1 福島国際研究産業都市区域(※2)内の区域であって、新産業創出等推進事業(※3)の実施の促進が、産業集積の形成等を図る上で特に有効であると認められる区域。
※2 原子力災害による被害が著しい区域であって、福島イノベーション・コースト構想における重点分野に関する先端的な研究開発を行う拠点の整備等により産業集積の形成等を図るべき区域
※3 福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成等を図る上で中核となる、新たな産業の創出等に資する事業
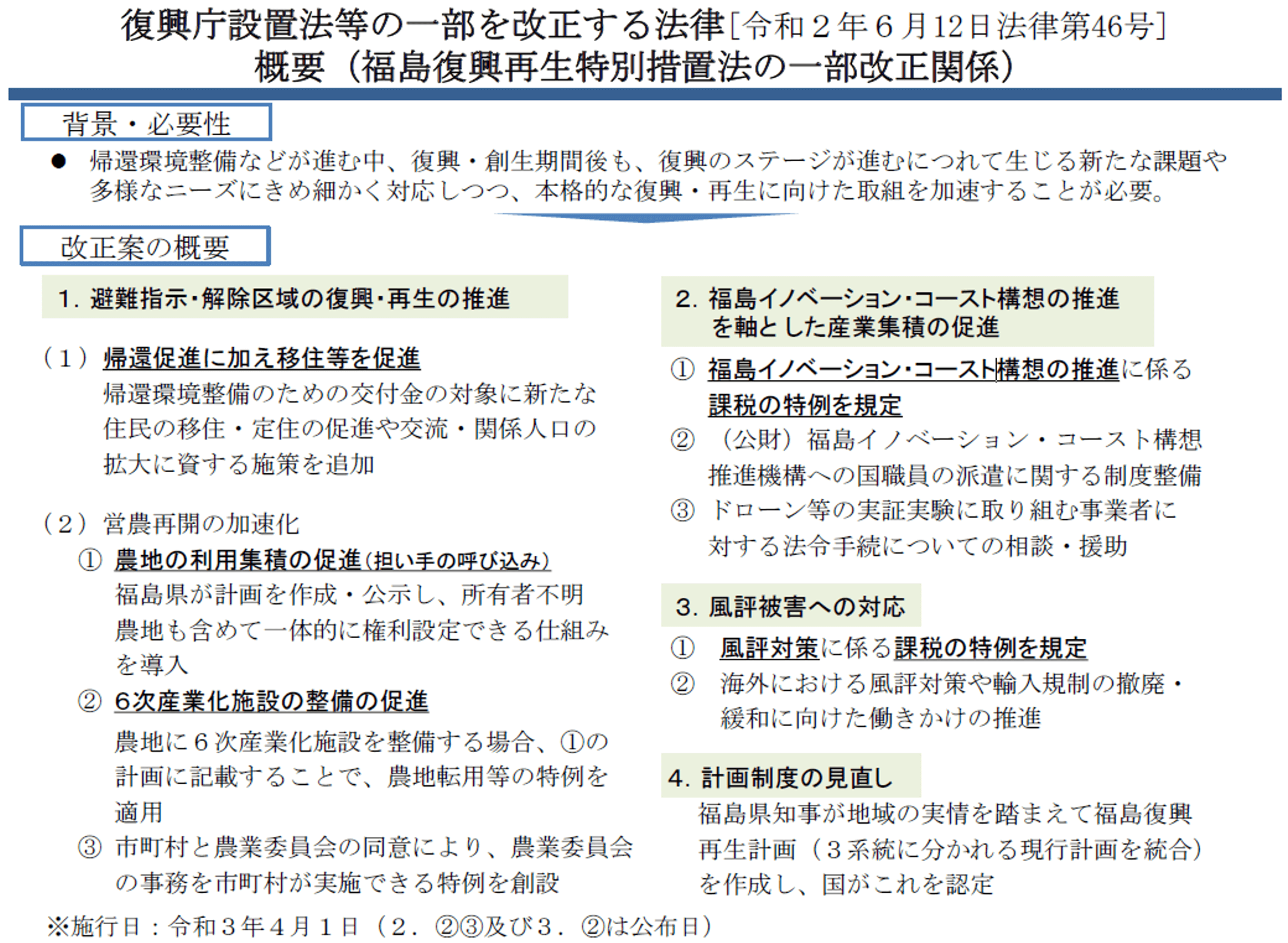
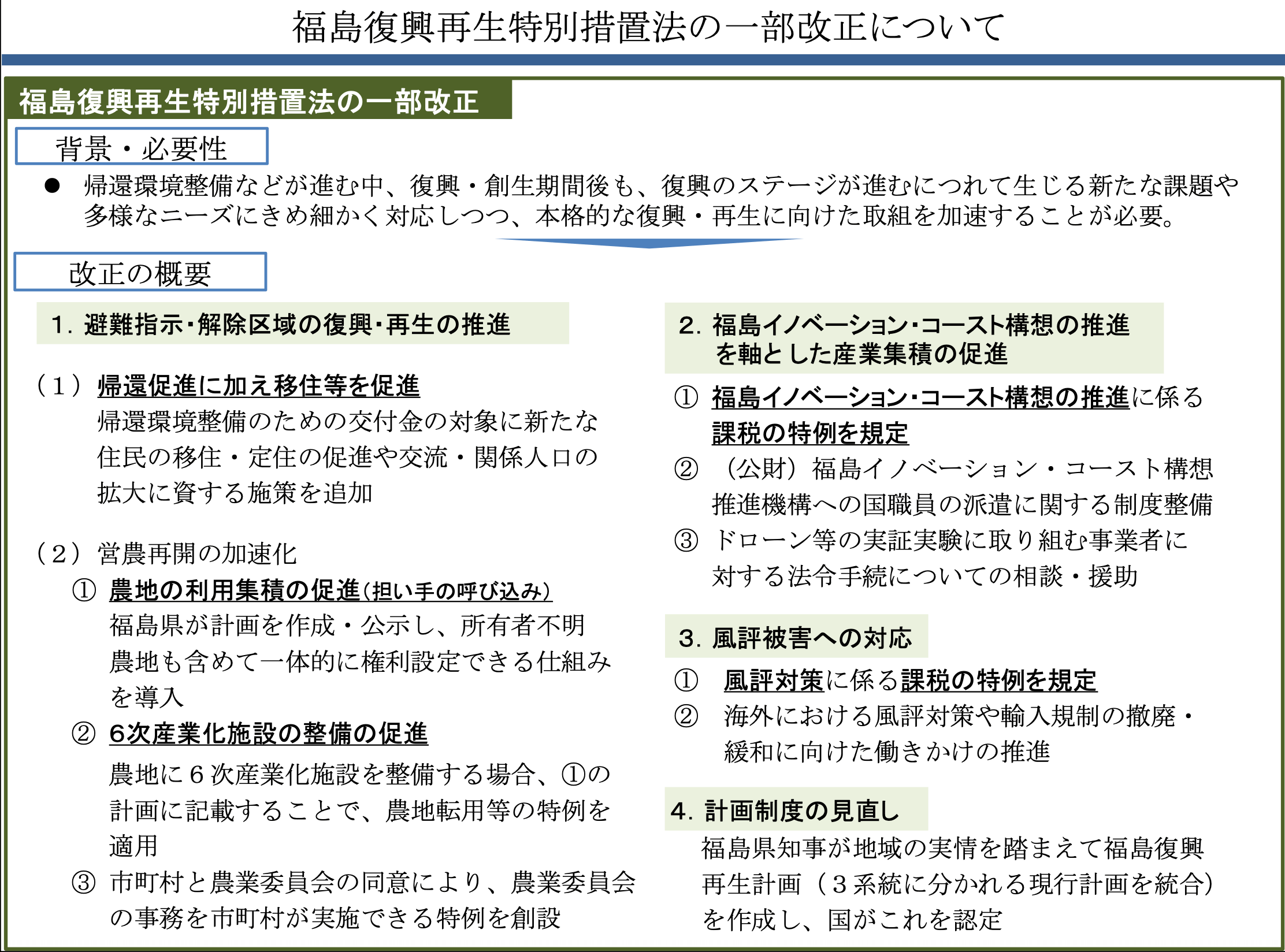
(5) 適用実績
※ 福島特措法に基づく個別施策の適用実績については、7章の各節を参照。
1) 福島復興再生基本方針
福島特措法第5条に基づき、平成24年7月に原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「福島復興再生基本方針」という。)が策定され、避難解除等区域等と福島全域それぞれについて、福島復興再生の方針や具体方策が示された。
平成29年には、同年の福島特措法の改正と、「東日本大震災 復興加速化のための第6次提言」(平成28年8月24日自由民主党・公明党)及び「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」(平成28年12月20日閣議決定)等の内容を反映した改訂が行われ、特定復興再生拠点区域復興再生計画や、官民合同チームの強化、風評対策や福島イノベーション・コーストの推進等が盛り込まれた71。
令和3年には、令和2年6月の福島特措法の改正(令和3年4月全面施行)を受け、移住・定住促進や農地利用集積の促進、新たな風評対策や福島イノベーション・コースト構想の更なる推進に向けた施策が盛り込まれ、第2復興・創生期間において、引き続き国が前面に立って取り組む方針が示された72。
策定及び改定の経緯は、以下の通り。
- 71 「福島復興再生基本方針の概要」平成29年6月30日、復興庁
https://www.reconstruction.go.jp/topics/20170629151224.html (令和5年7月19日閲覧) - 72 「福島復興再生基本方針の概要」令和3年3月26日、復興庁
https://www.reconstruction.go.jp/topics/20210325191726.html (令和5年7月19日閲覧)
| 策定・改定日 | 項目 | |
| 平成24年7月13日 | 福島復興再生基本方針 | 平成24年3月の福島特措法当初法制定を受けて策定 |
| 平成29年6月30日 | 福島復興再生基本方針(改定) | 平成29年5月の福島特措法改正等を受けて策定 |
| 令和3年3月26日 | 福島復興再生基本方針(改定) | 令和2年6月の福島特措法改正等を受けて策定 |
| 令和4年8月26日 | 福島復興再生基本方針(改定) | 令和4年6月の福島特措法改正等を受けて策定 |
2) 各種関連計画の策定
先述のとおり、福島特措法の中で福島県知事等が作成する各種計画が規定された。各計画の策定状況は以下のとおりである。
a)内閣総理大臣が策定する計画
・ 避難解除等区域復興再生計画(内閣総理大臣)(平成25年3月19日決定、平成26年6月20日改定)
b)福島県が策定する計画
・ 産業復興再生計画(福島県)(平成25年5月28日認定)
・ 重点推進計画(福島県)(平成25年4月26日認定、平成30年4月25日認定、平成31年4月1日軽微な変更、令和2年5月1日変更認定)
・ 福島復興再生計画(福島県)(令和3年4月9日認定、令和4年12月26日変更認定)
・ 企業立地促進計画(福島県)(平成25年6月10日策定、平成25年8月8日、平成27年10月30日、平成29年9月15日、令和3年4月20日変更)
c)市町村、事業者等が策定する計画
・ 生活拠点形成事業計画(県、各市町村)(令和4年12月時点で県及び15市町村の計画を策定)
・ 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(認定事業者)(平成26年1月より360計画を認定(令和4年9月30日時点))
・ 帰還環境整備事業計画(帰還・移住等環境整備事業計画)(県、市町村等)(令和4年12月時点で県及び45市町村等の計画を策定)
・ 特定復興再生拠点区域復興再生計画(各市町村)(平成29年9月~平成30年5月に6町村(双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村)の計画を策定)
| 項目 | 策定・改定日 | |
| 避難解除等区域復興再生計画 (内閣総理大臣) |
平成25年3月19日 内閣総理大臣決定 |
平成24年3月の福島特措法当初法制定を受けて策定 |
| 同(改定) | 平成26年6月20日 改定 |
避難指示解除の動き、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」(福島復興指針 平成25年12月閣議決定)等を受けて改訂 |
| 産業復興再生計画(福島県) | 平成25年5月28日 内閣総理大臣認定 |
平成24年3月の福島特措法当初法制定を受けて策定 |
| 重点推進計画(福島県) | 平成25年4月26日 内閣総理大臣認定 |
平成24年3月の福島特措法当初法制定を受けて策定 |
| 重点推進計画(福島県) | 平成30年4月25日 内閣総理大臣認定 平成31年4月1日 軽微な変更 |
平成29年5月の福島特措法改正、平成 29 年6月の福島復興再生基本方針改定等を受けて策定 |
| 同(変更) | 令和2年5月1日 内閣総理大臣認定 |
令和元年12月9日の「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」策定(復興庁、経済産業省、福島県)を受けて変更 |
| 福島復興再生計画(福島県) | 令和3年4月9日 内閣総理大臣認定 |
令和2年6月の福島特措法改正等を受けて策定 |
| 同(変更) | 令和4年12月26日 内閣総理大臣認定 |
令和4年6月の福島特措法改正等を受けて策定 |
| 企業立地促進計画(福島県) | 平成25年6月10日策定 平成25年8月8日変更 平成27年10月30日変更 平成29年9月15日変更 令和3年4月20日変更 |
平成25年5月の福島特措法改正等を受けて策定 |
| 生活拠点形成事業計画(県、各市町村) | 令和4年12月時点で県及び15市町村の計画を策定 | 平成25年5月の福島特措法改正等で計画を位置付け |
| 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(認定事業者) | 平成26年1月より360計画を認定(令和4年9月30日時点)73 | 平成25年5月の福島特措法改正等で計画を位置付け |
| 帰還環境整備事業計画(帰還・移住等環境整備事業計画)(県、市町村等) | 令和4年12月時点で県及び45市町村等の計画を策定 | 平成27年5月の福島特措法改正等で計画を位置付け |
| 特定復興再生拠点区域復興再生計画(各市町村) | 平成29年9月~平成30年5月に6町村の計画を策定 | 平成29年5月の福島特措法改正で計画を位置付け |
出所)福島県福島復興再生特別措置法ウェブサイトより作成
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-tokusoho1002.html (令和5年7月15日閲覧)
- 73 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定状況の概要(公表)(令和4年9月30日時点 福島県)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-tokusoho1065.html (令和5年7月15日閲覧)
3) 福島復興再生協議会
先述のとおり、福島特措法当初法の第70条において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進に関し必要な協議を行うための組織として、「原子力災害からの福島復興再生協議会」が位置付けられた。これにより、従来から開催されていた、国と福島県の関係者からなる「原子力災害からの福島復興再生協議会」が法律上の協議会として位置付けられることとなった。
令和4年度時点で、国側構成員としては復興大臣(議長)と、総務、農林水産、経済産業、環境、復興の各大臣ないし副大臣、県側構成員としては県知事、県議会議長、市長会代表、町村会等代表、いわき市長、福島県商工会議所連合会長、福島県農業協同組合中央会長が参加し、事務局を復興庁及び福島県が務めている。
| 項目 | 開催日 | 備考(主な議論テーマ等) |
| 第1回 | 平成23年8月27日 | 東日本大震災からの復興の基本方針、福島県復興ビジョン |
| 第1回幹事会 | 平成23年9月13日 | 原子力災害からの福島再生特別法(仮称) |
| 第2回 | 平成23年10月17日 | 福島県要望の基金への対応 |
| 第2回幹事会 | 平成23年11月16日 | 東日本大震災復興特別区域法概要 |
| 第3回 | 平成24年1月8日 | 福島県復興計画(第一次) |
| 第4回 | 平成24年2月4日 | 福島特措法について |
| 第5回(法定第1回協議会) | 平成24年4月22日 | 福島の再生に向けた今後の課題 |
| 第3回幹事会 | 平成24年6月1日 | 福島復興再生基本方針(素案・調整中)について |
| 第6回(法定第2回協議会) | 平成24年7月1日 | 福島復興再生基本方針(案)について |
| 第4回幹事会 | 平成25年2月14日 | 福島対応体制、復興・再生に向けた予算、福島特措法の一部改正について |
| 第7回(法定第3回協議会) | 平成25年2月17日 | 福島対応体制の抜本強化について |
| 第8回(法定第4回協議会) | 平成25年8月11日 | 平成26年度国の予算に向けて |
| 第9回(法定第5回協議会) | 平成26年8月9日 | 平成27年度国の予算に向けて |
| 第10回(法定第6回協議会) | 平成27年2月1日 | 福島特措法の一部改正,平成26年度補正予算案・平成27年度予算案について |
| 第11回(法定第7回協議会) | 平成27年8月8日 | 平成28年度国の予算に向けて |
| 第12回(法定第8回協議会) | 平成28年3月27日 | 「復興・創生期間」の福島復興再生に向けて |
| 第13回(法定第9回協議会) | 平成28年7月31日 | 平成29年度ふくしま復興・創生に向けて |
| 第14回(法定第10回協議会) | 平成29年1月28日 | 福島特措法の一部改正について |
| 第15回(法定第11回協議会) | 平成29年8月6日 | 福島イノベーション・コースト構想推進分科会について |
| 第16回(法定第12回協議会) | 平成30年2月18日 | 福島復興・再生に向けた取組状況 |
| 第17回(法定第13回協議会) | 平成30年8月9日 | 平成31年度ふくしま復興・創生に向けて |
| 第18回(法定第14回協議会) | 平成31年3月30日 | 福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真(骨子案)について |
| 第19回(法定第15回協議会) | 令和元年8月8日 | 令和2年度ふくしま復興・創生に向けて |
| 第20回(法定第16回協議会) | 令和2年2月24日 | 復興庁設置法等の一部を改正する法律案について |
| 第21回(法定第17回協議会) | 令和2年8月30日 | 令和3年度ふくしま復興・創生に向けて |
| 第22回(法定第18回協議会) | 令和3年2月21日 | 福島復興・再生に向けた取組状況 |
| 第23回(法定第19回協議会) | 令和3年8月5日 | 令和4年度ふくしま復興・創生に向けて |
| 第24回(法定第20回協議会) | 令和4年2月12日 | 福島復興・再生に向けた取組状況 |
| 第25回(法定第21回協議会) | 令和4年8月27日 | 令和5年度ふくしま復興・創生に向けて |
https://www.reconstruction.go.jp/topics/000818.html (令和5年7月15日閲覧)
(6) 評価・課題
原子力災害からの復興・再生は中長期的な対応が必要であり、現在においても現在進行形で各種取組が進んでいるところである。自然災害だけでなく原子力災害にも直面しているという特殊な状況を踏まえ、福島県のみに適用される法律として制定された本法は、福島県としても、同県の復興・再生の要となる枠組みであると評価している。
「東日本大震災の復興施策の総括」(令和元年10月23日東日本大震災の復興施策総括に関するワーキンググループ)Ⅲ2.(2)④「今後の大規模災害に向けた教訓」によれば、「過去に例のない規模の原子力災害という特殊性を踏まえ、当該原子力災害からの復興に特化した新法を制定した上で、復興の進捗状況に応じた法改正を行い、政府としての基本方針や制度的基盤を整備することで、福島の復興・再生に着実に貢献してきたといえる。今後起こり得る大規模災害に対しては、災害の規模や態様、被害の状況や地域特性に応じて制度を検討することが必要である」とされている。
5. 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質が広く拡散し、当該物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと等のため、避難指示の対象とならなかった地域の住民を含めて、被災者は健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、これらの被災者に対する各種支援、特に放射線への感受性が高いと言われる子どもへの配慮が求められた。
政府からは、避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置等を内容とする「福島復興再生特別措置法」(平成24年法律第25号。以下「福島特措法」という。)の法律案が国会に提出されていた。しかし、これは地域の復興再生に重点を置いたものであり、原子力事故による被災者の生活支援を推進するための法整備が別途必要との指摘もなされていた74。
このような状況において、特に子どもの医療費の免除等に係る検討を進めてきた自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会、公明党、みんなの党、日本共産党、社会民主党・護憲連合及び新党改革からは、平成24年3月14日に「平成二十三年東京電力原子力事故による被害からの子どもの保護の推進に関する法律案」(以下「野党案」という。)が参議院に提出された。
野党案においては、原子力事故による被害から子どもを保護するための施策に関して基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、政府が基本計画を策定し、国は地域ごとの放射線量の算出、子ども及び妊婦の被ばく放射線量の評価、生涯にわたる定期的な健康診断、医療費に係る負担の減免、学校給食等における放射性物質の検査、子どもの学習等支援や放射線に関する教育及び啓発等の措置を講ずることとされた。
また、民主党からは、いわゆる「チェルノブイリ法75」を参考として、被災者が居住・移動・帰還について自らの意思で選択することを支援する施策を幅広く講ずるために「東京電力原子力事故の被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律案」(以下「与党案」という。)が同月28日に参議院に提出された。
与党案においては、放射線量が政府による避難指示の基準(年間積算線量20mSv(ミリシーベルト))を下回っているが、一定の基準以上である地域(以下「支援対象地域」という。)に居住し、または居住していた者等の生活支援等に関する施策について、基本理念や国の責務を定め、国は汚染状況の調査、移動の支援・住宅の確保・就業の支援等に関する施策、健康への影響に関する調査や医療の提供等の措置を講ずることとされた。
野党案及び与党案は、いずれも被災者の生活支援を図るという主旨から立案されたものであり、平成24年3月29日の(参)東日本大震災復興特別委員会において、それぞれの発議者から趣旨説明がなされた後、これらを統合するための協議がなされることとなった。その結果、同年6月14日の同委員会において、両法律案は撤回されて、与野党の合意に基づく「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律案」草案が発議され、同草案が全会一致により委員会提出法律案となった。
本法律案においては、子ども及び妊婦への特別な配慮がなされるべきという野党案の理念を重視しつつ、被災者が居住・移動・帰還について自らの意思で選択することを支援するために必要な施策を講ずることとされた。具体的には、政府が基本方針を定め、国は発災時に支援対象地域に居住等していた被災者のため、医療の確保、子どもの就学等の援助、食の安全及び安心の確保、住宅確保や就業支援に関する施策、放射線による健康への影響に関する調査や医療費の減免等に関する施策を講ずることとされた。
また、野党案及び与党案にはなかった家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援等が追加されるとともに、医療費の減免を受けることができる子どもや妊婦の疾病が放射線に起因するものか否かについての立証責任は国にあるものとされた76。
- 74 例えば、日本弁護士連合会は「福島の復興再生と福島原発事故被害者の援護のための特別立法制定に関する意見書」(平成24年2月16日)において、福島特措法案は「福島地域の経済的な復興と再生を主たる目的とし、個人の生活再建のための援護措置は盛り込まれていない」としている。
また、後に本法律案の草案が審議された平成24年6月14日(参)東日本大震災復興特別委員会においては、発議者の増子輝彦議員から「福島復興再生特別措置法が福島という地域の復興再生に重点を置いたものとなっております。これに対して、この草案は(中略)被災者の生活支援等に関する施策の基本となる事項を定めたもので(中略)観点を異にいたしており、対象を福島の住民に限定していないことからも、福島復興再生特別措置法とは別に制定する必要がある」旨説明されている。 - 75 1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故の被害者支援について、1991年にウクライナ共和国等で定められた法律。原発事故による汚染地域を放射線量に基づき、隔離地域、退去地域、移住権付居住地域等に区分し、一定の要件に該当する当該地域の住民が自主的に移住する際の住宅支援をはじめ、医療や経済的な支援を受ける権利等を定めている。
- 76 第180回国会衆議院東日本大震災復興特別委員会会議録(以下「第180回国会(衆)復興特会議録」という。)第7号6頁(平成24年6月19日)等。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
上述のとおり、平成24年3月14日に自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会、公明党、みんなの党、日本共産党、社会民主党・護憲連合及び新党改革の共同提案による野党案が参議院に提出された。また、同月28日には民主党から与党案が参議院に提出され、翌29日の(参)東日本大震災復興特別委員会において、福島特措法案の採決後、野党案及び与党案それぞれの趣旨説明がなされた。
その後、6月14日の同委員会において、両法律案は撤回され、与野党の合意に基づく「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律案」草案が発議され、同草案が全会一致により委員会提出法律案となった。なお、採決後、平野達男復興大臣から「本法律案が成立した後は、これに基づき、子どもに特に配慮して行う被災者の生活支援等に関する施策の推進に各府省一体となって最善の努力をしてまいる所存」である旨発言がなされた。
本法律案は、6月15日に(参)本会議において全会一致で可決、同月19日の(衆)東日本大震災復興特別委員会でも可決され、21日の(衆)本会議において全会一致で可決・成立した。
本法律は、6月27日に公布・施行された。
国会審議においては、主に以下の点について議論がなされた。
1) 国の責務
国の責務が規定された趣旨について質問がなされ、発議者から、原子力災害によって国民の生命、身体及び財産に危険が生じる場合には、国にはそれらを保護する使命がある。また、国がこれまで原子力政策を推進してきたことから、今回の事故について社会的な責任を負っていると考えられる。これらの2つの要素が相まって、被災者の支援については、国として責務を負っていることを明確にしたものである旨答弁された。
なお、当該規定によって、東京電力の第一義的責任がいささかも軽減されるものではない旨付言された77。
- 77 第180回国会参議院東日本大震災復興特別委員会会議録(以下「第180回国会(参)復興特会議録」という。)第8号6頁(平成24年6月14日)。なお、「社会的な責任」という文言については、福島特措法案の審議において議員修正によって同法律案第1条にも追記されたものであり、その内容等については、第180回国会(衆)復興特会議録第6号7頁(平成24年3月8日)。
2) 主務大臣等
本法律案には主務大臣や各施策の所管省庁が規定されていないため、責任の所在が不明確となり、施策の実効性が弱まるのではないかという指摘がなされた。これに対し、発議者からは、本法律案に規定されている施策は多岐にわたるが、個々の施策の内容から所管省庁は明らかであり、特に明記しなくても足りる。基本方針の取りまとめについては、復興庁が行うことを想定しており、閣議決定を経ることが望ましい旨答弁された。
また、こうした議論を受けて、復興大臣からは、復興庁が基本方針を取りまとめて、各省庁に責任を持って施策を実行してもらう。各施策についての全体調整は復興庁が担う旨答弁された78。
併せて、発議者からは、議員連盟等を設けて、支援対象地域の基準、各施策の具体化や財源の確保等についてチェックしていきたい旨答弁がなされた79。
- 78 第180回国会(衆)復興特会議録第7号7~9頁(平成24年6月19日)。
- 79 第180回国会(参)復興特会議録第8号5頁(平成24年6月14日)、第180回国会(衆)復興特会議録第7号12頁(平成24年6月19日)等。なお、本法律案成立後の平成25年1月22日に政府による法律の実施を監視し、確実に施策を実行させるために超党派の「子ども・被災者支援議員連盟」発足。
3) 支援対象地域の放射線量の基準等
東京電力福島第一原子力発電所の事故に対応するために、その周辺地域では平成23年4月に以下の3つの区域が設定された。
| 区域名 | 対象範囲 | 概要 |
|---|---|---|
| 警戒区域 | 原子力発電所から半径20km圏内 | 原則立入禁止、宿泊禁止 |
| 計画的避難区域 | 年間積算線量が20mSvを超える区域 | 立入可、宿泊原則禁止 |
| 緊急時避難準備区域 | 原子力発電所から半径30km圏内 | 避難の準備、立入・宿泊可 |
その後、同年12月に原子炉が冷温停止状態となったことを受けて、新たに以下の3つの区域へと再編する見直しが進められていた。
| 区域名 | 対象範囲 | 概要 |
|---|---|---|
| 帰還困難区域 | 年間積算線量が50mSvを超える区域 | 原則立入禁止、宿泊禁止 |
| 居住制限区域 | 年間積算線量20~50mSvの区域 | 立入・一部事業活動可、宿泊原則禁止 |
| 避難指示解除準備区域 | 年間積算線量20mSv以下となることが確実な区域 | 立入・事業活動可、宿泊原則禁止 |
このような状況の中、本法律案における支援対象地域の放射線量については「一定の基準以上」と規定され、具体的な数値は定められなかった。その理由等について質問がなされ、発議者からは次のとおり答弁がなされた80。
・支援対象地域の放射線量の基準については、1mSvに向けて81、毎年見直していくことが想定されており、その都度法改正が必要とならないよう、あえて法律には数値を規定しなかった。
・国が一方的に基準を定めることで、地域やコミュニティを分断することは避けるべきであり、被災者等の意見を聴きつつ、多様な実情を総合的に勘案して決めていくことが必要である。
・具体的な基準については政府が定める基本方針を踏まえて、適切に定められることを期待する。
さらに、支援対象地域については、少なくとも福島県全域が対象となるべき、1mSv以上の地域を対象とすべき、放射線量の違いによって支援内容に差をつけるような線引きをすべきではない等の議論がなされた82。
- 80 第180回国会参議院東日本大震災復興特別委員会会議録第8号9頁(平成24年6月14日)、第180回国会(衆)復興特会議録第7号4,9,12頁(平成24年6月19日)等。
- 81 国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年勧告は、被ばく状況を計画的に管理できる平常時(計画被ばく状況)、事故や核テロ等の非常事態(緊急時被ばく状況)、事故後の回復や復旧の時期等(現存被ばく状況)の3つの状況に分けて防護の基準を定めており、一般公衆の線量限度について、計画被ばく状況では年間1mSv以下、現存被ばく状況では参考レベルを年間1~20mSvとしている。
- 82 第180回国会(参)復興特会議録第8号9頁(平成24年6月14日)、第180回国会(衆)復興特会議録第7号4頁(平成24年6月19日)等。
4) 放射線による健康への影響に関する調査の位置付け等
平成23年6月から福島県においては、全県民を対象とした県民健康管理調査が開始されていた。また、福島特措法では、当該調査を福島県が行うことができることとし、その財源として活用される福島県民健康管理基金83への拠出を念頭に国は必要な財政上の措置を講ずることとする旨規定された84。
一方、本法律案第13条第2項では、国が放射線による健康への影響に関する調査について必要な措置を講ずることとしている。これらの関係について質問がなされ、発議者からは、本法律案による措置については、以下の点で県民健康管理調査よりも拡充されているが、同調査もその措置の一つに該当し得る旨答弁がなされた85。
・福島県以外の被災者も対象となるよう国に義務を課していること。
・少なくとも、子どもである間に一定の基準以上の放射線量が計測された地域に居住したことがある者等については、生涯にわたって実施されるよう必要な措置が講ぜられることとしていること。
なお、県民健康管理調査は福島県の自治事務として実施されていたが、これらの調査については、法定受託事務とすることを検討すべきとの議論があった86。
- 83 平成23年7月25日に成立した平成23年度一般会計補正予算(第2号)に福島県原子力被災者・子ども健康基金として計上された交付金962億円のうち、健康管理・調査事業分782億円を用いて造成。
- 84 制定時の福島特措法第26条及び第29条。第180回国会(参)復興特会議録第6号8頁(平成24年3月29日)等。
- 85 第180回国会(参)復興特会議録第8号10頁(平成24年6月14日)。
- 86 第180回国会(参)復興特会議録第6号6項(平成24年3月29日)等。
なお、自由民主党や公明党等の野党は、これらの調査を法定受託事務とする「平成二十三年東京電力原子力事故に係る健康調査等事業の実施等に関する法律案」を平成24年3月29日に参議院に提出、同法律案は同年9月7日(参)本会議で継続審査とされた。一方、同年3月29日の(参)東日本大震災復興特別委員会では、平野復興大臣から、県民健康管理調査については福島県からの要望があり自治事務として整理された旨説明がなされた。
5) 医療費減免の対象等
福島県においては、福島県民健康管理基金を用いて、平成24年10月から県内に住所を有する18歳以下の子どもの医療費を無料化することした。当初、福島県からは、国による対応が求められたが、公的医療制度が税金及び受診料で成り立っているものであり、別途国費を充てることまでは困難と判断された87。一方、本法律案第13条第3項には、国が被災者である子ども及び妊婦の医療費を減免するために必要な施策その他被災者への医療の提供に係る必要な施策を講ずる旨規定されている。
これらの関係等について質問がなされ、発議者からは、同項による施策の対象は必ずしも福島県内に住所を有する子どもに限らないが、減免の対象から被ばくに起因しないものは除かれるという違いがあり、本法律案成立後には、両者の関係について適切に調整されていくものと理解している旨答弁がなされた88。
その上で、当該減免は国費によることから、その対象や程度等は際限のない野放図なものであってはならないが、国は被災者を可能な限り支援するために国民の理解を得る最大限の努力をすべきである旨答弁がなされた89。
なお、同項に規定する「その他被災者への医療の提供に係る必要な施策」として、大人についても医療費の減免に係る施策が講じられることもあり得る旨答弁がなされた90。また、対象となる疾病については「被ばくに起因しないものは除かれる」と定められているが、当該規定はネガティブリストであり、原則として全ての疾病が対象となり、被ばくに起因しないことの立証責任は国にある旨答弁がなされた91。あわせて、医師が疾病と被ばくの因果関係を判断するためのガイドラインの必要性等についての議論がなされた92。
- 87 第180回国会(参)復興特会議録第6号5頁(平成24年3月29日)等。
なお、広島市及び長崎市への原子爆弾投下による被爆者については、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(平成6年法律第117号)に基づき、国費によって放射能に起因する疾病等に係る医療費が無料化されている。 - 88 第180回国会(参)復興特会議録第8号10頁(平成24年6月14日)。
- 89 第180回国会(参)復興特会議録第8号4頁(平成24年6月14日)。
- 90 第180回国会(衆)復興特会議録第7号10頁(平成24年6月19日)。
- 91 第180回国会(参)復興特会議録第8号9頁(平成24年6月14日)、第180回国会(衆)復興特会議録第7号6頁(平成24年6月19日)。
- 92 第180回国会(衆)復興特会議録第7号12,13頁(平成24年6月19日)。
(3) 法概要・措置内容
1) 概要・目的
被災者の不安の解消、安定した生活の実現のため、主に自主避難者を対象とした被災者の生活支援等に関し、国が必要な施策を講ずる責務を有すること等を定めた理念法である。
2) 基本理念・国の責務
第2条において、被災者の生活支援等に当たっての基本理念として、正確な情報提供、被災者が自らの意思で居住・移動・帰還を選択できるようにすること、外部及び内部被ばくに伴う被災者の健康上の不安の早期解消、いわれなき差別の防止、子ども及び妊婦に対する特別の配慮及び支援の必要性が継続する間の確実な実施が定められた。
また、法第3条においては、国会審議における主な議論として上述したとおり、国の責務について定められた。
3) 基本方針
法第5条において、政府は、子どもに特に配慮して行う被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する基本方針を策定しなければならないこととされ、基本方針には、施策の推進に関する基本的方向や基本的な事項等のほか、法第8条の支援対象地域に関する事項を定めることとされた。
4) 支援対象地域で生活する被災者への支援
法第8条において、支援対象地域(放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域)で生活する被災者を支援するために、国は、医療の確保、子どもの就学等の援助、家庭や学校等における食の安全及び安心の確保、放射線量の低減や生活上の負担の軽減のための地域における取組の支援及び自然体験活動等を通じた心身の健康の保持に関する施策等を講ずることとされた。
なお、支援対象地域の放射線量の基準等については、国会審議における主な論点として上述したとおりである。
5) 支援対象地域以外の地域で生活する被災者への支援
法第9条において、支援対象地域から移動して支援対象地域以外で生活する被災者を支援するために、支援対象地域からの移動の支援、移動先における住宅の確保・子どもの学習等の支援・就業の支援・地方公共団体による役務の円滑な提供及び支援対象地域の地方公共団体との関係の維持に関する施策等を講ずることとされた。
6) 支援対象地域以外の地域から帰還する被災者への支援
法第10条において、支援対象地域に帰還する法第9条に規定する被災者を支援するため、国は、支援対象地域への移動の支援及び支援対象地域における住宅の確保・就業の支援・地方公共団体による役務の円滑な提供に関する施策等を講ずることとされた。
また、法第8条から第10条までに規定するいずれの被災者についても、家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援に関する施策その他の必要な施策を講ずることとされた。なお、当該子どもに対する支援に関する施策については、国会審議において、家族に会う際にかかる旅費や通信費用の軽減、カウンセリング、心のケアなどを念頭においている旨発議者から答弁がなされた93。
- 93 第180回国会(衆)復興特会議録第7号4頁(平成24年6月19日)。
7) 放射線による健康への影響に関する調査
法第13条第2項前段において、被災者の定期的な健康診断の実施その他原子力事故に係る放射線による健康への影響に関する調査について、国は必要な措置を講ずることとされた。また、同条後段において、少なくとも、子どもである間に一定の基準以上の放射線量が計測された地域に居住したことがある者等に係る健康診断については、生涯にわたって実施されるよう必要な措置を講ぜられることとされた。
なお、同項に基づく措置の一つに福島県が実施する県民健康管理調査が該当し得ること等については、国会審議における主な議論として上述したとおりである。
8) 医療の提供
法第13条第3項において、国は、被災者である子ども及び妊婦が医療(原子力事故に係る放射線による被ばくに起因しないものは除く。)を受けたときに負担すべき費用を減免するために必要な施策その他被災者への医療の提供に必要な施策を講ずることとされた。
なお、同項に基づく施策と福島県が福島県民健康管理基金を用いて行う18歳以下の子どもの医療費無料化との関係や減免の対象等については、国会審議における主な議論として上述したとおりである。
9) 附則関係
本法律は公布の日(平成24年6月27日)から施行することとされた。また、国は毎年支援対象地域等の対象となる区域を見直すこととされた。
(4) 適用実績
1) 原子力災害による被災者支援施策パッケージ
a. 経緯
本法律の施行を受けて、政府は法第5条に規定する基本方針を策定しなければならなかったが、基本方針には法第8条に規定する支援対象地域を定めることとされており、そのために必要となる当該地域の放射線量については、国会審議における議論も含めて様々な意見があった94。また、数値基準を設けることで、当該地域が危険であるという誤解やこれに基づく風評被害の発生、線引きによる住民の分断等も懸念された。
こうしたことから、支援対象地域の放射線量については、科学的知見も含めて内外の有識者の意見を聞き、その結果も踏まえる必要があると考えられた95。このため、平成25年3月7日の復興推進会議・原子力災害対策本部合同会合においては、根本復興大臣から、適切な地域指定のあり方を検討するためにも、線量水準に応じた防護措置の具体化について原子力災害対策本部で議論を行って年内を目途に一定の見解を示すこと、また、その検討に当たっては原子力規制委員会が科学的・技術的な見地からの役割を十分に果たすことが要請された。
このような状況にあって、法施行から9か月を経ても基本方針は策定されていなかった。しかし、支援対象地域が定められないから被災者の生活支援等が進まないという事態を避けるために、政府では「自主避難者等への支援に関する関係省庁会議96」を開催し、平成25年3月15日に関係省庁の連名による「原子力災害による被災者支援施策パッケージ ~子どもをはじめとする自主避難者等の支援の拡充に向けて~」(以下「施策パッケージ」という。)を取りまとめた。
- 94 参議院決算委員会(第180回国会閉会後)会議録第1号第12頁(平成24年10月18日)、第183回国会参議院本会議会議録第5号14頁(平成25年2月6日)等。
- 95 第183回国会参議院予算委員会会議録第3号29頁(平成25年2月19日)等。
- 96 復興副大臣を座長として、復興庁、内閣府、消費者庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、経済産業省、環境省及び原子力規制庁で構成し、平成25年2月13日に第1回を開催。
b. 概要
施策パッケージの内容は、大きく「子どもの元気を復活させる先進的な取組」、「健康不安に対して、安心を確保する取組」及び「健康不安に伴い生じた生活上の負担への支援」の3つに分けられ、93項目の施策が盛り込まれた。また、各施策の趣旨・目的等に応じて、それぞれ異なる対象地域が定められた。
なお、今後については、より効果的かつ効率的な施策の推進に向けて「自主避難者等への支援に関する関係省庁会議」において適宜フォローアップを行うとともに、被災者や自治体の様々な意見を聞き、専門的な知見も活用しつつ、施策パッケージの拡充に向けて引き続き検討を進めることとされた。
c. 特徴的な施策
施策パッケージに盛り込まれた特徴的な施策として、子どもの運動機会を確保する全天候型運動施設等の新たな整備、健康不安を解消する福島県内外でのリスクコミュニケーションの強化、母子避難者等に対する高速道路の無料措置、全国における賃貸型応急住宅の供与期間の延長(平成25年3月末までを平成26年3月末までに延長)等が挙げられる。
このうち、高速道路の無料措置については、平成25年4月26日から開始された。原子力事故の発生時に福島県浜通り・中通り(警戒区域等を除く)及び宮城県丸森町に居住しており97、当該地域外に避難して二重生活を強いられている母子避難者等が対象者とされ、避難元市町村が交付する証明書によって、避難元及び避難先それぞれの最寄りインターチェンジ間の走行が無料となった。当該証明書は令和2年度までに2,306件交付された。
なお、対象となる避難元については、健康不安が特に強かったと考えられる地域として、東京電力福島第一原子力発電所からの距離、避難指示等対象区域との近接性、放射線量に関する情報、自主避難者の多寡などの状況、社会的・経済的な地域の一体性といった要素を総合的に勘案して定められた98。
- 97 福島県で対象となる具体的な市町村は、中通りが、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町及び鮫川町、浜通りが、相馬市、南相馬市、新地町及びいわき市となる。
なお、警戒区域等からの避難者に対しては、別途、平成24年4月1日から生活再建に向けた一時帰宅等の移動を対象に無料措置が実施されている。 - 98 平成25年3月15日根本復興大臣記者会見。
2) 基本方針
a. 経緯
施策パッケージのとりまとめ後も基本方針の策定には時間を要し、国会においても進捗状況等について質疑がなされていた99。また、平成25年8月22日には、国が基本方針を策定しないことが違法であることの確認等を求める福島県、宮城県及び栃木県からの自主避難者等によって、国は東京地方裁判所に提訴された100。
基本方針に定めることとされた事項のうち、非常に難しいと考えられたのが支援対象地域に関する事項だった。立法過程において当該地域の放射線量の基準が定められず、法律上、主務大臣や所管省庁についても明確にされていないことで、本法律の執行、特に基本方針の策定に係る作業には時間を要した。
政府における検討の過程では、支援対象地域を放射線量の数値で一律に確定することと、被災者の不安の解消や地域の分断の防止といったことをいかに両立させるのかが論点となった。また、そもそも20mSvを下回る空間線量水準において、住民の生活パターン等を考慮せずに、健康への影響に差が出る画一的な数値があると考えることが必ずしも合理的ではないとの見解もあった。さらに、施策パッケージと同様に、施策の趣旨・目的に応じて対象となる地域は異なるべき等の議論もなされていた101。
こうしたことを踏まえ、法第8条においては支援対象地域について放射線量が一定の基準以上である地域と規定されているが、この「一定の基準以上の放射線量」を単純な数値ではなく、「相当な放射線量」と解釈すること、また、支援対象地域で講じられる施策の一部を必要とする地域やそもそも放射線量には関わりなく講じられるべき施策もあるため、支援対象地域に準ずる地域を設けること等について検討が重ねられた。
その結果、支援対象地域については、「原発事故発生後、年間積算線量が20mSvに達するおそれのある地域と連続しながら、20mSvを下回るが相当な線量が広がっていた地域」という考え方がとられた。これにより、支援対象地域を「福島県中通り及び浜通りの市町村(避難指示区域等を除く。)」とするとともに、施策ごとに準支援対象地域を定めた基本方針案が作成された。
当該基本方針案について、平成25年8月30日から9月23日までの間、パブリックコメントが行われるとともに、9月11日及び13日には福島県及び東京都で政府主催の説明会が開催された。パブリックコメントには、支援対象地域に関する事項2,707件、放射線による健康への影響調査・医療の提供に関する事項1,481件、住宅の確保765件、移動の支援525件など計4,963件(重複計上あり)の意見が寄せられた。
こうした過程を経て、平成25年10月11日に法第5条の規定による「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」が閣議決定された102。
- 99 第183回国会参議院東日本大震災復興特別委員会会議録第5号4頁(平成25年5月10日)、第183回国会参議院消費者問題に関する特別委員会会議録第6号9頁(平成25年6月12日)等。
- 100 当該訴訟については、平成25年12月27日に原告が訴えを取り下げた。
- 101 第183回国会参議院東日本大震災復興特別委員会会議録第3号16,24頁(平成25年4月17日)等。
- 102 法第5条では求められていないが、国会審議において、基本方針については閣議決定を経ることが望ましいとされたことは上述のとおり。
b. 概要
基本方針は、「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方向」、「支援対象地域に関する事項」、「被災者生活支援等に関する基本的な事項」及び「その他被災者生活支援等施策の推進に関する重要事項」からなり、支援対象地域及び準支援対象地域については上述のとおり定められた。
被災者生活支援等施策に関する基本的な事項は、「汚染状況調査」、「除染」、就学等の援助・学習等の支援、食の安全及び安心の確保、移動の支援、住宅の確保や健康への影響調査・医療の提供等の「被災者への支援」等からなり、施策パッケージには入っていない新規・拡充施策も含めて64項目の施策が盛り込まれた。
その他重要事項として、関係省庁の各施策の概要や対象地域等を記した資料を別途取りまとめて公表すること、また、基本方針は支援対象地域等の見直しにあわせて必要に応じ内容を見直すこととした。
c. 主な施策及び施策とりまとめ
これまでの取組を拡充する施策として、福島近隣県を含めた外部被ばく状況の把握、民間団体を活用した福島県外への避難者に対する情報提供事業や、支援対象地域に居住していた避難者の公営住宅への入居円滑化等が挙げられる。公営住宅への入居円滑化については国土交通省から全国の事業主体に要請がなされ103、入居の応募に必要となる「居住実績証明書」の累計発行件数は1,171件(令和4年4月現在)となっている。
その他、移動の支援については、引き続き、母子避難者等に対する高速道路の無料措置が盛り込まれた。また、住宅の確保については全国における借上型応急住宅の供与期間の延長(平成26年3月末までを平成27年3月末までに延長)等が盛り込まれた。
また、医療の提供については、「被ばく量の観点から、事故による影響が見込まれ、支援が必要と考えられる範囲(子ども・妊婦の対象範囲や負傷・疾病の対象範囲)を検討するなど、県民健康管理調査や個人線量把握の結果等を踏まえて、医療に関する施策の在り方を検討」することとされた104。
あわせて、「「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」に関する施策とりまとめ」が公表された。同とりまとめにおいては、基本方針に盛り込まれた施策その他の被災者支援に関する施策について、支援内容ごとに分類した上で119項目が掲載された。
- 103 各都道府県知事・政令市長あて国土交通省住宅局長通知「「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について」(平成26年6月18日国住備第32号)、「公営住宅法施行令第1条第3号の収入の認定の特例について」(平成26年6月18日国住備第33号)等。
- 104 当該施策については環境省が所管し、「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」を設置。同会議は、平成25年11月から平成26年12月までに計14回開催された。
3) 基本方針の改定
a. 経緯
平成27年度までの集中復興期間の終了に当たり、翌年度からの第1期復興・創生期間における被災者の生活支援等についての方針を示す必要があった。また、発災から4年が経過し、避難指示区域以外の放射線量が大幅に低減している一方、避難先での生活の定着といった状況も生じていた。こうしたことから、被災者が自ら居住地を定めて、安心して生活ができるよう、帰還や定住の支援に重点を置く方針を明らかにするため、基本方針を改定することとなった。
改定に当たっての考え方として、支援対象地域については、避難する状況にはないことを明記する一方、被災者が帰還又は他の地域への定住を新たに判断するためには一定の期間を要することから、当面、縮小又は撤廃はしないこととされた。
基本方針の改定案については、平成27年7月10日から8月8日までの間、パブリックコメントが行われるとともに、7月11日及び12日に北海道、山形県及び沖縄県における「県外自主避難者等への情報支援事業」支援情報説明会・交流会での説明がなされ、同月17日及び18日には東京都及び福島県で説明会が開催された。パブリックコメントには、支援対象地域に関する事項1,201件、放射線による健康への影響調査・医療の提供に関する事項502件、住宅の確保455件など計1,515件(重複計上あり)の意見が寄せられた。
こうした過程を経て、平成27年8月25日に法第5条の規定による「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」の改定について閣議決定された。
b. 概要
改定された基本方針(以下「改定基本方針」という。)は、改定前同様、「基本的方向」、「支援対象地域に関する事項」、「基本的な事項」及び「その他重要事項」からなり、支援対象地域については、「法の規定に従えば縮小又は撤廃することが適当と考えられるが、当面、放射線量の低減にかかわらず、縮小又は撤廃しない」こととされた。
基本的な事項については、改定前のように個別施策を網羅的に列挙することはやめ、特に重要な住宅の確保や放射線による健康への影響調査、医療の提供等について記載することとされた。このうち、「住宅の確保」については、「福島県が避難指示区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅の供与期間を平成29年3月末までとしたことは105、支援対象地域における大幅な放射線量の低減等とも整合的である」旨明記された。
また、「放射線による健康への影響に関する調査、医療の提供等」については、改定前の基本方針を踏まえて開催された環境省の専門家会議において、平成26年12月に「今回の事故による放射線被ばくによる生物学的影響は現在のところ認められておらず、今後も放射線被ばくによって何らかの疾病のリスクが高まることも可能性としては小さいと考えられる」、しかし、「住民の懸念が特に大きい甲状腺がんの動向は慎重に見守る必要がある」等とする中間とりまとめが示されていた106。これを受けて、改定基本方針においては、福島県の県民健康調査における甲状腺検査の充実、リスクコミュニケーション事業の継続・充実等に取り組むこととされた。
- 105 「東日本大震災に係る仮設・借上げ住宅の供与期間の延長について」(平成27年6月15日福島県避難者支援課)において、応急仮設住宅の供与期間については、全県一律で平成29年3月末まで延長するとともに、避難指示区域以外からの避難者に対する平成29年4月以降の取扱いについては、災害救助法に基づく応急救助から、新たな支援策へ移行していくこととされた。
- 106 「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議中間とりまとめ」(平成26年12月)34頁等。
c. 施策とりまとめ
改定基本方針においても、関係省庁の各施策の概要や対象地域等を記した資料を別途取りまとめて公表することとされた。これを受けて、平成27年10月2日に「「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」に関する施策とりまとめ」が公表された。
同とりまとめにおいては、被災者支援に関する施策について、支援内容ごとに分類した上で95項目が掲載された。
なお、平成28年以降も毎年同様の取りまとめがなされて、公表されている。
4) 支援対象地域の見直し
法附則第2項においては、放射線量に係る調査の結果に基づき、毎年支援対象地域等の対象となる区域を見直すこととされている。このため、平成26年12月26日に支援対象地域を見直した結果、発災以降の放射線量は全体として低減傾向にあるものの、一方で今後もなお支援が必要と考えられることなどを総合的に勘案し、引き続き、支援対象地域については、「福島県中通り及び浜通りの市町村(避難指示区域等を除く。)」とすることとされた。
また、平成27年には、基本方針の改定に当たって、被災者が帰還又は他の地域への定住を新たに判断するためには一定の期間を要することから、支援対象地域は当面縮小しないこととされた。平成28年以降も、毎年支援対象地域を見直した結果として、改定基本方針も踏まえ、支援対象地域については、引き続き、「福島県中通り及び浜通りの市町村(避難指示区域等を除く。)」とされている。
6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災によって多数の事業者が事業用資産に甚大な被害を受け、既往債務が負担になって新規資金調達が困難となる等のいわゆる二重債務(二重ローン)の問題が生じるとの指摘がなされ、国会においても、被災者向け金融対策の中心的な課題として、多くの議論が行われた。
政府は平成23年6月、「二重債務問題への対応方針」を取りまとめ、この中で中小企業及び農林水産業等向け対応として、旧債務について、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)や民間金融機関等が出資する「中小企業再生ファンド」(産業復興機構)を被災県に設立し、過剰債務を抱えているが事業再生の可能性のある中小企業に対し、出資や債権買取り等を含めた支援を実施していくとの方針を示した。
これに対し、従来型の中小企業対策では足りず、より多くの事業者を対象とするため、債務の負担を軽減しつつその再生を支援することを目的とした公的な機構を、資金調達に係る政府保証枠等を設けた新たな法律に基づいて設立する必要があるとして、第177回国会中の平成23年7月11日、自由民主党、公明党及びたちあがれ日本・新党改革から「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案」が参議院に提出された。
(2) 国会審議、公布・施行経緯
本法律案は、参議院では平成23年7月29日、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(英:The Corporation for Revitalizing Earthquake-Affected Business、以下「CREB」という。)による金融機関等からの債権買取価格や買い取った債権の管理・処分に係る規定について修正が行われた上で可決され、衆議院に送付された。
第177回国会が閉会し、本法律案が衆議院で継続審議となった後も、民主党、自由民主党及び公明党による三党協議が行われ、本法律案を修正して成立させることで合意がなされた。
第179回国会中の平成23年11月15日、衆議院で三党合意に基づき、CREBの業務、債権の買取価格、CREBが買い取った債権の管理・処分等について修正が行われた上で、与党の民主党・国民新党も賛成に回って可決され、同月21日、参議院でも可決されて成立に至った。
本法律の施行日は平成24年2月23日である(ただし、CREBの設立等に関する規定は公布の日から施行されている。)。CREBは同月22日に設立され、同年3月5日から業務を開始した。
国会審議においては、主に以下の点について議論107がなされた。
- 107 参考文献「二重債務問題の解決策構築に向けた国会論議」立法と調査 2011.10 No.321。
1) CREBを新たな法律で設立する必要性
CREBを法律で設立する必要性について、発議者は、平時の対応を超えた臨時・特異的な措置が必要であり、被災地域において事業再生を図ることを支援するためには、やはり従来の中小企業支援では全く足りないと考えている108、との認識を示し、大規模な震災に対する特別な対応の必要性を指摘した。加えて、産業復興機構の場合は特段の立法措置を要しないことと比較して、特定の目的で刑罰や債権回収停止命令まで付けて、しかも大きな買取り枠ができるような保証が書けるというのは新しい法律がなければ対応できない109と、立法措置が不可欠であるとの考えを示した。
一方、阪神・淡路大震災等の過去の災害で債権の買取り制度を設けなかったこととの違いについて、地震そのものの被害に加え、津波による事業用地等の流失、原発災害により、これまでの災害とは比較にならない甚大な被害があり、過去の災害とはかなり質が異なる特異なものであることから、本法律案により二重ローンの買取り機構を設けることが国民の皆さんにも御理解いただけるのではないか109、との認識を示した。さらに、今後の災害発生時への対応については、災害の状況に応じて改めて検討していかなければならないと思っている109、との見解が示された。
- 108 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第11号 平成23年7月28日。
- 109 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号 平成23年7月27日。
2) 産業復興機構のスキームの課題
政府案による産業復興機構のスキームの課題について、罰則規定等のガバナンスの問題、債権買取りのために必要な資金規模、中小機構による運営等について議論が行われている。
a. 罰則規定等のガバナンスの問題
発議者からは罰則規定等のガバナンスの問題について、主務官庁からの監督が基本的には法律上に規定されておらず、職員等についての罰則規定も法律上には全く規定されていないため、何も法律を作らずにガバナンスが保たれるとは思えない108との指摘がなされた。これに対し、政府は、それぞれの設立の根拠法において、特段の罰則規定は設けられていないが、(産業復興機構へのつなぎ役となる相談窓口である)産業復興相談センターには産業再生法上秘密保持の義務が課せられており、改善の命令、認定の取消しも可能である。また、中小機構が出資する投資事業有限責任組合契約においては、重大な背信行為、義務の違反行為について、損害賠償請求や除名の対象となるので、組合契約を通じて適切な管理体系を作っていくことができると考えている108、との見解を明らかにした。また、法的な裏付けがない中で、産業復興相談センターが親身に事業者からの相談に応じてくれるのかという質問については、政府から、地域の金融機関の意見も聞き、運営方針などで明らかにしていきたい、また、投資事業有限責任組合契約も結ぶので、その中で、買取価格の在り方などについても明らかにしていきたい108、との考えが示された。
- 108 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第11号 平成23年7月28日。
b. 債権買取りのために必要な資金の問題
債権買取りのために必要な資金規模について、発議者から、潜在的に22兆円の債権がある被災地域で、中小機構による出資1,500億円というのは焼け石に水の金額である109、と資金不足が指摘された。一方、政府からは、現時点では、中小機構の手持ち資金で対応できると考えているが、今後、財源が不足すれば、財政当局と相談しながら対応していきたい108、との答弁があったほか、第二次補正予算で8,000億円の予備費があるので、必要があればすぐに使って十分な資金を準備させていただきたい108、との答弁があった。
- 108 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第11号 平成23年7月28日。
- 109 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号 平成23年7月27日。
c. 中小機構による運営の問題
中小機構が運営を担うことについて、発議者から、中小機構は、事業仕分けの対象となり、その業務運営や多額の繰越欠損金を抱えた財務状況について多くの指摘がなされ、国庫返納も求められた組織であり、思い切った業務運営はできない108、との疑問が呈された。一方、政府からは、一定程度の破産更生債権や繰越欠損金が存在することは事実だが、資力の乏しい中小企業の融資を行ってきたこと、金利等の経済環境の変化などに起因するものと考えており、独立行政法人に移行して以来、破産更生債権や繰越欠損金は着実に削減しており、独立行政法人評価委員会においても、財務内容を含めた業務実績についておおむね中期計画を達成していると評価されている108、との見解が示された。さらに、経済産業省が所管する産業復興機構に農林水産事業者から相談は来るのか、との疑問に対しては、ワンストップの窓口を作って農業関係者あるいは医療関係者もしっかり対応するよう、窓口の強化も人材補強もしっかり計画に入れている109、との答弁があった。
- 108 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第11号 平成23年7月28日。
- 109 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号 平成23年7月27日。
3) CREBへの出資及び政府保証の規模
CREBへの出資について、発議者からは、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、中小企業庁で200億円を出資して成立するものであり、おおよそ各々160億円、20億円、20億円ぐらいの配分と見込んでいる109、主務大臣が認めるような事業会社、金融機関、投資資金を持つ機関投資家などが出資することは、あくまでも預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構の出資があってのことであり、結果として、国が100%出資になってもかまわない108、との考えが示された。
政府保証の規模について、当初参議院では2兆円と議論されており、被災地域にある金融機関の債権額を総合的に勘案した上に、日本の不良債権比率が最大だった時期、あるいは欧米でリーマン・ショック前後に最大であった時期の歩留りを掛けて、個人の住宅ローンや大企業を除外すると、当座のところでは2兆円あればよいと考える109、との認識が示されていた。その後、衆議院で、被災三県で現在約5,000億円の条件変更や一時停止があり、沿岸部の農協・漁協は約500億円、福祉医療機構は約110億円で合計5,600億円だが、リース債権は入っておらず、今後膨らむ可能性もあるため、当面5,000億円は必要110、と5,000億円に修正した。
- 108 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第11号 平成23年7月28日。
- 109 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号 平成23年7月27日。
- 110 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号 平成23年11月14日。
4) CREBの人員・組織体制
CREBの人員・組織体制について、発議者から、当初の5年間については役員3人、職員200人体制で進めながら、その後は管理が主となるので、少しずつ減らしていくことになるのではないか109、との見通しが、経営や再生のプロの活用については、まずは最低限の生活と復旧を行うのに5年はかかるので、その時点では、商工会で長く窓口を担当された方等がまず話を徹底的に聞く相談業務となり、その後、コンサルタントにお願いするという次のステージに行くというように二段階で考えている109、との見通しが示された。
- 109 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号 平成23年7月27日。
5) 債権買取価格と債務免除
債権買取価格については、原案で規定されていた「適正な時価を上回ってはならない」という規定について、発議者から、余り高過ぎては金融機関を利するだけになってしまい、余り安過ぎては誰もこの機構に売ることがないので、被災事業者の債務を負担軽減しながら再生をいかにして図るかというところで、おのずから導かれるものと思う109、との考えが示されていた。しかし、迅速な債権買取のためには、より客観的な規定・基準が必要である108、との指摘を受け、「支援基準で定める割合を乗じて得た額を基本とし、その上で、事業の再生計画、被災地域の復興の見通し等を個別案件ごとに総合的に勘案していくことが必要である108、との認識が示された。こうした議論の結果、参議院可決案においては、「機構が債権の買取りを行う場合の価格は、適正な時価によるものとし、(中略)債権の価額に(中略)支援基準で定める割合を乗じて得た額を基本とする」とされた。その後衆議院において、モラルハザードを犯してはならない。一定率での買取りを義務付けると、銀行への補助金となりうる110、との指摘を受け、「適正な時価を上回ってはならない」として原案の規定に戻す再修正がなされた。
債権免除については、原案では買取り額が債権額を下回る場合には、差額を免除するよう「努めなければならない」と規定としていたが、債権買取りスキームの実効性を高める観点から参議院可決案においては、「免除しなければならない」に修正された。その後衆議院において、CREBの持続可能性及びモラルハザードの観点から「免除することができる」に再修正された。
なお、発議者からは、第1条の債務の負担を軽減しつつその再生を支援する目的に沿った形で債務軽減を図っていきたい110、との補足がなされている。
- 108 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第11号 平成23年7月28日。
- 109 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号 平成23年7月27日。
- 110 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号 平成23年11月14日。
6) 国民負担の最小化
CREBの最終的な損失が国民負担となる可能性について、発議者からは、債権の買取り機関の立法例では、いずれも時限の機関で、最終的な債務超過分の全部又は一部を政府が補助できるという形になっており、20年後の国会の判断で、当然そういった道があり得るということである、初めから一般会計を出し切るという形にしかならない政府の案よりは、財政赤字に与える悪影響がないと考えている108、の認識が示された。また、国民負担を最小に抑えるために、預金保険機構が持っている資金を活用するべきではないかとの指摘に対しては、預金保険機構が出資し、被災地域の金融システムの安定化に資することであるから、当然、御指摘のようなことを考えながら国民負担を最小化する努力をしていきたい109、との答弁があった。一方、政府からは、現在の預金保険機構の法律では、破綻金融機関でなければ使えないと判断すべき108、との見解が示された。
- 108 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第11号 平成23年7月28日。
- 109 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号 平成23年7月27日。
7) CREBと産業復興機構との関係について
CREBと産業復興機構との関係について、発議者より、既に各県の産業復興機構が各地域の実情に応じて支援対象を決めており、その整理をまず尊重する、そして、CREBは産業復興機構による支援の対象とすることが困難なものを対象とし、具体的には、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者を重点的な対象とする、その上で、各県の産業復興機構と相互補完し支援の充実を図る110、と示された。
- 110 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号 平成23年11月14日。
(3) 法概要・措置内容
本法律は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外への流出を防止することによって、被災地域における経済活動の維持を図ることを目的としており、そのために新設するCREBを活用して、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、過大な債務を負っている被災事業者であって、被災地域において事業の再生を図ろうとするものに対して、債権買取り等の様々な支援業務を通じて債務の負担を軽減しながらその再生を支援することを目的とした。
1) 対象事業者
法第19条第1項において、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、東日本大震災の被災地域として政令で定める地域において債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするものは、CREBに対して再生支援の申し込みをすることができるとされた。
2) CREBの業務
法第16条において、CREBは以下の業務などを営むこととされた。
・対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り、
・対象事業者に対する資金の貸付け(対象事業者の事業の継続に欠くことができないものに限る。)、債務保証、出資、事業の再生に関する専門家の派遣及び事業活動に関する必要な助言
・債権買取り等に係る債権の管理及び譲渡その他の処分
3) 支援決定期限・支援期間
法第19条第7項において、支援決定は平成29年2月22日まで(主務大臣認可により1年延長可)に行わなければならないとされた。
また、法第27条第5項において、CREBは、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、支援決定の日から15年以内に、当該支援決定に係る全ての再生支援を完了するように努めなければならないとされた。
※ 支援決定期限については、平成28年12月20日、主務大臣認可により平成30年2月22日までに延長。更にその後、平成30年2月1日に成立した改正法(同月7日施行)により、令和3年3月31日までに延長された。
4) 支援基準
法第18条において、主務大臣は、再生支援をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下、支援基準)を定めることとされた。
主務大臣は、支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、被災地域を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならないとされた。また、できる限り多くの事業者に再生の機会を与えることとなるよう適切に配慮するとともに、東日本大震災復興基本法第3条の東日本大震災復興基本方針及び被災地域の地方公共団体が東日本大震災からの復興に係る計画を定めている場合における当該計画との整合性に配慮しなければならないとされた。
5) 組織・体制
法第3条において、CREBは全国で一つに限り設立される株式会社であるとされ、法第8条において、CREBの発起人は、CREBの設立に当たっては主務大臣の認可を申請しなければならないとされた。
また、法第4条において、預金保険機構・貯金保険機構は、常時、CREBが発行している株式の総数の2分の1以上に当たる数の株式を保有していなければならないとされた。
また、法第40条において、政府は、CREBによる資金の借入れ又は社債に係る債務について、政府保証を付すことができるとされた。
6) 産業復興機構等との連携・協力
法第64条において、被災事業者の事業再生のために、CREBと産業復興機構等は、相互に連携を図るよう努めなければならないとされた。
7) 政策金融機関の協力
法第62条第3項において、政策金融機関は、民間金融機関が対象事業者に対して行う資金の貸付け等では、事業の再生に必要な資金を確保できない場合は、CREBの要請を受けて、資金の貸付けに係る審査を行い、当該必要な資金の貸付けを行うよう努めなければならないとされた。
8) 主務大臣
法第56条第1項において、この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣(一部の条文のみ)、農林水産大臣及び経済産業大臣とされた。
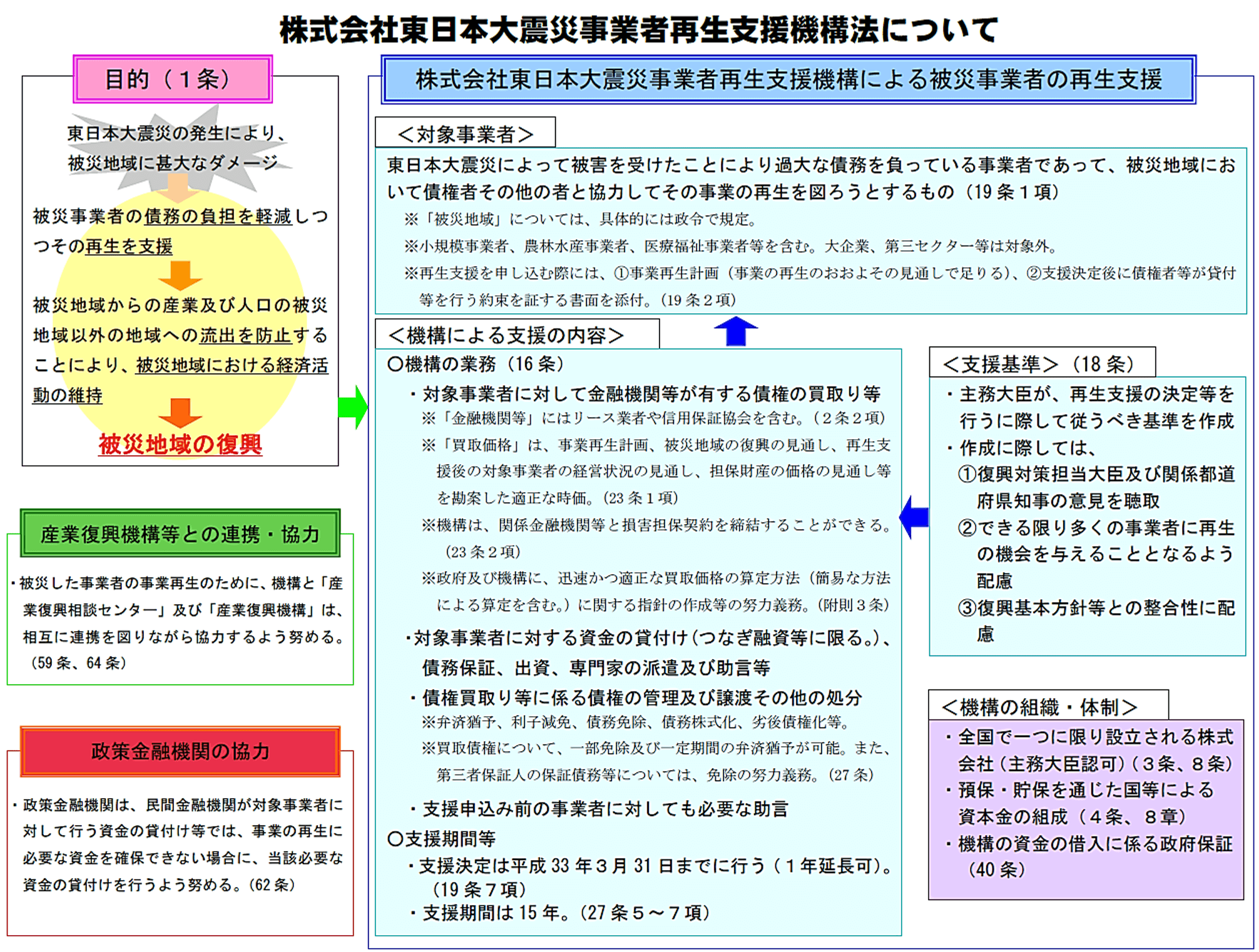
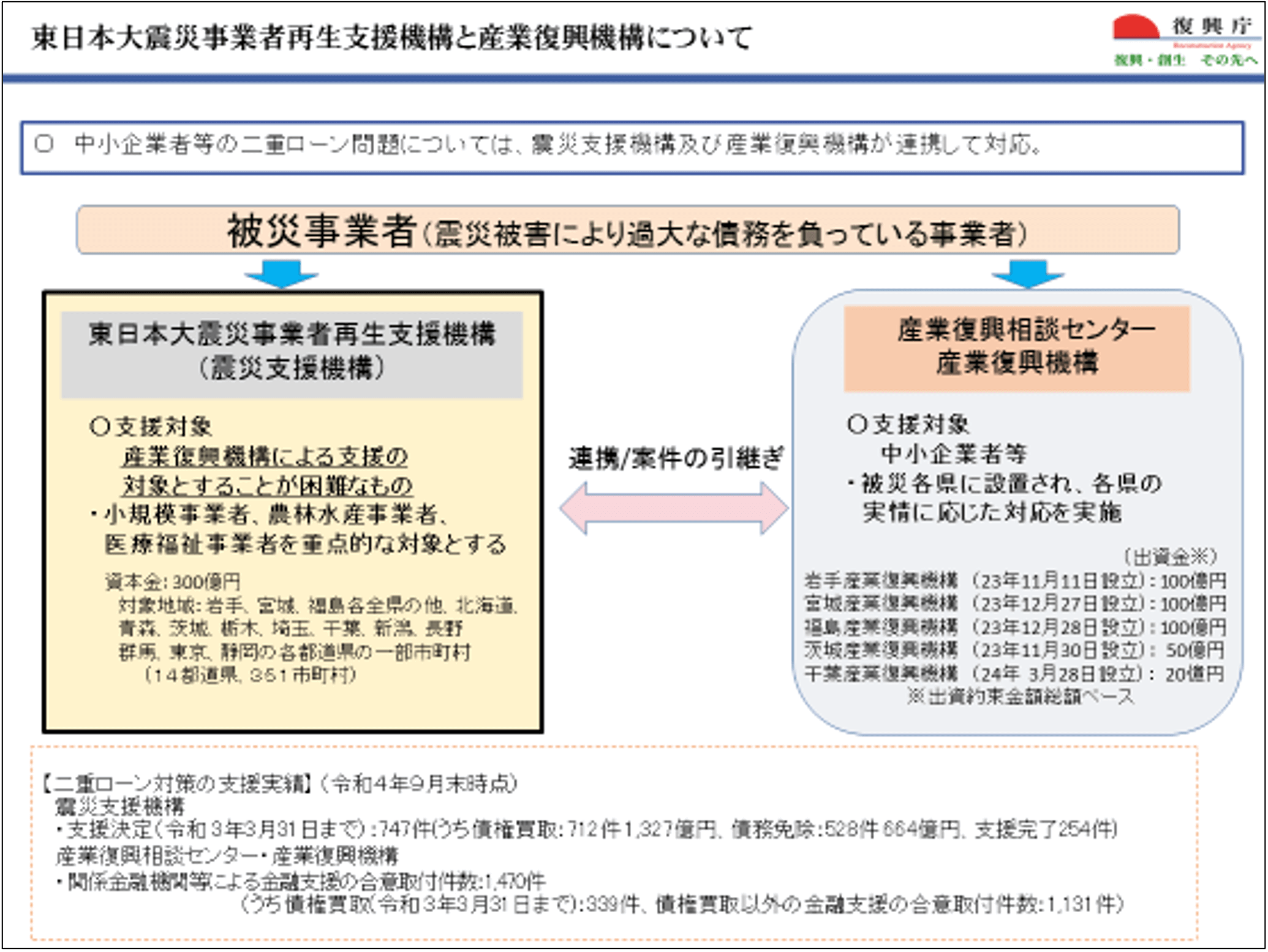
(4) 適用実績
支援決定期間が満了した令和3年3月31日までに、事業再生等に関する相談件数が 2,939 件、支援決定を行った案件が747件であった。このうち債権買取りは712件1,327億円、債務免除は528件664億円であった。
また、支援決定後に支援完了した先は、令和4年9月末時点で261件であった。
なお、産業復興相談センター・産業復興機構は、支援決定期間が満了した令和3年3月31日までに、金融支援の合意取付件数が1,415件、そのうち債権買取を行った件数が339件であった。
※ なお、CREB含む二重ローン問題への対応全般については、6章1節も参照。
(5) 評価・課題
(2)7)に記載の通り、CREBの支援対象は産業復興機構による支援の対象とすることが困難なものを対象とし、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者を重点的な対象としており、CREBと産業復興機構が相互補完を行いつつ支援が行われてきた。具体的には、既往債務が負担となり新規の資金調達が困難となっている被災事業者に対する、CREBによる債権買取等の支援を通じて、被災地域の経済活動・雇用の維持に貢献した。近年では新型コロナウイルス感染症拡大等による事業環境への影響を考慮の上、個々の被災事業者の置かれた状況に応じてきめ細かく対応してきた。今後も引き続き、個々の被災事業者に寄り添った対応が重要な課題である。
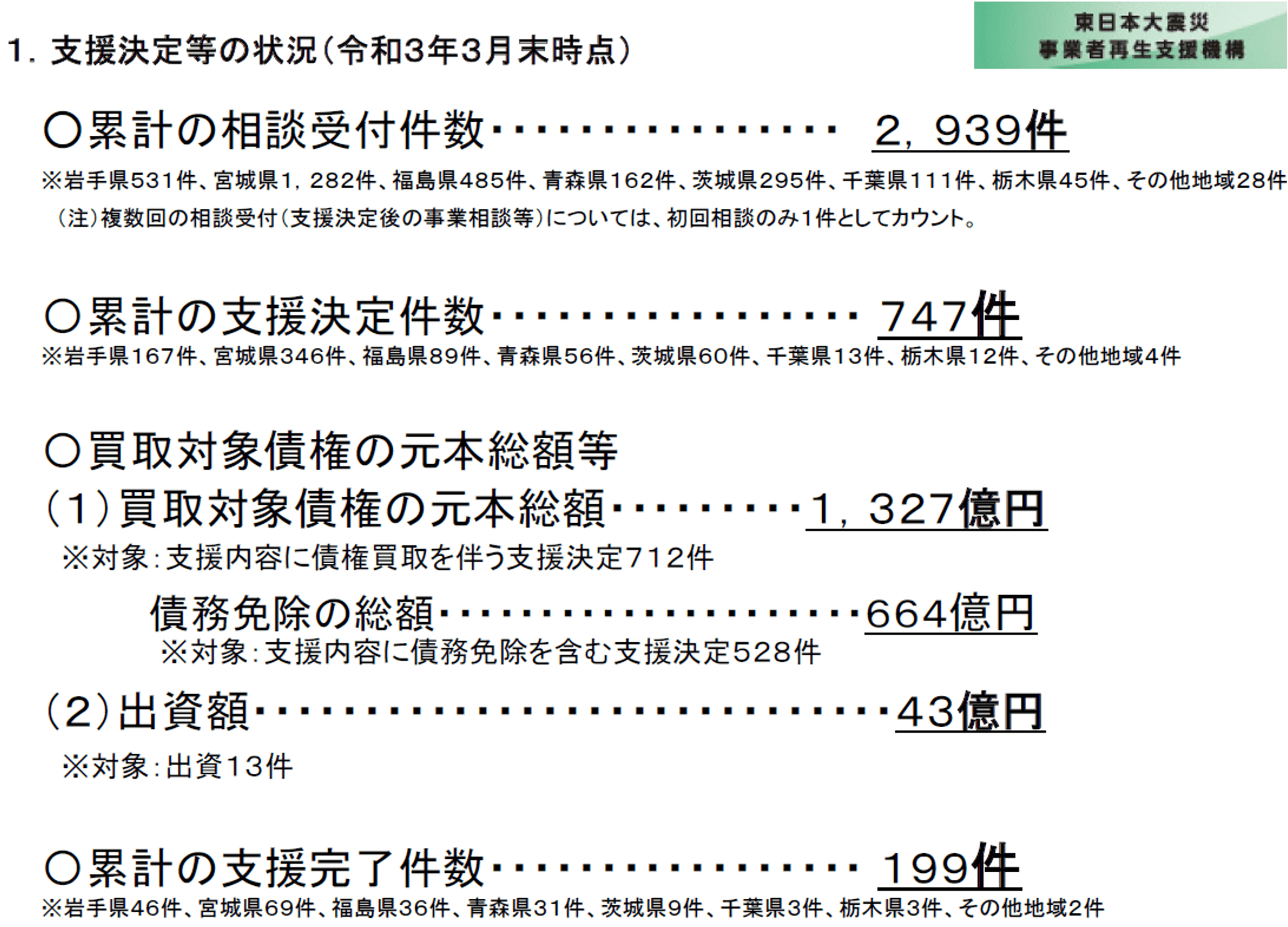
7. 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
被災した市町村の中には、行政機能が麻痺し、災害復旧等に係る工事を十分に実施できないところが数多くあり、県においても、膨大な事業を抱えて、工事の実施が極めて困難となっている状況が発生した。
既存制度によっても、地方自治法に基づき他の地方公共団体に事務を委託することは可能ではあったが、規約を定めて議会の議決を経る必要があり、国に委託する場合には協定の締結等が必要になるとともに一部手続が委託側の地方公共団体に残ることとなるため、いずれも速やかな工事が必要な場面には馴染まないものと考えられた。また、一部の公物管理法には代行制度が設けられていたが、それも工事が高度の技術を要する等一定の要件に合致する場合に限られていた。
このため、政府では災害復旧工事の権限代行制度についての検討111が進められ、被災した地方公共団体からも国において早期に工事に着手すること等の要望112が提出されていた。
こうした状況において、一刻も早い災害復旧を実現し、被災地における住民生活の安全、安心の確保や経済社会活動の速やかな回復を図るため、国又は県が被災した地方公共団体に代わって、公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を実施できるよう新たな制度を創設する「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律」が制定されることとなった。
- 111 平野内閣府副大臣が被災者生活支援特別対策本部の下に設置された「被災地の復旧に関する検討会議」第1回会議(平成23年3月29日)後の記者会見において「権限代行制度については、必要なものは早急に法改正を行いたい。例えば河川では、国直轄管理河川と県管理河川に分かれている。県管理河川は県が復旧工事をするのが基本だが、対応できないときには国の力を借りることができる制度を用意するのもいい」旨発言。
- 112 宮城県「仙台湾沿岸仙台南部海岸の復旧について(緊急要望)」(平成23年3月30日)、宮城県「東北地方太平洋沖地震災害に関する緊急要望書」(平成23年4月2日)、北海道東北地方知事会「東日本大震災に係る要望書」(平成23年4月11日)等。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年4月22日に閣議決定、国会に提出された。同年4月27日に(衆)国土交通委員会で可決、翌28日に(衆)本会議において全会一致で可決され、同日、(参)国土交通委員会で可決、(参)本会議において全会一致で可決・成立した。
なお、本法律案は、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案と一括して審議された。
本法律は、4月29日に公布・施行された。
(3) 法概要・措置内容
国又は県は、被災した地方公共団体の長から要請があり、その地方公共団体における工事の実施体制などの実情を勘案して、必要があると認められるときには、国又は県の自らの事務の遂行に支障のない範囲内で災害復旧等に係る工事を代行することができることとされた。
代行の対象となる工事、要請する者及び代行主体は、次の表のとおりであり、基本的にそれぞれの工事の災害復旧事業及び改良復旧事業を代行主体が実施できることとされた113。
- 113 砂防工事、地すべり防止工事及び急傾斜地崩壊防止工事については、災害関連緊急事業も対象となる。また、下水道工事については、改良復旧事業は対象とならない。
| 工事 | 要請する者→代行主体 | 工事 | 要請する者→代行主体 |
| 漁港工事 | 県→国、市町村→県 | 地すべり防止工事 | 県→国 |
| 砂防工事 | 県→国 | 下水道工事 | 市町村→県 |
| 港湾工事 | 県→国 | 河川工事 | 県→国、市町村→国又は県 |
| 道路工事 | 県→国、市町村→国又は県 | 急傾斜地崩壊防止工事 | 県→国 |
| 海岸工事 | 県→国、市町村→国又は県 |
代行主体は、工事の施行に必要な調査のための土地立入権限等も代行することとされ、また、被災した地方公共団体の費用負担については、当該地方公共団体が自ら災害復旧等に係る工事を施行した場合の負担額と同額とされた。
(4) 適用実績
本法律の適用実績は、平成25年3月現在で、海岸工事が仙台海岸深沼地区海岸等8件、道路工事が宮古市二級市道沼の浜青の滝線等6件、港湾工事が大船渡港野々田地区岸壁等3件、漁港工事が気仙沼漁港等2件となっている。
(5) その後の法改正等
本法律によって創設された代行制度は、「大規模災害からの復興に関する法律」(平成25年法律第55号)において他の大規模災害にも適用できる制度として一般化され、また、個別の公物管理法においても代行制度の充実が図られ、平成28年熊本地震等における災害復旧事業に活用されている114。
- 114 平成28年熊本地震では、道路法に基づき一般国道325号について、大規模災害からの復興に関する法律に基づき県道熊本高森線等について、災害復旧事業の代行がなされている。
8. 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律(平成23年法律第34号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
市街地の復興のために都市計画決定や土地区画整理事業を行おうとする場合、それまでの間に無秩序な建築が行われると、後の事業実施等に大きな支障が生じるおそれがある。このため、公共の福祉の観点からの財産権に対する合理的な規制として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条では、市街地に災害があった場合、特定行政庁は区域を指定し、最長で2か月間、建築物の建築を制限又は禁止できることとしている。
通常、この2か月間に都市計画決定等を行うことが見込まれており、阪神・淡路大震災でも発災当初は同条による建築制限が行われたが、2か月後からは、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第7条による建築制限に移行した。
しかし、東日本大震災の被災地では、都市計画を立案して必要な手続を進めるための行政機能が麻痺し、計画案を縦覧しようにも土地の所有権等を有する者の確認をとることが事実上困難であり、宮城県からは建築基準法第84条に基づく建築制限の期間延長について要望が提出されていた115。
こうしたことから、同条の規定に関わらず、発災から最長8か月まで建築制限を延長できることとする「東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律」が制定されることとなった。
- 115 宮城県「東日本大震災に対処するための特別立法等を求める要望書」(平成23年4月8日)。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年4月22日に閣議決定、国会に提出された。4月27日に(衆)国土交通委員会で可決、翌28日に(衆)本会議において全会一致で可決され、同日、(参)国土交通委員会で可決、(参)本会議において全会一致で可決・成立した。委員会においては、財産権の制約に係る憲法上の問題等について議論がなされた116。
なお、本法律案は、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案と一括して審議された。
本法律は、4月29日に公布・施行された。
- 116 平成23年4月27日(衆)国土交通委員会において、谷公一議員による「補償なく財産権を制限することに憲法上の問題がないのか。期間が1年であっても憲法違反にならないのか」という主旨の質問に対し、内閣法制局の政府参考人から「対象区域を限定し、被災市町村の非常に厳しい実情の中で最小限の期間について建築制限を可能にするもので、憲法上は、必要かつ合理的な範囲内の制約であると考えている。実情と乖離して必要以上に制限をかけることは、財産権の制限ということで非常に問題がある」旨の答弁等がなされている。
(3) 法概要・措置内容
東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地を所轄する特定行政庁は、当該市街地の健全な復興を図るためにやむを得ない場合に、災害発生の日から6か月以内の期間に限って、指定した区域の建築を制限・禁止できることとされた。また、特に必要があると認めるときは、さらに2か月を超えない範囲内において期間を延長できることとされた。
なお、延長期間については、被災した地方公共団体が震災により失われた基本的なデータを再度整理し、避難所に分散している住民の意見を聴き、都市計画決定等を行うために必要な最小限の期間を見込んで、最長8か月と定められた。
また、対象となる区域については、被災市街地復興特別措置法第5条第1項各号に該当する区域、すなわち、相当数の建築物の滅失、不良街区の形成のおそれ等が客観的に認められる区域に限定された。
(4) 適用実績
本法律は、宮城県気仙沼市、南三陸町、女川町、石巻市、東松島市、名取市及び山元町の計7市町において適用された。これらの市町における一連の建築制限の期間及び根拠法については、次の表のとおりである。
| 宮城県 | 石巻市 | |||||||
| 気仙沼市 | 南三陸町 | 女川町 | 東松島市 | 名取市 | 山元町 | 釜地区等 | 鮎川・雄勝 | |
| 発災 2か月 |
4/8~5/11 基準法84条 |
制限なし | 4/8~5/11 基準法84条 |
制限なし | ||||
| 発災 6か月 |
5/12~11/10本法律 ※ 石巻市鮎川・雄勝は5/28から、山元町は7/1から、東松島市は10/31まで 気仙沼市・女川町は区域を一部縮小 |
|||||||
| 発災 8か月 |
9/12~ 被災市街地 復興特別措置法 |
|||||||
| 発災 8か月 以降 |
11/11~ 被災市街地復興特別措置法 ※ 東松島市は11/1から |
11/11~ 基準法 39条 |
制限なし | |||||
9. 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災においては、津波により2万haを超える農地が冠水した。早期の営農再開を図るためには、海水の侵入による塩害の除去を含め、農地及び農業用施設の復旧に緊急に取り組む必要があった。また、地域農業の再生を目指すためには、災害復旧とあわせて農用地の再編、整備、土地改良施設の改良等の対策を講じることが求められた。
しかし、既存の災害復旧事業には除塩事業が含まれていなかった。また、国が農地を災害復旧する事業もなく、被災地からは除塩対策についての国庫補助制度の創設や国による農地の災害復旧事業の実施について要望が提出されていた117。
以上のことから、除塩事業の創設等を図る「東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律」が制定されることとなった。
- 117 宮城県「東日本大震災に対処するための特別立法等を求める要望書」(平成23年4月8日)。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年4月26日に閣議決定、国会に提出された。4月30日に(衆)農林水産委員会で可決、(衆)本会議において全会一致で可決され、5月2日に(参)農林水産委員会で可決、(参)本会議において全会一致で可決・成立した。委員会においては、衆参ともに附帯決議が付された118。
なお、本法律案は、東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律案と一括して審議された119。
本法律は、5月2日に公布・施行された。
- 118 附帯決議には、我が国農林漁業における被災地域の位置付けを明確化した上で、復旧・復興へのマスタープランと工程表を示すこと、除塩に関する技術の開発・普及に努めること、また、除塩事業を土地改良事業とみなすこととしている特例措置について、恒久措置とすることを検討すること等が盛り込まれた。
- 119 東日本大震災により著しい被害を受けた地域について、海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の期日、選挙人名簿の調製等に関する特例措置を講ずるもの。土地改良法の特例に関する法律と同じく成立し、平成23年法律第44号として、同年5月2日に公布・施行された。
(3) 法概要・措置内容
津波による海水の浸入のために農用地が受けた塩害を除去するために行う除塩事業については、国、都道府県、市町村又は土地改良区が災害復旧の土地改良事業として行うことができることとされた。また、国又は都道府県が農家等からの申請によらずに災害復旧とあわせて土地改良施設の変更や区画整理の事業を行うことができることとするなど事業実施の手続が見直された。あわせて、これらの国営事業における国庫負担の嵩上げ及び都道府県営事業等に対する国の補助の嵩上げ措置が講じられた。
(4) 適用実績
本法に基づき、定川地区(宮城県石巻市及び東松島市)、仙台東地区(宮城県仙台市)、名取川地区(宮城県名取市)、亘理山元地区(宮城県亘理町及び山元町)及び南相馬地区(福島県南相馬市)において国による農地等の災害復旧事業を行ったほか、被災地域において、津波による災害に対処するための除塩等の事業が行われた。この結果、津波により被災した農地2万1,480haから公共用地等への転用が見込まれるものを除いた復旧対象農地1万9,690haについて、令和4年1月末時点において95%で営農再開が可能となった。
(5) その後の法改正等
除塩事業については、「土地改良法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第39号)によって、土地改良法(昭和24年法律第195号)上の災害復旧事業として位置付けられ、他の災害においても適用される恒久措置となった。
10. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災では、地震や津波によって約2,000万トンの災害廃棄物が発生し、被災地の住民生活や経済活動の一刻も早い復興に向けて、これらの迅速かつ適切な処理が喫緊の課題となった。しかし、その処理を行うこととされていた市町村の中には、運搬車両や作業人員の不足等から進捗が遅れている地域があり、県内外の広域的な処理体制の構築が課題となっていた。
このため、政府においては国の直轄事業とする特例措置等について議論がなされ120、一方、自由民主党においては処理費の全額国庫負担等を内容とする法整備の検討が進められた。また、被災した地方公共団体からも国が直轄で災害廃棄物を処理すべき等の要望が提出されていた121。
- 120 平成23年5月8日のNHK番組において仙谷由人官房副長官から「国が直轄事業として災害廃棄物を処理する特例措置について議論している」旨発言。
- 121 宮城県「東日本大震災に対処するための追加予算措置等を求める要望書」(平成23年5月20日)等。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
平成23年7月1日に自由民主党、公明党、みんなの党及びたちあがれ日本の共同提案により、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案」(以下「野党案」という。)が衆議院に提出された。また、同月8日には、政府において、「東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案」(以下「政府案」という。)が閣議決定され、同、国会に提出された。
両法律案については、7月28日に(衆)本会議において趣旨説明及び質疑が、その後、(衆)東日本大震災復興特別委員会において、8月2日に質疑が行われたが、これらの一本化が図られ、同月9日に「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案」122起草案が提出されて、全会一致により委員会提出法律案となった。
なお、政府案と野党案の主な違いとしては、①国の責務規定等の有無、②代行主体、③費用負担のあり方がある。
このうち、①については、野党案にあった国の責務等が基本的に委員会提出法律案にも盛り込まれることとなった。
②については、政府案では環境大臣、野党案では国と規定されていたところ、委員会提出法律案では環境大臣と規定されることとなった。ただし、政府案にはなかった「環境大臣が災害廃棄物の処理を行うときには、東日本大震災復興対策本部の総合調整の下、関係行政機関の長と連携協力する」旨の規定が追加された123。
③について、災害廃棄物の処理が代行されるときには、政府案では市町村は自ら処理した場合と同額を負担すること、野党案では国が全額を負担することとされていた。また、市町村が自ら処理した場合の費用負担について、政府案では国は必要な財政上の措置を講ずるよう努めること、野党案では国が全額を補助することとされていたところ、委員会提出法律案では基本的に政府案としつつ、市町村の負担を軽減するため、地域グリーンニューディール基金を活用する旨の規定が追加された。
起草案採決後「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する件」が決議された124。
本法律案は、8月11日に(衆)本会議において全会一致で可決、(参)東日本大震災復興特別委員会でも可決され、翌12日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。
本法律は、8月18日に公布・施行された。
- 122 平成23年7月1日に自由民主党、公明党、みんなの党及びたちあがれ日本から提出された法律案と名称は同じだが、別の法律案である。
- 123 野党案が代行主体を国とした趣旨について、平成23年7月28日(衆)本会議で提案者の小里泰弘議員からは「当面の主体は環境省だが、復興庁設置後は同庁が主体となることを期待する。それまでは、復興対策本部が総合調整を図り、国土交通省等も効率的に活用する体制整備を求めるもの」である旨答弁がなされている。
- 124 決議には「災害廃棄物の処理に関する措置を講ずるに当たっては、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体の意向を最大限に尊重すること」「災害廃棄物処理事業に係る国庫補助を控除した地方の一時負担分について、グリーンニューディール基金を通じた支援により、国の実質負担額を平均95%とし、残りの地方負担額についても全額交付税措置を行い、実質的に100%国の支援とすること」「東日本大震災により特にその処理が必要となった廃棄物のうち、放射性物質によって汚染された廃棄物の処理に関しては、特段の配慮を要することに鑑み、必要な措置を講ずること」等が盛り込まれた。
(3) 法概要・措置内容
国の責務として災害廃棄物の処理に関する基本的な方針及び工程表を定めること等が、国が講ずべき措置として災害廃棄物に係る仮置場及び最終処分場の早急な確保のための広域的協力の要請等が定められた。
また、環境大臣は、震災により甚大な被害を受けた市町村の長から要請があり、当該市町村の災害廃棄物の処理の実施体制、専門的な知識・技術の必要性、広域的な処理の重要性を勘案して、必要があると認められるときは、東日本大震災復興対策本部の総合調整の下、関係行政機関の長と連携協力して、当該市町村に代わって災害廃棄物の処理を行うこととされた。
費用負担については、上述のとおり規定された。
(4) 適用実績
本法律が施行された時点で、すでに岩手県及び宮城県においては、市町村と県とが連携して災害廃棄物の処理に当たる方針が固まっていたため、国による代行処理はなされなかった。一方、福島県においては、相馬市、新地町、南相馬市及び広野町の災害廃棄物について、国による代行処理がなされた。
(5) その後の法改正等
復興庁設置法(平成23年法律第125号)により、環境大臣が代行する際の「東日本大震災復興対策本部の総合調整の下」という規定は、「復興庁の設置後は「復興庁の長である内閣総理大臣の総合調整の下」」と改められた。
また、災害廃棄物の処理の代行制度については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律」(平成27年法律第58号)によって、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に位置付けられ、他の災害においても適用される恒久措置となった。
11. 津波対策の推進に関する法律(平成23年法律第77号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
津波による人的被害は、迅速かつ適切な行動によって相当程度軽減することができるため、津波に関する国民の理解と関心を深めることが特に重要である。しかし、従来、津波対策については、災害対策基本法等において他の災害と一体的に規定されているに過ぎなかった。
東日本大震災を受けて、これまでの津波対策が必ずしも十分でなかったことを国として率直に反省し、津波に関する最新の知見及び先人の知恵、行動その他の歴史的教訓を踏まえつつ、津波対策に万全を期することが求められた。
以上のことから、津波災害の特性に対応した法整備として、「津波対策の推進に関する法律」が制定された。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
平成22年6月11日に自由民主党及び公明党から「津波対策の推進に関する法律案」が衆議院に提出された125。その後、東日本大震災の発生を受けて、平成23年6月9日に(衆)災害対策特別委員会において、同法案は撤回、各党合意を得た「津波対策の推進に関する法律案」起草案が提出され、全会一致により委員会提出法律案となった。
委員会提出法律案においては、平成22年の法律案に加えて、前文、事業者及び国民の津波対策に協力する努力義務、津波からの迅速かつ円滑な避難を確保するための措置、危険物を扱う施設の津波からの安全の確保等が規定された。
また、起草案採決後、「津波対策の推進に関する件」が決議された。
本法律案は、同年6月10日に(衆)本会議において全会一致で可決、同月15日に(参)災害対策特別委員会でも可決され、同月17日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。
本法律は、6月24日に公布・施行された。
- 125 本法律案は、平成22年チリ地震による津波の際、住民避難が必ずしも円滑になされなかったことを受けて、津波に対する国民の意識を喚起すること等を目的として提出されたもの。
(3) 法概要・措置内容
前文において、これまでの津波対策が必ずしも十分でなかったことを国として率直に反省し、津波対策に万全を期する必要がある旨規定された。
また、第1条以下では、津波対策の推進についての基本的認識が示され、国及び地方公共団体は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)等に基づく災害対策に当たっては、本法律の趣旨及び内容を踏まえ、津波対策を適切に実施しなければならないこととされた。
さらに、ソフト面の努力義務として、国に対しては津波対策に係る連携協力体制の整備等、国及び地方公共団体に対しては津波に関する防災教育・訓練の実施や迅速・円滑な避難を確保するための措置を講ずること等、地方公共団体に対してはハザードマップの作成等による津波被害についての周知等が定められた。
なお、国は地方公共団体がハザードマップを作成等する場合には必要な財政上の援助を行うことと規定され、当該規定は、平成29年3月31日限り、その効力を失うこととされた。
ハード面の努力義務としては、国及び地方公共団体に対して津波対策のための施設の整備等、地方公共団体に対して津波対策に配慮したまちづくりの推進等が定められた。
また、津波対策についての国民の理解と関心を深めるため、11月5日を津波防災の日とすることとされた126。
- 126 11月5日は、安政元(1854)年、安政南海地震の発生日。紀伊国広村(現和歌山県広川町)の郷士浜口梧陵が収穫した稲を積み上げていた稲むらに火を放ち、地震による津波の襲来を住民に知らせて、多くの人々の命を救った故事「稲むらの火」が知られている。
(4) その後の法改正等
津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第3号)により、国及び地方公共団体に対して津波対策における情報通信技術の活用の努力義務が課せられるとともに、国は地方公共団体がハザードマップを作成等する場合には必要な財政上の援助を行うこととする規定の効力を令和9年3月31日まで延長する等の改正がなされた。
12. 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)
13. 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第124号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災では、我が国における観測史上最大のマグニチュード9.0という巨大な地震と津波により、多くの死傷者・行方不明者が出るとともに、地域全体が壊滅的被害を受けるなど未曽有の災害となり、「災害には上限がない」こと、このような大規模な津波による災害を克服するためには、海岸堤防等の整備といった従来からのハード施策とともに、避難体制の整備等のソフト施策を適切に組み合わせる多重的な防御を講じる必要があるとの認識が共有された127。復興構想会議の提言128では、同様の認識が示されるとともに、「津波により壊滅的な被害を受けた地方公共団体や、今後大規模な津波の襲来が想定される地方公共団体において、津波災害に強い地域づくりを推進するに当たっての基本となる新たな一般的な制度を創設し、津波災害に強い地域づくりの考え方を国が示す必要がある」とされた。また、中央防災会議の専門調査会中間とりまとめ129では、今後の津波対策を構築するに当たっては、発生頻度は極めて低いものの発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスのレベル(住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で設定する津波)と、発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらすレベル(防波堤など構造物によって津波の内陸への侵入を防ぐ海岸保全施設等の建設を行う上で想定する津波)の二つのレベルの津波を想定する必要があるとされた。こうした新たな津波防災まちづくりの考え方について早期に方向性を示すべく、社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会計画部会(国土交通省)が検討を行い、平成23年7月6日に緊急提言「津波防災まちづくりの考え方」を示した130。
こうした新たな津波防災の考え方に立脚し、ハード・ソフト施策を総動員し、多重防御による津波防災地域づくりを総合的に推進するために必要な法制度として「津波防災地域づくりに関する法律」が制定されるとともに、あわせて、「津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」において、水防法等の関係法令においても新たな津波対策の考え方に基づいた制度が創設されることとなった。
- 127 No.11津波対策の推進に関する法律(平成23年6月24日公布・施行)では、津波の人命被害は適切な避難等で相当程度軽減できる等の基本的認識が示された。
- 128 なお、『復興への提言~悲惨のなかの希望~』(平成23年6月25日東日本大震災復興構想会議)。また同提言では、「大自然災害を完全に封ずることができるとの思想ではなく、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方」、「たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるような観点」が重要であるとし、防潮堤等の構造物に頼る防御から、「逃げる」ことを基本とする防災教育の徹底やハザードマップの整備など、ソフト面の対策を重視するとともに、防潮堤等に加え、交通インフラ等を活用した地域内部の第二の堤防機能(いわゆる二線堤)、土地のかさ上げ、避難地・避難路・避難ビル、災害リスクを考慮した土地利用・建築規制を一体的に行うなど、ソフト・ハードの施策を総動員の必要性が指摘されていた。
- 129 中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会中間とりまとめ~ 今後の津波防災対策の基本的考え方について ~」平成23年6月26日
- 130 平成23年5月18日に同計画部会で示された国土交通大臣からの問題意識に応えるもの。「なんとしても人命を守る」という考え方に基づき、「1)地域ごとの特性を踏まえ、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせ、総動員させる「多重防御」の発想による津波防災・減災対策」「2)従来の、海岸保全施設等の「線」による防御から、「面」の発想により、河川、道路や、土地利用規制等を組み合わせたまちづくりの中での津波防災・減災対策」「3)避難が迅速かつ安全に行われるための、実効性のある対策」といったような新たな発想による津波防災まちづくりのための施策を計画的、総合的に推進する仕組みを構築することが提言された。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
両法律案は、いずれも平成23年10月28日に閣議決定、国会に提出され、一体的に国会において審議された。同年11月29日、(衆)国土交通委員会において可決され、12月1日、(衆)本会議において全会一致で可決された。同年12月6日、(参)国土交通委員会において可決され、12月7日、(参)本会議で可決・成立した。衆参の国土交通委員会の採決に際しては、いずれも両法律案に対して附帯決議が付されており、津波対策に関する基本法ともいうべき「津波対策の推進に関する法律」に定められた施策が推進されるよう十分配慮すること、海岸堤防の整備も着実に推進すること、津波浸水想定の設定や避難施設等の確保に対して国が十分に支援を行うこと等が盛り込まれた131。
本法律は、同年12月14日に公布、12月27日に施行された。
- 131 国会審議においては、避難施設等への国の財政支援の必要性、津波災害特別警戒区域に設定される地価下落への懸念等の議論があった。
(3) 法概要・措置内容
〇 津波防災地域づくりに関する法律
ハード・ソフトの施策を組み合わせた多重防御による津波に強い地域づくりを推進するため、新法が制定され、主に下記の規定が設けられた。
① 国土交通大臣は、基本指針を定めなければならない。
② 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、基礎調査を行い、津波浸水想定(津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深)を設定するものとする。
③ 市町村は、津波防災地域づくりを総合的に推進するための推進計画を作成することができる。推進計画区域内における特例措置としては、
(ⅰ)土地区画整理事業において、防災性の高い市街地の整備を促進するため、津波防災住宅等建設区(事業の施行区域内で、嵩上げや高台切土等の安全対策を講じられる土地)を設定できることとし、設定された場合は、住宅や公益的施設の所有者が、換地先を同区内とするよう申し出ることができる旨の特例(照応の原則の例外)
(ⅱ)容積率算定の際に、津波避難に資する一定の建築物について、自家発電設備室や災害用備蓄倉庫等の部分について、建築審査会を経ずとも特定行政庁の認定により不算入とできる特例
(ⅲ)一定の場合に、防災安全集団移転促進事業の事業計画を都道府県知事が例外的に定めることができることとする特例
を規定。
④ 津波が発生した場合に都市機能を維持する拠点となる市街地整備に含まれる施設を一団の都市施設ととらえた「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」として、都市計画に定めることができることとし、全面買収方式での整備を可能とする。
⑤ 発生頻度が極めて低い最大クラスの津波が遡上した場合にその浸水の拡大を防ぐために内陸に設ける盛土構造物、閘門等を新たに「津波防護施設」と定め(比較的発生頻度の高い津波に対して整備される海岸保全施設等とは別物)、都道府県知事又は市町村長を管理者として指定する(国庫補助の対象となる)。
⑥ 都道府県知事が、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を津波災害警戒区域(イエローゾーン)として指定でき、このうち一定の開発行為及び建築を制限すべき土地の区域を津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)として指定できることとする。後者の区域内においては、社会福祉施設、病院、学校に一定の開発規制がかかるほか、市町村長は、市町村条例で定める区域(レッドゾーン)内について住宅等の規制を追加できる。
○ 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
新しい津波防災の考え方に対応するため、水防法、気象業務法等について、下記の改正が行われた。
① 水防法
水防法は、水災害一般に対し、水防組織や水防活動等のソフト面を中心に規定している法律であるが、津波への対策強化に係る改正と、津波以外の水災にも共通する要素に関する改正が行われた。
・ 法律上「津波」を明確に位置付けるとともに、水防管理者等の巡視の対象に「津波防護施設」を追加。
・ 水防計画について、津波発生時における水防活動に従事する者の安全確保に配慮されなければならない旨を追加。
・ 氾濫時の都道府県知事により立退きの指示について、津波が含まれること、氾濫開始以前も含まれることを明確にしつつ、指示の対象を、居住者だけでなく、滞在者等も追加。
② 気象業務法
気象庁は、航空機や船舶、水防活動のための予報・警報をしなければならないとなっており、水防法の改正も踏まえ、洪水・高潮に加えて津波もその対象に追加。
③ その他、土地収用法や建築基準法等において、津波防護施設や擁壁に関する手続を迅速化する等の規定を追加。
(4) 適用実績
本法律に基づき、平成23年12月27日に「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針」が国土交通大臣により策定された。なお、より詳細なガイドラインとして、「津波防災地域づくり推進計画作成ガイドライン」が平成28年に策定、平成30年に改訂されるほか、自治体による計画作成等を支援するため、手引きや事例集作成、支援チーム組成、研修等が行われた。
津波浸水想定の設定、津波災害警戒区域の指定及び推進計画の作成状況は、下記の通り。
(令和4年3月31日時点)
津波浸水想定設定済み(38道府県) (※津波浸水想定設定対象外(7県))
津波災害警戒区域指定済み(20道府県)、うち津波災害特別警戒区域指定済み(静岡県)
推進計画策定済み(17市町村)
東日本大震災の被災地における復興まちづくり事業においては、以下の適用実績がある。
「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」 24件
(岩手県陸前高田市高田南地区、宮城県気仙沼市朝日町地区等)
(5) その後の法改正等
本法律によって創設された「一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画の策定」は、「大規模災害からの復興に関する法律」(平成25年法律第55号)において他の大規模災害にも適用できる制度として一般化されている。
また、「集団移転促進事業に関する特例」についても、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律」(昭和47年法律第132号)の改正により一般化されている。
14. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)
2章4節3.で記載。
15. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号)
2章4節3.で記載。
16. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
地方財政の負担の緩和又は被災者に対する特別の助成が特に必要と認められる災害については、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号。以下「激甚災害法」という。)に基づき、当該災害を激甚災害として指定し、地方公共団体等による災害復旧事業等への国庫補助率の嵩上げや中小企業事業者への保証の特例など特別の財政援助や助成措置が講じられる激甚災害制度が設けられている132。
しかし、東日本大震災については、その被害の甚大さから、同制度の対象とはなっていない施設の復旧等に対する財政援助、いわゆる激甚災害法の「横出し」や被災者等への特別の助成を講ずることとする立法措置が求められた。このため、地方公共団体に対する財政援助や被災者のための社会保険料の減免、中小企業者に対する金融上の支援等の特別の助成措置について定める「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が制定されることとなった。
なお、阪神・淡路大震災についても、同様の趣旨から「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成7年法律第16号。以下「阪神・淡路財特法」という。)が制定されている。
- 132 東日本大震災についても、発災翌日の平成23年3月12日に「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が閣議決定、翌13日に公布され、激甚災害に指定されている。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年4月26日に閣議決定、国会に提出された。4月30日に(衆)災害対策特別委員会で可決、(衆)本会議において全会一致で可決され、5月2日に(参)災害対策特別委員会で可決、(参)本会議において全会一致で可決・成立した。委員会においては、被災者生活再建支援金の支給、災害廃棄物の処理への財政支援、原子力災害への本法律案の適用、激甚災害法の見直し等について議論がなされた133。
本法律は、5月2日に公布・施行された。
- 133 平成23年5月2日(参)災害対策特別委員会では、市町村による災害廃棄物の処理については、本法律案による最大9/10までの補助率嵩上げと交付税措置によって、実質的に地方負担はゼロになる旨答弁がなされた。また、原子力災害からの復旧等について、本法律案は原子力災害による被害にも適用できるが、それが原子力事業者の賠償責任を軽減させるものではない旨答弁がなされている。なお、激甚災害法の見直しについては、災害の都度、諸制度の隙間や国及び地方公共団体の財政状況等も勘案し、予算ともあわせて国会の判断を仰ぐことが適切と考えている旨答弁された。
(3) 法概要・措置内容
第一に、「地方公共団体等に対する特別の財政援助」として、公共土木施設や社会福祉施設等の復旧、災害廃棄物の処理などへの補助等について、被災した地方公共団体の財政力と被害の状況に踏まえ補助率を嵩上げすることとした。特に公共土木施設については対象となる事業の負担額を合算し、標準税収入と比較することによって段階的に補助率を決定する、いわゆる総合負担軽減方式が採用された。
これらの措置は24項目にわたり134、阪神・淡路財特法による19項目には含まれなかった集落排水施設、災害廃棄物の処理、被災した市町村の臨時庁舎等に係る措置も追加された。
こうした「地方公共団体等に対する特別の財政援助」の対象となる地域として、特定被災地方公共団体が定められ、都道府県については、災害救助法の適用があった県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県)とされた。
また、市町村については、東日本大震災135に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)が適用136された市町村のうち、以下のいずれかに該当する市町村を政令で定めるものとされた137。
・震度6弱以上
・住宅の全壊戸数が一定規模以上138
・津波予報区内の最大津波観測値が2.4m以上であり、浸水被害が確認されている
・公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が5%超139
第二に、社会保険の加入者等についての負担の軽減について、被災者、事業主に対する社会保険料の免除、被災者の医療費窓口負担等の免除、行方不明者の死亡推定による遺族年金等の速やかな支給等の措置を講ずることとした。
第三に、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等について、被災した農業、漁業者及び中小企業者に対する信用保険の保険てん補率の拡充、政策金融の償還期間の延長等を行うこととした。
その他、地方債の発行の特例措置など幅広い特別の措置を講ずることとした。
なお、上記の第二、第三及びその他の措置をあわせた「被災者等に対する特別の助成措置」は、阪神・淡路財特法による59項目に対して、116項目に及んだ。
これらの「被災者等に対する特別の助成措置」の対象地域として、特定被災区域が定められ、当該区域については、東日本大震災に際して災害救助法が適用された市町村及びこれに準ずる区域として被災者生活再建支援法の適用対象地域(全壊世帯数が0のものを除く)のうち、政令で定めるものとされた。
なお、本法律の執行経費を含む平成23年度一般会計補正予算(第1号)が、平成23年4月22日に閣議決定され、同月28日に国会提出、同年5月2日に(参)本会議において全会一致で可決・成立している140。
- 134 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年法律第87号)によって、被災者生活再建支援金に係る補助の特例が創設され、最終的には25項目となる。
- 135 東日本大震災は、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害」と定義されているが、対象とする地震には3月12日に発生した長野県北部の地震も含まれる。それぞれの地震の震源の位置、発生メカニズムは異なるものの、東北地方太平洋沖地震に伴い、大きな地殻変動が観測され、概ね東西方向に伸張、南北方向に圧縮するひずみを広範囲に与えており、現在の科学的知見でその関連性については他の地域への地震発生への影響を与える可能性が否定できないため、本法律上は、一連の災害として扱うこととされた。
- 136 帰宅困難者対応のための災害救助法の適用は除く。
- 137 特定被災地方公共団体には、特別の財政援助が行われるため、本来は被害額と当該市町村の税収を比較し、負担の大きなものを選定すべきであった。しかし、東日本大震災では、広範囲に甚大な被害が発生しており、地方公共団体ごとの具体的な被害額の把握には相当の期間を要すると考えられた。一方、被災地における応急復旧等のためには、迅速に特別の財政援助を講ずる必要があったことから、特定被災地方公共団体の選定に当たっては、上記のとおり、地元負担額と税収との比較に加えて、災害外形的規模、現時点で把握されている被害等も基準とすることとされた。
- 138 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)別表第三に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村とされた。当該別表では市町村の区域内の人口規模に応じて住家が滅失した世帯の数が定められている。なお、半壊は2戸をもって全壊1戸とされる。
- 139 当該基準については、平成23年8月12日に「査定事業費が確定していない段階においては、査定後明らかに該当すると見込まれること(早期局激の指定と同様に基準の2倍で運用。)」が追加された。すなわち、査定事業費の見込額による地元負担額の標準税収入割合が10%超であれば、基準に該当することとされた。
- 140 東日本大震災からの早期復旧に向け4兆153億円を計上。内訳としては、災害廃棄物処理事業費3,519億円、災害対応公共事業関係費12,019億円(道路、港湾、空港施設、水道、下水道等の復旧経費)、施設費災害復旧費等4,160億円(学校施設、介護・医療施設、警察・消防施設等の復旧経費)、災害関連融資関係経費6,407億円、その他東日本大震災関係経費8,018億円等。
(4) その後の法改正等
平成23年7月29日に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年法律第87号)が公布・施行され、被災者生活再建支援金補助金について、東日本大震災に限り、既に支給した支援金を含め国の補助率が50%から80%に引き上げられる措置が本法律に追加された141。
また、平成23年8月12日に公布・施行された「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年法律第96号)によって、原子力発電所事故災害に対処する固定資産税等の課税免除などによる減収額を埋めるため、地方債を起こすことができるものとする特例措置等が本法律に追加された142。
- 141 補助率を50%から80%に引き上げることに伴い、関連予算として、平成23年度一般会計補正予算(第2号)(平成23年7月25日成立)に被災者生活再建支援金補助金3,000億円が計上された。また、地方負担となる残りの20%についても、同補正予算によって増額される特別交付税で全額を手当てすることとされた。
- 142 本法律制定時から、地方債に係る特例措置等は規定されており(第9条等)、平成23年法律第96号による追加措置はこれらの特例の拡充とみなせるため、「被災者等に対する特別の助成措置」の項目数については、同法による改正後も変更はない。
(5) 措置一覧(平成23年7月29日現在)
① 地方公共団体等に対する特別の財政援助[24項目(阪神・淡路19項目)]
※ (ⅲ)公共施設にある公的医療機関と(ⅳ)民間施設にある民間医療機関はあわせて1項目としてカウントしている。
| 東日本大震災財特法 | (参考)阪神・淡路財特法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 条 | 現行の原則 | 財特法特例 | 現行の原則 | 財特法特例 |
| 水道施設の補助特例 | 3 | 1/2(予算)【水道法】 | 8/10~9/10 | 1/2(予算)【水道法】 | 8/10 |
| 工業用水道施設の補助特例 | 3 | 45/100(予算)(激甚指定かつ震度6以上の場合8/10)【工業用水道事業法】 | 45/100(予算)【工業用水道事業法】 | 8/10 | |
| 改良住宅等の補助特例 | 3 | 1/2(予算)【住宅地区改良法】 | 1/2(予算)【住宅地区改良法】 | 8/10 | |
| 交通安全施設等の補助特例 | 3 | 1/2(法律)【警察法、交通安全施設等整備事業推進法】 | 1/2(法律)【警察法、交通安全施設等整備事業推進法】 | 8/10 | |
| 都市施設の補助特例 | 3 | 1/2(予算)【都市計画法】 | 1/2(予算)【都市計画法】 | 8/10 | |
| 廃棄物処理施設の補助特例 | 3 | 1/2(予算)【廃掃法】 | 1/2(予算)【廃掃法】 | 8/10 | |
| 集落排水施設の補助特例 | 3 | 1/2予算補助(予算)(激甚指定かつ標税割合10%を超えると8/10)※ 施設定義の法律はない | 1/2予算補助(予算)※ 施設定義の法律はない | ― | |
| 東日本大震災財特法 | (参考)阪神・淡路財特法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 条 | 現行の原則 | 財特法特例 | 現行の原則 | 財特法特例 |
| 老人福祉施設等の補助特例 | 48 | 1/2(予算)【老人福祉法】 | 2/3 | 1/2(予算)【老人福祉法】※ | 2/3※ |
| 地域包括支援センター・ 介護老人保健施設の補助特例 |
48 | 地域包括支援センター 1/2(予算)【介護保険法】 介護老人保健施設 1/3(予算)【介護保険法】 |
2/3 1/2 |
― 1/3(予算)【老人保健法】 |
― ― |
| 障害者支援施設等の補助特例 | 48 | 1/2(予算) 【障害者自立支援法】 |
2/3 | 1/2(予算) 【知的障害者福祉法等】 |
2/3 |
| 社会事業授産施設の補助特例 | 48 | 1/2(予算)【社会福祉法】 | 2/3 | 同左 | 同左 |
| 身体障害者社会参加支援施設の補助特例 | 48 | 1/2(予算) 【身体障害者福祉法】 |
2/3 | 同左 | 同左 |
| 東日本大震災財特法 | (参考)阪神・淡路財特法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 条 | 現行の原則 | 財特法特例 | 現行の原則 | 財特法特例 |
| 警察施設 | 4 | 1/2(法律)【警察法】 | 2/3 | 同左 | 同左 |
| 市町村の仮庁舎等 | 6 | ― | 2/3 | ― | ― |
| 消防施設 | 7 | 1/3(法律)【消防施設強化促進法】 1/2(政令)【【緊急消防援助隊に関する政令】 |
2/3 | 同左 | 同左 |
| 保健所 | 44 | 1/2(予算)【地域保健法】 | 2/3 | ― | ― |
| 火葬場 | 45 | 1/2(予算)【墓埋法】 | 2/3 | 同左 | 同左 |
| 公的医療機関 | 46 | 精神科以外1/2(予算) 精神科 1/2(法律) 【医療法・精神保健福祉法】 |
2/3 | 精神科以外1/2(予算) 精神科 1/2(法律) 【医療法・精神保健福祉法】 |
2/3(公立病院に限る。) |
| と畜場 | 47 | 1/2(予算)【と畜場法】 | 2/3 | 同左 | 同左 |
| 中央卸売市場 | 106 | 4/10(法律)【卸売市場法】 | 2/3 | 同左 | 同左 |
| 東日本大震災財特法 | (参考)阪神・淡路財特法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 条 | 現行の原則 | 財特法特例 | 現行の原則 | 財特法特例 |
| 民間医療機関 (救急医療等、精神科病院) |
46 | 救急医療等 1/2(予算) 精神科 1/2以内(法律) 【医療法・精神保健福祉法】 |
1/2 | 救急医療 ― 精神科 1/2以内(法律) 【医療法・精神保健福祉法】 |
1/2(救急医療は病院に、精神科は指定病院に限る) |
| 商店街振興組合等の共同施設 | ― | ― | ― | ― | 1/2 |
| 東日本大震災財特法 | (参考)阪神・淡路財特法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 条 | 現行の原則 | 財特法特例 | 現行の原則 | 財特法特例 |
| 被災者生活再建支援金 | 5条の2 | 1/2(法律) 【被災者生活再建支援法】 |
8/10 | ― | ― |
| 神戸港埠頭公社の管理する 外貿埠頭、フェリー埠頭の岸壁 |
― | ― | ― | ― | 8/10 |
| 宮城県フェリー埠頭公社の 管理する岸壁等 |
135 | 建設、改良に係る無利子貸付(災害復旧を含まず) 【港湾法】 |
無利子貸付 | 建設、改良に係る無利子貸付(災害復旧を含まず) 【港湾法】 |
神戸港埠頭公社に対する補助及び無利子貸付 |
| 仙台空港の滑走路等 | 136 | 80/100【空港法】 | 85/100 | ― | ― |
| 仙台空港旅客ターミナルビル | 137 | ― | 県に対する無利子貸付 | ― | ― |
| 災害廃棄物処理(ガレキ処理) | 139 | 1/2【廃掃法】 | 1/2~8/10~9/10 | 1/2【廃掃法】 | ― |
② 被災者等に対する特別の助成措置[116項目(阪神・淡路59項目)]
| 東日本大震災財特法 | (参考)阪神・淡路財特法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 条 | 現行の原則 | 財特法特例 | 現行の原則 | 財特法特例 |
| 歳入欠かん債及び災害対策債の発行可能年度の特例 | 8 | 災害の発生した日の属する年度に限り、歳入欠かん債及び災害対策債を発行可能 【災害対策基本法】 |
23年度以降も発行可能(期限は政令で定める)(国が財政融資資金で引受け) | 災害の発生した日の属する年度に限り、歳入欠かん債及び災害対策債を発行可能 【災害対策基本法】 |
6年度及び7年度に発行可能(1年延長) |
| 地方債の特例 | 9 | ― | 地方税法改正法等による地方税等の減収額を埋めるための地方債発行を可能とした上で基準財政収入額の算定方法の特例を設ける(国が財政融資資金で引受け) | ― | ― |
| 基準財政収入額の算定方法の特例 | 10 | ― | ― | ― | |
| 東日本大震災財特法 | (参考)阪神・淡路財特法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 条 | 現行の原則 | 財特法特例 | 現行の原則 | 財特法特例 |
| 一般会計から漁船再保険及び漁業共済保険特別会計への特例繰入れ | 34 | ― | 一般会計から漁船再保険及び漁業共済保険特別会計への特例繰入れ | ― | ― |
| 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の積立金の特例 | 35 | ― | 積立金の年度途中での取崩しを可能とする | ― | ― |
| 日本政策投資銀行の危機対応業務に備えた財務基盤強化 | 36 | 政府からの出資、交付国債の交付等は平成24年3月末まで(以降は不可) 【政投銀法】 |
政府からの出資期間の延長(3年間) 交付国債の交付・償還・返還期間の延長(3年間) |
― | ― |
| 災害援護資金の償還期間の延長等 | 103 | 償還期間 10年以内 貸付利率 3% 【災害弔慰金法】 |
償還期間 13年以内 貸付利率 無利子(保証人を立てない場合は1.5%) |
― | ― |
| 中小漁業融資保証保険の填補率引上げ | 109 | 保証保険・融資保険の填補率 7/10 【中小漁業融資保証法】 |
保証保険・融資保険の填補率 9/10 | ― | ― |
| 農業改良資金の償還期間等の延長 | 110 | 償還期間 10年以内 据置期間 3年以内 【農業改良資金融通法】 |
償還期間 13年以内 据置期間 6年以内 |
― | ― |
| 農業近代化資金の償還期間等の延長 | 111 | 償還期間 20年以内 据置期間 7年以内 【農業近代化資金融通法】 |
償還期間 23年以内 据置期間 10年以内 |
― | ― |
| 農業信用保証保険の填補率引上げ | 112 | 保証保険・融資保険の填補率 7/10【農業信用保証保険法】 | 保証保険・融資保険の填補率 9/10 | ― | ― |
| 漁業近代化資金の償還期間等の延長 | 113 | 償還期間 20年以内 据置期間 3年以内 【漁業近代化資金融通法】 |
償還期間 23年以内 据置期間 6年以内 |
― | ― |
| 林業・木材産業改善資金の償還期間等の延長 | 114 | 償還期間 10年以内 据置期間 3年以内 【林業・木材産業改善資金助成法】 |
償還期間 13年以内 据置期間 6年以内 |
― | ― |
| 沿岸漁業改善資金の償還期間等の延長 | 115 | 償還期間 10年以内 据置期間 3年以内 【沿岸漁業改善資金助成法】 |
償還期間 13年以内 据置期間 6年以内 |
― | ― |
| 林業経営基盤強化法に関する資金の償還期間等の延長 | 116 | 償還期間 55年以内 据置期間 35年以内 【林業経営基盤強化等促進資金融通等暫定措置法】 |
償還期間 58年以内 据置期間 38年以内 |
― | ― |
| 担い手育成農地集積資金の償還期間等の延長 | 117 | 償還期間 25年以内 据置期間 10年以内 【農業経営基盤強化促進法】 |
償還期間 28年以内 据置期間 13年以内 |
― | ― |
| 就農支援資金の償還期間等の延長 | 118 | 償還期間 12年以内 据置期間5年以内 【青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法】 |
償還期間 15年以内 据置期間 8年以内 |
― | ― |
| 林業労働力確保促進法に関する資金の償還期間の延長 | 119 | 償還期間 15年以内 【林業労働力確保促進法】 |
償還期間 18年以内 | ― | ― |
| 持続性の高い農業生産方式導入促進法による資金の償還期間の延長 | 120 | 償還期間 12年以内 据置期間 3年以内 【持続性の高い農業生産方式導入促進法】 |
償還期間 15年以内 据置期間 6年以内 |
― | ― |
| 日本政策金融公庫による農林漁業者等に対する貸付の償還期間等の延長 | 121 | 償還期間 15-35年 据置期間 3-30年 【日本政策金融公庫法】 |
償還期間・据置期間を各々3年間延長 | ― | ― |
| 中小企業者と農林漁業者との連携促進法による資金の償還期間等の延長 | 122 | 償還期間 12年以内 据置期間 5年以内 【中小企業者と農林漁業者との連携促進法】 |
償還期間 15年以内 据置期間 8年以内 |
― | ― |
| 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用促進法による資金の償還期間等の延長 | 123 | 償還期間 12年以内 据置期間 3年以内 【農林漁業有機物資源のバイオ燃料原材料としての利用促進法】 |
償還期間 15年以内 据置期間 6年以内 |
― | ― |
| 米穀の新用途への利用促進法による資金の償還期間等の延長 | 124 | 償還期間 12年以内 据置期間 3年以内 【米穀の新用途への利用促進法】 |
償還期間 15年以内 据置期間 6年以内 |
― | ― |
| 公共建築物等における木材の利用促進法による資金の償還期間の延長 | 125 | 償還期間 12年以内 【公共建築物等における木材の利用促進法】 |
償還期間 15年以内 | ― | ― |
| 地域資源活用による新事業創出及び地域の農林水産物の利用促進法による資金の償還期間等の延長 | 126 | 償還期間 12年以内 据置期間 5年以内 【地域資源活用による新産業創出及び地域農林水産物利用促進法】 |
償還期間 15年以内 据置期間 8年以内 |
― | ― |
| 中小企業信用保険法の特例 | 128 | 保険価額限度 普通:2億 無担保:8千万 小口:1,250万 填補率 普通:7割 無担保:8割 小口:8割 【中小企業信用保険法】 |
保険価額限度 普通:2億 無担保:8千万 小口:1,250万 (一般保証とは別枠) 填補率 普通、無担保、小口とも 9割 |
保険価額限度 無担保:2千万 小口:5百万 填補率 無担保、小口とも8割 【中小企業信用保険法】 |
保険価額限度 無担保:1千万 小口:1千万 (一般保証とは別枠) 填補率 無担保、小口とも9割 |
| 小企業設備導入資金助成法による資金の償還期間延長 | 129 | 償還期間 7年以内 【小企業設備資金助成法】 |
償還期間 9年以内 | 償還期間 5年以内 【中小企業近代化資金助成法】 |
償還期間 7年以内 |
| 中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等 | 130~132 | ― | 工場、事業場、周辺施設の整備、貸与 | ― | ― |
| 商工中金による中小企業者に対する貸付の特例 | ― | ― | ― | ― | 当初3年は年利3%5年を限度に国の利子補給 |
| 商工中金の危機対応業務に備えた政府出資の期限延長 | 133 | 商工中金の危機対応業務への政府出資の期限:23年度末まで 【商工中金法】 |
商工中金の危機対応業務への政府出資の期限:26年度末まで | ― | ― |
| 住宅金融支援機構による融資(宅地被害) | 138 | 災害復興住宅融資 災害により滅失・損傷した住宅の復旧に必要な資金を融資 【住宅金融支援機構法】 |
宅地のみの被害を対象とする融資の追加 | 災害復興住宅貸付 据置期間3年 受付期間2年 【住宅金融公庫法】 |
災害復興住宅貸付 阪神淡路を対象に追加据置期間5年 受付期間を一定の場合延長災害復興宅地貸付制度の創設 |
| 東日本大震災財特法 | (参考)阪神・淡路財特法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 条 | 現行の原則 | 財特法特例 | 現行の原則 | 財特法特例 |
| 恩給法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例 | 11 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 一般職の職員の給与に関する法律の適用の特例 | 12 | 行方不明職員に対する給与の精算は1年後 | 退職手当が支給される場合3月間不明で死亡と推定 | ― | ― |
| 国家公務員災害補償法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例 | 13 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 国家公務員退職手当法の適用の特例 | 14 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | ― | ― | |
| 地共済法の退職共済年金の決定の特例 | 15 | 年金の受給権は受給者本人からの請求が必要 | 特別支給の退職共済年金受給者について、受給者本人からの請求がなくとも支給可能とする | ― | ― |
| 地共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例 | ― | 一定の場合は支払いの免除が可能 | ― | ― | 一部負担金の支払い免除 |
| 地共済法の入院時食事療養費の額の特例 | 16 | 入院時食事療養費について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 地共済法の入院時生活療養費の額の特例 | 17 | 入院時生活療養費について自己負担分を控除して支給 | ― | ― | |
| 地共済法の保険外併用療養費の額の特例 | 18 | 保険外併用療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 地共済法の療養費の額の特例 | 19 | 療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 地共済法の訪問看護療養費についての特例 | ― | 一定の場合は訪問看護療養費を全額支給 | ― | 一部控除した額を支給 | 看護療養額を全額支給 |
| 地共済法の家族療養費の額の特例 | 20 | 家族療養費について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 地共済法の家族訪問看護療養費についての特例 | ― | 一定の場合は家族訪問看護療養費を全額支給 | ― | 一部控除した額を支給 | 看護療養額を全額支給 |
| 地共済法の死亡に係る給付の特例 | 21 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 地共済法の長期給付等に関する施行法の死亡に係る給付の特例 | 22 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | ― | ― | |
| 地方公務員災害補償法の死亡に係る給付の特例 | 23 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | ― | ― | |
| 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の死亡に係る給付の特例 | 25 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | ― | ― | |
| 国共済法の退職共済年金の決定の特例 | 26 | 年金の受給権は受給者本人からの請求が必要 | 特別支給の退職共済年金受給者について、受給者本人からの請求がなくとも支給可能とする | ― | ― |
| 国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例 | ― | 一定の場合は支払いの免除が可能 | ― | ― | 一部負担金の支払い免除 |
| 国共済法の入院時食事療養費の額の特例 | 27 | 入院時食事療養費について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 国共済法の入院時生活療養費の額の特例 | 28 | 入院時生活療養費について自己負担分を控除して支給 | ― | ― | |
| 国共済法の保険外併用療養費の額の特例 | 29 | 保険外併用療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 国共済法の療養費の額の特例 | 30 | 療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 国共済法の訪問看護療養費についての特例 | ― | 一定の場合は訪問看護療養費を全額支給 | ― | 一部控除した額を支給 | 看護療養額を全額支給 |
| 国共済法の家族療養費の額の特例 | 31 | 家族療養費について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 国共済法の家族訪問看護療養費についての特例 | ― | 一定の場合は家族訪問看護療養費を全額支給 | ― | 一部控除した額を支給 | 看護療養額を全額支給 |
| 国共済法の死亡に係る給付の特例 | 32 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 国共済法の長期給付に関する施行法の死亡に係る給付の特例 | 33 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | ― | ― | |
| 私学共済法の標準給与の改定の特例 | 38 | 標準給与は、給与の高低が生じた月から3か月後の月から改定 | 給与に著しく高低が生じた月からの改定を可能とする | 同左 | 同左 |
| 国共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の準用 | 39 | 年金の受給権は受給者本人からの請求が必要 | 特別支給の退職共済年金受給者について、受給者本人からの請求がなくとも支給可能とする | ― | ― |
| 国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に関する規定の準用 | 40 | 入院時食事療養費等について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 国共済法の死亡に係る給付の特例に関する規定の準用 | 41 | 行方不明者の遺族に対する死亡を給付事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 私学共済法の掛金の免除の特例 | 42 | ― | 災害地域における私立学校において、教職員に対する給与の支払いに著しい支障が生じている場合、私学共済の掛金(介護保険の第二号保険料を含む)の免除ができることとする。 | 同左 | 同左 |
| 健康保険の標準報酬月額の改定の特例等 | 49 | 標準報酬月額は、報酬に著しく高低が生じた月から3か月後の月から改定 | 報酬に著しく高低が生じた月からの改定を可能とする | 同左 | 同左 |
| 健康保険の一部負担金の支払いの免除 | ― | 一定の場合は支払いの免除が可能 | ― | ― | 一部負担金の支払い免除 |
| 健康保険の入院時食事療養費の額の特例 | 50 | 入院時食事療養費について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 健康保険の入院時生活療養費の額の特例 | 51 | 入院時生活療養費について自己負担分を控除して支給 | ― | ― | |
| 健康保険の保険外併用療養費の額の特例 | 52 | 保険外併用療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 健康保険の療養費の額の特例 | 53 | 療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 健康保険の訪問看護療養費についての特例 | ― | 一定の場合は訪問看護療養費を全額支給 | ― | 一部控除した額を支給 | 看護療養額を全額支給 |
| 健康保険の家族療養費の額の特例 | 54 | 家族療養費について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 健康保険の家族訪問看護療養費についての特例 | ― | 一定の場合は家族訪問看護療養費を全額支給 | ― | 一部控除した額を支給 | 看護療養額を全額支給 |
| 健康保険の日雇特例被保険者に係る特例 | 55 | ― | 第50条~第54条の規定について、日雇特例被保険者に準用する。 | 同左 | 同左 |
| 健康保険の特別療養費の額の特例 | 56 | 特別療養費について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 健康保険の保険料の免除の特例 | 57 | ― | 災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払いに著しい支障が生じている場合、健康保険の保険料(介護保険の第二号保険料を含む)の免除ができることとする。 | 同左 | 同左 |
| 健康保険における国庫補助の特例 | 58 | ― | 全国健康保険協会の特例措置に伴う給付費の増加分に対して、予算の範囲内で国庫補助を行う。 | ― | ― |
| 船員保険の標準報酬月額の改定の特例等 | 59 | 標準報酬月額は、報酬に著しく高低が生じた月から1か月後の月から改定 | 報酬に著しく高低が生じた月からの改定を可能とする | 同左 | 同左 |
| 船員保険法等の死亡に係る給付の特例 | 60 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 船員保険の一部負担金の支払いの免除 | ― | 一定の場合は支払いの免除が可能 | ― | ― | 一部負担金の支払い免除 |
| 船員保険の入院時食事療養費の額の特例 | 61 | 入院時食事療養費について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 船員保険の入院時生活療養費の額の特例 | 62 | 入院時生活療養費について自己負担分を控除して支給 | ― | ― | |
| 船員保険の保険外併用療養費の額の特例 | 63 | 保険外併用療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 船員保険の療養費の額の特例 | 64 | 療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 船員保険の訪問看護療養費についての特例 | ― | 一定の場合は訪問看護療養費を全額支給 | ― | 一部控除した額を支給 | 看護療養額を全額支給 |
| 船員保険の家族療養費の額の特例 | 65 | 家族療養費について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 船員保険の家族訪問看護療養費についての特例 | ― | 一定の場合は家族訪問看護療養費を全額支給 | ― | 一部控除した額を支給 | 看護療養額を全額支給 |
| 船員保険の保険料の免除の特例 | 66 | ― | 災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払いに著しい支障が生じている場合、船員保険の保険料(介護保険の第二号保険料を含む)の免除ができることとする。 | 同左 | 同左 |
| 船員保険の失業保険金支給の特例 | ― | 雇用保険制度において一定の場合はみなし失業による失業給付を支給 | ― | ― | みなし失業による失業保険金の支給 |
| 国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例 | 67 | 入院時食事療養費について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 国民健康保険の入院時生活療養費の額の特例 | 68 | 入院時生活療養費について自己負担分を控除して支給 | ― | ― | |
| 国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例 | 69 | 保険外併用療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 国民健康保険の療養費の額の特例 | 70 | 療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 国民健康保険の特別療養費の額の特例 | 71 | 特別療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 国民健康保険における国の負担等の特例 | 72 | ― | 市町村の特例措置に伴う給付費の増加分に対し予算の範囲内で国庫補助を行う。 | ― | ― |
| 後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特例 | 73 | 入院時食事療養費について自己負担分を控除して支給 | 自己負担を免除し全額支給 | 同左 | 同左 |
| 後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特例 | 74 | 入院時生活療養費について自己負担分を控除して支給 | ― | ― | |
| 後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特例 | 75 | 保険外併用療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 後期高齢者医療の療養費の額の特例 | 76 | 療養費について自己負担分を控除して支給 | ― | ― | |
| 後期高齢者医療の特別療養費の額の特例 | 77 | 特別療養費について自己負担分を控除して支給 | 同左 | 同左 | |
| 後期高齢者医療における国の負担等の特例 | 78 | ― | 後期高齢者医療広域連合の特例措置に伴う給付費の増加分に対し予算の範囲内で国庫補助を行う。 | ― | ― |
| 老人保健の訪問看護療養費についての特例 | ― | 後期高齢者医療において、一定の場合は訪問看護療養費を全額支給 | ― | 一部控除した額を支給 | 看護療養額を全額支給 |
| 労働者災害補償保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例 | 79 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 中小企業退職金共済法の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用の特例 | 80 | 行方不明者の遺族に対する退職金の支給は1年後 | ― | ― | |
| 労働保険の保険料の免除の特例 | 81 | ― | 災害地域における事業所において、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の場合、労働保険料の免除ができることとする。 | ― | ― |
| 雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例 | 82 | 解雇等離職者の基本手当の給付日数を、原則60日延長する。 | 更に60日分の個別延長給付を支給する(最大120日)。 | ― | ― |
| 石綿による健康被害の救済に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例 | 83 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 石綿による健康被害の救済のため支給される給付等に充てる一般拠出金の免除の特例 | 84 | ― | 災害地域における事業所において、労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じている等の場合、一般拠出金の免除ができることとする。 | ― | ― |
| 障害児施設給付費の支給に要する費用に係る国の負担の特例 | 85 | 都道府県等が支弁する障害児施設給付費の支給に要する費用について、国及び都道府県等がそれぞれ負担する。 | 都道府県等の災害減免の適用に伴う障害児施設給付費の支給に要する費用の増加分について国庫補助する。 | ― | ― |
| 指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助 | 86 | 指定知的障害児施設等における食費及び居住費について自己負担 | 都道府県等は指定知的障害児施設等における食費及び居住費を減免することとし、その費用の額に相当する額を国が補助する。 | ― | ― |
| 介護給付費等の支給に要する費用に係る国の負担等の特例 | 87 | 市町村が支弁する介護給付費等の支給に要する費用について、国、都道府県、市町村がそれぞれ負担する。 | 市町村の災害減免の適用に伴う介護給付費等の支給に要する費用の増加分について国庫補助する。 | ― | ― |
| 指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助 | 88 | 指定障害者支援施設等における食費及び居住費について自己負担 | 市町村は指定障害者支援施設等における食費及び居住費を減免することとし、その費用の額に相当する額を国が補助する。 | ― | ― |
| 介護給付及び予防給付に要する費用に係る国の負担等の特例 | 89 | 介護給付及び予防給付に要する額については、国、都道府県、市町村、第1、2号被保険者がそれぞれ負担する。 | 市町村の特例措置に伴う給付費の増加分について国庫補助を行う。 | ― | ― |
| 介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助 | 90 | 介護保険施設等における食費及び居住費等に関する費用について自己負担。 | 介護保険施設等における食費及び居住費等の減免分について国庫補助を行う。 | ― | ― |
| 特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助 | 91 | 特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費について自己負担。 | 特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費の減免分について国庫補助を行う。 | ― | ― |
| 特定介護老人福祉施設等における食費及び居住費に関する補助 | 92 | 特定介護老人福祉施設等における食費及び居住費について自己負担。 | 特定介護老人福祉施設等における食費及び居住費の減免分について国庫補助を行う。 | ― | ― |
| 戦傷病者戦没者遺族等援護法の死亡に係る遺族年金等の支給に関する規定の特例 | 93 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、遺族年金等の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例 | 94 | 標準報酬月額は、報酬の高低が生じた月から3か月後の月から改定 | 報酬の著しい高低があった月から標準給与を改定できることとする。 | 同左 | 同左 |
| 厚生年金保険の保険料の免除の特例 | 95 | 各被保険者の標準報酬月額の16.058%を保険料として規定し、その納付義務を事業主に課している。 | 災害地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払いに著しい支障が生じている場合、厚生年金保険料の免除ができることとする。 | 同左 | 同左 |
| 老齢厚生年金の裁定の特例 | 96 | 老齢厚生年金の支給については、受給者本人からの請求に基づいて厚生労働大臣が裁定する。 | 特別支給の老齢厚生年金受給者について、受給者本人からの請求がなくとも支給可能とする | ― | ― |
| 厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例 | 97 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 老齢基礎年金の裁定の特例 | 98 | 老齢基礎年金の支給については、受給者本人からの請求に基づいて厚生労働大臣が裁定する。 | 特別支給の老齢厚生年金受給者等について、受給者本人からの請求がなくとも支給可能とする | ― | ― |
| 国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例 | 99 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 確定給付企業年金法の遺族給付金の支給に関する規定の適用の特例 | 100 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | ― | ― | |
| 確定拠出年金法の死亡一時金の支給に関する規定の適用の特例 | 101 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | ― | ― | |
| 子ども手当の拠出金の免除の特例 | 102 | 事業所等は平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法に基づく拠出金の納付義務がある。 | 厚生年金保険料等が免除された場合、拠出金の納付義務を免除する。 | 同左 | 同左 |
| 農林漁業団体共済組合の標準給与の改定の特例 | ― | ― | ― | 標準給与の改定は4か月後になる | 標準給与を当月から改訂できる |
| 農林漁業団体共済組合の掛金免除の特例 | ― | ― | ― | ― | 被災団体の掛金免除 |
| 農林漁業団体共済の死亡に係る給付の特例 | 107 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 農業者年金の保険料の免除等の特例等 | 108 | 農業年金の被保険者は毎月保険料を納付しなければならない。 | 被保険者からの申し出に応じて、保険料を免除する。行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡一時金の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | 同左 | 同左 |
| 農業者年金の経営委譲年金の額の特例 | ― | ― | ― | ― | 保険料のみなし納付 |
| 雇用保険法による雇用安定事業等の特例 | ― | ― | ― | ― | 内定者についても雇用安定事業を適用可能 |
| 公害健康被害の補償等に関する法律の死亡に係る給付の特例 | 140 | 行方不明者の遺族に対する死亡を支給事由とする給付等は1年後 | 行方不明者の生死が3月間不明の場合、死亡を支給事由とする給付の支給規定の適用に当たっては、死亡したものと推定 | ― | ― |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律の適用の特例 | 141 | 行方不明職員に対する給与の精算は1年後 | 退職手当が支給される場合、3月間不明で死亡と推定 | ― | ― |
| 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例 | 142 | 食事療養標準負担額等を自己負担 | 食事療養標準負担額等の免除 | ― | ― |
(6) 特定被災地方公共団体及び特定被災区域一覧(平成24年2月22日現在)
① 特定被災地方公共団体(9県、178市町村)
(都道府県)
青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 千葉県 新潟県 長野県
(市町村)
北海道:茅部郡鹿部町** 二海郡八雲町** 広尾郡広尾町* 厚岸郡浜中町*
青森県:八戸市 三沢市 上北郡おいらせ町 三戸郡階上町
岩手県:宮古市 大船渡市 花巻市 北上市* 久慈市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市 奥州市 岩手郡滝沢村 紫波郡矢巾町 西磐井郡平泉町* 気仙郡住田町 上閉伊郡大槌町 下閉伊郡山田町 同郡岩泉町 同郡田野畑村 同郡普代村 九戸郡野田村 同郡洋野町
宮城県:仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市 刈田郡蔵王町 同郡七ケ宿町* 柴田郡大河原町 同郡村田町 同郡柴田町 同郡川崎町 伊具郡丸森町* 亘理郡亘理町 同郡山元町 宮城郡松島町 同郡七ケ浜町 同郡利府町 黒川郡大和町 同郡大郷町 同郡富谷町 同郡大衡村 加美郡色麻町** 同郡加美町** 遠田郡涌谷町 同郡美里町 牡鹿郡女川町 本吉郡南三陸町
福島県:福島市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市* 伊達郡桑折町 同郡国見町 同郡川俣町 安達郡大玉村* 岩瀬郡鏡石町 同郡天栄村 耶麻郡猪苗代町 河沼郡湯川村* 西白河郡西郷村 同郡泉崎村 同郡中島村 同郡矢吹町 東白川郡棚倉町 同郡矢祭町** 同郡塙町** 同郡鮫川村* 石川郡玉川村 同郡浅川町 同郡古殿町 田村郡三春町* 同郡小野町 双葉郡広野町 同郡楢葉町 同郡富岡町 同郡川内村 同郡大熊町 同郡双葉町 同郡浪江町 同郡葛尾村 相馬郡新地町 同郡飯舘村
茨城県:水戸市 日立市 土浦市 石岡市 結城市** 下妻市* 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 取手市 牛久市** つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 坂東市* 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 東茨城郡茨城町 同郡大洗町 同郡城里町 那珂郡東海村 稲敷郡美浦村 同郡河内町* 北相馬郡利根町
栃木県:宇都宮市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 那須烏山市 芳賀郡益子町 同郡市貝町 同郡芳賀町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 同郡那珂川町
埼玉県:久喜市**
千葉県:千葉市 銚子市 船橋市** 成田市 佐倉市* 旭市 習志野市 我孫子市 浦安市 印西市 匝瑳市* 香取市 山武市 印旛郡栄町* 香取郡神崎町* 山武郡大網白里町* 同郡九十九里町 同郡横芝光町 長生郡白子町*
新潟県:十日町市 中魚沼郡津南町
長野県:下高井郡野沢温泉村** 下水内郡栄村
② 特定被災区域(222市町村)
青森県:八戸市 三沢市 上北郡おいらせ町 三戸郡階上町
岩手県:盛岡市 宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市 二戸市 八幡平市 奥州市 岩手郡雫石町 同郡葛巻町 同郡岩手町 同郡滝沢村 紫波郡紫波町 同郡矢巾町 和賀郡西和賀町 胆沢郡金ケ崎町 西磐井郡平泉町 気仙郡住田町 上閉伊郡大槌町 下閉伊郡山田町 同郡岩泉町 同郡田野畑村 同郡普代村 九戸郡軽米町 同郡野田村 同郡九戸村 同郡洋野町 二戸郡一戸町
宮城県:仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市 刈田郡蔵王町 同郡七ケ宿町 柴田郡大河原町 同郡村田町 同郡柴田町 同郡川崎町 伊具郡丸森町 亘理郡亘理町 同郡山元町 宮城郡松島町 同郡七ケ浜町 同郡利府町 黒川郡大和町 同郡大郷町 同郡富谷町 同郡大衡村 加美郡色麻町 同郡加美町 遠田郡涌谷町 同郡美里町 牡鹿郡女川町 本吉郡南三陸町
福島県:福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市 伊達郡桑折町 同郡国見町 同郡川俣町 安達郡大玉村 岩瀬郡鏡石町 同郡天栄村 南会津郡下郷町 同郡檜枝岐村 同郡只見町 同郡南会津町 耶麻郡北塩原村 同郡西会津町 同郡磐梯町 同郡猪苗代町 河沼郡会津坂下町 同郡湯川村 同郡柳津町 大沼郡三島町 同郡金山町 同郡昭和村 同郡会津美里町 西白河郡西郷村 同郡泉崎村 同郡中島村 同郡矢吹町 東白川郡棚倉町 同郡矢祭町 同郡塙町 同郡鮫川村 石川郡石川町 同郡玉川村 同郡平田村 同郡浅川町 同郡古殿町 田村郡三春町 同郡小野町 双葉郡広野町 同郡楢葉町 同郡富岡町 同郡川内村 同郡大熊町 同郡双葉町 同郡浪江町 同郡葛尾村 相馬郡新地町 同郡飯舘村
茨城県:水戸市 日立市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 取手市 牛久市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 坂東市* 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 東茨城郡茨城町 同郡大洗町 同郡城里町 那珂郡東海村 久慈郡大子町 稲敷郡美浦村 同郡阿見町 同郡河内町 北相馬郡利根町
栃木県:宇都宮市 足利市 佐野市* 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 芳賀郡益子町 同郡茂木町 同郡市貝町 同郡芳賀町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 同郡那珂川町
埼玉県:久喜市*
千葉県:千葉市 銚子市 市川市 船橋市 松戸市 野田市** 成田市 佐倉市 東金市 柏市** 旭市 習志野市 八千代市 我孫子市 浦安市 印西市 富里市 匝瑳市* 香取市 山武市 印旛郡酒々井町 同郡栄町 香取郡神崎町* 同郡多古町 同郡東庄町 山武郡大網白里町* 同郡九十九里町 同郡横芝光町 長生郡白子町*
新潟県:十日町市 上越市 中魚沼郡津南町
長野県:下水内郡栄村
市町村のうち、*は平成23年8月17日追加、**は平成24年2月22日追加。なお、岩手県東磐井郡藤沢町は、平成23年9月26日に岩手県一関市と合併したため、一関市に含まれている。
17. 地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)
2章4節3.で記載。
18. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号)
2章4節3.で記載。
19. 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成23年法律第64号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災では地震に加え、前例のない大規模な津波が発生したため、家財が損壊するに留まらず、全く別の場所に流されるという事態が生じ、多くの被災者の方が一般旅券を紛失し、更には紛失した自らの旅券を探すことさえできない状況が生じた。
こうした状況に対処するため、①東日本大震災により一般旅券を失った被災者に追加的な経済的負担を負わせることなく東日本大震災前の(一定の有効期間が残った一般旅券を有するという)原状を回復し、もって被災者の生活再建及び地域産業・経済の復興に寄与すること、②また、被災者に紛失届の提出(失効手続)を行うインセンティブを与え、地震時点で被災者が有していた旅券を早急に失効させることにより旅券秩序を回復すること、を目的として、当該旅券の紛失届を提出した被災者に対し、国の手数料143を徴収することなく、当該旅券の有効期限までの一般旅券である「震災特例旅券」を発給することを可能とする「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律」が制定されることとなった。
- 143 当時の旅券法(昭和26年法律第267号)における一般旅券の発給に係る手数料(国への納付分)は、20年旅券が1万4千円、5年旅券が9千円(12歳未満の者は4千円)、それ以外の旅券が4千円。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年5月13日に閣議決定、国会に提出された。同年5月25日に(衆)外務委員会において全会一致で可決、翌26日に(衆)本会議において全会一致で可決され、同年5月31日に(参)外交防衛委員会において全会一致で可決、翌6月1日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。
本法律は、平成23年6月8日に公布、関係政省令とともに同日から施行された。
(3) 法概要・措置内容
東日本大震災により居住する住宅等が全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受け、地震発生時に有効であった一般旅券を紛失等した被災者が、当該旅券の紛失届を提出するとともに、本法律案の施行日(平成23年6月8日)から平成25年3月31日までの間に申請を行った場合には、外務大臣は、当該被災者が平成23年3月11日時点で有していた一般旅券(以下「紛失旅券」という。)の有効期限までを有効期間とする震災特例旅券(有効期間は、月を単位とする5年以内の期間であってその満了の日が紛失旅券の有効期間満了の日以前の日であるものとする。)を手数料(国への納付分)なしで発行することができることとされた。
また、上記特例により発行された有効期間5年の震災特例旅券の有効期限が被災者の紛失旅券の有効期限より1か月以上前である場合には、外務大臣は、当該被災者の申請に応じ、再度紛失旅券の有効期限までを有効期間とする震災特例旅券(有効期間は、月を単位とする5年以内の期間であってその満了の日が紛失旅券の有効期間満了の日以前の日であるものとする。)を手数料(国への納付分)なしで発行することができることとされた144。
なお、震災特例旅券の交付に係る事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とされ、震災特例旅券の発行に関する事務の一部145は都道府県知事が行うことができることとされた。
- 144 外務省及び都道府県が有する一般旅券作成システム上、5年を超え、かつ、10年未満の有効期間の旅券を作成することができないことから、まずは有効期間5年の震災特例旅券を発給した上で、当該震災特例旅券の有効期間満了の際に残りの5年を超える部分を有効期間とする震災特例旅券を再度発給することとされた。
- 145 都道府県が処理する事務の内容については、東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令(平成23年政令第165号)第2条第1項において、震災特例旅券の作成(旅券法第7条の規定による電磁的方法による記録を含む。)の事務とされている。
(4) 適用実績
震災特例旅券の発行実績は、1回目の発行数が1,952件、2件目の発行数が246件であった146。
- 146 いずれも外務省調べ。
(5) その後の法改正等
当該法律については、東日本大震災から10年が経過した令和3年3月11日以降、震災特例旅券の発給の申請が行われることが想定されなくなったことから、東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律(令和4年法律第34号)により、廃止された。
20. 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成23年法律第102号)ほか
(1) 立案経緯・制定趣旨
平成11年4月から平成17年3月末までに合併申請を行い、平成18年3月末までに合併した市町村(以下「合併市町村」という。)においては、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「旧合併特例法」という。)に基づき、合併年度及びこれに続く10年度に限り、市町村建設計画147に盛り込まれた事業について、合併特例債148を充当することができることとされてきた。
しかし、東日本大震災発生により、被災地域の内外を問わず、合併市町村における市町村建設計画に基づく合併特例事業の推進にも大きな影響が生じた。すなわち、被災地域の合併市町村にあっては、大規模な財政支出を伴う復旧・復興事業を優先させる必要があるため、従来予定していた市町村建設計画に基づく事業の中止や延期をせざるを得ない状況が生じ、大震災による直接の被害を受けなかった合併市町村にあっても、例えば、沿岸部の合併市町村では、津波被害の状況等を踏まえ、市町村建設計画に位置付けられていた公的施設の立地・構造等の見直しや防災施設、市町村内の連絡道路等の充実強化など新たな対応を図る必要が生じ、市町村建設計画の変更を余儀なくされる事態が生ずることも想定された。
このような中で、被災市町村においては、例えば、平成13年度に合併した岩手県大船渡市や茨城県潮来市が、平成23年度末に合併特例債の発行期限を迎えることとなっていた。
こうしたことから、被災団体をはじめとする関係地方公共団体等から、合併特例債の発行可能期間の延長が強く要請され、政府においても実態調査が行われるとともに、自民党において、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に限り、合併特例債の発行可能期間を5年度間延長する案が取りまとめられ、平成23年7月26日の総務部会において了承された。これを受け、民主党においては、平成23年8月10日の総務部門会議において、自民党案への対応が協議され、「合併特例債の発行可能期間の延長に関する提言」149がまとめられるとともに、緊急の特例措置として、自民党案の内容に沿った法案を(衆)総務委員会提出法律案として提出することが了承された。
このような経緯を経て、平成23年度においてなお合併特例債を発行することができる合併市町村であって、特定被災区域150をその区域とするものが合併特例債を発行することができる期間を5年度間延長することを内容とする「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」(以下、この20において「合併特例債法」という。)が制定された。
- 147 旧合併特例法第5条に基づき、合併協議会が作成する合併市町村の建設に関する基本的な計画をいう。
- 148 合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う事業に充当することができる地方債。なお、旧合併特例法第11条の2第1項の規定により、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、合併特例債をもってその財源とすることができる。
- 149 同提言では、政府に対し、合併特例債の発行可能期間の延長について、①対象自治体は全ての合併市町村とすること、②延長期間は、被災団体について10年程度、被災地以外の地方公共団体について少なくとも数年程度とすることなどの内容の法改正を行うことが求められていた。
- 150 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年8月11日に(衆)総務委員会において、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案として起草、全会一致により委員会提出法律案とすることとされ、同日に(衆)本会議において可決された。その後、同月23日に(参)総務委員会において全会一致で可決、翌24日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。衆参の委員会においては、①合併特例債を発行できる期間について、必要があると認められる場合は、期間の延長等適切な措置を講ずること、②被災地域以外に所在する合併市町村においても、当該合併市町村の実情を考慮し、類似の期間の延長に係る特例措置を講ずること、といった内容の決議・附帯決議がなされている151。
本法律は、平成23年8月30日に公布、同日から施行された。
- 151 (参)総務委員会の附帯決議は以下のとおり。
- 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 - 一、合併特例債を発行できる期間の延長は、東日本大震災の被災地域に所在する合併市町村の実情を考慮した緊急の特例措置であることから、当該合併市町村における復旧・復興事業の見通し等、実態の把握に努めるとともに、当該合併市町村の要望を踏まえ、必要があると認められる場合は、期間の延長等適切な措置を講ずること。
- 二、被災地域以外に所在する合併市町村においても、東日本大震災に起因する事情により市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施が遅延する等の影響が生じている場合には、当該合併市町村の実情を考慮し、被災地域の合併市町村に対するものと類似の期間の延長に係る特例措置を講ずること。
- 右決議する。
(3) 法概要・措置内容
平成23年度においてなお合併特例債を発行することができる合併市町村であって、特定被災区域をその区域とするものが合併特例債を発行することができる期間を10年度から5年度間延長し、15年度とすることとした。
(4) 改正経過・概要
1) 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第36号)
a. 立案経緯・制定趣旨
合併特例債法により、被災市町村については、合併特例債の発行可能期間が5年間延長されたが、10年程度の復興計画の策定を検討する団体が多く、復興計画の期間中は復興事業を優先せざるを得ず、合併特例債充当事業の実施が困難であることが見込まれた。また、被災市町村以外の団体にあっても、東日本大震災を踏まえた見直しが必要になる事業もあると考えられ、このような場合、市町村建設計画の変更を経て、新たな計画に基づく事業を実施するまでには5年程度を要することが見込まれた。
こうした状況や合併特例債法に付された附帯決議の趣旨を踏まえ、被災市町村が合併特例債を発行することができる期間を15年度から5年度間延長するとともに、被災市町村以外の合併市町村が合併特例債を発行することができる期間を10年度から5年度間延長することを内容とする「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が制定された。
b. 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年11月1日に閣議決定され、国会に提出された。同年12月8日に(衆)総務委員会に付託されたが、翌9日の(衆)総務委員会において閉会中審査の扱いとすることが全会一致で可決された。
その後、平成24年1月24日の(衆)総務委員会に再付託され、同年6月7日に全会一致で可決、翌8日に(衆)本会議において全会一致で可決され、さらに、同月19日に(参)総務委員会において全会一致で可決、翌20日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。なお、(衆)本会議、(参)総務委員会及び(参)本会議においては、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案と一括して審議された。
本法律は、平成24年6月27日に公布、同日から施行された。
c. 法概要・措置内容
被災市町村が合併特例債を発行することができる期間を15年度から5年度間延長し20年度とするとともに、被災市町村以外の合併市町村が合併特例債を発行することができる期間を10年度から5年度間延長し15年度とすることとされた。
また、法律の題名が「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」に改められる等の改正がなされた。
2) 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第19号)
a. 立案経緯・制定趣旨
本法律案については、平成30年4月10日に(衆)総務委員会において、自由民主党、立憲民主党・市民クラブ、希望の党・無所属クラブ、公明党、無所属の会、日本維新の会及び社会民主党・市民連合の7会派共同提案として起草され、委員会提出法律案として国会に提出された。起草の趣旨については、以下のとおりである152。
- 152 第196回国会(衆)総務委員会(平成30年4月10日)坂本哲志委員の発言より抜粋。
合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債、いわゆる合併特例債につきましては、旧合併特例法に基づき、合併年度及びこれに続く10年度に限り発行が認められていたものでありますが、東日本大震災に伴って、平成23年及び24年に法制上の措置が講じられ、その発行可能期間が、東日本大震災で被災した合併市町村につきましては合併年度及びこれに続く20年度、それ以外の合併市町村については合併年度及びこれに続く15年度にそれぞれ延長されました。
しかし、その後も、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況にあります。
本起草案は、このような最近における合併市町村の実情に鑑み、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律を改正し、合併特例債の発行可能期間を更に5年間延長しようとするものであります。
b. 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、上記のとおり、平成30年4月10日に(衆)総務委員会において、全会一致で可決され、同月12日に(衆)本会議において全会一致で可決された。さらに、同月17日に(参)総務委員会において全会一致で可決、翌18日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。
なお、(衆)総務委員会及び(参)総務委員会では、採決に当たって、①合併特例債の発行可能期間が合併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられた趣旨を踏まえ、今後、合併特例債の発行期間の更なる延長を行うことなく、合併市町村が市町村建設計画に基づく事業等を期間内に実施・完了することができるよう、必要な助言を行うこと、②住民合意に基づいて合併特例債が効果的・計画的に活用されるよう、周知徹底を図ること、についてその実現に努めるべき、といった内容の決議・附帯決議がなされた153。
本法律は、平成30年4月25日に公布・施行された。
- 153 (参)総務委員会の附帯決議は以下のとおり。
- 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 - 一、合併特例債の発行可能期間が合併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられた趣旨を踏まえ、今回の延長発行期間を更に延長することなく、合併市町村が市町村建設計画に基づく事業等を住民合意を尊重し、期間内に実施・完了することができるよう、必要な助言を行うこと。
- 二、今後の人口減少等による公共施設等の需要の変化等の地域の実情を踏まえ、合併市町村において、住民合意に基づいて合併特例債が効果的・計画的に活用されるよう、周知徹底を図ること。
- 右決議する。
c. 法概要・措置内容
被災市町村が合併特例債を発行することができる期間を20年度から5年度間延長し25年度とするとともに、被災市町村以外の合併市町村が合併特例債を発行することができる期間を15年度から5年度間延長し20年度とすることとされた。
また、法律の題名が「東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」に改められた。
21. 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第39号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)は、過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図ることを目的とする過疎地域自立促進のための財政上その他の特別措置を講ずること等を内容とする法律であり、平成22年の改正法により、過疎地域の要件の追加やソフト事業に対する支援措置の拡充等が行われ、有効期限がそれまでの平成22年3月31日から平成28年3月31日と延長されていた。
東日本大震災の影響発生により、過疎対策事業の大幅な遅れが想定され、過疎地域自立促進特別措置法の期限内(平成28年3月31日)において総合的かつ計画的な施策を展開することが困難な状況が生じていたことから、被災市町村等から法の期限延長を求める強い要望が上がったことを受け、各党各会派で協議が重ねられた結果、法の有効期限を平成33年(令和3年)3月31日まで5年間延長することを内容とする「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」が制定された。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成24年6月12日の(衆)総務委員会委員長提案の法案として国会に提出された。その後、6月13日の(衆)本会議に上程、全会一致で可決され、6月19日の(参)総務委員会及び6月20日の(参)本会議で全会一致で可決、成立し、平成24年6月27日に公布・施行された。なお、(衆)本会議、(参)総務委員会及び(参)本会議においては、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案と一括して審議された。
本法律は、平成24年6月27日に公布・施行された。
(3) 法概要・措置内容
過疎地域自立促進特別措置法の有効期間が平成28年3月31日までから、平成33年(令和3年)3月31日までと5年間延長された。
22. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
福島原子力発電所の事故による損害の賠償は、原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)によれば、原則として東京電力の責任の下で行われるべきものであるが、損害賠償手続の円滑な進行の観点から、原賠法に基づき平成23年4月11日に設置された原子力損害賠償紛争審査会が、東京電力が賠償すべき損害を類型化等し、数次にわたり指針を示していた。一方で、東京電力は、同年4月15日、避難住民等に対する損害賠償の「仮払補償金」の支払いを発表し(一世帯当たり100万円、単身世帯75万円。後に10~30万円の追加仮払補償金が支払われている。)、同月26日から支払い手続を開始し、さらに、5月には農林漁業者、6月には中小企業者への仮払いを開始した。
しかし、3か月経っても事故収束が見通せない中で損害賠償範囲が確定せず、原子力損害賠償紛争審査会の示す指針の範囲に入らない損害があるとの指摘や、東京電力による法律に基づかない仮払補償金の支払いでは、金額やスピード等において当面の被害者救済の観点から不十分である等の指摘がなされていた154。このような状況を受け、国による被害者への仮払いの実施及び自治体が設置する原子力被害応急対策基金への補助を2本柱とする本法律(いわゆる「原子力被害者早期救済法」)155が、制定されることとなった。
- 154 発議者による趣旨説明等より。
- 155 なお、本法律の略称は、提案者は「原子力被害者早期救済法」としているが、「仮払い法」との俗称で呼ばれることもある。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
平成23年6月21日に、本法律案は、自由民主党、公明党、みんなの党、たちあがれ日本・新党改革の野党4会派の共同提案により参議院に発議された。同年7月8日の趣旨説明以降、与野党で修正協議が重ねられたが、国と東京電力の仮払いの役割分担の明確化、国からの求償に東京電力が応じることの担保といった点について協議が整わず156、7月14日(参)東日本大震災復興特別委員会では原案のまま審議され、原案どおり可決、翌15日に(参)本会議で可決された。衆議院では、与野党間において修正協議が行われ、同月26日に修正案が同委員会に提出され、修正案及び原案が可決されるとともに、附帯決議157が付された(政府提出の原子力損害賠償支援機構法案(後述)の修正案及び原案も、同じ委員会で審議・採決がなされた。)。同月28日に(衆)本会議において可決され、翌29日に(参)本会議で衆議院の回付案が同意され、成立した。
衆議院での主な修正点は、「国が行う仮払金の支払は、特定原子力損害を受けた者の早期の救済のために迅速なものであり、かつ、国民負担の観点から適正なものでなければならない」旨の追加、福島県を念頭に支払い事務の一部を行うこととされる都道府県に過重な負担を課さないように配慮を求める規定の追加、主務大臣の拡大、施行期日の延長等である。
本法律は、同年8月5日に公布、同年9月18日に施行された。
- 156 平成23年7月14日(参)東日本大震災復興特別委員会での浜田昌良議員答弁より
- 157 附帯決議には、関連制度との有機的連携、国と原子力事業者それぞれが仮払いを行うことでの混乱・遅延の防止や原子力事業者が国の求償に応じることを事前に確認する手続等の必要な措置を講じること等が盛り込まれた。
(3) 法概要・措置内容
特定原子力損害(福島第一原子力発電所の事故による損害であって、原子力事業者が賠償の攻めに任ずべきもの。)の賠償支払に時間を要すること等の特別の事情があることに鑑み、緊急の措置として、国が被害者に仮払金を支払うものとされた。対象となる損害範囲は原子力損害賠償紛争審査会の示す指針を大前提にしつつ、東京電力と国の役割分担は政令で明確化することとされた158。仮払金の額は、簡易な方法により算定した概算額に10分の5を下らない政令で定める割合(政令では「10分の5」)を乗じて得た金額とされた。仮払金の支払に関する事務については、国のほか、政令で定める者(原子力損害賠償支援機構、東京電力)に一部事務を委託できることとされた。東京電力による損害賠償との関係については、被害者が賠償等を受けた場合はその限度において国は仮払金を支払わないものとし、国が仮払金を支払った場合はその限度において、被害者が有する損害賠償請求権を代位して行使するものとされた。
また、原子力損害賠償紛争審査会の示す指針の範囲外となる被害等があること等を踏まえ159、経済社会・住民生活への事故の影響の防止・緩和のために地方公共団体が実施する応急対策の事業に充てるため、福島県を念頭に、地方公共団体に原子力被害応急対策基金を設け、国が必要な補助をすることとされた。
- 158 平成23年7月25日(衆)東日本大震災復興特別委員会にて、浜田昌良議員より、「東京電力がどんどん早くやるものはこれは東京電力に任せようと。精神損害みたいなものですね、十万円で。(略)ところが、やはり風評被害、これは大変です。こういうものについては、霞が関の知恵も使って、農水省とか観光庁とか、そういう知恵を使って国がやっていくという役割分担をすればいい。(略)例えば社会福祉法人とか文教関係とかまた医療法人に払われていないという実態もあります。そういうものについては最終的に国が責任を持つということで、今回役割分担させていただきました。」旨の答弁がされている。
- 159 基金設置の趣旨として、平成23年7月11日(参)東日本大震災復興特別委員会において、浜田昌良議員から「例えば自主避難の方々、また圏外の中小企業の方々(略)一片の二次補正予算で対応するのではなくて、基金を設けるのであれば明確に法律に位置付けるべき」、佐藤正久議員から「指針から漏れた仮払金という性格のものだけではなく、地方自治体が特措法に基づきまして実施しますいろんな事業、除染とかあるいは健康管理にも使える」等の答弁があり、規模は、3,000億円や5,000億円との答弁があった。
(4) 適用実績
1) 国による仮払金の支払い
本法に基づく政府による賠償金の仮払いの対象については、東京電力による本賠償の開始までに要すると見込まれる期間や仮払金を受領することの緊急性等を踏まえ、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成23年政令第294号)に基づき、福島県、茨城県、栃木県又は群馬県において観光業を行う中小企業者が受けた本件事故によるいわゆる風評被害を対象とすることとした。政府は、政令に基づき原子力損害賠償支援機構、東京電力に事務委託を行いつつ、平成23年9月21日より仮払金の支払請求の受付を開始し、平成24年3月19日までに対象事業者から64件の仮払請求を受け付け、そのうち50件について、総額17億円を支払った。当該仮払いについて、政府は、東京電力に対して求償を行い、仮払金として支払った全額を東京電力より受領した。
2) 原子力被害応急対策基金
設置先:福島県
基金事業期間:平成23年度~29年度
補助金交付額:平成24年2月10日に成立した平成23年一般会計(東日本大震災復旧・復興予備費)により福島県原子力被害応急対策基金として計上された交付金(放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(応急対策事業))403億円を用いて造成。
主な使途:東日本大震災に伴う原子力発電所事故による被害を受けた者を早期に救済することを目的として、米の全袋検査等の検査機器整備(農林水産物、食品等の安全・安心復元事業)や、子供の自然体験活動等の事業を実施。
(5) その後の法改正等
本法に基づく政府による賠償金の仮払いの取組の経験を踏まえ、今後、万が一原子力損害が生じた際にも、同様に仮払いが実施できるよう、原子力事業者による迅速な仮払いの実施を促す枠組みとして、国が仮払いのための資金を貸し付ける制度が、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第90号)において恒久的に措置され、同法において、国は当該貸付けに関する業務を原子力損害賠償・廃炉等支援機構に行わせることが出来る旨の規定も併せて整備された。
23. 原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
原子力事故については、原賠法は原子力事業者の無過失責任・責任集中を原則としつつ(3条1項本文、4条)160、巨額になると見込まれる損害賠償を担保するための措置として、上限1,200億円(賠償措置額)を民間保険又は政府補償で備えておくことになっていた。しかし、それを超える場合については、政府が必要と認める時は、国会の議決の範囲内で必要な援助を行うことができる(16条)としていた。福島原子力事故は当初からこの賠償措置額では到底足りないと見込まれた161ため、政府としても、平成23年4月11日、閣僚級の「原子力発電所事故による経済被害対応本部」(翌月9日に「原子力発電所事故経済被害対応チーム」へ改称)162を発足させ一連の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故163による経済被害についての対応の枠組みを議論することとした。一方、東京電力は、仮払補償金の支払いや、原子力の代替となる火力発電の燃料確保費等により、厳しい資金調達環境に置かれていった。
平成23年5月10日、東京電力が原子力経済被害担当大臣に対し、「原子力損害賠償に係る国の支援のお願い」を提出し、原賠法に基づく公平かつ迅速な賠償を行う旨の表明を行うとともに、資金面の困難から電力安定供給や被害者補償に支障を来しかねない状態に陥るおそれがあることを理由として、原賠法第16条に基づく政府の援助の枠組みを要請した。同日、国から6点の確認事項(経営合理化等)を示し、翌日、東京電力がこれらを了承する旨回答した。これを受け、原子力発電所事故経済被害対応チームは5月13日に決定した「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて」(6月14日にそのまま閣議決定)において、「第一に、迅速かつ適切な損害賠償のための万全の措置、第二に、東京電力福島原子力発電所の状態の安定化及び事故処理に関係する事業者等への悪影響の回避、そして第三に、国民生活に不可欠な電力の安定供給という三つを確保しなければならない。」ことを理由とし、「これまで政府と原子力事業者が共同して原子力政策を推進してきた社会的責務を認識しつつ、原賠法の枠組みの下で、国民負担の極小化を図ることを基本として東京電力に対する支援を行う」旨を示した164。
同方針を踏まえ、原子力損害が発生した場合の損害賠償に対応する支援組織の設立等を内容とする原子力損害賠償支援機構法が、同事故に限らない恒久的な一般法として制定されることになった。
- 160 なお、原子力事業者が免責される場合として「異常な天変地異等」(原賠法3条1項ただし書)との規定があり、東日本大震災がこれに該当するかどうかが問題となったが、これについては、「人類の予想していないような大きなもの」「全く想像を絶するような事態」だとした原賠法制定時の国会答弁を引用し、「今回の福島原子力発電所の事故は第3条の第1項本文を適用することを前提に」とする平成23年4月19日文部科学大臣答弁などがされ、同ただし書は適用せず、東京電力の責任とすることを前提に、対応が進められていった。
- 161 平成23年7月8日(衆)本会議では、既に600億円近い仮払いが実施された旨答弁がされている。
- 162 構成員は、チーム長:原子力経済被害担当大臣、副チーム長:内閣官房長官、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣等で、事務局は内閣官房であった。
- 163 なお、福島第二原子力発電所事故については、本法律に基づく制度・措置の対象とはなっていない。
- 164 このほか、国民負担の極小化の観点から、同決定文書の「厳正な資産評価、徹底した経費の見直し等を行うため、政府が設ける第三者委員会の経営財務の実態の調査に応じること」を踏まえ、「東京電力に関する経営・財務調査委員会」(委員長の下河辺和彦弁護士ほか有識者で構成)が平成23年5月24日に設置され、全10回開催し、10月3日に報告書を取りまとめている。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年6月14日に閣議決定、国会に提出された。7月8日に(衆)東日本大震災復興特別委員会で原子力経済被害担当大臣から提案理由説明を行ったが、国の責任のあり方、東京電力を国が資金面で支援することの是非や同社の資産処分・法的処理の必要性、国民負担の懸念、当時の総理の「脱原発」方針との関係等をめぐって議論は紛糾し、5回・約20時間にわたる質疑が行われた末、与野党の修正協議が整い、7月26日、本法案に対する修正案と、前述の原子力被害者早期救済法案に対する修正案とが一体的に審議・採決されることとなった165。同日、本法案については2つの修正案が提出されたが、趣旨説明・質疑が行われ、民主党、自由民主党、公明党、たちあがれ日本提出の修正案が可決された166。また、附帯決議167が付された。同月28日、(衆)本会議で政府原案は修正議決された。8月2日、(参)東日本大震災復興特別委員会で衆議院送付の原案通り可決され、翌日、(参)本会議で可決・成立した。
衆議院の修正で追加された内容は、①国の責務規定(「これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的責任」)168、②国債が交付されても特別資金援助に係る資金が不足するときに限り、政府は機構に資金を交付することができること169、③機構は原子力事業者の委託を受け損害賠償の全部又は一部の支払を行うことができること170、④原賠法等の見直しに係る検討条項(後述)等である。
本法律は、平成23年8月10日に公布・施行された。
- 165 原子力被害者早期救済法で国が仮払いを行うのであれば、本法律に基づく機構を通じた国の支援は不要ではないか等の議論もあり、与野党で議論が対立していたが、平成23年7月26日(衆)東日本大震災復興特別委員会では「支援機構法案と五野党提出された仮払い法案とは、相対する法案ではなくて、原発事故の被害者に対する賠償を迅速かつ適切に行うための法案であると考えており」との総理答弁、「この機構の法案、それから、今まさにそれと両立するものとしての仮払いの法案、この二つが成立をすることによって、東京電力の仮払いもこれまで以上にスピードを上げて」との担当大臣答弁等がある。
- 166 みんなの党より、原子力事業者の破綻スキームを新設する本法案の修正案が提出されたが、否決された。
- 167 附帯決議には、原子力政策における国の関与・責任の在り方について早急に見直しを行うこと、東京電力の再生の在り方について事故収束、事故調査・検証の報告、概ねの損害賠償額などを見つつ改めて検討すること等、衆議院で11項目、参議院で15項目が盛り込まれた。
- 168 国の責任について、政府側は「法律の条文あるいは文言として国の責任という言葉はないが、この法律を決めるに当たっての閣議決定の中では、原子力事業者と共同して原子力政策を推進してきた国の社会的責任を踏まえという形で書いている」(平成23年7月12日(衆)東日本大震災復興特別委員会の海江田原子力経済被害担当大臣・経済産業大臣)等の答弁をしていたが、修正協議で追加された。
- 169 いわゆる「真水規定」は政府案にもあったが(現68条)、修正理由について平成23年7月26日(衆)東日本大震災復興特別委員会で「五十一条の真水がありませんと、交付国債の資金交付が終わった後にだれも補償されない、被害者の救済ができないということになってしまいますので、その意味で、ちょっと原案の方で少し不明確になっていたものを明確にしたということでございます」との柿沼正明議員の答弁がある。
- 170 同規定の趣旨について、平成23年7月26日(衆)東日本大震災復興特別委員会で「東電が仮払いをする部分と国が立てかえ払いをするという二つのルートがあるわけですけれども、効率よくやるためには、東電が実は被災者に対しての口座を知っておって、東電が管理をするのが、東電を通じてやるのが一番いいわけですけれども、東電が手いっぱいになっているわけでありますので、東電と機構が連携をしてやる。したがって、東電がやれない部分の一部、全部と一応書いていますけれども、東電の委託を受けてやることによって効率的に賠償を進めるという視点であります」との西村康稔議員の答弁がある。
(3) 法概要・措置内容
原子力事業に係る巨額の損害賠償が生じる可能性を踏まえ、原子力事業者による相互扶助の考えに基づき、将来にわたって原子力損害賠償の支払等に対応できる支援組織(原子力損害賠償支援機構。以下単に「機構」という。)を中心とした仕組みを構築するものである。具体的には、下記事項が規定された。
・ 原子力損害が発生した損害賠償に備えるため、原子力事業者から負担金の収納を行い、機構に積立てを行う。
・ (通常援助)原子力事業者が損害賠償を実施する上で機構の援助を必要とするときは、資金援助(資金の交付、株式の引受け、融資、社債の購入等)を行う。当該資金援助に必要な資金を調達するため、政府保証債の発行、金融機関からの借入れをすることができる。
・ (特別援助)機構が原子力事業者に資金援助を行う際、政府の特別な支援が必要な場合、原子力事業者とともに「特別事業計画」を作成し、主務大臣が認定する。この場合、政府は機構に国債を交付し、機構は国債の償還(現金化)を求める。国債が交付されてもなお損害賠償に充てるための資金が不足するおそれがあると認めるときに限り、政府は機構に対し、必要な資金の交付を行うことができる。機構は、政府保証債の発行等により資金を調達し、事業者を支援する。
・ 機構から援助を受けた原子力事業者は、特別負担金を支払う。機構は、負担金等をもって国債の償還額に達するまで国庫納付を行う(ただし、負担金によって電気の安定供給等に支障を来す、利用者に著しい負担を及ぼす等の場合、政府は機構に対して必要な資金の交付を行うことができる)。
・ 機構は、損害賠償の円滑化のため、被害者からの相談対応、原子力事業者が保有する資産の買取り、賠償支払の代行(及び原子力事業者からの委託を受けて賠償の支払、国等の委託を受けて仮払金※の支払)を行うことができる。
※原子力被害者早期救済法に基づく国による仮払金
・ 機構は、負担金について、原子力事業者ごとに計数管理を行う171。
・ 検討条項(附則)として、①法施行後できるだけ早期172に、原子力賠償制度における国の責任の在り方等について検討を加え、原賠法の改正等の抜本的な見直し等の必要な措置を講ずること、②法施行後早期に、政府、東京電力、他の原子力事業者の負担の在り方等について、国民負担最小化の観点から改めて検討すること、③エネルギー政策の在り方についての検討を踏まえつつ、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を加え、原子力に関する法律の抜本的な見直し等の必要な措置を講ずること。
- 171 議員修正で追加された規定。一般の負担金と特別負担金を区分経理すべきとの議論もあったが、相互扶助の制度趣旨に照らしこのような規定に落ち着いた。
- 172 附帯決議では、①の「できるだけ早期」とは「1年を目途」、②の「早期に」は2年とされた。
(4) 適用実績
原子力損害賠償支援機構は、本法律に基づく認可法人として、平成23年9月12日に設立(理事長:杉山武彦氏)、26日に業務を開始した。設立時の機構の出資金は、国が平成23年度第二次補正予算で計上した70億円と、各原子力事業者による70億円の合計140億円で、同機構は、本法第41条第1項に基づき、令和3年3月までに、東京電力に対して9兆8,181億円の資金交付を実施しており、同条第2項に基づき、東京電力が発行する1兆円の株式の引受けを行っている。
(5) その後の法改正等
原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成26年法律第40号)により、東電に資金援助を行い最大株主として経営全体を監督してきた同機構に、賠償支援に加えて、事故炉の廃炉に関する技術支援等を総合的に行わせるため、廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究・開発や、助言、指導、勧告等の業務が追加された173。これにより、法律名が「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」に、機構の名称が「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に改称され、機構に廃炉支援部門を設置する等の改組がなされた。
さらに、「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」(平成28年12月20日閣議決定)を踏まえ、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第30号)により、東京電力が廃炉の実施責任を果たしていくという原則を維持しつつ、長期にわたる巨額の資金需要に対応するための制度として、事故炉の廃炉を行う原子力事業者に対し、廃炉に必要な資金を、毎年度、機構に積み立てる義務を課すこととした。
また、附則で検討することとされた①原子力賠償制度については、原子力損害賠償制度専門部会における議論を踏まえ、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第90号)において、国による仮払資金の貸付制度の創設等の改正が行われた。加えて、同部会においては、今後の損害賠償措置のあり方については、迅速かつ公正な被害者への賠償の実施、国民負担の最小化、原子力事業者の予見可能性の確保といった観点も踏まえつつ、現行の原賠法の目的や官民の適切な役割分担等に照らして、引き続き慎重な検討が必要との見解が示されており、引き続き検討を行うこととしている。②本件事故の損害賠償の負担のあり方については、国と東京電力の役割について、平成25年末の閣議決定において、賠償、除染及び中間貯蔵施設事業の費用に関する政府の方針を決定した。③エネルギー政策の検討を踏まえた原子力に関する法律の抜本的な見直しについては、原子力に関する法律を抜本的に改正し、これまで、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正(平成24年法律47号)により、世界で最も厳しい規制基準を策定した。また、第4次エネルギー基本計画(平成26年4月閣議決定)において、原子力の利用においてはいかなる事情よりも安全性を最優先することや、「安全神話」と決別して世界最高水準の安全性を不断に追求していくことが重要であることを示すとともに、原子力災害対策特別措置法改正(平成24年法律第47号)により、原子力災害に備えた避難計画の充実を図り、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第90号)により、原子力事業者による損害賠償実施方針の作成・公表を義務付ける等の措置がなされたが、原子力政策については、今後も、内外の情勢変化を踏まえながら不断に見直していくこととしている。
- 173 平成26年4月22日(参)経済産業委員会において「実態面から見てみましても、原賠機構は東電の最大の株主であります。ですから、日頃から自主的に強い監督ができるわけでありますし、さらに、原賠機構法に基づいて作成をされます特別事業計画、これは東電と機構が共同で作るわけでありますが、ここに廃炉の実施状況や実施体制の整備に関する記載を追加することによりまして、今後必要な場合には主務大臣によります命令を発動できるような形になってまいります。このように、賠償機構のスキームを活用することで国が廃炉そして汚染水対策に積極的に関与でき、実効ある対策の実施と監督が可能になると考えております。」との経済産業大臣答弁がされている。
24. 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
福島第一原子力発電所の事故では、周辺の市町村から多数の住民が住民票を移さないまま全国に分散避難するとともに、9町村が役場ごと移転を余儀なくされるというかつてない事態が生じた。当初は、本来は避難元の地方公共団体が行うべき医療・福祉、教育といった行政サービスの提供について、住民票を移していない場合においても避難先の地方公共団体(避難先団体)においてできる限り確保されるよう、「特別な配慮」を要請する等の通知が、各行政サービスを所管する省庁から発出された。
しかし、原発事故の収束には一定期間を要することが明らかになり、通知のみで避難先の地方公共団体に事務処理を義務付けることはできないこと、地方自治法(昭和22年法律第67号)では、他の自治体に自らの住民に関する事務を処理してもらうためには個々に協議して事務の委託をすることが必要となっていた174こと、避難元に住民票を残すことによって、将来帰還できるようになる時まで、避難元の地域・自治体と元の住民との絆を維持することが必要だと考えられることになったことから、例外的な法制度が求められるようになった。平成23年5月9日に総務大臣と福島県飯舘村の村長との意見交換でこうした問題意識が共有されたことが立法化の一つの契機となり、6~7月に関係地方公共団体と関係閣僚級との意見交換会が重ねられ175、避難先団体に住民票を移していない避難住民に対する行政サービスの提供を避難先団体に義務付ける内容の本法律(いわゆる「原発避難者特例法」)が制定されることとなった。
- 174 地方自治法第252条の14に基づく事務の委託については、平成23年8月2日(衆)総務委員会において、「現行法でやろうと思えばできるんですが、一つ一つの事務の委託について契約を結ぶとか、それについて議会の議決が必要だとか、告示をしなければいけないとか、煩瑣なと言うと現行法に対して失礼になりますけれども、非常に厳格な手続を要するわけであります。」との片山総務大臣答弁がされている。
- 175 具体的には、原子力被災者生活支援チーム・被災者生活支援チーム・総務省の担当大臣が、6月4日と7月11日には避難元市町村長と、7月4日には避難先市町村長と意見交換を行い、それぞれの実情の把握等を行った。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年7月22日に閣議決定、国会に提出された。同日、「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案」176も国会に提出され、衆・参両院において両法案は一括審議されることとなった。8月2日、(衆)総務委員会において、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党案の3派共同提案による修正案が提出され、原案及び修正案ともに全会一致で可決された。同日、修正後の法案が(衆)本会議において全会一致で可決された。8月4日、(参)総務委員会で全会一致で可決され、翌5日に参議院本会議において全会一致で可決され、成立した。なお、衆・参の総務委員会では附帯決議177が付されている。
衆議院での修正内容は、本法律の対象となる「避難住民」以外の避難を余儀なくされている住民についても国が必要な措置を講ずるものとする附則第3条を加えるものである178。
本法律は、8月12日に公布・施行された。
- 176 避難区域内等の不動産や自動車といった資産や警戒区域内の資産の代替資産について、固定資産税や不動産取得税等の特例を講ずるもの。2章4節3.参照。
- 177 附帯決議には、本法律の趣旨に沿った対応や配慮のほか、指定市町村以外の福島県市町村の住民のうち福島原発事故災害の発生を受けて自主的に避難している住民の実態を早急に把握し適切な対応に努めること等が盛り込まれた。
- 178 特定避難勧奨地点(いわゆる「ホットスポット」)の住民などについては、同地点が、対象となる地区や世帯が局地的なものであることや、政府として一律に避難を求めているものではないことに鑑み、本法律によらずとも既存の地方自治法の規定に基づく個別協議等をすれば足りるとして、政府案ではこれらの者に関する規定は置かれていなかった。また、津波等により避難している者についても、市町村の全住民という規模ではないことや、原子力災害ほど長期間の避難は想定されないことから、政府案ではこれらの者に関する規定は置かれていなかった。
(3) 法概要・措置内容
東日本大震災における警戒区域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域等をその区域に含む市町村(後述の指定市町村))及び当該市町村の区域を包括する都道府県(後述の指定都道府県)について、①避難住民(住民票を残したまま市町村区域外に避難している住民)に対する避難先団体での適切な住民サービスの提供と、②住所移転者(住民票を避難先に移した元住民)と避難元の地方公共団体との関係維持を図るため、次の事項が規定された。
1) 避難住民に係る事務処理の特例
避難元の地方公共団体(指定市町村・指定都道府県。以下「避難元団体」という)は、法律又は政令に基づく事務のうち避難住民に関するものであって、自ら処理することが困難である事務について、総務大臣への届出等を経れば、避難先団体が処理することとすることができることとする。その際、避難住民から避難元団体に、及び避難元団体から避難先団体に対し、避難住民の情報(氏名、生年月日、性別、住所、避難場所)を通知し、これにより把握した避難住民に関し、避難先団体は事務処理を代わって実施するとともに、事務処理に要する経費も原則として避難先団体が負担することとなる(国は必要な財政上の措置を講ずる)。
2) 住所移転者に係る措置
避難元団体は、特定住所移転者(住所移転者のうち、引き続き避難元団体に関心を有し、指定市町村及び指定県から情報提供などを受けることを希望する申出をしたもの)に対し、情報提供や地元訪問の事業など、住民交流を促進するための事業の推進に努めることとし、国は必要な財政上の措置を講ずる。
(4) 適用実績
1) 避難住民に係る事務処理の特例
・ 避難元団体(指定都道府県・指定市町村)の指定状況
◾️ 1県13市町村(平成23年9月16日告示時点より変更なし)
◾️ 指定都道府県:福島県
◾️ 指定市町村:いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村
・ 避難先団体が処理する事務として総務大臣が告示した事務
◾️ 11法律268事務(令和4年4月時点)
◾️ 医療・福祉関係:要介護認定等、保育所入所、予防接種、子ども手当の支給、障害者・障害児への介護給付費等の支給決定等の事務
◾️ 教育関係:児童生徒の就学等、義務教育段階の就学援助等の事務
・ 避難住民の受入れ事務に要する経費については、地方交付税により措置
2) 住所移転者に係る措置
平成24年度より、避難元団体による避難住民及び特定住所移転者との関係維持に資するための施策に要する経費に対し、震災復興特別交付税措置を講じている。
(5) その後の法改正等
本法律は、避難元自治体の一方的な意思により、避難先団体に行政サービスの提供の義務(法令に定めのない行政サービスについても努力義務)を課すという、極めて例外的な法制度となっているが、これは、原発事故により生じた全国的な分散避難といった未曽有の事態を受け、限定的に運用されることを念頭に、関係者の理解を得て、立法化に至ったものである。
25. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故により大気中に放出された放射性物質は、周辺地域以外にも、東北・関東地方を中心に広範に拡散し、それにより汚染された廃棄物や土壌等に起因する住民の健康及び生活環境への影響が懸念された。このため、事故由来放射性物質による環境の汚染に一刻も早く対処し、人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減することが、喫緊の課題となった。
一方で、放射性物質による環境汚染については、原子力・環境の法制度で棲み分けがされており、従来、環境基本法は「原子力基本法(昭和30年法律第186号)その他の関係法律で定めるところによる」として放射性物質を規制の対象から除外しており、同様の考え方の下、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)や廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号))も、放射性物質による汚染を適用除外としていた。他方、原子力基本法の下で、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「炉規法」という。)は、基本的に原子力事業者が適切に管理することを前提にしており、発電所内で原子力事業者の管理下にある廃棄物の取扱い等については定めていたが、放射性物質が施設外に広範囲に拡散する事態への対処は想定されていなかったため、適切な根拠制度がなく、手順等の定めもない状況にあった。
そのような中、環境省は、原子力災害対策本部や経済産業省と連携し、平成23年5月2日に「福島県内の災害廃棄物の当面の取扱い」を取りまとめ、避難区域及び計画的避難区域で当面災害廃棄物の処分を行わない方針を示し、平成23年6月23日には「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」において避難区域、計画的避難区域等以外の「放射性汚染物質により汚染されたおそれのある災害廃棄物」の取扱方針も示した。他方で、首都圏の清掃工場焼却灰や東日本各都県の下水道汚泥から高濃度の放射性物質が検出され、また福島県内の小中学校の除去表土の処分方法が決まらず校庭に仮置きされるなどの事態も発生していた。国会において様々な委員会でこの問題が取り上げられるとともに、周辺自治体からも国主導の早期除染を望む声が相次ぎ179、これまでの解釈による対応を超えた根本的な対策が求められた。そこで、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(放射性物質汚染対処特措法)が、議員立法で制定されることとなった。
- 179 例えば、平成23年7月28日(衆)総務委員会において、富岡町長、川俣町長等から発言あり。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
放射性物質に汚染された廃棄物の処理及び土壌の除染について規定する法案の準備に向けて民主党、自由民主党、公明党共同で法案の提出準備が進められ180、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法案」が起草され、平成23年8月23日、(衆)環境委員会提案の法案とすることが可決された。同法案は、同日の(衆)本会議で可決された後、同月25日の(参)環境委員会に付託され、同月26日に(参)本会議で可決・成立した。(衆)環境委員会では、それまでの国会での議論も踏まえ、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する件」が決議され、国と地方公共団体等の責任・役割の相違、費用の全額を国が一旦負担した上で国が関係原子力事業者に必要な求償を行うこと、放射性廃棄物の処理や除染の措置に関する基準の速やかな設定、国の責務による最終処分場の確保等が盛り込まれた。(参)環境委員会では附帯決議が付され、同様の内容が盛り込まれた。
本法律は、同年8月30日に公布され、一部は同日施行されたが、区域の設定や技術基準の策定などには一定の期間が必要となるため、全面施行は平成24年1月1日となった。一方で、除染は直ちに取り組む必要のある喫緊の課題であることから、原子力災害対策本部は平成23年8月26日に「除染に関する緊急実施基本方針」を決定、本決定に基づき福島県に対し基金創設のための補助金を拠出するなど、除染のための措置を講じた。
- 180 平成23年8月8日(衆)予算委員会における馳議員から「四月以来、我が党も、また公明党の皆さん方も、随分と、早くルールをつくれ、法律をつくれとやかましく言ってきたんですが、いまだに出てきていないので、実は二週間ほど前から、私が自民党の担当者として、また公明党の江田康幸さん、そして御党、民主党の担当者もおられます、名前は言いませんけれども、現場で詰めてきております。」との発言がある。
(3) 法概要・措置内容
1) 責務・基本方針
国は「これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任」に鑑み必要な措置を講ずること、地方公共団体は国の施策に協力すること、関係原子力事業者は、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する施策に協力すること等が定められた。
環境大臣が環境汚染への対処に関する基本方針の案を策定し、閣議決定を求めることとされた。
2) 放射性物質により汚染された廃棄物の処理
環境大臣は、その地域内の廃棄物が特別な管理が必要な程度に汚染されているおそれがある地域を「汚染廃棄物対策地域」として指定するとともに、放射能濃度が8,000Bq/kgを超えるものを指定廃棄物として指定することとし、対策地域内廃棄物(汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物)及び指定廃棄物の処理は国が行うこととされた。
3) 放射性物質により汚染された土壌等の除染等の措置等
環境大臣は、汚染の著しさ等を勘案し、国が除染等を実施する必要がある地域を「除染特別地域」として指定するとともに、同地域外でも一定以上の汚染状態又はそのおそれが著しいと認められる地域を「汚染状況重点調査地域」に指定することとし、前者については国が、後者については市町村等が除染等を実施することとされた。
4) 費用負担
国は、汚染への対処に関する施策を推進するために必要な費用について財政上の措置等を講ずることとされた。また、本法律の措置は、事故由来放射性物質を放出した関係原子力事業者の負担のもとに実施されることとされた。
5) その他
検討条項(附則)として、一般的な見直し条項のほか、放射性物質に関する法制度のあり方についての検討、原子力発電所の事故に係る原子炉等についての必要な法整備等が盛り込まれた。
(4) 適用実績
平成23年11月11日には基本方針が閣議決定され、環境汚染の状況についての監視・測定、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理、土壌等の除染等の措置等に係る考え方が取りまとめられた。平成23年12月28日に汚染廃棄物対策地域及び除染特別地域として11市町村(4市町村は一部地域)、同日及び平成24年2月28日には、汚染状況重点調査地域として104市町村を指定した。除染特別地域については平成29年3月に、汚染状況重点調査地域については平成30年3月末で面的除染が完了している。
※詳細は7章3節1.を参照
(5) その後の法改正等
平成24年6月に成立した原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の制定に伴い、環境基本法が改正され、放射性物質による環境汚染の防止のための措置を原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除された。これを受け、翌年、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第60号)により、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の関係法律についても、放射性物質による環境汚染を適用除外とする規定が削除されるとともに、関連の規定が整備された。
なお、附則に盛り込まれた原子力発電所の事故に係る原子炉等についての必要な法整備等についても、原子力規制委員会設置法の制定及びこれに伴う炉規法や原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)等の改正等の対応がなされた。
26. 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
原子力発電所の事故により、放射性物質に汚染された廃棄物や、除染等の実施に伴う除去土壌や廃棄物(以下「除去土壌等」という。)が大量に発生することとなったが、これら膨大な除去土壌等の最終処分の方法をすぐには明らかにしがたい状況にあったことから、一定期間、安全に集中的に貯蔵・管理する「中間貯蔵施設」が必要不可欠となった。平成23年8月27日、これを福島県内に設置することについて、菅直人総理大臣から福島県知事に要請がなされた。さらに、中間貯蔵施設の具体的なイメージを示した「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処において必要な中間貯蔵施設等の基本的考え方について」(ロードマップ)が、同年10月29日に環境省により策定された181。
こうした中間貯蔵を福島県内で行うことについては、福島県等の自治体から強い反発があったが、国は、中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了する方針を繰り返し説明してきており、これを法律で規定する等の担保が求められていた。
また、長期にわたる中間貯蔵に係る一連の事業を実施するに当たり、国が第三者に委託する際には、単なる契約関係のみを持つ民間企業ではなく、国が株式の過半数を保有し、環境大臣の指揮監督下にあり、かつ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)という処理困難な廃棄物の処理の実績を持つ日本環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という)に担わせることが適当であるため、JESCOを中間貯蔵・環境安全事業株式会社に改組し、その事業に中間貯蔵に係る事業を追加する方針となった。
これらの内容を規定するため、「日本環境安全事業株式会社法」が改正されることとなった。
- 181 中間貯蔵施設を福島県内に設置する方針は、本法律の前に、放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針(前述)や福島特措法に基づく福島復興再生基本方針にも盛り込まれた。その後、具体的な設置場所については、自治体との調整を経て、最終的に双葉町・大熊町となった。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成26年10月3日に閣議決定、国会に提出され、10月31日の(衆)環境委員会において全会一致で可決、11月4日の(衆)本会議において賛成多数で可決された。その後、同月18日の(参)環境委員会で賛成多数で可決され、翌19日の(参)本会議において賛成多数で可決・成立した。衆参の採決においては附帯決議が付され、最終処分地の選定等に必要な技術開発等の工程表を作成し、その取組の進捗状況について毎年国会に報告することや、除去土壌等の輸送ルートの策定等について地元の意見を十分に聞くこと等が盛り込まれた。
本法律は平成26年11月27日に公布、同日に一部施行され、同年12月24日に本格施行された。
(3) 法概要・措置内容
本法律は、放射性物質汚染対策特措法に基づく除去土壌等や特定廃棄物のうち、福島県内除去土壌等(福島県内において生じた除去土壌等及び特定廃棄物(事故由来放射性物質による汚染が著しいもの等))を対象にしており、国の責務として、中間貯蔵施設の整備・安全確保等に必要な措置を講ずることとされたほか、「中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」こととされた。
また、JESCOが、国、県、県内の市町村その他の者の委託を受けて新たに中間貯蔵事業を担うこととし182、JESCOの名称が「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に、法律の題名が「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」に変更された。なお、同社は、引き続き、PCB廃棄物処理事業等も行うこととされている。
なお、「中間貯蔵」の定義については、「最終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について、福島県内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分」とされた。
- 182 平26年10月28日(衆)環境委員会にて、これまで放射性物質を扱ってこなかったJESCOの適格性・体制については、「高濃度のPCBに関してはJESCOが唯一であり、受け入れの管理からその技術の管理、その中で労働者の管理、そして環境への排出等を相当緻密に積み重ねてこられた事業体として適切である」「民間会社は、JESCOのような特殊会社に対する強い指揮監督権を国は有しておらず、国が求める期間、法人の業務として中間貯蔵事業が継続されることが法律などにより担保されていない」と答弁されている。
(4) 適用実績
平成26年12月24日に同法律が施行されたことを受け、JESCOは社名を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に変更し、本社に「中間貯蔵事業部」を、福島県いわき市に「中間貯蔵管理センター」を設置した。また、従来業務であるPCB廃棄物処理事業については体制等に変更なく(事業所名の変更はあった)継続することとなった。
また、平成27年3月に輸送が開始され、福島県内の除染で発生した除去土壌等について、帰還困難区域を除き令和3年度末までに中間貯蔵施設へ概ね搬入完了するという目標を達成した。令和4年12月末時点で約1,338万m3の除去土壌等(帰還困難区域を含む)が中間貯蔵施設に搬入されている。
27. 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(平成25年法律第32号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
原賠法第18条第2項第1号は「原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと」を原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)の事務として規定しており、文部科学省は、審査会の和解の仲介の手続を実施する組織として「原子力損害賠償紛争解決センター」(通称ADRセンター)を設置(平成23年9月1日から業務開始)し、被害者と東京電力の間の和解の仲介を行っていた。しかし、審査会には毎月300件を超える和解の仲介の申立てがあり、当時の処理状況に鑑みると、民法(明治29年法律第89号)第724条の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効である「被害者が損害及び加害者を知ったときから3年」(いわゆる短期消滅時効。最短で平成26年3月)経過前に全ての案件を処理することは困難な見込みであった183。
しかし、民法上、和解の仲介の申立てには時効中断の効力が認められていないため、時効の完成前に和解がなされる見込みがない場合には訴訟手続に移行せざるを得ず、また、新たに利用しようとする者も、時効の完成を危惧して和解の仲介の利用を躊躇することになり、被害者にとって利点のある和解仲介制度が活用されなくなるおそれがあった。
このため、被害者が時効の完成を懸念することなく和解の仲介手続を利用されるようにするため、緊急に必要な措置として、本法律(いわゆる「原賠ADR時効中断法」)が制定されることとなった184。
- 183 平成25年5月17日(衆)文部科学委員会において、「申込件数につきましては、5月16日、昨日の時点までで、6422件」「標準的な案件につきまして、申し立てから3カ月程度での終結を目指すということを掲げておりました。しかしながら、申し立て件数につきましては、先ほど申し上げましたように相当多数に上るという実情がございまして、平成24年までに申し立てがあった件数につきまして、現時点で、平均的に見ますと、終結までに8カ月以上を要しているというのが実情でございます。」、同月28日(参)文教科学委員会において、「昨年の3月から7月にかけましては大体月間で400件台、一番これまで多かった件数といたしましては昨年の5月に480件に上るお申立てをいただいていた時期もございました。ところが、最近になりましてこの申立ての件数は今減少傾向に実はなっておりまして、今年の4月では月間大体340件程度のお申立てをいただいている」との文部科学省答弁がある。
- 184 なお、前例として、公害紛争処理法や男女雇用機会均等法等、他法律の中にも同様の規定の例があった。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成25年4月23日に閣議決定、国会に提出された。5月17日の(衆)文部科学委員会では、日本共産党、社会民主党・市民連合から、そもそも短期消滅時効を適用しないこととする修正案が出されたが否決されるとともに、原案通り可決され、同月21日に(衆)本会議で全会一致で可決され、同月28日に(参)文教科学委員会で可決、翌29日に(参)本会議で全会一致で可決・成立した。なお、衆参いずれにおいても、原子力損害の賠償請求権について短期消滅時効及び消滅時効・除斥期間に関して法的措置の検討を含む必要な措置を講じること等を含む附帯決議が付された。
本法律は、平成25年6月5日に公布・施行された。
(3) 法概要・措置内容
本法律では、審査会が和解の仲介を打ち切った場合185に、和解の仲介を申し立てた者がその旨の通知を受けた日から一月以内に訴えを提起したときは、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなすものとされた。これにより、和解の仲介の途中で時効が経過した場合でも、和解の仲介の打切りの通知を受けた日から一月以内に裁判所に訴訟を提起すれば、和解の仲介を申し立てた時点が訴訟提起の時点とみなされることになり、その時点で時効が中断することから、債務者である東京電力は当該裁判において賠償債務の時効消滅を主張することはできなくなる。
- 185 本法律第2条では、和解仲介の打切り理由が「和解の仲介によっては申立てに係る東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争が解決される見込みがない」場合に限って時効中断の効力が認められることとされているが、審査会が和解の仲介を打ち切った場合にはすべからくこの理由に該当することとなる。
(4) その後の法改正等
平成29年の民法(債権法)改正で時効中断の規定も改正されたこと等から、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の中で「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の完成猶予の特例に関する法律」に名称変更等される等の改正があった。
その後、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第90号)において、本件事故に限らず、原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続一般について、和解の仲介が打ち切られた場合における時効の中断に係る特例(原賠法第18条の2)が置かれるとともに、本法律は廃止された。
28. 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成25年法律第97号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
福島原子力発電所事故の原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効に関しては、前述の原賠ADR時効中断法が制定されたほか、東京電力の総合特別事業計画(原子力損害賠償支援機構法に基づき平成25年2月等認定)において柔軟な対応が約束され、同社により、起算点を遅らせる、被害者と直接協議している期間は時効期間として算入せず事実上停止しているものとして扱うといった措置が講じられてきた。しかしながら、今般の原子力損害が、避難費用、財物損害、就業補償、精神的損害など多岐にわたる上に、被害者の多くは証拠収集が困難である等、事故から3年を経過する平成26年3月までに損害賠償が終わる見込みが立たず、賠償請求権が時効消滅するおそれがあった。
このような状況について、日本弁護士連合会186をはじめとする各団体や、前述の原賠ADR時効中断法の国会審議においても、今般の原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効に関して特別の立法措置をとるべきとの主張が強くなされたところであった187。
平成25年11月8日、自民党・公明党の提言「原子力事故災害からの復興加速化に向けて~全ては被災者と被災地の再生のために~」(与党3次提言)がまとめられ、この中で、「原子力損害賠償に関する消滅時効に対して地元の不安の声が残されていることに鑑み、こうした不安を払拭するため、時効停止・延長に関する法的措置を含む対応策を、与党と連携して検討すること。」が盛り込まれた。また同月、「与党・原子力損害に係る賠償請求権の時効問題に関するワーキングチーム(座長:額賀福志郎議員(自民党)、座長代理:大口善徳議員(公明党))」が設置され、民法724条前段(3年の短期消滅時効期間)は10年に延長する等の案が採用されることとなった。その後、自民党及び公明党における与党内手続と並行して、野党各党からも賛同を得て、本法律(いわゆる「原賠時効特例法」)が衆議院文部科学委員委員長から提案されることとなった。
- 186 日本弁護士連合会の平成25年4月18日の意見書では、短期消滅時効を適用しない等の主張であったが、同年7月18日の意見書では、「権利行使が可能となった時から10年間」等の立法措置を平成25年末までにすべきとの主張がなされた。
なお、前述した通り、衆参の原賠ADR時効中断法採決時の附帯決議にも盛り込まれた。 - 187 時効問題に対する包括的な立法措置の必要性について、文部科学大臣は、平成25年5月28日(参)文教科学委員会で「民法で規定された時効期間を延長したり時効を撤廃した場合の御指摘のデメリットとしては、例えば、被害者、加害者双方にとって、責任や損害の額などを明確にするために必要な書類の散逸により紛争解決が困難となったり、早期解決に向けたインセンティブが損なわれるなど、紛争解決が逆に長引いてしまうのではないかということが考えられます。他方で、被害者の中には民法が規定する時効期間内に損害請求することが困難な事情を抱えている方もいる可能性もあるということもありますので、こうした事情を踏まえつつ、今後とも、各省庁とも連携しつつ検討していくことが必要ではないかと現時点で考えております」と答弁している。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成25年11月27日の(衆)文部科学委員会で、委員会提出法律案とすることが全会一致で議決されるとともに、本案に関する決議188が議決された。同法案は、翌28日の(衆)本会議でも全会一致で可決され、12月3日の(参)文教科学委員会及び翌4日の(参)本会議においても全会一致で可決され、成立した。衆参いずれにおいても、本法案について討論は行われなかった。
本法律は、平成25年12月11日に公布・施行された。
- 188 「東日本大震災に係る原子力損害の被害者に対する賠償の適切かつ確実な実施に関する件」。政府に、賠償の実施状況の定期的確認及びその結果等を踏まえた時効に関する法制上の措置の検討を求めるもの。
(3) 法概要・措置内容
本法律は、特定原子力損害(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による損害であって、東京電力が賠償責任を負うもの)を対象に、下記2点を定めている。
1) 早期かつ確実な賠償を実現するための措置
特定原子力損害の被害者への早期賠償のための体制を国が構築するために必要な措置として、下記が規定された189。
・国の行政機関における特定原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備(具体的には、経済産業省資源エネルギー庁原子力損害対応室の拡充等が想定されている。)
・紛争の迅速な解決のための原子力損害賠償紛争審査会及び裁判所の人的体制の充実(具体的には、審査会の和解仲介に係る人的体制の充実、裁判所による人的体制の充実に必要な予算上の措置等が想定されている。)
・原子力損害賠償支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化(原子力損害賠償支援機構法に基づき行っている情報提供窓口の設置等の被害者に対するサポート体制を一層強化することが想定されている。)
- 189 東京弁護士会発行『LIBRA Vol.14 No.3』2014/3「法令解説 原賠早期賠償特例法」(衆議院法制局 皆川治之氏)の記事を参考にしている。
2) 消滅時効の特例
特定原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例として、民法第724条を下記のように読み替えることとされた。
| 民法第724条(当時) | 読替後 |
| 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 | 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。損害が生じた時から20年を経過したときも、同様とする。 |
前段の短期消滅時効「10年間」については、被害者の不安払拭等に足る一定以上の長期間にする必要性等が総合的に勘案され、民法第167条第1項の債権消滅時効(10年間)も参考に設定された。また、後段の「20年」の除斥期間については、晩発性の健康損害について除斥期間の起算点を当該「損害が発生した時」とする判例法理が確立していることを踏まえ、これと同趣旨で、除斥期間の起算点を「損害が生じた時」と明記したものである190。
- 190 東京弁護士会発行『LIBRA Vol.14 No.3』2014/3「法令解説 原賠早期賠償特例法」(衆議院法制局 皆川治之氏)の記事を参考にしている。
(4) その後の法改正等
平成29年の民法(債権法)改正で消滅時効の規定も改正されたこと等から、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の中で「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効の特例に関する法律」に名称変更等されるとともに、民法に新設された第724条の2は適用しないこととする等の改正があった。
その後、事故発生から10年を迎えるに当たって、原賠時効特例法提出時の立法事実であった、避難生活を余儀なくされたことによる証拠収集の困難さや、賠償の請求に要する時間の問題などの状況は変化してきていること、東京電力が「原子力損害賠償債権の消滅時効に関する当社の考え方について(令和元年10月30日)」において、引き続き、「原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について(平成25年2月4日)」の通り、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も、特別事業計画に基づき最後の一人まで賠償を貫徹するべく、消滅時効に関して柔軟な対応を行うとの方針を表明していること等を踏まえ、時効期間の再延長を目指すよりも、引き続き、積極的な広報や東京電力に適切な対応を促すなどの取組を通じて、早期賠償完了につなげていくことが適切であるとの考えから、上記期間の再延長は、行われなかった191。
- 191 日本弁護士連合会からは、短期消滅時効を「20年間」に再延長する等の意見書が令和2年3月18日に公表された。
29. 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年法律第112号)
30. 国会法の一部を改正する法律(平成23年法律第111号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
福島原子力発電所の事故の調査・検証については、政府としては、平成23年5月24日の閣議決定192に基づき、「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」(畑村洋太郎(東京大学名誉教授・工学院大学教授)はじめ10人の学識経験者により構成。いわゆる「政府事故調」)193を設置したが、この委員会が法令ではなく閣議決定に基づくことから権限が曖昧であるとの批判や、政府の対応の検証を政府に置かれる機関が行うことへの批判があった194。
そのような中、自民党は、国会に第三者により構成する事故調査機関(証人喚問(罰則付き)権限を有する)を設置する骨子案をまとめた。また、公明党も、国会に事故調査機関を置くべきとし、さらに国会議員で構成する両院合同調査特別委員会を置く等の骨子案をまとめた。その後、両党で調整が進められ、平成23年8月9日、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案(第177回国会衆法第24号)及び国会法の一部を改正する法律案(第177回国会衆法第25号)(以下2法まとめて「野党法案」という。)が、自由民主党・無所属の会、公明党及びたちあがれ日本の3会派より提出された。
- 192 「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会の開催について」(平成23年5月24日)。
- 193 平成23年12月26日に中間報告、平成24年7月23日に最終報告書を取りまとめ(全13回開催)、平成24年9月28日に廃止。なお、本件事故に関しては、国会事故調や政府事故調のほか、いわゆる民間事故調(福島原発事故独立検証委員(平成24年2月27日報告))及びいわゆる東電事故調(福島原子力事故調査委員会(平成24年6月20日報告))がそれぞれ調査・報告を行った。
- 194 平成23年5月31日(参)文教科学委員会で草川昭三議員より「政府も検証される立場にあると思うんで、委員会の設置根拠が法律ではなく閣議決定にとどめたことに私は懸念を持っておるものです。(略)五月二十四日の閣議決定では委員会の調査目的や範囲がはっきりしない。」との発言有り。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
野党法案の提出を受け、両議院の議院運営委員会の理事を中心に、各会派をメンバーとする実務者協議が行われた。当初、与党側は、公正取引委員会や人事院のように行政機関ではあるものの内閣から強い独立性を持った機関とすることを主張した。しかし野党側は、国会に事故調査機関を置くことが前提であると主張し、第177回国会中には結論は出ず、次期臨時国会において成案を得るようにする旨が確認された。その後も引き続き与野党の実務者協議が行われ、その結果、野党法案をベースに与党意見を一部反映した成案が取りまとめられた195。
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案(第178回国会衆法第2号)及び国会法の一部を改正する法律案(第178回国会衆法第1号)は、平成23年9月29日の(衆)議院運営委員会で、同委員会提出の法律案とすることに全会一致で決し、同日の(衆)本会議に緊急上程され、全会一致で可決された。翌30日に(参)議院運営委員会及び(参)本会議で、それぞれ全会一致をもって可決された。
両法律は、10月7日に公布・10月30日に施行された。
- 195 与野党の立案・協議経緯については、中川博史(衆議院法制局法制企画調整部企画調整課)「国会原発事故調査委員会の設置」時の法令1906号(平成24年5月)P.4以下、塩崎恭久『「国会原発事故調査委員会」立法府からの挑戦状』(東京プレスクラブ、平成23年12月)及び岡田祐二(元塩崎恭久衆議院議員秘書)「国会原発事故調査委員会設置の経緯と法制上の課題」法律のひろば(平成24年4月)P.24以下を参考にしている。なお、与党調整後の修正点は、「両院合同協議会」が、調査について、自らは行わず、専ら第三者機関からの要請を受けて国政調査権を発動する側面支援を行うことになった点、第三者機関の調査(原則公開)の事前又は事後に予備的又は補完的調査ができることを明記した点等である。
(3) 法概要・措置内容
1) 国会法の一部を改正する法律
附則が追加され、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故の原因究明等のため、国会に、両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)を置き、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(以下「国会事故調」という。)を置くこととされた。両院合同協議会の設置期限は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法が効力を有する期間とされている。
なお、このように、国会議員ではない民間の有識者を構成員とした第三者機関が国会に置かれたことについては、「憲政史上初の試み」と言われている196。また、国会という政治の場に置かれる国会事故調については、政治的中立性の確保が強調された197。
- 196 例えば、平成23年12月8日第3回両院合同協議会にて、小平会長より、「国会におきましても、憲政史上初めて、国会議員以外の有識者から成る第三者機関として、事故調査委員会を設けることを全会一致で決定した」との発言がある。
- 197 平成23年9月29日(衆)議院運営委員会及び翌日の(参)議院運営委員会において確認された両法の運用に関する申合せにおいて、「本院所属議員においては、党派的な立場から(中略)政治的に利用し、又はこれに政治的な影響を与えてはならないこと」「(前略)いささかも政治的中立性に欠けるとの疑念を持たれることのないよう留意すること」等が盛り込まれている。
2) 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法
東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故の原因究明等のため、国会に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置き、委員長及び委員9人をもって組織し、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命することとされた。
国会事故調は、必要に応じ、参考人招致198ができるとともに、国や原子力事業者等の関係者に対し資料提出を要求することができることとされた。また、特に必要があると認めるときは、両院合同協議会に対し、国政調査を行うよう要請することができることとされた。
国会事故調は、任命の日から起算して概ね6か月後を目途として、報告書をまとめ、その提出をもってその調査活動を終了することとし、法律自体は、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失うこととされた。また、国会事故調の報告書は内閣に送付することとされ、これに関連して、上記1)の国会法改正では、内閣は、当分の間、毎年、国会に、同報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならないこととされた。
- 198 民間委員に国政調査権を共有することについては野党内でも様々な議論があり、自民党案では「証人喚問」(罰則あり)の権限を付与していたが、公明党との調整によって削除され、参考人招致にとどめられた(岡田祐二(元塩崎恭久衆議院議員秘書)「国会原発事故調査委員会設置の経緯と法制上の課題」法律のひろば(平成24年4月)より)。
(4) 適用実績
1) 両院合同協議会
平成23年11月2日、衆参両議院の議長の指名で、両院からそれぞれ15人ずつ計30人が指名された。同日の第1回両院合同協議会で、会長に小平忠正(衆)議院運営委員長、会長代理に鶴保庸介(参)議院運営委員長が指名された。
その後、平成23年12月1日、12月8日に開催し、委員の推薦等が行われた。
2) 国会事故調
平成23年12月1日、両院合同協議会において、委員長及び委員の推薦が議決され、翌日、衆参両議院の本会議において承認され、同月8日、衆参両議院の議長により、黒川清委員長(医学博士、東京大学名誉教授、元日本学術会議会長)はじめ10人が任命された。
関係者ヒアリング、原子力発電所視察、タウンミーティング等を重ね、平成24年7月5日の第20回委員会で、規制当局に対する国会の監視、政府の危機管理体制の見直し、新しい規制組織の要件等の7つの提言を含む報告書がまとめられ、同日に両院議長に提出された199。
- 199 各事故調の報告書の内容は、7章1節参照。
3) 内閣からの報告
政府は、国会事故調及び政府事故調の報告書の提言を受けた政府によるフォローアップについて、平成24年11月に事故調フォローアップ有識者会議(座長:北澤宏一氏(民間事故調(福島原発事故独立検証委員会)委員長、前独立行政法人科学技術振興機構理事長)、事務局:内閣官房)を設置する等して検討し、これまでに平成24年度(平成25年6月)~令和3年度(令和4年6月)の11回にわたって「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置」を閣議決定し、国会に報告した。
31. 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成23年法律第42号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災はその被害が広範であり被害額の算定に時間を要することから、補正予算は平成23年度の補正予算として編成される方針となり、補正予算を複数回編成するという前提の下、平成23年4月28日に平成23年度第一次補正予算案(4兆153億円)が国会に提出された。
政府は、この平成23年度第一次補正予算に必要な財源を確保する必要があったが、国の厳しい財政状況からすれば財政健全化の方向性を示すことが必要であり、大規模な財政出動が必要となる復興段階を前にした復旧段階の一次補正については、国債に頼らない200で確保することとし、経済危機対応・地域活性化予備費の減額(約8,000億円)や基礎年金国庫負担の年金特会への繰入の減額(約2兆5,000億円)等によりその確保が行われることとなった。
なお、このうちの基礎年金国庫負担については、震災前の平成22年12月に、平成23年度限りの措置として、基礎年金給付費の2分の1と36.5%(当時の国庫負担割合)の差額を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構特例業務勘定の利益剰余金、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金、外国為替資金特別会計の剰余金を臨時財源とする形で国庫負担とすることが決定201されていたところ、その方針を平成23年4月19日に修正202することで、平成23年度第一次補正予算の財源としたものである。
これらの財源を東日本大震災の復興に活用できるようにするための特別措置を定め、平成23年度第一次補正予算の財源を確保する「東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」を整備した。
- 200 平成23年5月1日 第177回国会参議院予算委員会 菅直人内閣総理大臣(対藤井基之議員)
- 201 財務大臣・厚生労働大臣・国家戦略担当大臣 合意書 「平成23年度以降の基礎年金国庫負担の取扱いについて」(平成22年12月22日)
- 202 財務大臣・厚生労働大臣・国家戦略担当大臣 合意書 「平成23年度の基礎年金国庫負担について」(平成23年4月19日)
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年4月28日に閣議決定、国会に提出された。4月30日に(衆)財務金融委員会において全会一致で可決、同日に(衆)本会議において全会一致で可決され、5月2日に(参)財政金融委員会において全会一致で可決(※附帯決議あり)、同日、(参)本会議において全会一致で可決・成立した。
本法律は、平成23年5月2日に公布・施行された。
なお、同日、平成23年度第一次補正予算は成立した。
※(参)財政金融委員会における附帯決議
東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 東日本大震災の被災地域が一刻も早く復興するよう、道路、鉄道等の交通ネットワークの速やかな復旧・復興など、対応に万全を期すこと。
一 平成23年度第一次補正予算における財源措置として活用した年金臨時財源については、平成23年度第二次補正予算の編成に際して見直しも含めた検討を行うこと。
一 子ども手当、高速道路無料化及び農家戸別所得補償等の歳出策の在り方については、平成23年度第二次補正予算の編成に向けて、早急に見直しの検討を進めること。
一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構からの国庫納付については、臨時異例の措置とするとともに、JR三島貨物会社への支援や北陸新幹線の債務償還等を確実に実施すること。
(3) 法概要・措置内容
平成23年度において、東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付の特例措置が定められた。
1) 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ
財政投融資特別会計財政融資資金勘定から1兆588億円を一般会計に繰り入れることができることとされた。
2) 外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ
決算上の剰余金の繰入れに加えて、外国為替資金特別会計から2,308億5,896万1,000円を一般会計に繰り入れることができることとされた。
3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、特例業務勘定から1兆2,000億円を国庫に納付しなければならないこととされた。
4) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付の特例
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、高速道路勘定から2,500億円を国庫に納付しなければならないこととされた。
32. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第7条において、国は、「復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること」及び「財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること」等により、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとされ、また、第8条において、「国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債を発行するもの」とされ、当該公債(以下「復興債」という。)については、「その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするもの」とされた。
同法第3条に基づき策定された「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年8月11日改定 東日本大震災復興対策本部)では、「平成27年度末までの5年間の「集中復興期間」に実施すると見込まれる施策・事業(平成23年度第一次補正予算等及び第二次補正予算を含む)の事業規模については、国・地方(公費分)合わせて、少なくとも19兆円程度と見込まれる」とされ、その財源については、「次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯し負担を分かち合うことを基本とする」こととし、「5年間の「集中復興期間」中の復旧・復興事業に充てる財源は、平成23年度第一次補正予算等及び第二次補正予算における財源に加え、歳出の削減、国有財産売却のほか、特別会計、公務員人件費等の見直しや更なる税外収入の確保及び時限的な税制措置により13兆円程度を確保する」こととされた。
加えて同方針においては復興債について「その発行のあり方について十分検討するとともに、従来の国債とは区分して管理する」こと、「その償還期間は、集中復興期間及び復興期間を踏まえ、今後検討する」こと、「時限的な税制措置は、償還期間中に行い、その税収は、全て復興債の償還を含む復旧・復興費用に充て、他の経費には充てないことを明確化するため、他の歳入とは区分して管理することとする」ことが盛り込まれた。
さらに、同方針では、「平成23年度第三次補正予算の編成にあわせ復興債の発行及び税制措置の法案を策定し国会に提出する」こととされ、「税制措置の具体的内容については、8月以降、本基本方針を踏まえ、税制調査会において検討し、具体的な税目、年度毎の規模等を組み合わせた複数の選択肢を東日本大震災復興対策本部に報告した上で、政府・与党において改めて検討を行い、同本部において決定する」こととされた。
税制調査会においては、平成23年9月16日に「復興・B型肝炎対策財源としての税制措置の「複数の選択肢」(国税)」203が示され、「[1]基幹税のうち、所得税・法人税に負担を求める204」場合と「[2]基幹税(所得税・法人税)を中心にするが、個別間接税にも負担を求める205」場合の試算が10.4兆円程度と示された。この後、同年10月11日の税制調査会に「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」が示され、「復興特別所得税(仮称)」、「復興特別法人税(仮称)」及び「復興特別たばこ税(仮称)」の創設が盛り込まれた。
これらの経緯を踏まえ、東日本大震災の復興財源についての法制化を目的として、税外収入に関する措置及び復興特別税の創設、復興債の発行等の措置等を規定する「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案」が内閣から国会に提出された。
一方、後述する国会審議において、衆議院において、復興特別所得税の課税対象期間及び税率の修正、復興特別たばこ税の削除、復興債等の償還期間の延長等を盛り込んだ修正案が決議され、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」として整備された。
- 203 「複数の選択肢」に係る試算例は、こうした一連の検討のプロセスにおける「議論の素材」、ないしは「たたき台」として活用されることを目的として策定するものであり、「復興の基本方針」及び「B型肝炎訴訟の全体解決の枠組みに関する基本方針」等に基づいて、できるだけ予断を交えずに、いくつかの技術的前提を置いて作業をしたもの
- 204 23年度税制改正事項(0.7兆円)を復興財源に充てるとともに、所得税(7.5兆円)・法人税(2.4兆円)に時限的な付加税を課すもの
- 205 23年度税制改正事項(0.7兆円)を復旧・復興財源に充てるとともに、所得税(5.5兆円)・法人税(2.4兆円)に付加税を課し、たばこ税(等)(1.7兆円)についても臨時の特別税を課すもの
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年10月28日に閣議決定、国会に提出された。11月7日に(衆)本会議で趣旨説明、質疑を行い、同月9日に(衆)財務金融委員会において趣旨説明、同月18日に質疑を行った後、民主党・自民党・公明党の3党共同提案による修正案が提出された。この修正案提出のまえに、「税関係協議結果」(平成23年11月10日、民主党、自由民主党及び公明党の3党税制調査会長合意)、「平成23年度第三次補正予算等に関して」(平成23年11月11日、民主党、自由民主党及び公明党の3党政策(政務)調査会長合意)、「税外収入等について」(平成23年11月15日、民主党、自由民主党及び公明党の3党実務者合意)といった合意が3党間で交わされている。同月22日に内閣提出案及び修正案に対し参考人招致・質疑が行われ、その後内閣総理大臣出席の下質疑を行い、同日に賛成多数で修正議決(※附帯決議あり)された。修正議決法案は、同月24日に(衆)本会議において賛成多数で可決された。
翌25日に(参)本会議において趣旨説明・質疑が行なわれ、同日(参)財政金融委員会において趣旨説明を行った。同月29日に同委員会にて質疑及び参考人招致・質疑が行われ、賛成多数で可決(※附帯決議あり)、翌30日に(参)本会議において賛成多数で可決・成立した。
本法律は、平成23年12月2日に公布・施行(一部を除く。)された。
国会では主に以下の論点についての議論がなされた。
1) 復興債の償還期間
当時同時に審議が行われていた第三次補正予算において建設公債発行対象経費が含まれることや、単年度の負担を軽減する観点から、償還期間を建設公債と同様に60年とすべき、との議論があった。当初復興債の償還期間を10年としていたところ、野田総理大臣からは「次の世代に負担を先送りせず、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うとの復興の基本方針における考え方に立って、その期間を設定しております。長い償還期間を設定すれば、単年度の税負担が小さくなることは事実でありますけれども、若い世代は負担をし続けることになる一方、高齢世代は短い期間しか負担を負わないこととなります」と答弁している206。また、復興債の償還を急ぐ理由として、「少子高齢化、人口減少により将来世代の負担が増加していく中で、将来世代へのさらなる負担の先送りは避けるべきであるという考え方や、税金の使途がはっきりと実感できる間に税制措置を行う方が理解をしていただきやすいのではないか、我が国の極めて厳しい財政状況、国家の信用が厳しく問われる歴史的な事態が進行している中、国債の信認の確保についても十分に配慮する必要があるという認識に基づき、その期間を設定しております」と答弁している207。その後、「税関係協議結果」において、償還期間は25年まで延長することとされた。
- 206 平成23年11月7日 第179回国会衆議院本会議 野田佳彦総理大臣答弁(対西村康稔議員)
- 207 平成23年11月7日 第179回国会衆議院本会議 野田佳彦総理大臣答弁(対西村康稔議員)
2) 区分管理
復興基本法においても言及されている、区分管理をどのような形で行うかについて、特別会計を設置すべきではないか、との質問に対し、野田総理大臣は「一般会計予算等において、復旧復興関連経費であることを項として明示するなど、他の経費と区分することとしており、これにより復興基本法及び復興の基本方針における区分管理及び資金の流れの透明化の要請に十分こたえることができる」としつつ、「特別会計の設置は、区分管理及び資金の流れの透明化の要請にこたえる一つの方法と考えられます」と答弁している208。「平成23年度第3次補正予算等に関して」において特別会計が設置されることとなった後は、特別会計設置の検討状況等についての質疑がなされた。
- 208 平成23年11月7日 第179回国会衆議院本会議 野田佳彦総理大臣答弁(対西村康稔議員)
3) 償還財源
政府案においては、復興特別たばこ税の創設が規定されており、そのことについて「昨年十月のたばこ税率の引き上げに伴い、たばこ税収、たばこの販売代金及びJTの利益が増加していることや、葉たばこ農家に対しJT等による支援策が講じられていること等を踏まえた検討を行った」としていた209。これに対し、たばこ税の増税は22年度の税制改正において増税したばかりであり、小売店や葉たばこ農家等への影響が懸念されること等が国会において指摘され、最終的に、当該税目は「税関係協議結果」において削除することとされた。また、当時消費税の増税についても議論があったことから、消費税を財源とすることについても議論されたが、野田総理大臣は「社会保障・税一体改革成案において今後社会保障財源として活用するべきとしていることから、政府税調で複数の選択肢をまとめる段階において、私から、選択肢から外すように指示した」と答弁している210。更に、更なる歳出削減が可能なのではないか、一般会計の決算剰余金が活用できるのではないか、国債整理基金特別会計の剰余金が活用できるのではないか、などといった税収以外の財源について問題提起がなされ、安易な増税に頼るべきではない、との指摘があった。なお、決算剰余金については、「平成23年度第3次補正予算等に関して」において償還費用の財源に優先して充てるよう努めることとされ、本法の附則において同旨の規定が追加された。
- 209 平成23年11月7日 第179回国会衆議院本会議 野田佳彦総理大臣答弁(対西村康稔議員)
- 210 平成23年11月7日 第179回国会衆議院本会議 野田佳彦総理大臣答弁(対西村康稔議員)
4) 企業優遇との批判
法人への付加税について、平成23年度税制改正において、企業の国際競争力の観点から実効税率を引き下げることとしていたことから、付加税を課したとしても実質的に減税なのではないか、法人課税を増やすべきではないか、といった点についても議論された。
※ (衆)財務金融委員会における附帯決議
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 財政投融資特別会計財政融資資金勘定の剰余金の復興財源への活用の検討に当たっては、予算編成過程において、同勘定の財務の健全性に配慮を行うこと。
一 日本たばこ産業株式会社の株式について、政府の保有義務割合を設立時発行済株式総数の二分の一以上から発行済株式総数の三分の一超に引き下げることによる同社株式の売却に当たっては、株式市況を見極めて売却時期を慎重に判断するとともに、修正後の附則第十三条に基づき、更なる同社株式の政府保有義務の見直しの検討に当たって「たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案」する際には、葉たばこ農家や小売店への影響等を十分見極めること。
一 修正後の附則第十三条に基づき、エネルギー対策特別会計に所属する株式の保有の在り方の見直しの検討に当たって「エネルギー政策の観点を踏まえ」る際には、日本の資源確保に係る権益確保、相手国の協力関係維持への影響等を十分見極めること。
一 本法案が多年度にわたる復興債の発行を認めるものであることに鑑み、復興債の発行に当たっては、復興基本法に規定する基本理念に照らして真に東日本大震災からの復興に資する施策の経費に充てること。
※ (参)財政金融委員会における附帯決議
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措 置法案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 財政投融資特別会計財政融資資金勘定の剰余金の復興財源への活用の検討に当たっては、予算編成過程において、同勘定の財務の健全性に配慮を行うこと。
一 日本たばこ産業株式会社の株式について、政府の保有義務割合を設立時発行済株式総数の二分の一以上から発行済株式総数の三分の一超に引き下げることによる同社株式の売却に当たっては、株式市況を見極めて売却時期を慎重に判断するとともに、修正後の附則第十三条に基づき、更なる同社株式の政府保有義務の見直しの検討に当たって「たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案」する際には、葉たばこ農家や小売店への影響等を十分見極めること。
一 修正後の附則第十三条に基づき、エネルギー対策特別会計に所属する株式の保有の在り方の見直しの検討に当たって「エネルギー政策の観点を踏まえ」る際には、日本の資源確保に係る権益確保、相手国の協力関係維持への影響等を十分見極めること。
一 本法案が多年度にわたる復興債の発行を認めるものであることに鑑み、復興債の発行に当たっては、復興基本法に規定する基本理念に照らして真に東日本大震災からの復興に資する施策の経費に充てること。
(3) 法概要・措置内容211
本法律は、税外収入の確保及び時限的な税制措置の創設と、つなぎとしての復興債の発行に関する措置の両者が、復旧・復興事業を実施するために必要な当面の財源とその償還財源という観点で不可分一体の関係をなすことから、両者を一括して法制化したものである。このことは、東日本大震災復興基本法第8条において、復興債の発行を認めるとともにあらかじめ償還の道筋を明らかにする旨が規定されていることとも整合的である。
本法律においては、第1章に総則を定め、第2章及び第3章として財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れと日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等の措置を定めている。これは、復興財源はまずは税外収入によるべきとの考え方によるものである。第4章及び第5章として復興特別所得税及び復興特別法人税(以下「復興特別税」という。)の創設に関する規定を設け、第6章にこれらの財源が確保されるまでのつなぎとしての復興債の発行等に関する措置を定め、第7章に復興特別税等の収入の使途に関する規定等を設けた。
主な規定及び措置内容は以下のとおり。
- 211 全体にわたって、財務省の広報誌であるファイナンスに掲載された、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について」(ファイナンス、2011年12月号)に基づいている。
1) 基本原則
復興債の収入をもって充てられる費用の財源は、歳出の削減に加えて、復興特別税、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金、日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の処分収入並びに国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入によって確保することとした。この原則により、これらの財源によって確保される範囲を超えて復興債を発行することはできないこととされるものであった。
2) 財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金の活用
財政投融資特別会計財政融資資金勘定では、金利動向等によって損失が発生することがあり得るため、毎年度の剰余金は、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)により、政令で定める水準(総資産の50/1,000)にいたるまで金利変動準備金として積み立てることとされているところ、本法律に基づき、平成24年度から平成27年度まで、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、各年度の予算をもって定める額を国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとしている。
なお、当時において、財政融資資金勘定の金利変動準備金は累次の特例措置が講じられてきた結果、ほぼ枯渇した状態にあり、行政刷新会議の特別会計仕分けにおいて金利変動準備金に必要額を積み立てることが必要な旨の評価結果が出されていたが、復興財源として活用することから、復興期間が終了するとされていた平成32年度(令和2年度)までの間、一般会計から財政融資資金勘定へ繰入れを行うことができることとする規定が、万が一に備えた特例措置として附則に設けられた。
3) 日本たばこ産業株式会社の株式の処分
日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)において、政府は、設立時に無償譲渡された株式の総数の2分の1以上の保有及び発行済株式総数の3分の1超を保有していなければならないこととされており、当時、政府は同社の株式総数の50%を、財政投融資特別会計の投資勘定において保有していた。
本法律においては、同社の株式の総数の3分の1を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式(同社の株式総数の約16.7%)を、復興債の償還費用財源に充てるため、同勘定から無償で国債整理基金特別会計に所属替を行い、できる限り早期に処分することとした。
加えて、附則において、日本たばこ産業株式会社の株式に係る政府保有義務割合を発行済株式総数の3分の1超に引き下げる措置を講じたが、定款変更等株主総会において3分の2以上の賛成が必要な特別決議を阻止することは引き続き可能であり、重要な経営政策への一定の公的関与の確保のために必要な政府保有比率の最低限度は引き続き確保されることとなった。
4) 東京地下鉄株式会社の株式の処分
政府は、東京地下鉄株式会社の発行済株式総数の53.4%を保有(うち50.4%分については国債整理基金特別会計に所属、旧国鉄清算事業団への無利子貸付の代物弁済により取得した3%分については一般会計に所属)していた。
本法律により、東京地下鉄株式会社の株式の処分収入を復興債の償還費用財源に充てるため、同社の株式のうち一般会計に所属している3%分の株式について、無償で国債整理基金特別会計に所属替をすることとした。
5) 復興特別税の創設
復旧・復興のための財源に係る税制措置については、「東日本大震災からの復興の基本方針」において、「復旧・復興のための財源については、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯し負担を分かち合うことを基本とする」とされたことを踏まえつつ、
① 経済への配慮、
② 簡素な税制、
③ 適切な税制措置の期間設定、
④ 平成23年度税制改正等との関係
といった観点等を総合的に勘案し、所得税額及び法人税額に対する時限的な付加税として、復興特別所得税及び復興特別法人税が創設されることとなった。
復興特別所得税については、現行の所得税額に対して平成25年1月から平成49年(令和19年)12月までの時限的な措置として、2.1%の付加税を創設した(納税義務者・源泉徴収義務者は所得税の納税義務者・源泉徴収義務者と同じとしている)。
また、復興特別法人税については、平成23年度税制改正における法人税の実効税率の引下げ及び課税ベースの拡大を実施した上で、平成24年度から平成26年度までの時限的な措置として、法人税額に対して10%の付加税を創設した。課税標準は法人税額とし、納税義務者は法人税の納税義務者と同じとしている。なお、平成23年度税制改正における法人税の実効税率引下げ及び課税ベース拡大の施行時期は平成24年度からとすることとされた。本法律では、これらの時限的な税制措置を実施するために必要な事項を規定した。
復興特別所得税の課税期間は、国会に提出した政府案においては、平成25年1月から平成34年(令和4年)12月までの10年間とされていたところ、衆議院における修正212により、平成25年1月から平成49年(令和19年)12月までの25年間とされた。また、復興特別所得税の税率についても、当初案の100分の4から100分の2.1とされた。さらに、時限的な税制措置として、たばこ1本につき1円の臨時特別税の創設に係る規定が設けられていたところ、当該規定については削除された。
- 212 民主党、自由民主党、公明党の3党の税制調査会長間で確認された「税関係協議結果」(平成23年11月10日)において、たばこ税の取扱いについてこれを盛り込まないこと、所得税付加税の期間を25年間(平成25年1月から平成49年12月)とすることとされている。
6) 復興債の発行
復興特別税等による収入が確保されるまでのつなぎとして、平成23年度第三次補正予算以降平成27年度までの各年度において、復興費用の財源に充てるため、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、復興債を発行することができることとした。
7) 年金臨時財源相当分の復興債の発行
平成23年度第一次補正予算において減額された基礎年金の国庫負担の追加に要する費用の財源として、復興債を発行することができることとした。
平成23年度当初予算において基礎年金国庫負担割合を36.5%から2分の1に引き上げるために年金臨時財源2.5兆円を確保していたが、平成23年度第一次補正予算の財源を確保するため、基礎年金国庫負担の年金特別会計への繰入れは減額補正された。その後、平成23年8月9日の民主党・自由民主党・公明党の3党の幹事長の「確認書」において、「第三次補正予算の編成の際に、復興債で補てんすることとし、そのための財源確保策と併せて、各党で検討する」こととされていた。
これらを踏まえ、平成23年度第三次補正予算において基礎年金国庫負担の追加のための費用を計上することとし、上記の経緯を踏まえてこれに必要な費用を復興費用とみなすことにより、復興債を発行することができることとしている。
8) 復興費用の範囲の明確化
復興債の発行対象経費である復興費用の範囲について、毎会計年度、国会の議決を経なければならないこととした。
復興債の発行対象経費は、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念及びこれを具体化する「東日本大震災からの復興の基本方針」に示されているが、極めて多岐にわたり一義的には明らかではないことから、予算総則で定めて国会の議決を経ることとしたものである。
9) 建設公債及び特例公債との関係
復興債の発行対象経費については、実態においては財政法第4条に基づく建設公債の発行対象経費である公共事業費と共通する部分が多いと考えられる。建設公債には、60年かけて償還する、いわゆる「60年償還ルール」が適用されている。しかし、「東日本大震災からの復興の基本方針」において、復興のための財源については、「次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯し負担を分かち合う」こととされており、60年償還ルールが適用される建設公債で賄うことは、東日本大震災復興基本法及び「東日本大震災からの復興の基本方針」の考え方になじまない。このため、復興費用については、建設公債の発行を認めないことを法律上明確に規定した。
なお、特例公債は一般会計予算の歳入歳出の差額を補てんするために発行が認められるものであり、特定の費用を賄うために認められる復興債や建設公債とはそもそも性質が異なることから、東日本大震災復興特別会計が存在しなかった平成23年度においては、「平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律」(平成23年法律第106号)を本法律で附則改正し、復興費用について特例公債の発行を認めないことを明確にしている。
10) 復興債の償還
復興債及び当該復興債に係る借換国債について、平成49年度(令和19年度)までの間に償還することとしている。
復興債は、特に償還財源において他の公債とは明確に区別され、毎年度見込まれる政府保有株式の処分収入や復興特別税の収入を順次償還に充てていくことになる。最後まで見込まれる収入は復興特別所得税であり、この課税期間が平成49年(令和19年)までであることから、復興債の償還年限を平成49年度(令和19年度)としたものである。
11) 収入の使途
復興基本法第9条では、復興に係る国の資金の流れについて、透明化を図ることが求められている。このため、本法律の規定に基づき確保した財源の使途については、復興費用と償還費用のいずれに充当するかを明確に規定した。
まず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金については、特別会計に関する法律により、政令で定める水準を超える場合には、超過金額の範囲内で国債整理基金特別会計に繰り入れることができる旨が規定されているところ、本法律に特例規定を設けることで、特別会計に関する法律に基づく政令で定められた金額にかかわらず国債整理基金特別会計に繰り入れて復興債の償還財源に充てることができることとされた。
次に、日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の売払収入については、政府保有義務が外れた部分の株式については国民共有の資産であることに鑑み、従来、国民共有の負債である国債の償還に充てることとされてきたことから、復興債の償還財源に充てることとされた。
なお、集中復興期間の終盤にかけて、復興特別税の収入が復興費用の金額を上回り、復興債の発行を行わなくて済む状況も想定されることから、復興特別税の収入については、復興費用と償還費用の双方の財源に充てることができることとされた。
12) 償還最終年度における精算規定
復興債の償還最終年度における精算規定として、平成49年度(令和19年度)における復興特別所得税の収入について、償還費用の財源に充ててもなお残余がある場合、当該残余の額については特例公債の償還財源に充てることとしている。また、復興債の償還が平成48年度(令和18年度)以前に完了する場合には、当該年度から平成48年度(令和18年度)までの復興特別税の収入等について、同様に特例公債の償還財源に充てることとされた。
特例公債については、本来その発行が望ましいものではないことから、速やかに減債に努める旨が特例公債法において規定されている。このため、残余がある場合の使途として、特例公債の償還財源に充てることとしたものである。
13) 復興財源確保のための措置の見直し
政府は、この法律の施行後適当な時期において、復興の状況等を勘案して、復興費用のあり方及び復興施策に必要な財源を確保するための各般の措置のあり方について見直しを行うこととしている。
14) 租税収入以外の収入による財源の確保
復興財源フレームの見直しを行うに際し、政府は、平成23年度から平成34年度(令和4年度)までの間において2兆円に相当する金額の償還費用の財源に充てる収入を確保することを旨として、次のⅰ)及びⅱ)について検討を行うこととし、その結果、株式の全部又は一部を保有する必要がないと認めるときは、法制上の措置その他必要な措置を講じた上で、当該株式について、できる限り早期に処分することとしている。
ⅰ)日本たばこ産業株式会社の株式について、たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性についての検討。
ⅱ)エネルギー対策特別会計に所属する株式について、エネルギー政策の観点を踏まえつつ、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性についての検討。
このほか、租税収入以外の収入による償還費用の財源を確保するため、日本郵政株式会社の株式213(政府に保有義務が課された、総株主の議決権の3分の1超に係る株式を除く。)について、日本郵政株式会社の経営の状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分のあり方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分することとしている。また、検討の結果に基づき平成34年度(令和4年度)までに行った株式の処分による収入については、償還費用の財源に優先的に充てることとしている。
- 213 日本郵政株式会社の株式については、「日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律」(平成21年法律第100号。以下「凍結法」という。)により売却の凍結が措置されている。したがって、当該株式を売却するためには、凍結法の廃止等を定めた、「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」及び郵政株式の売却及び郵政事業の実施主体の再編成を定めた「郵政改革法案」の成立が前提となる。
15) 決算剰余金の償還費用の財源への活用
政府は、平成23年度から平成27年度までの間の各年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金を公債又は借入金の償還財源に充てる場合においては、復興債の償還費用の財源に優先して充てるよう努めることとしている。
本規定は、民主党、自由民主党、公明党の3党で確認された「平成23年度第三次補正予算等に関して」を踏まえて、衆議院における修正により追加されたものである。
16) 復興特別税の負担軽減措置
上記14)及び15)により償還費用の財源の確保が見込まれる場合に、13)の見直しの結果に基づく復興費用の見込額を勘案しつつ、復興特別税に係る税負担の軽減のための所要の措置を講ずることとしている。
17) 復興に係る特別会計の設置
政府は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に係る歳入歳出を経理する特別会計を平成24年度において設置することとし、必要な法制上の措置を講ずることとされている。また、当該特別会計は、平成23年度第三次補正予算において発行した復興債の償還に係る債務等について承継することとされている。
本規定は、「平成23年度第三次補正予算等に関して」を踏まえ、衆議院における修正により追加されたものである。
(4) 改正経過・概要
1) 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)による改正
平成25年12月5日、「好循環実現のための経済対策」において、「経済の好循環を早期に実現する観点から、経済政策パッケージに盛り込まれた所得拡大促進税制の拡充や政労使会議での取組とともに、足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税を1年前倒しで廃止する」ことが決定された。
同対策においては、「復興特別法人税の一年前倒しでの廃止に当たっては、「集中復興期間」における25兆円程度のいわゆる「復興財源フレーム」の財源を確実に確保するために必要な金額を、平成24年度決算剰余金の一部を活用し、東日本大震災復興特別会計に繰り入れる」214こともあわせて示された。
同対策によって決定した復興特別法人税の1年前倒しでの廃止及び財源の補填について、法律上の規定を整備する「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月20日に成立し、同法の規定により「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」についても改正がなされた。
- 214 復興特別法人税の一年前倒しでの廃止に伴い、集中復興期間における「復興財源フレーム」の財源(25兆円程度)のうち約8,000億円が減収となるものであった。
2) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第23号)による改正
平成27年6月24日に復興推進会議が決定した「平成28年度以降の復旧・復興事業について」では、「被災地が安心して復興事業に取組むことができるよう、復興を更に加速させるため、・・・復興・創生期間5年間の財源を予め確保する」こととされた。同決定においては、「集中復興期間における復興事業費は、平成26年度における復興事業の執行状況を踏まえると、平成27年度予算までにおいて25.5兆円程度(国・地方合計(公費分))となる見込みであり215、復興・創生期間における復興事業費の見込み6.5兆円程度を踏まえると、復興期間10年間における復興事業費は合計で32兆円程度216と見込まれる」とされ、復興・創生期間における各年度の事業規模217の管理を適切に行い精度の高い予算とすることが決定されていた。
この時点において、「これまで計上した復興財源(26.3兆円)については、実績等を踏まえると28.8兆円程度の収入となると見込まれ」、これに加え、最大3.2兆円程度を確保することにより、復興・創生期間を含む復興期間10年間の復興財源32兆円程度を確保することとされた。この3.2兆円の確保については、①財政投融資特別会計財政融資資金勘定における平成27年度までの積立金の活用、同特別会計投資勘定からの受入れなど国の保有する資産の有効活用等による税外収入(決算剰余金を除く)の確保で0.8兆円程度、②一般会計からの繰入れで2.4兆円程度とすることとされた。
加えて、復興債については、「復興・創生期間における復興事業費を賄うための一時的なつなぎとして、同期間における復興債の発行を可能とする」こととし、「当該期間に発行される復興債を含め、復興期間に発行された復興債については、・・・平成49年度までに償還するもの」とされた。
同決定において盛り込まれた復興財源の確保及び復興債の発行について、法律上の規定を整備する「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第23号)」が平成28年3月31日に成立した。これにより、復興債の発行期間が平成32(令和2)年度までの5年間延長されるとともに、財政投融資特別会計投資勘定から国債整理基金特別会計への繰入金及び日本郵政株式会社の株式処分収入を復興債の償還費用に充てる等の措置を行うことが可能となった。
- 215 平成23年度から平成25年度までについては決算、平成26年度については決算見込み、平成27年度については予算による。
- 216 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)に基づき、事業者が負担すべき経費等は含まれていない。
- 217 復興・創生期間の各年度における事業規模は、平成28年度2.0兆円程度、平成29年度1.6兆円程度、平成30年度1.2兆円程度、平成31年度0.9兆円程度、平成32年度0.8兆円程度と試算していた。
3) 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)による改正
復興庁の設置期限を前に、当該期限を延長するための復興庁設置法等の改正と併せ、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び特別会計に関する法律が改正された。
本法律では、復興財源確保の特別措置等に係る期間の延長として、復興債の発行期間、政府保有株式の売却収入・その他税外収入の復興財源への充当期間等を5年間延長し、令和7年度までとした。加えて、特別会計に関する法律において、日本郵政が自己株式の消却を実施した場合の株式の所属替について規定したことと併せて、当該日本郵政株式の追加売却に伴う売却収入を復興債の償還財源に充当する規定を整備した。
当該法律は、一部公布日施行とされた規定を除き、令和3年度4月1日に施行された。
33. 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条の基本理念に基づき、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成23年8月11日改定 東日本大震災復興対策本部)においては、「実施する施策」として、「東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災等のための施策」(以下本項目において「全国防災事業」という。)が位置付けられた。この全国防災事業に要する費用としては、地方負担分等が約0.8兆円と推計され、その財源を地方団体自らが確保する必要があった。他方、全国防災事業は、現在および将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を構築するために不可欠な事業であることから、国を挙げて推進する必要があると考えられた。
税制調査会においては、平成23年9月16日に「復興・B型肝炎対策財源としての税制措置の「複数の選択肢」(地方税)」 が示され、「[1]基幹税のうち個人住民税に負担を求める218」場合と「[2]基幹税(個人住民税)とともに、個別間接税(地方たばこ税)にも負担を求める219」場合の試算が0.8兆円程度と示された。この後、同年10月11日の税制調査会に「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」が示され、個人住民税の均等割の標準税率特例及び地方たばこ税の税率特例が盛り込まれた。
これらを踏まえ、円滑に地方団体が事業実施をできるよう、臨時的に個人住民税(道府県民税・市町村民税)の均等割の標準税率及び地方たばこ税(道府県たばこ税・市町村たばこ税)の税率を引き上げることで、必要な財源を確保することとし、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案」は提出された。この法律案による個人住民税の均等割の標準税率特例により0.15兆円、地方たばこ税の税率特例により0.48兆円、加えて平成23年度税制改正による個人住民税の所得控除等の見直しにより0.20兆円を合わせて、約0.8兆円程度の財源を確保する見込みであった。
なお、特別税方式ではなく、標準税率及び税率の引き上げとした理由には、新たな税制措置が時限措置である中、納税者や特別徴収義務者の負担に配慮し、簡素な仕組みが求められたところ、仮に特別税を創設した場合には申告書やシステム等に大きな修正が各地方団体において必要となり、多額の経費を要することが挙げられる。また、個人住民税均等割については、地方団体が全国防災事業を実施する際、財源を歳出削減により捻出するか、税により捻出するか等について選択することを可能とすべく、一律の税率引き上げではなく、標準税率を引き上げることとした。
一方、後述する国会審議において、修正決議がなされ、個人住民税の均等割の標準税率の特例について、適用期間を5年度間延長して10年度(平成26年度~平成35年度(令和5年度))とし、標準税率に加算する額を500円から1,000円に引き上げるとともに、地方たばこ税の税率の特例に関する規定を削除することとされた。この結果、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」は個人住民税の均等割の標準税率の特例により、全国防災事業の地方負担分財源を確保する(個人住民税の均等割の標準税率特例により、0.6兆円、加えて平成23年度税制改正による個人住民税の所得控除等の見直しにより0.20兆円を合わせて、約0.8兆円程度の財源を確保する)法律として整備された。
- 218 個人住民税均等割の税率を時限的に引き上げる(0.6兆円)とともに、23年度税制改正事項(個人住民税の所得控除等の見直しによる増収額約0.06兆円(平年度ベース))(0.2兆円)を復興財源に活用。
- 219 個人住民税均等割の税率の時限的な引上げ(0.15兆円)及び地方たばこ税の臨時の引上げ(0.48兆円)とともに23年度税制改正事項(個人住民税の所得控除等の見直しによる増収額約0.06兆円(平年度ベース))(0.2兆円)を復興財源に活用。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年10月28日に閣議決定、国会に提出された。11月7日に(衆)本会議で趣旨説明、質疑を行い、同月17日に(衆)総務委員会において趣旨説明、同月22日民主党・自民党・公明党の3党共同提案による修正案が提出され、質疑を行い、賛成多数で修正議決(※附帯決議あり)が行われた。修正議決法案は、同月24日に(衆)本会議において賛成多数で可決された。
翌25日に(参)本会議において趣旨説明・質疑が行なわれ、同日(参)総務委員会において趣旨説明を行った。同月29日に同委員会にて質疑が行われ、賛成多数で可決(※附帯決議あり)、翌30日に(参)本会議において賛成多数で可決・成立した。
本法律は、平成23年12月2日に公布・施行された。
衆議院における修正案の提出経緯は以下のとおり。
法案提出を受けて、民主党・自民党・公明党の3党の税制調査会長が協議を行い、たばこ税は盛り込まないこと、個人住民税均等割を10年間1,000円引き上げることなどの「税関係協議結果」が平成23年11月10日に合意された。
これを受けて、「平成23年度第三次補正予算等に関して」(平成23年11月11日、民主党、自由民主党及び公明党の3党政策(政務)調査会長合意)、「税外収入等について」(平成23年11月15日、民主党、自由民主党及び公明党の3党実務者合意)が交わされ、「税関係協議結果」に沿った修正案が提出された。
国会では主に以下の論点についての議論がなされた。
1) 復興財源としての個人住民税の均等割の標準税率引き上げの是非
全国防災対策事業としていても結果的には、被災地あるいは大規模災害が想定される地域が中心となって防災対策費の配分が行われると想定されること、また、個人住民税の住民への応益性の強さ及び自治体の課税自主権の観点といった、税としての性格上から、個人住民税の均等割の標準税率引き上げの是非についての指摘がなされた。この点については、原理原則の税の性格を踏まえつつも、「全国民がひとしく受けていただくという意味で地方住民税で幅広く薄く御負担をいただく」ものとし、さらに各事業は一定の防災力強化につながるものであることから「応益性を持っていることは事実」として、理解を求めた。
2) 均等割とした理由
均等割とした理由についての指摘に対し、「できるだけ広く薄く」という観点から納税義務者の数220を勘案し、「広ければ広いほど額が少なくなるという意味」で、個人住民税の均等割の引き上げにより確保することとしたとしている。
- 220 均等割5,936万人、所得割5,477万人、所得税5,052万人。
3) 低所得者層への配慮・担税力に応じた引き上げの必要性
個人住民税の均等割の標準税率引き上げについて、低所得者における負担が大きいとの観点から、等しい負担とは言えず、担税力に応じた負担とすべきとの指摘があった。この点、所得に応じた負担としては、国の復興財源確保のために所得税に付加税を課すこととしており、国税の所得税は定率とし、地方税の個人住民税は定額とすることで、「両者のバランスをとる負担をお願いするという一方を担っている」という形をとったものとの整理を行った。また、修正案でも同様の指摘がなされたが、同様の整理の上、均等割は、非課税限度額制度により、所得が低く担税力が弱い者には課税されないほか、障害者、寡婦等で合計所得金額が125万円以下(令和3年度以降においては、135万円以下)の者については非課税になる、低所得者にも配慮をした仕組みになっている点も踏まえての理解を求めた。
4) 既に超過課税を行っている自治体での対応
森林環境保全等の施策の財源に充てること等を目的として、個人住民税均等割の超過課税を実施している都道府県が31団体ある中での対応については、超過課税とは異なり、あくまで今般の措置は全国的に標準税率の引き上げとして行うものであることについての理解を求めた。
※ (衆)総務委員会における附帯決議
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
・ 個人住民税均等割の標準税率の特例措置については、法案の修正の経緯を踏まえ、住民の生命・財産の安全に直結する緊急防災・減災事業の財源確保のために講じられるものであることを明らかにしつつ、国民の理解が得られるよう、周知広報を徹底すること。また、法案の修正に伴い、緊急防災・減災事業の実施に不測の支障が生ずることのないよう措置すること。
・ 緊急防災・減災事業の実施については、各地方公共団体の自主的判断を尊重するとともに、緊急防災・減災事業を実施しなかった団体や既定経費の節減等により個人住民税均等割の税率を引き上げることなく事業を実施した団体が不利益に取り扱われることのないようにすること。
・ 緊急防災・減災事業の実施に伴い同種の既存事業の縮減が行われ、個人住民税均等割の引上げにより得られた財源が他の事業の財源として振り替えられたのと同様の結果を招くことのないようにすること。
※ (参)総務委員会における附帯決議
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法施行に当たり、次の事項について、その実現に努めるべきである。
・ 個人住民税均等割の標準税率の特例措置については、法案の修正の経緯を踏まえ、住民の生命・財産の安全に直結する緊急防災・減災事業の財源確保のために講じられるものであることを明らかにしつつ、国民の理解が得られるよう、周知広報を徹底すること。また、法案の修正に伴い、緊急防災・減災事業の実施に不測の支障が生ずることのないよう措置すること。
・ 緊急防災・減災事業の実施については、各地方公共団体の自主的判断を尊重するとともに、円滑な事業の執行に向け、適切な支援を行うこと。また、同事業を実施しなかった団体や既定経費の節減等により個人住民税均等割の税率を引き上げることなく同事業を実施した団体を不利益に取り扱うことのないようにすること。
・ 緊急防災・減災事業の実施に伴い同種の既存事業の縮減が行われ、個人住民税均等割の税率の引上げにより得られた財源が他の事業の財源として振り替えられたのと同様の結果を招くことのないようにすること。
(3) 法概要・措置内容
内閣提出時の法律案においては、以下の特例が盛り込まれた。
・個人住民税の均等割の標準税率特例
平成26年度から平成30年度までの各年度分の個人住民税の均等割の標準税率について、道府県民税にあっては年額200円を、市町村民税にあっては年額300円を加算
・地方のたばこ税の税率特例
平成24年10月1日から平成29年9月30日までの間に売り渡し等が行われた製造たばこに係る地方のたばこ税の税率について、道府県たばこ税にあっては1,000本本につき395円を、市町村たばこ税にあっては1,000本本につき605円を、加算
一方、衆議院での修正案により、法律の措置内容は以下のとおりとされた。
・個人住民税の均等割の標準税率特例
平成26年度から平成35年度(令和5年度)までの各年度分の個人住民税の均等割の標準税率について、道府県民税及び市町村民税に年額500円を加算
34. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律(平成23年法律第11号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災からの復興のため、個人や企業が寄付や支援物資等により支援を行うなか、国会議員が地方自治体や日本赤十字社党への寄付を行うことは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の2の規定(公職の候補者等の寄附の禁止)に抵触する疑義があることから、歳費を削減し、その削減分を被災地の復旧・復興に回すことで、被災者の苦難を分かち合うことが検討された。そのような中、民主党、自民党、公明党の幹事長・国会対策委員長による会談が行われ、国会議員1人当たりの歳費(給与)を300万円削減することで3党が合意した(平成23年3月28日221)。これを受け、平成23年4月から9月までの各議院の議長・副議長及び議員の歳費の月額をそれぞれ50万円ずつ削減する特例を措置する「平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律」が制定された。
- 221 平成23年3月28日 日本経済新聞「歳費300万円削減、民自公3党合意 改正案を提出へ」
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年3月31日に衆議院議院運営委員長の発議により、衆議院議院運営委員会の委員会提出法律案として衆議院に提出された。同日に全会一致で(衆)本会議において可決され、(参)議院運営委員会において全会一致、(参)本会議において賛成多数で可決・成立した。
本法律は、同日に公布され、翌4月1日に施行された。
(3) 法概要・措置内容
東日本大震災によって、多数の人々が犠牲になり、多数の被災者が多大の苦難を強いられ、不自由な生活を余儀なくされている状況に鑑み、多くの国民と共に被災者の苦難を分かち合い、被災者の生活の早期の再建、被災地域の産業の早期の復興その他の被災地域の復旧復興に資するため、各議院の議長、副議長及び議員の歳費の月額をそれぞれ50万円減額する措置を講じた。
本法律の附則において、平成23年4月分から同年9月分までの歳費の月額について適用される旨規定された。
なお、本法律の題名及び趣旨(同法第1条)においては、「平成二十三年東北地方太平洋沖地震」という地震呼称が用いられており、これは法律案立案当時において、震災の正式呼称が定まっていなかったためである(「東日本大震災」という呼称は同年4月1日に閣議決定。)。
また、本法律により削減される歳費の額は国会全体で21億6,600万円であった222。
- 222 雅粒社「時の法令(1884号)」平成23年6月30日 P.34
35. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
月例給を平均0.23%引き下げること等を内容とする平成23年9月30日の人事院勧告223に鑑み、給与の改定について定めるとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員の給与に関する特例を定める「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」が制定された。
- 223 政府は、我が国の厳しい財政状況と東日本大震災に対処する必要性に鑑み、平成23年6月3日に閣議決定された国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案が、「今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価できることなど」を理由に、人事院勧告を実施するための給与法改正法案を提出しないことを平成23年10月28日に閣議決定していた。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成24年2月22日に民主党・自由民主党・公明党の3党提出により、衆議院へ議員提出法案として提出された。同日に(衆)総務委員会に付託され、翌23日に自由民主党・公明党より、修正案が提出され、賛成多数で修正議決された。同日に(衆)本会議において賛成多数で可決された。同月28日に(参)総務委員会において賛成多数、翌29日に(参)本会議において賛成多数で可決・成立した。
本法律は、同日に公布され、翌3月1日に施行(一部を除く。)された。
なお、衆議院における修正議決の結果、附則第12条において、「地方公務員の給与については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする」旨の規定が盛り込まれた。
(3) 法概要・措置内容
・人事院勧告に係る給与改定
平均0.23%の俸給月額の引下げを行うとともに、経過措置額を平成26年4月に全額廃止し、それを原資に昇給回復する措置を講ずることとされ、また、特別職給与法224及び防衛省職員給与法225の適用者についても、一般職に準じて改定することとされた。
・給与減額支給措置(措置期間:平成24年4月~平成26年3月末)
- 224 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)
- 225 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
1) 一般職給与法226適用者
・俸給月額
本省課室長相当職員以上(指定職、行(一)10~7級) ▲9.77%
本省課長補佐・係長相当職員(行(一)6~3級) ▲7.77%
係員(行(一)2、1級) ▲4.77%
その他の俸給表適用職員については、行(一)に準じた支給減額率
・俸給の特別調整額(管理職手当) 一律▲10%
・期末手当及び勤勉手当 一律▲9.77%
・委員、顧問、参与等の日当 上限額を▲9.77%
・地域手当等の俸給月額に連動する手当(期末・勤勉手当を除く。)の月額は、減額後の俸給月額等の月額により算出
- 226 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
2) 特別職給与法適用者
・俸給月額等
内閣総理大臣 ▲30%
国務大臣クラス・副大臣クラス ▲20%
大臣政務官クラス、常勤の委員長等・大公使等(上記以外の者) ▲10%
・期末手当
内閣総理大臣、国務大臣・副大臣クラス 俸給月額の支給減額率と同じ
上記以外の者 一律▲9.77%
・非常勤の委員等の日当 上限額を▲9.77%
・秘書官 一般職給与法適用対象者に準じて措置
3) 防衛省職員給与法適用者
・俸給月額等 一般職の国家公務員と同様の減額措置を実施
・給与減額支給措置の特例
自衛官(将・将補(一)を除く。)並びに自衛隊の部隊及び機関に勤務する事務官等については、平成24年4月1日から6月を超えない範囲内で政令で定める期間における給与減額支給措置の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
4) その他
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第5号)においても、これに準ずる措置がなされた。
地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応することとされた。
36. 特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第15号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
平成23年度第一次補正予算や第二次補正予算等の東日本大震災からの復旧・復興に係る予算は、一般会計に当初計上されていたが、東日本大震災復興基本法第9条においては、「国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする」と規定され、復興に係る国の資金の流れの透明化が法律によって要請されていた。
加えて、「東日本大震災からの復興の基本方針」では、「平成27年度末までの5年間の「集中復興期間」に実施すると見込まれる施策・事業(平成23年度第一次補正予算等及び第二次補正予算を含む)の事業規模については、国・地方(公費分)合わせて、少なくとも19兆円程度と見込まれる」とされ大規模な復興予算が見込まれた。さらに、同方針においては、復興債について「その発行のあり方について十分検討するとともに、従来の国債とは区分して管理する」こと、「その償還期間は、集中復興期間及び復興期間を踏まえ、今後検討する」ことや、復興債の償還財源とする「時限的な税制措置は、償還期間中に行い、その税収は、全て復興債の償還を含む復旧・復興費用に充て、他の経費には充てないことを明確化するため、他の歳入とは区分して管理することとする」ことが盛り込まれた。
このような状況の中、政府は、平成23年第三次補正予算からは、①一般会計予算等において復旧・復興関連であることを予算の項に明示をして他の経費と区分する、②予算書と併せて国会に提出する予算説明において、復旧・復興関連の財源経費を総覧できる資料を用意する、③復興債の発行残高及び償還年次を財政法二十八条に基づき国会に提出する予算参考書類に他の公債と区分して記載する、という手法で区分管理をすることを提案していた 。しかし、一層の透明化の観点から、国会において、衆議院修正により、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に附則第17条が追加され、「政府は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に係る歳入歳出を経理する特別会計を平成24年度において設置することとし、必要な法制上の措置を講ずること」とされた。
同条の規定を踏まえ、東日本大震災復興特別会計(以下「復興特会」という。)を設置することとし、その目的、管理及び経理等について定める「特別会計に関する法律の一部を改正する法律」を整備した。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成24年1月24日に閣議決定、国会に提出された。
2月21日に(衆)本会議で趣旨説明、質疑を行い、同月29日に(衆)財務金融委員会において趣旨説明、3月8日に賛成多数で可決され、同日に(衆)本会議において賛成多数で可決された。
同月21日に(参)本会議において趣旨説明・質疑が行われ、翌22日に(参)財政金融委員会において趣旨説明を行った。同月29日に同委員会にて賛成多数で可決、翌30日に(参)本会議において賛成多数で可決・成立した。
本法律は、平成24年3月31日に公布、翌4月1日に施行された。
(3) 法概要・措置内容
特別会計に関する法律に新たに節(第18節)を設け復興特会の目的、管理及び経理等についての規定(第222条から第233条まで等)が新たに設けられた。
1) 目的
東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることとされた。
2) 管理
復興特会は、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官並びに会計検査院長を含む全省庁の長等の共管とされ、内閣総理大臣(復興大臣)は、復興特会全体の計算整理事務(予算書・決算書等のとりまとめ)を担うこととされた。
3) 歳入・歳出
主な歳入項目は、復興特別税の収入、復興債の発行収入金及び一般会計からの繰入金(歳出削減分、税外収入)とされた。また、主な歳出項目は、復興事業に要する費用、復興債の元利償還金等とされた。
4) 歳出予算の区分の特例
歳出予算の執行責任の明確化を図るため、歳出予算について組織の別に区分して計上することとされた。
5) その他(改正法附則)
復興庁設置法(平成23年法律第125号)第21条の規定により復興庁が廃止されたときは、復興特会は、別に法律で定めるところにより、廃止するものとされた。また、平成23年度に発行した復興債の償還に係る債務等を復興特会に帰属させることとされた。
37. 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律(平成23年法律第69号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
民法では、「相続は、死亡によって開始」(第882条)し、「相続人は、相続開始の時から被相続人の一切の権利義務を承継する」(第896条前段)が、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる」(第915条)となっている。
東日本大震災では、多く死亡・行方不明者が出たが、その家族等の多くも家財や重要書類等を喪失し避難所生活を送る等の状況にあったほか、関係者との連絡等が困難、津波被災地や原発避難地域では立入禁止等により不動産の状況把握が困難等の状況もあった。このため、被災者が、3か月(いわゆる「熟慮期間」)以内に、被相続人の財産や負債を調査・把握し、相続するか否かを決断して手続を取ることが可能な状況ではなかった。また、熟慮期間の延長制度についても、被災地の弁護士会等が被災者への広報・啓発等の活動を行ってはいたが、十分な制度周知や家庭裁判所への延長申請がこの期間内に期待できる状況にはなかった227。
こうした被災地の現状に鑑み、相続人が相続の承認又は放棄をするかどうかの十分な熟慮期間を確保する必要性が指摘されていたが228、政府は、前述の延長制度があることや、自動的に熟慮期間を延長することに伴って生じ得る不利益等に鑑み慎重であったため229、発災から3か月後の6月11日を経過した後、本法律が議員立法として制定されることとなった。
- 227 下記意見書及び『災害復興法学』岡本正(2017.4)より。同書籍によれば、被災地で実施した法律相談について、例えば岩手県(3月中旬~5月下旬。4,925件)では、全相談内容に占める「遺言・相続」関係の相談割合が、25.6%に上っている。
- 228 例えば、日本弁護士連合会は平成23年5月26日に「自己のために相続の開始があったことを知った時から1年に伸長する特別の立法措置を早急に講じるべき」との意見書を提出している。
- 229 平成23年6月15日(衆)法務委員会において、法務大臣は「家庭裁判所においてこの期間を伸長できるということにしておりまして、早期安定等の要請と、個別の事案において不当な結論にならないような要請と、その二つの間の調整として個別の対応ということを考えているわけで、自動的に熟慮期間を延長するということには、他の相続人や利害関係人の利害を害するおそれがあるんじゃないかという懸念もございます。(略)基本法を預かる法務省としては、これはやはり慎重な検討をさせてもらいたいということで、もちろん、立法府においてそうした立法府としての慎重な検討の上に立法をされることについて法務省として異議を唱えるということではございませんが、法務省、つまり内閣提出法案とはしなかったということでございまして」と答弁している。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年6月15日、民主党から起草案が(衆)法務委員会に提出され、原案どおり(衆)法務委員会提出法律案となった。翌16日に(衆)本会議で可決、同日(参)法務委員会でも可決され、翌17日に(参)本会議で可決・成立した。
本法律は、平成23年6月21日に公布・施行された。
(3) 法概要・措置内容
東日本大震災の被災者である相続人が、生活の混乱の中で、相続の限定承認、相続放棄等を行うことができないまま相続の承認又は放棄をすべき期間を徒過することにより不利益を被ることを防止するため、この熟慮期間を平成23年11月30日まで延長するものである。
具体的には、「相続人」が、「東日本大震災の被災者」((4)参照)である場合が対象である。
また、被相続人が震災で死亡した場合に限らず、それ以前に死亡していた場合で、相続人が熟慮期間の進行中に震災の被害に遭ったケースも対象としている(具体的には、平成22年12月11日以後に自己のために相続の開始があったことを知った者)。
熟慮期間の延長期限は、上記いずれのパターンにおいても、一律、「平成23年11月30日」とされた230。
さらに、附則において、この法律の施行日前に民法第921条第2号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人(熟慮期間内に限定承認又は相続放棄しなかった者)についても適用するとの遡及適用の規定が置かれている231。ただし、同附則において、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、施行日前に同条第1号に掲げる場合に該当することとなったとき(相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき)は、この限りではないとされている232。
- 230 平成23年6月15日(衆)法務委員会における階猛議員答弁によれば、11月30日とした理由は、当時の政府の見解として、仮設住宅が概ねお盆明けにはできるとされていたことから、8月末には多くの被災者の生活が安定すると見込み、そこから通常の熟慮期間である3か月後の設定としたものである。
- 231 平成23年6月15日(衆)法務委員会において、大口善徳議員より「被相続人の債権者が相続を前提として相続人の固有の財産を差し押さえたり、あるいは、相続人からこの相続人の固有の財産を原資として弁済を受け取るような場合に、その相続放棄によって覆される場合の不利益について」の憲法上の問題に係る質問があり、辻恵議員より、憲法29条の財産権の保障は絶対的なものではなくて合理的な範囲内で制約されるという前提で、「今回のような未曾有の大震災という事態の中で、熟慮期間を十分に保障されないということ、そこを何とか救済しなければいけないという必要性が大きく上回るものであろうというふうに考えるものであります。そういう意味で、受忍範囲の問題であろう」との答弁がされている。
- 232 平成23年6月15日(衆)法務委員会において、大口善徳議員より、熟慮期間延長を知らずに民法921条第1号に該当する行為をした者の扱いについて質問があり、法務大臣から、動機の錯誤に当たり無効主張し得るとし、具体的には、「動機が表示されて法律行為の内容になっておれば、これは錯誤無効を主張することができるとされているわけでありますが、個別の事案における相続人の認識であるとか、あるいは法律行為が行われた際のいろいろな事実関係に応じてそこは変わってくるので、最終的には裁判所によって判断されるべきもの」と答弁している。
(4) 適用実績
本特例は、相続人が、東日本大震災が発生した平成23年3月11日において、下記表の区域内に住所を有していた場合を対象とした。
※ 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市区町村の区域から東京都の区域を除いた市区町村の区域。
| 岩手県 | 全市町村 |
| 宮城県 | 全市町村 |
| 福島県 | 全市町村 |
| 青森県 | 八戸市、上北郡おいらせ町 |
| 茨城県 | 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、稲敷郡阿見町、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町 |
| 栃木県 | 宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町 |
| 千葉県 | 千葉市美浜区、旭市、習志野市、我孫子市、浦安市、香取市、山武市、山武郡九十九里町 |
| 新潟県 | 十日町市、上越市、中魚沼郡津南町 |
| 長野県 | 下水内郡栄村 |
(5) その後の法改正等
平成25年6月21日公布・施行の災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号)の中で、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)が改正され、災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護のための規定として、第6条として熟慮期間の延長規定(災害発生日から1年を上限とし、政令で定める期間)が置かれた。これにより、東日本大震災に限らず、大規模な災害一般について、熟慮期間の延長が政令で措置できることとなった。
38. 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第86号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
災害弔慰金は、自然災害により死亡した者の遺族に対し支給を行うとされ、その遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫又は祖父母とされていた。一方、平成23年当時における社会情勢と家族のあり方の変化により、兄弟姉妹が同一世帯で生活する・生計を維持するという家族形態も存在しており、東日本大震災においても、兄弟姉妹で世帯を構成している者が犠牲になる場合があり、また、他制度に基づく遺族給付金の支給範囲と格差が生じているとの指摘もなされていた。さらに、自治体によっては、独自財源の災害弔慰金として、兄弟姉妹もその範囲に含めうる旨の条例を制定していたところもあり、自治体間での不均衡も生じていた。そのため、災害弔慰金の支給遺族の範囲に、他の遺族のいずれもが存しない場合に、死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹を加える「災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第86号)」が制定された。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年7月14日に衆議院災害対策特別委員長により起草され、同日、委員会提出法律案として衆議院に提出された。同日に全会一致で(衆)本会議において可決され、同月25日に(参)災害対策特別委員会において全会一致、同日、(参)本会議においても全会一致で可決・成立した。
本法律は、同月29日に公布・施行された。
(3) 法概要・措置内容
災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)を加えた。ただし、死亡した者の死亡当時における配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限ることとされた。
また、附則において、本法律による改正後の規定は平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する旨の遡及措置が講じられた。
なお、本法律の施行通知においては、本改正に係る条例改正に関する条例案を示し、地方公共団体へ、条例改正及びこれに伴う事務の迅速な取組を促した。この際、条例改正を待たずとも、本法律の施行後においては、改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の要件を満たす兄弟姉妹に対して災害弔慰金を支給することが可能である旨を明示し、地方公共団体における迅速な弔慰金支給を図った。
39. 災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成23年法律第100号)
40. 東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成23年法律第103号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災によって、多くの被災者が職を失うほか、多額の住宅ローンの残債務等を抱える被災者が多数見込まれる等の状況にあったが、こうした厳しい経済状況に置かれていた被災者のために支給される被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金、義援金について、当時、差押えを禁止する規定がなかったため、その制度目的や寄付者の意図に反して、債権者により差し押さえられ、被災者の生活再建の妨げとなることが懸念されていた233。これは、恩給や年金には差押禁止が明記されていることとのバランスも失していた234。
政府は、民主党での議論も踏まえ、平成23年6月17日、二重債務問題に関する関係閣僚会合において「東日本大震災における「二重債務問題への対応方針」について」を取りまとめた。この中で、「被災者生活再建支援金、義援金、弔慰金に関しては、その請求権及び支払い済みの金銭に対する差押えを禁止する法案の成立後には、これらの差押えが禁止されることを踏まえ、強制執行等の手続において混乱を生じないように配意する。」旨が盛り込まれた。
民主党・自由民主党・公明党の3党による実務者協議において検討が進められ、同年7月14日、3党共同で差押え禁止法案を発議する方針が確認され、「災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」及び「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が制定されることとなった。
- 233 提案者から、「言うまでもなく、支援金、弔慰金、見舞金に関しては制度の目的に、義援金に関しては寄附者の意図に照らして、被災者自らにおいて、被災者らの明日への第一歩のために使っていただくべきお金です。被災者の多くが二重ローンに苦しむ中、その趣旨に反して、銀行や金融機関、サラ金や高利貸しが被災者に対する債権を回収するために差し押さえて横取りしてしまうことは、私たちの正義に反します」との趣旨説明がされている。また、日本弁護士連合会の平成23年6月23日意見書では、これら見舞金的な性質の給付金について「いずれも一身専属的に給付されるものである。したがって,受給者に対する債権者の引当てとなる責任財産を形成するものとは予定されておらず,受給者以外の第三者のために消費されることは社会的にも是認できるものではない」と主張されている。
- 234 『災害復興法学』岡本正(2017.4)より。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
両法律案(第177回参法第14号及び第15号)は、平成23年8月3日、3党共同で参議院に提出された。その後、両法案は8月9日に撤回、同日、同名同内容の両法律案(第177回参法第19号及び第20号)を(参)災害対策特別委員会提出法律案とすることで全会一致で可決した。翌10日、(参)本会議において全会一致で可決され、同月23日、(衆)災害対策特別委員会及び(衆)本会議でいずれも全会一致で可決・成立した。なお、(参)災害対策特別委員会において、災害弔慰金及び災害障害見舞金、被災者生活再建支援金並びに東日本大震災関連義援金の差押え禁止等に関する決議が全会一致で議決235された。なお、衆参両院とも、本法案について討議は行われなかった。
両法律は、平成23年8月30日に公布・施行された。
- 235 民主党・新緑風会、自由民主党、公明党、みんなの党及び日本共産党の各派共同提案。強制執行に当たり差押えが禁止された金銭であることを特定・識別することが可能となるよう都道府県及び市町村等が発行する証明書類等の実情を調査した上で裁判所と情報の共有を図るなど、本法の適切な運用がなされるよう努めることとされた。
(3) 法概要・措置内容
1) 災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律
災害により死亡した者の遺族への弔意、身体又は精神に著しい障害を負った者への見舞、生活基盤に著しい損害を受けた者の生活再建の支援を確実なものとする必要性は、東日本大震災に限ったものではないことから、災害一般に共通するものとして、措置がなされた。
具体的には、災害弔慰金、災害障害見舞金及び被災者生活再建支援金の支給を受ける権利について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされ、支給を受けた金銭についても、差し押さえることができないこととされた。
2) 東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
いわゆる「義援金」には法的根拠はなく、様々なルートで集金・交付されるものがあり、災害によって交付要件や金額は様々であるが、この法律の対象となる「義援金」は、東日本大震災の被災者又は遺族を支援し又は慰謝する等のために自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従い交付する金銭に限定し、措置がなされた。
具体的には、東日本大震災関連義援金の交付を受ける権利について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされ、交付を受けた金銭についても、差し押さえることができないこととされた。
(4) その後の法改正等
義援金については、その後、平成28年の熊本地震やその後の豪雨などの災害でも個別法により差押禁止とされてきた(本法律も含め全5法)。その一方で、国会閉会中には個別立法措置を取ることは困難であること等が懸念されており、令和3年6月11日、自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和3年法律第64号)が公布・施行され、被災者生活再建支援金や災害弔慰金等だけでなく、義援金236も、自然災害一般について差押禁止財産となった。
- 236 自然災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従って被災者等に交付する金銭を自然災害義援金とした。
41. 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成24年法律第6号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災においては、被災地において、前述の相続問題ほか、二重ローン、解雇、相隣関係、賃貸借問題など、被災者から多くの法的相談のニーズがあり、さらに、原子力発電所事故の被害者からの膨大なニーズも想定されていた。これらに対応するため、現地や各地域の弁護士会が被災地での法律相談に対応するほか、日本司法支援センター(いわゆる「法テラス」)も出張所を設ける等して対応に当たってきた237。しかし、法テラスの業務は総合法律支援法(平成16年法律第74号)に規定されており、そのうち民事法律扶助業務としては、無資力者238に対する民事裁判等手続の代理援助及び書類作成援助(弁護士・司法書士への報酬・実費の立替え等)、法律相談援助(無料の法律相談)が業務内容となっていたため、裁判外紛争解決手続(ADR)や行政不服申立に関する援助ができなかったほか、地震保険等を受領したために無資力要件に該当しない被災者等にも援助ができない状況にあった。被災者の資力要件の確認に係る事務的負担等も指摘されていた。また、阪神・淡路大震災の際に(財)法律扶助協会(法テラスの前身)による財政支援を受けて地元弁護士会がADRセンターを立ち上げて対応した実績もあったため、東日本大震災においても、仙台弁護士会が平成23年4月に(震災ADR)を立ち上げたが、総合法律支援法の範囲外であったため、法テラスからの財政支援は受けられなかった239。こうした状況を踏まえ、特別立法の必要性が指摘されていたが、政府は、特に資力要件については法律扶助制度の根幹にかかわるとして、慎重な検討が必要としていた240。本法律(いわゆる「法テラス震災特例法」)は、議員立法として制定されることとなった。
- 237 平成23年12月14日の日本弁護士連合会会長声明。会長声明時点で、被災地の法律相談実績は3万4千件超。
- 238 単身で月収18万2000円以下、保有資産180万円以下、4人家族で月収29万9000円以下、保有資産300万円以下等。
- 239 「災害復興法学」岡本正(2017.4)より。
- 240 平成23年4月13日及び平成23年12月2日(衆)法務委員会、平成24年2月7日(参)予算委員会での法務大臣答弁。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の3派共同提案の起草案を、平成24年3月16日に(衆)法務委員会提出法律案とすることで可決され、同日、(衆)本会議で全会一致で可決、同月22日に(参)法務委員会で可決され、23日に(参)本会議で可決・成立した。なお、(参)法務委員会においては、無資力要件なく業務を行うことになる法テラスの財務状況への懸念から、適正な会計処理や、業務実施状況(貸倒率等)の報告等を求める附帯決議が付された。
本法律は、平成24年3月29日に公布、4月1日に施行された。
(3) 法概要・措置内容
法テラスに、新たに、東日本大震災法律援助(震災法律援助)を行わせることとされた。同事業の対象は、東日本大震災の被災者※であり、業務内容は、民事裁判等手続の代理援助、書類作成援助及び法律相談援助である。また、本業務に必要な費用に充てるため、法テラスが長期借入金をすることができることとされた。
平時の民事法律扶助業務との相違点としては、①援助を受ける被災者の資力の状況を問わないこと、②民事裁判等手続に加え、ADR及び行政不服申立手続の準備・追行(民事裁判等手続に先立つ和解交渉も含む)も援助できること、③訴訟代理援助及び書類作成援助として法テラスが立て替えた弁護士報酬等(立替金)の償還・支払を、民事裁判等手続等の準備中・追行中は猶予することが挙げられる。
※東日本大震災に際し災害救助法が適用された町村の区域(東京都の区域を除く。)241に平成23年3月11日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者。また、本法津は施行日から3年を経過した日に失効することとされた。
- 241 具体的な市町村は、37.(4)記載の通り。
(4) 適用実績
本法律による援助件数は、下表のとおり(平成24年度~令和2年度の合計)。
| 震災代理援助 | 震災書類作成援助 | 震災法律相談援助 | |
| 岩手県 | 219件 | 0件 | 80,130件 |
| 宮城県 | 867件 | 85件 | 180,796件 |
| 福島県 | 1,321件 | 65件 | 100,154件 |
| 全国計 | 10,578件 | 173件 | 456,754件 |
| ※ 平成24年(2,699件)が最高、令和元年(100件が)最低 | ※ 平成30年(54,765件)が最高、平成24年(42,981件)が最低 |
(5) その後の法改正等
1) 本法律の延長、再延長
3年後の法律失効を控えた時点においても、震災法律援助のニーズが減らず、原子力損害の賠償請求権の消滅時効が10年に延長されたことや、仮設住宅からの退去や高台移転といった復旧・復興の進捗に伴う法的相談も見込まれること等も踏まえ、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第4号)により3年間延長され、さらに、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第5号)により、3年間再延長され、平成33(令和3)年3月31日までとされた。
2) 総合法律支援法の改正
平成28年6月3日に公布された総合法律支援法の一部を改正する法律(平成28年法律第53号)において、大規模な災害一般について、被災者に対する資力を問わない無料法律相談「被災者法律相談援助」が新設され242、平成28年4月の熊本地震等において制度が活用された。
- 242 本法律とは異なり、「法律相談業務」のみとし、「1年以内で政令で定める期間」とした点について、平成28年5月26日(参)法務委員会において、「特に需要が大きいと考えられる無料の法律相談援助を特別措置法の制定を待つことなく政令によって迅速に実施できるようにする一方で、一年間の期間があれば、その間に大規模災害の被災状況等を踏まえ、法律相談だけではなく代理援助や書類作成援助等の法的援助を実施する必要があるかどうか、その必要があるとしてどのような特別措置法を制定するのが適当か、そういった検討を行うとともに、必要があればその特別措置法を制定することによって被災者のニーズに的確に応えることができる」との法務省答弁がされている。
42. 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第80号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災により金融機能に様々な影響が懸念される中、広域にわたる被災地域において、面的に金融機能を維持・強化するとともに、預金者に安心感を与える枠組みを設けることが、地域経済の復興を図る上で不可欠と考えられた。
このため、国の資本参加を通じて金融機関の金融仲介機能を強化する枠組みである金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号。以下「金融機能強化法」という。)等が改正され、国の資本参加を受けようとする場合に、経営責任が問われないことを明確化するなどの震災の特例が設けられた243。
- 243 法案提出に先立ち、平成23年5月13日に金融担当大臣談話「東日本大震災を受けた金融機能の確保について」が発表されている。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年5月27日に閣議決定、国会に提出された。6月8日に(衆)財務金融委員会において全会一致で可決、翌9日に(衆)本会議において全会一致で可決され、6月21日に(参)財務金融委員会において全会一致で可決、翌22日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。委員会においては、衆参ともに附帯決議が付された244。
本法律は、平成23年6月29日に公布、関係政省令・告示とともに同年7月27日から施行・適用された。
- 244 (衆)財務金融委員会では、採決に当たって、政府は、①東日本大震災で被災した中小企業者及び住宅ローン利用者等における二重債務の問題については、被災者の生活・経営の再建に資するよう、国として、必要な対応について、早急に検討を進めること、②協同組織金融機関の特例に関し、原発地域の金融機関も含め事業再構築等の申請期限の延長の申出がある場合、実情を十分に勘案して適切に対処すること、について十分配慮すべきであるという附帯決議が付された。
また、(参)財務金融委員会では、採決に当たって、政府は、①これまでに実施されている東日本大震災に係る各種の金融上の措置については、引き続き迅速かつ弾力的な対応が行われるよう特段の配慮を払うとともに、今後の復旧・復興、被災者の生活・事業の再建に向けた資金需要に適切に応える対策を講ずること、②東日本大震災による未曾有の被害を受け、生活の本拠や生計の手段を失った被災者の生活・事業の再建が、今後の復旧・復興に向けた大きな課題であることを踏まえ、被災した住宅ローン利用者及び中小企業者等に係る二重債務の問題に関しては、被災者の再スタート支援に資するよう、必要な対応について、早急に検討を進めること、③被災企業のリース債務等に係る問題についても、被災者及びリース会社等の実情を踏まえ、十分に配意すること、について十分配慮すべきであるという附帯決議が付された。
(3) 法概要・措置内容
本法律は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講じ、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期すものであり、その主な内容は次のとおりである。
・震災特例金融機関等に対する資本の増強に係る特例等
震災特例金融機関等(東日本大震災の影響により、主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために、自己資本の充実が必要となった金融機関等をいう。)が国の資本参加を受けようとする場合の経営強化計画の策定において、経営責任が問われないことが明確化されるとともに、収益性・効率性等の向上の具体的な目標を求めない等の震災の特例が設けられた。
・協同組織中央金融機関による特定震災特例協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特例
① 特定震災特例協同組織金融機関(東日本大震災の影響により、主として業務を行っている 地域における円滑な信用供与を実施するために、自己資本の充実が必要となった協同組織金融機関のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるものをいう。)について、協同組織金融機関の特性に鑑み、国と協同組織中央金融機関が共同して資本参加を行う枠組みが設けられた。
② ①の枠組みにおいて、協同組織中央金融機関は資本参加を受ける特定震災特例協同組織金融機関の経営を指導する役割を担うこととされるとともに、将来の事業再構築に伴い繰越損失の処理が必要となった場合には預金保険の資金等を活用することにより参加資本を整理することが可能とされた。
・国の資本参加等の申請期限の延長
国の資本参加等の申請期限が当時の平成24年3月末から平成29年3月末まで延長された。
| 本則 | 震災特例 | ||||
| 一般的特例 | 協同組織金融機関向け特例 | ||||
| 資本参加の対象 | 全金融機関 | 信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった金融機関 | 東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められる協同組織金融機関 | ||
| 計画記載事項 | 計画期間 | 3年以内 | 5年以内 | ||
| 収益性及び効率性の向上に係る目標及び方策 | 必要 | 不要 但し、一般的特例では収益の見通しを記載する必要 |
|||
| 中小企業金融円滑化に係る目標及び方策 | 必要 | 不要 但し、被災者への信用供与の状況や震災からの復興に資する方策を記載する必要 |
|||
| 資本参加基準 | 公的資金の回収が困難でないこと | 必要 | 不要 | ||
| 適切な資産査定がなされていること | 必要 | 利用可能な直近の情報に基づき適切に資産査定がなされていれば可 | 不要 | ||
| その他 | 配当率 | 平時の水準に設定 (12か月TIBOR(足許0.38%)+1~2%) |
預金保険機構の金融機能強化勘定における資金調達コストに設定(平成24年度は0.20%) | ||
| 参加資本の種類 | 銀行 | 原則として優先株式 | 株式・劣後債・劣後ローン | ― | |
| 協同組織金融機関 | 優先出資・劣後ローン・優先信託受益権 | 信託受益権 (優先劣後関係なし) |
|||
| 参加資本の取崩しによる返済 | 可能 | ||||
| 事業再構築に伴う資本整理 | 不可 | 可能 | |||
(4) 適用実績
金融機能強化法の震災特例に基づき、12の金融機関に対し、合計2,310億円の資本参加が行われた。
| 地域銀行 | 信用金庫 | 信用組合 | ||||||||||
| 仙台銀行 | 筑波銀行 | 七十七銀行 | 東北銀行 | きらやか銀行 | 宮古信用金庫 | 気仙沼信用金庫 | 石巻信用金庫 | あぶくま信用金庫 | 相双信用組合 | いわき信用組合 | 那須信用組合 | |
| 資本 参加額 (億円) |
300 | 350 | 200 | 100 | 300 | 150 | 180 | 200 | 200 | 160 | 200 | 70 |
| 決定日 | 平成23年 9月14日 |
平成23年 12月 8日 |
平成24年 9月13日 |
平成24年2月2日 | 平成23年 12月28日 |
平成24年 3月14日 |
||||||
| 実行日 | 平成23年 9月30日 |
平成23年 12月28日 |
平成24年 9月28日 |
平成24年 12月28日 |
平成24年2月20日 | 平成24年 1月18日 |
平成24年 3月30日 |
|||||
43. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第89号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災により漁業者・農業者に甚大な被害が発生する中、漁業者・農業者の経営再開・再建に向け、農漁協系統の金融機能を維持・強化するとともに、漁業者・農業者等の貯金者に安心感を与える枠組みが必要と考えられた。
このため、農漁協系統の金融機能の強化を目的とする農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)が改正され、東日本大震災に対処して特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るため、その自己資本の充実に関する震災の特例が設けられた。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年6月3日に閣議決定、国会に提出された。7月14日に(衆)農林水産委員会において全会一致で可決、翌15日に(衆)本会議において全会一致で可決され、7月26日に(参)農林水産委員会において全会一致で可決、翌7月27日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。委員会においては、衆参ともに附帯決議が付された245。
本法律は、平成23年8月3日に公布、関係政省令とともに同年9月26日に施行された。
- 245 (衆)農林水産委員会及び(参)財務金融委員会では、採決に当たって、①改正法の運用に当たっては、指定支援法人及び農水産業協同組合貯金保険機構の緊密な連携と適切な役割分担の下、被災農業者・漁業者の経営・生活の円滑な再建に資することを旨として実施すること、②東日本大震災で被災した農林漁業者等における二重債務の問題については、被災者の経営・生活の再建に資するよう、国として、必要な対応を実施すること、③被災地域の復興の重要な担い手である農業協同組合、漁業協同組合等については、自ら被災している場合もあることから、地域の復興計画に則した共同利用施設等の復興支援に万全を期すること、④本法の改正は、公的資金の注入によらず被災地域の農漁協系統の金融機能の維持・強化を図るものであるが、農漁協系統組織はその構成員のための組織であるという原点を踏まえ、貸出し等の金融業務の実施に当たってはあらゆる面で公平・公正かつ円滑な資金の融通に支障がないよう適正に行うこと、政府は、このことについて、実態把握に努め、必要に応じ具体的な措置をとること、の実現に努めることという附帯決議が付された。
(3) 法概要・措置内容
本法律は、東日本大震災に対処して特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るため、その自己資本の充実に関する特別の措置を講じ、特定農水産業協同組合等の信用事業の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期すものであり、その主な内容は次のとおりである。
・震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の申込み等
指定支援法人(再編強化法に基づく指定支援法人をいう。以下同じ。)は、農林中央金庫から震災特例組合等(東日本大震災の影響により、自己資本の充実を図ることが主として事業を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった特定農水産業協同組合等のうち信用事業に係る経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるものをいう。以下同じ。)が発行する優先出資の引受け等に係る要請を受けた場合において、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対し、当該優先出資等(以下「特定優先出資等」という。)の取得の申込みをすることができることとされた。
・特定優先出資等の取得の決定
機構は、指定支援法人から平成29年3月31日までに申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該申込みに係る特定優先出資等の取得を行うかどうかの決定を求めることとし、主務大臣は、震災特例組合等から提出された信用事業計画等に照らして、優先出資等の取得を行うべきとの決定をすることとされた。
・認定の申請
震災特例組合等は、機構による特定優先出資等の買取りがあった日から起算して10年を経過する日までに、信用事業が改善した旨の認定又は信用事業再構築(信用事業の健全化の合併等をいう。以下同じ。)に伴う資本整理を可とする旨の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならないこととされた。
・特定優先出資等の消却に必要な金銭の贈与
機構は、震災特例組合等が特定優先出資等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、 主務大臣の認可を受けて、当該消却に必要な金銭の贈与を行うことができることとされた。
(4) 適用実績
再編強化法に基づき、岩手県、福島県、宮城県の8農協及び1漁協に対し、総額570億円の優先出資の引受けが行われた。
| 岩手県 | 福島県 | 宮城県 | |||||||
| 組合名 | 大船渡市農協 | ふたば農協 | そうま 農協 |
南三陸 農協 |
いしのまき農協 | 仙台 農協 |
名取岩沼農協 | みやぎ 亘理農協 |
宮城県 漁協 |
| 引受額 (百万円) |
10,790 | 9,660 | 9,900 | 1,350 | 5,470 | 10,510 | 750 | 1,860 | 6,680 |
| 引受日 | 平成24年2月24日 | 平成24年3月23日 | |||||||
| 返済日 | 平成28年 5月27日 |
平成28年 1月13日 |
平成28年3月25日 | 平成30年7月27日 | |||||
44. 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成23年法律第41号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
平成23年度第一次補正予算に伴う地方財政補正措置として、東日本大震災に係る特別の財政需要に対応するための特別交付税の増額を行うため、平成23年度分の地方交付税の総額(特別交付税)に1,200億円を加算すること等を内容とする「平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」が整備された。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年4月26日に閣議決定、国会に提出された。同月30日に(衆)総務委員会において全会一致で可決、同日、(衆)本会議において全会一致で可決され、5月2日に(参)総務委員会において全会一致で可決、同日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。
本法律は、同日に公布・施行された。
(3) 法概要・措置内容
東日本大震災による被害状況は極めて甚大であり、平成23年度第一次補正予算に係る災害弔慰金の地方負担額、行政機能の維持や被災者支援に係る応急対応経費及び被災地域の応援に要する経費等について、多額の経費が見込まれることから、これらの特別の財政需要に対応するため、平成23年度分の地方交付税の総額(特別交付税)に1,200億円を加算する措置が講じられた。
なお、この措置による増加額相当額(1,200億円)については、平成23年度分の一般会計から交付税及び贈与税配付金特別会計への繰入金の額を1,200億円加算することとし、未曽有の超大規模災害であることなどを踏まえ、臨時異例の措置として、後年度において各年度分として交付すべき地方交付税の総額から減額するなどの措置は講じないこととされた。
また、この1,200億円は、全て特別交付税に加算するものであることから、平成23年度の普通交付税及び特別交付税の総額の特例として、1,200億円をいったん控除してその100分の94に相当する額を普通交付税の総額とし、一方、その100分の6に相当する額に1,200億円を加算した額を特別交付税の総額とする特例規定等が設けられた。
45. 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第116号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
平成23年度第三次補正予算に伴う地方財政補正措置として、東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応する「震災復興特別交付税」を交付できるようにするため、平成23年度の地方交付税の総額を1兆6,635億円増額すること等を内容とする「平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律」が制定されることとなった。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年10月28日に閣議決定、国会に提出された。11月22日に(衆)総務委員会において全会一致で可決、同月24日に(衆)本会議において全会一致で可決され、11月29日に(参)総務委員会において全会一致で可決、翌30日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。
なお、本法律案は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案と一括して審議された。
本法律は、平成23年12月2日に公布、関係政省令とともに同日から施行246された。
- 246 関係省令(地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成23年総務省令第52号))については、一部を除き同日施行。
(3) 法概要・措置内容
・平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の改正内容
東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応するため、平成23年度分の地方交付税の総額に1兆6,635億円を震災復興特別交付税として加算することとした。この際、震災復興特別交付税が、復旧・復興等について被災団体が起債によらず財政運営できるよう、事業の実施状況に合わせてその金額を措置し財政負担をゼロとするというものであり、復興債などにより特別に財源が確保されるということに合わせて、臨時・異例の措置として対応するものであることから、法律上、通常の特別交付税の加算とは異なるものとしてその趣旨目的を明確にするなど、通常の特別交付税とは区別した規定が設けられた。
また、通常、地方交付税の繰越しを行う場合については、当該年度分の地方交付税の総額から当該年度分の普通交付税及び特別交付税の額を控除した額以内の額を繰り越すこととしているところ、当時の状況として、当該年度分として必要な特別交付税の所要額の確定が困難となっていたことから、復興事業等の実施状況を勘案して、震災復興特別交付税額のうち平成24年度に必要な額の繰越しを可能とする規定が設けられた。
加えて、特別交付税の決定時期を原則12月と3月と定める地方交付税法(昭和25年法律第211号)第15条第2項の規定の特例として、震災復興特別交付税の決定時期に関する特例が設けられたほか、震災復興特別交付税の増額の影響が震災復興特別交付税を除く通常の特別交付税の12月交付額の上限額に及ばないようにするために必要な読替規定が設けられた。
・地方交付税法の改正内容
東日本大震災により今後の財政事情等への不安要素のある中で、地方団体における予見可能性、国会における民主的統制が必要と考えられたことから、第三次補正予算に伴う全国緊急防災事業に係る地方債の後年度の元利償還金を基準財政需要額へ算入することが法律上明記された。
・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)の改正内容
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)等の施行による地方税の減収額を埋めるため、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第9条において、歳入欠かん債を発行して後年度の元利償還に対して普通交付税を措置することとされていたところであるが、地方税の減収額についても震災復興特別交付税で対応することとしたため、当該既定の削除が行われるなどの所要の規定の整備が行われた。
46. 平成二十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律(平成23年法律第88号)
(1) 立案経緯・制定趣旨
東日本大震災の当面の復旧対策に対応するための必要な財政措置を盛り込んだ平成23年度第二次補正予算の財源として、新たな国債発行に依存しないという観点から、平成22年度歳入歳出の決算上の剰余金を充てるため、歳入歳出の決算上の剰余金の処理に関する特例を定める「平成二十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律」が制定された。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年7月15日に閣議決定、国会に提出された。7月20日に(衆)財務金融委員会において可決、同日に(衆)本会議において可決され、7月25日に(参)財政金融委員会において可決、同日に(参)本会議において可決・成立した。
(参)財政金融委員会では、採決に当たって、政府は、①東日本大震災による未曽有の被害からの着実な復旧・復興が目下の最重要課題であることを踏まえ、更なる補正予算の編成に当たっては、財政規律にも配慮しつつ、本格復興に向けた施策の早急な具体化に万全を期すこと、②保有外貨資産の為替差損等により平成22年度の日本銀行の国庫納付金が予算額を大きく下回ったこと等を踏まえ、政府は、ファンダメンタルズを反映しない過度の為替変動への適正な対処に留意するとともに、日本銀行も適正な資産管理や効率的な業務運営を行いつつ、外貨資産の保有及びリスク管理の在り方について検討すること、について十分配慮すべきであるという附帯決議が付された。
また、本法律は、平成23年7月29日に公布・施行された。
(3) 法概要・措置内容
歳入歳出の決算上の剰余金のうち2分の1を下らない金額は、公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法第6条第1項の規定を平成22年度の剰余金について適用しないこととした。
47. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成23年法律第2号)ほか
(1) 立案経緯・制定趣旨
平成23年4月には統一地方選挙が予定されていたところ、東日本大震災により著しい被害を受けた地域の地方公共団体においては、東日本大震災の影響により多くの住民が本来の住居を離れていること、災害復旧のために選挙事務を執行する職員がその職務を遂行することが困難であること、選挙の執行のために必要な施設や資材の確保にも著しい困難をきたすことが想定され、選挙を執行することが当面不可能な状況が生じていた。
このため、公職選挙法の例外として、東日本大震災により著しい被害を受けた地域の地方公共団体について、統一地方選挙の期日を延期する等の措置を講ずる「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」(以下「選挙期日震災特例法」という。)が制定された。
(2) 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年3月16日に閣議決定、国会に提出された。3月17日に(衆)政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において全会一致で可決、同日に(衆)本会議において可決され、同日に(参)政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において可決、翌18日に(参)本会議において可決・成立した。
本法律は、平成23年3月22日に公布、関係政令とともに同日から施行された。
(3) 法概要・措置内容
選挙の期日の延期について、東日本大震災の影響により、統一地方選挙の期日においては選挙を適正に行うことが困難として総務大臣が指定する市町村及び当該市町村の区域を包括する県の議会の議員または長の選挙の期日は、この法律の施行の日から起算して2月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日とすることとされた。なお、これらの市町村の指定に当たっては、総務大臣はあらかじめ当該県の選挙管理委員会の意見を、当該県の選挙管理委員会が総務大臣に意見を述べる場合には、あらかじめ当該市町村の選挙管理委員会の意見を聴くものとすることとされた。
また、本法律の施行の日から平成23年6月10日までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員または長の任期について、この法律の規定により選挙を行う場合は、当該選挙期日の前日までの期間とすることとされた。
加えて、本法律の規定により行われる選挙については、寄附等の禁止期間の特例等が設けられた。
| <第1次指定(平成23年3月23日)> | ||
| 包括する県 | 指定市町村 | 延期される選挙 |
| 岩手県 | 陸前高田市 大槌町 山田町 田野畑村 普代村 野田村 |
岩手県知事選挙、岩手県議会議員選挙 陸前高田市議会議員選挙 大槌町長選挙 山田町議会議員選挙 田野畑村議会議員選挙 普代村長選挙、普代村議会議員選挙 野田村議会議員選挙 |
| 宮城県 | 仙台市 塩竈市 多賀城市 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 女川町 |
宮城県議会議員選挙 仙台市議会議員選挙 塩竈市長選挙、塩竈市議会議員選挙 多賀城市議会議員選挙 亘理町議会議員選挙 山元町議会議員選挙 松島町長選挙 七ヶ浜町長選挙、七ヶ浜町議会議員選挙 女川町議会議員選挙 |
| 福島県 | 相馬市 広野町 双葉町 新地町 川内村 葛尾村 |
福島県議会議員選挙 相馬市議会議員選挙 広野町議会議員選挙 双葉町議会議員選挙 新地町議会議員選挙 川内村議会議員選挙 葛尾村議会議員選挙 |
| <第2次指定(平成23年3月28日)> | ||
| 包括する県 | 指定市町村 | 延期される選挙 |
| 岩手県 | 盛岡市 久慈市 二戸市 雫石町 洋野町 滝沢村 |
盛岡市議会議員選挙 久慈市議会議員選挙 二戸市議会議員選挙 雫石町議会議員選挙 洋野町議会議員選挙 滝沢村議会議員選挙 |
| 宮城県 | 白石市 村田町 川崎町 利府町 富谷町 色麻町 大衡村 |
白石市議会議員選挙 村田町長選挙 川崎町長選挙 利府町議会議員選挙 富谷町議会議員選挙 色麻町長選挙 大衡村議会議員選挙 |
| 福島県 | 福島市 会津若松市 郡山市 白河市 須賀川市 国見町 川俣町 鏡石町 磐梯町 猪苗代町 会津坂下町 柳津町 檜枝岐村 昭和村 西郷村 |
福島市議会議員選挙 会津若松市長選挙、会津若松市議会議員選挙 郡山市議会議員選挙 白河市議会議員選挙 須賀川市議会議員選挙 国見町議会議員選挙 川俣町議会議員選挙 鏡石町議会議員選挙 磐梯町長選挙、磐梯町議会議員選挙 猪苗代町長選挙 会津坂下町長選挙 柳津町長選挙 檜枝岐村長選挙、檜枝岐村議会議員選挙 昭和村議会議員選挙 西郷村議会議員選挙 |
| <第3次指定(平成23年3月31日)> | ||
| 包括する県 | 指定市町村 | 延期される選挙 |
| 茨城県 | 水戸市 | 水戸市長選挙、水戸市議会議員選挙 |
(4) 改正経過・概要
1) 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第55号)
a. 立案経緯・制定趣旨
本法律案の改正前の選挙期日震災特例法により、選挙が延期される団体については、統一地方選を行う団体に限られていた。一方で、災害状況が明らかになる中で統一地方選の対象団体以外の団体についても選挙の執行が困難な団体があることが判明したため、統一地方選対象外の団体についても同様に選挙期日の延期の対象とすること等を内容とする「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」が制定された。
b. 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、平成23年5月10日に閣議決定、国会に提出された。5月13日に(衆)政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において全会一致で可決、同月17日に(衆)本会議において全会一致で可決され、翌18日に(参)政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において全会一致で可決、同月20日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。
(衆)政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会では、採決に当たって、①これらの選挙期日の延期は被災地域の実状を考慮したやむを得ない臨時特例措置であり、関係地方公共団体においてできる限り早期に選挙が執行できるよう政府は十分な支援を行うこと、②本委員会は、災害の復旧・復興の状況を考慮しつつ、この期日までに選挙を行うことが困難な場合には、関係地方公共団体の意見を十分踏まえ、適切な措置を講ずることとする、という附帯決議が付された。
また、(参)政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会では、採決に当たって、①選挙期日等の延期は、被災地域の実状を考慮したやむを得ない臨時措置であることから、関係地方公共団体においてできる限り早期に選挙が執行できるよう、政府は十分な支援を行うこと、②被災地域の復旧・復興の状況を考慮しつつ、選挙期日等の延期の期限までに選挙を行うことが困難な場合には、関係地方公共団体の意見を十分踏まえ、適切な措置を講ずるものとする、という附帯決議が付された。
本法律は、平成23年5月27日に公布、関係政令とともに同日から施行された。
c. 法概要・措置内容
統一地方選対象外の団体についても選挙期日の延期の対象とし、延期後の選挙期日は、現行法の施行の日から2月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日とする等の改正がなされた。なお、対象団体の指定及び選挙期日を定める政令の立案に当たっては、総務大臣は県選挙管理委員会の意見を、県選挙管理委員会は市町村選挙管理委員会の意見をそれぞれ聴き、その意見を尊重するものとされた。
また、法律の題名等に用いられていた「平成二十三年東北地方太平洋沖地震」が「東日本大震災」に改められた247。
- 247 「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」に名称が変更された。
| <平成23年5月27日指定分> | ||
| 県 | 指定市町村 | 延期される選挙 |
| 岩手県 | 釜石市 | 釜石市議会議員選挙 |
| 宮城県 | 大郷町 加美町 |
大郷町議会議員選挙 加美町長選挙 |
| 福島県 | 大熊町 | 大熊町長選挙249 |
| <平成23年7月7日指定分> | ||
| 県 | 指定市町村 | 延期される選挙 |
| 宮城県 | 名取市 | 名取市議会議員選挙(補欠選挙) |
- 248 当時既に統一地方選対象団体として指定されていた市町村の統一地方選対象外の選挙についても、本法律による改正により、統一地方選対象の選挙と同様に延期された。(宮城県村田町議会議員選挙)
- 249 2)の改正により、選挙期日の延期の期限が平成23年12月31日まで延期されたことに伴い、議会議員選挙も同様に延期された。
2) 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第92号)
a. 立案経緯・制定趣旨
本法律案については、平成23年7月28日に(衆)政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、起草され、委員会提出法律案として国会に提出された。起草の趣旨については、以下のとおりである250。
- 250 第177回国会(衆)政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会(平成23年7月28日)松崎公昭委員長の発言より抜粋。
もとより、選挙は民主主義の根幹をなすものであり、できる限り早期に実施されなければなりません。災害の復旧復興に多忙をきわめる中で、有権者の把握や執行体制の整備などの困難な課題を乗り越えて、多くの団体では延期期限内に選挙を実施することとなりましたが、それでもなお、選挙を適正に実施することが困難であるとして延期期限の延長を求める意見も関係団体から寄せられております。
これを受け、理事会等において協議いたしましたところ、本委員会におきましては、前回、5月13日に、特例法案を議決するに際し付した附帯決議において、本委員会は、「関係地方公共団体の意見を十分踏まえ、適切な措置を講ずることとする。」としているところから、各会派において合意し、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を提案することとなりました。
b. 国会審議及び公布・施行経緯
本法律案は、上記のとおり、平成23年7月28日に(衆)政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、委員会提出法律案として提出されることとされた251。その後、同日に(衆)本会議において全会一致で可決され、翌29日に(参)政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において全会一致で可決、同年8月3日に(参)本会議において全会一致で可決・成立した。
なお、(参)政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会では、採決に当たって、選挙期日等の延期は、被災地域の実状を考慮したやむを得ない臨時措置であることから、関係地方公共団体においてできる限り早期に選挙が執行できるよう、政府は、本法施行に当たり、関係地方公共団体の意向等を踏まえ、選挙実施体制確立のために必要な職員の派遣その他の人的支援、被災地域において選挙を実施するために追加的に必要となる経費に対する財政的支援、その他避難者の所在の把握や不在者投票を円滑に実施するための措置など、関係地方公共団体に対して十分な支援を行うこと、という附帯決議が付された。
本法律は、平成23年8月10日に公布、関係政令とともに同日から施行された。
- 251 (衆)政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会での審査は省略されている。
c. 法概要・措置内容
本法律により、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を選挙期日震災特例法の施行日から起算して2月を超え6月を超えない範囲内(平成23年9月22日まで)から平成23年12月31日まで延期することとされた。
また、特例選挙期日の告示日について、本法律による改正前の選挙期日震災特例法に規定する告示日(例えば、町村の選挙は選挙期日の5日前)以前の日とすることができるようにすることとされた。
(5) 適用実績
選挙期日震災特例法により選挙を延期した団体及びそれぞれの団体の任期満了期日並びに特例選挙期日については、図表2-3-93のとおりである。
| 県 | 団体名 | 任期満了期日 | 特例選挙期日 | |
| 長 | 議員 | |||
| 岩手県 | 4/29 | 4/29 | 9/11 | |
| 岩手県 | 盛岡市 | 9/1(※2) | 5/1 | 8/28 |
| 久慈市 | ― | 4/29 | 8/7 | |
| 陸前高田市 | ― | 4/29 | 9/11 | |
| 釜石市(※1) | ― | 8/31(※3) | 9/11 | |
| 二戸市 | ― | 4/30 | 7/31 | |
| 雫石町 | ― | 5/8 | 7/31 | |
| 滝沢村 | ― | 4/30 | 7/31 | |
| 大槌町 | 5/7 | 8/31(※2) | 8/28 | |
| 山田町 | ― | 4/29 | 9/11 | |
| 田野畑村 | ― | 4/30 | 8/28 | |
| 普代村 | 4/30 | 4/30 | 6/26 | |
| 野田村 | ― | 4/29 | 8/7 | |
| 洋野町 | ― | 4/30 | 6/19 | |
| 宮城県 | ― | 4/29 | 11/13 | |
| 宮城県 | 仙台市 | ― | 5/1 | 8/28 |
| 塩竈市 | 4/30 | 4/30 | 9/11 | |
| 白石市 | ― | 4/29 | 7/31 | |
| 名取市(※1) | ― | 6/20 (※3、4) |
11/13 | |
| 多賀城市 | ― | 4/30 | 9/11 | |
| 村田町 | 5/24 | 8/3(※3) | 8/28 | |
| 川崎町 | 5/8 | ― | 8/28 | |
| 亘理町 | ― | 4/30 | 11/13 | |
| 山元町 | ― | 4/30 | 11/13 | |
| 松島町 | 4/21 | ― | 9/11 | |
| 七ヶ浜町 | 4/29 | 4/29 | 9/11 | |
| 利府町 | ― | 4/29 | 9/11 | |
| 大郷町(※1) | ― | 6/30(※3) | 9/11 | |
| 富谷町 | ― | 4/29 | 9/11 | |
| 大衡村 | ― | 4/29 | 9/11 | |
| 色麻町 | 4/29 | ― | 8/28 | |
| 加美町(※1) | 6/16(※3) | ― | 8/28 | |
| 女川町 | 9/18(※3) | 4/29 | 11/13 | |
| 福島県 | ― | 4/29 | 11/20 | |
| 福島県 | 福島市 | ― | 4/30 | 7/31 |
| 会津若松市 | 4/26 | 4/29 | 8/7 | |
| 郡山市 | ― | 4/30 | 9/4 | |
| 白河市 | 7/28(※2) | 4/30 | 7/10 | |
| 須賀川市 | ― | 4/29 | 9/4 | |
| 相馬市 | ― | 4/29 | 11/20 | |
| 国見町 | ― | 4/29 | 6/19 | |
| 川俣町 | ― | 4/29 | 11/20 | |
| 鏡石町 | ― | 4/29 | 9/4 | |
| 檜枝岐村 | 4/30 | 4/30 | 5/29 | |
| 磐梯町 | 4/30 | 4/30 | 6/26 | |
| 猪苗代町 | 4/26 | ― | 6/26 | |
| 会津坂下町 | 4/29 | ― | 6/26 | |
| 柳津町 | 4/29 | ― | 6/26 | |
| 昭和村 | ― | 4/29 | 6/26 | |
| 西郷村 | ― | 4/29 | 8/28 | |
| 広野町 | ― | 4/29 | 11/20 | |
| 川内村 | ― | 4/29 | 11/20 | |
| 大熊町(※1) | 9/19(※3) | 10/31(※3) | 11/20 | |
| 双葉町 | ― | 4/29 | 11/20 | |
| 葛尾村 | ― | 4/29 | 11/20 | |
| 新地町 | ― | 4/29 | 11/20 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 4/26 | 4/30 | 5/29 |
(※2)任期満了選挙
(※3)統一選挙対象外選挙
(※4)補欠選挙
(注)日付はいずれも平成23年
48. その他の規制緩和措置等
東日本大震災に対応するため、政令以下の法令等においても、各府省がそれぞれ特例的な措置等を講じており、これらの措置等については、内閣府が「東日本大震災に関連した各府省の規制緩和等の状況」(平成23年4月19日公表・平成24年12月12日更新)252として取りまとめている(附属資料参照)。
同とりまとめには、各府省の通知等による規制緩和や法律に基づき災害時における特別措置を行政庁が発動するもの等が掲載されており、計213項目に及ぶ(東日本大震災復興特別区域法に関連する措置は含まれていない)。なお、当該資料には、一部、16.等との立法措置と重複する法律上の規制緩和等措置も含まれているが、当時の政府において規制緩和等を網羅的に整理した貴重な資料であるため、1.~47.との重複排除等はせず、そのまま掲載することとした。
これらの措置としては、例えば、
・ 特定非常災害特別措置法に基づく政令上の措置として、各種許認可の存続期間や証明書の有効期限を延長するもの
・ 省令・命令上の措置として、本人確認の方法等を柔軟にするもの
・ 告示による措置として、資格・試験制度等に係る各種期限の特例や免除等や、各種支払・納付期限の延長等、新規規制の導入時期を遅らせるもの
・ 通知・通達・事務連絡その他方法によるものとして、救援や被災者支援のための行為について一定の規制の例外を認めるもの、震災関連事業等における法適用の考え方等を明らかにするもの、食品表示等の変更が間に合わないこと等を一時的に許容するもの、入国・在留に係る手続を柔軟にするものや、輸出入関係の手続簡素化等
などが挙げられる。
このほか、同とりまとめには掲載されていない民事法上の課題への対応として、遺体未発見の行方不明者に係る死亡届添付書類の簡略化や倒壊・流出等した建物の職権滅失登記等の負担軽減も図られた253。
また、借家が滅失した賃借人の保護等を図るための「罹災都市借地借家臨時処理法」(昭和21年法律第13号)及び滅失したマンションの再建を円滑化するための「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(平成7年法律第43号)は対象となる災害を政令指定することにより適用されるが、東日本大震災については、被災地方公共団体からの意見聴取等の結果、具体的な法的必要性がないと判断され、適用しないこととされた254。
- 252 内閣府HP https://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/shinsai.html (令和5年7月19日閲覧)
- 253 参議院事務局企画調整室「東日本大震災に係る法務・司法分野の主な取組と今後の課題」2012.6『立法と調査』No.329
- 254 東日本大震災以前の「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」では、滅失したマンションについてのみ、区分所有者の多数決でその再建を決議できることとしていたところ、東日本大震災の被災地では具体的なニーズが存在しなかった。しかし、震災後、同法は「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成25年法律第62号)によって改正され、滅失以外にも重大な被害を受けたマンションについて、本来は全員同意が必要な取壊し決議等が多数決で可能となる制度が創設された。これを受けて、平成25年政令第231号で東日本大震災が同制度の適用対象となる災害として指定され、仙台市のマンションにおいて、多数決によって建物敷地売却決議がなされている。
